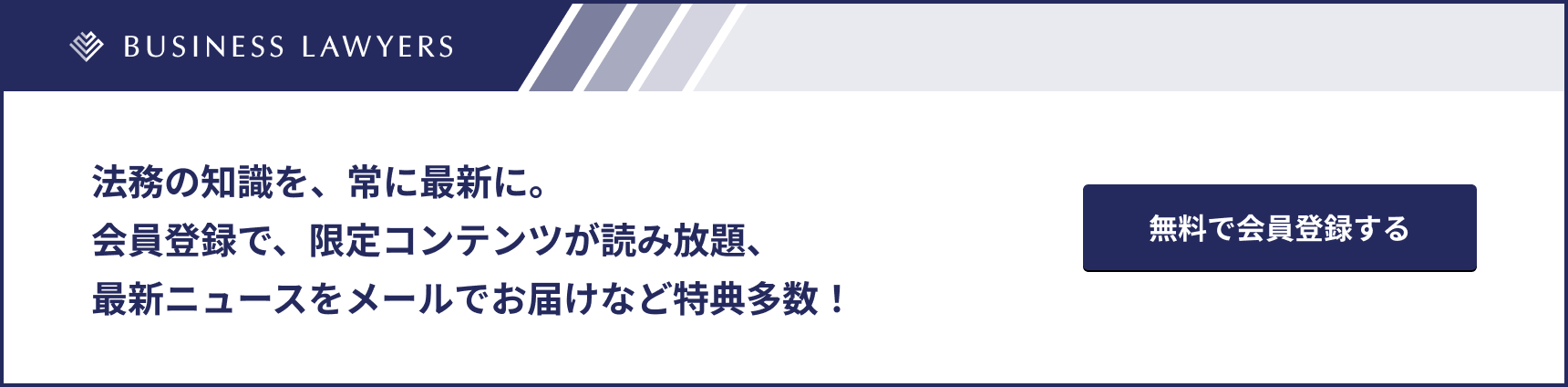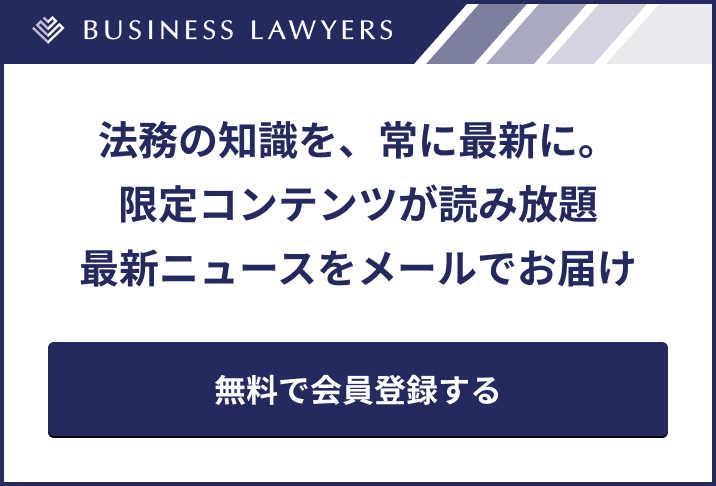株主総会を成功に導く運営ポイント
コーポレート・M&A 更新
目次
株主総会の運営実務は多岐にわたりますが、事前準備から事後処理まで一連の流れを正確に把握し、各段階で会社法や定款に則った適切な手続を行うことが不可欠です。ここでは、「BUSINESS LAWYERS」掲載の人気記事をもとに、株主総会に関する基礎知識、運営の流れやポイントなどを整理します。
なお、関連記事のタイトルは一部要約しています。より詳細な情報はリンク先の記事本文をご参照ください。
株主総会の基礎知識
株主総会とは
株主総会は、株式会社の最高意思決定機関です。会社法上、株式会社においては必ず設置する必要があり、取締役や監査役の選任・解任、定款変更、重要な経営事項の決議などを行います。
株主総会には、原則として議決権を持つ株主が出席します。
株主総会の種類と開催時期・場所
(1)開催時期
株主総会には、年に1回必ず開催される「定時株主総会」と、必要に応じて随時開催される「臨時株主総会」の2種類があります。
定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集することが会社法で義務付けられています。つまり、年1回の開催は義務付けられているものの、具体的な期限はありません。
会社法では、株主総会で議決権を行使できる株主を確定する「基準日」を定めており、基準日株主の権利行使は「基準日から3か月以内」とされています。日本では多くの企業が3月末に事業年度を締め、基準日も3月末に設定しているため、結果として6月に定時株主総会が集中する傾向にあります。
(2)開催場所
会社法上、株主総会の開催場所に特段の制限はありません。一定の要件を満たせば、株主総会のオンライン(バーチャル)開催や、リアルとオンラインのハイブリッド開催も可能です。
株主総会の決議事項と決議方法
株主総会において決定する事項を、決議事項といいます。
株主総会の決議事項は、会社の機関設計により異なりますが、会社の経営に関する事項や、役員等の選任・解任に関する事項、株主の利害に関する事項などが挙げられます。たとえば、取締役会設置会社では法令・定款で定められた事項のみが株主総会の決議事項となり、取締役会非設置会社ではより広範な事項が決議対象となります。
決議する内容の重要性によって株主総会決議の要件(定足数、表決数)が異なり、普通決議、特別決議、特殊決議という大きく3つの方法に分けられます。役員の任期や、議決権の取扱いなど、会社法の規定を正確に把握しておくことが重要です。
株主総会のスケジュール例
6月開催の定時株主総会の一般的な運営スケジュールは、次のとおりです。
株主総会のスケジュール例(3月末決算の監査役会設置会社の場合)
| 時期 | 項目 | 期限など | |
|---|---|---|---|
| 3月末日 | ① | 事業年度末日、基準日※1 電子提供制度に係る書面交付請求の期限 |
|
| 4月上旬 | ② | 総株主通知の受領※2 | |
| 4月中旬 | ③ | 監査役・会計監査人に対し、事業報告・計算書類・それらの附属明細書・連結計算書類を提出(事業報告・その附属明細書は監査役のみに提出) | |
| 4月下旬 | ④ | 株主提案権の行使期限 | ⑫の8週間前まで |
| 5月上旬 | ⑤ | 会計監査人から特定取締役・特定監査役に対し、会計監査報告の内容を通知 | ③から4週間経過した日まで |
| 5月中旬 | ⑥ | 特定監査役から特定取締役・会計監査人に対し、監査役会監査報告の内容を通知(事業報告・その附属明細書についての監査報告は特定取締役のみに通知) | ⑤から1週間経過した日まで |
| ⑦ | 取締役会決議(計算書類・事業報告・それらの附属明細書・連結計算書類の承認、株主総会招集決定) | ||
| ⑧ | 決算発表 | ||
| 6月初旬頃 | ⑨ | 株主総会資料の電子提供措置の開始 | ⑫の3週間前の日まで |
| 6月上旬 | ⑩ | 招集通知の発送 | ⑪の2週間前まで |
| 6月下旬 | ⑪ | 書面投票・電子投票の期限 | ⑫の前日のある時点(午後5時など) |
| ⑫ | 株主総会の開催 | 通常は①から3か月以内 | |
| ⑬ | 取締役会の開催(代表取締役の選定など)、監査役会の開催(常勤監査役の選定など) | 通常は⑫と同日 | |
| ⑭ | 株主総会議事録の作成・備置 | 備置期間は、本店に10年間、支店に5年間 | |
| ⑮ | 議決権行使結果に関する臨時報告書の提出 | ⑫の後遅滞なく | |
| 7月上旬 | ⑯ | 商業登記の申請期限 | ⑫から2週間以内 |
※1 株式会社は、一定の日を「基準日」として、その日時点の株主名簿上の株主を、後日における権利行使ができる者と定めることができます(会社法124条1項)。
※2 総株主通知とは、証券保管振替機構から発行者(会社)に対して行われる、基準日などの時点における株主の氏名、住所、株式数などの通知をいいます(社債、株式等の振替に関する法律151条1項)。総株主通知により、会社は、基準日時点の株主を把握することができます。
出所:「株主総会の運営マニュアル – 事前準備、当日対応、終了後の実務まで」
以下では、事前準備、当日の運営、事後処理の各段階で必要な作業やポイントを説明していきます。
株主総会の事前準備
有価証券報告書の総会前開示
「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」の公表などといった金融庁の働きかけもあり、株主総会前に有価証券報告書を開示する上場企業が急増しています。金融庁の公表資料 1 によると、2025年3月期決算企業では、約55%が総会前に開示する見込みです。これは前年の1.8%から大幅な増加です。また、総会前開示の時期も早まっており、前期(2024年)は株主総会前日の開示が多かったところ、2025年は7日以上前に開示を前倒しする企業が増えました。
招集通知の作成・発送、想定問答の作成など
株主総会の成否は、事前準備にかかっているといっても過言ではありません。総会当日までに必要な準備事項としては、たとえば日時・場所の決定、招集通知の作成・発送、議案の検討・決定などが挙げられます。議事運営マニュアルや想定問答集の作成、会場設営や受付体制の整備も欠かせません。
また、株主総会の開催に先立って株主から株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。
株主総会当日の運営
株主総会当日は、会場設営や受付、議事進行、トラブル対応など、臨機応変かつ円滑な対応が求められます。
災害などの不測の事態に備えた開催・運営についても検討しておく必要があるでしょう。
株主総会後の実務
株主総会議事録の作成
株主総会議事録は、株主総会における決定事項や議事の経過を記録化したものであり、その運営の適切性を確保する役割を果たすとともに、ステークホルダーへの情報提供という機能も有します。株主総会議事録の記載例や、作成・備置等にあたっての実務ポイントは、次の記事をご参照ください。
登記手続などその他の実務
株主総会終了後は、株主総会議事録の作成以外にも、登記手続や開示対応など多くの業務があります。決議事項によっては、法定の公告や官報掲載が必要な場合もあります。また、登記事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に変更登記を行わないと過料の対象となります。
株主総会に関する最新動向
株主総会実務を進めるうえでは、アクティビスト対応や人的資本開示など、新しいトピックのキャッチアップも欠かせません。以下では、トレンドや最近の事例に関する記事を紹介します。
-
金融庁「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会 事務局説明資料」(2025年6月11日)参照。 ↩︎

弁護士ドットコム株式会社