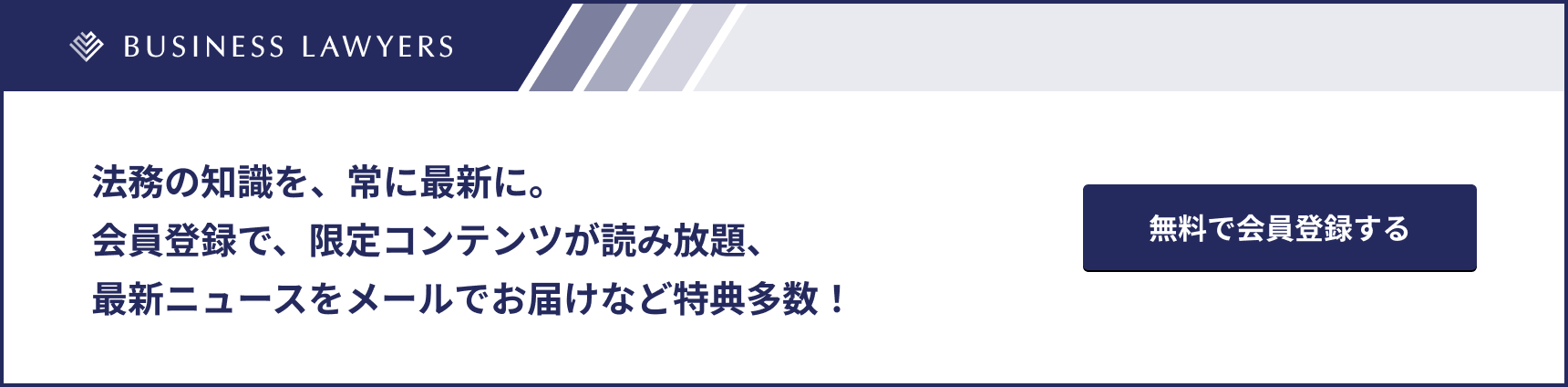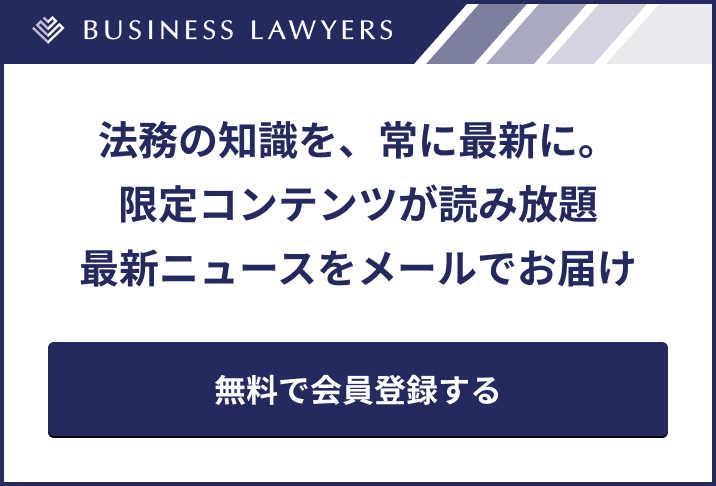秘密保持契約(NDA)とは?一般的な内容をひな形付きで解説
取引・契約・債権回収
目次
秘密保持契約(NDA)をチェックする際には、まず、自社が情報を開示する側と受領する側のどちらなのか、あるいはどちらにも当てはまるのかを確認することが必要です。そのうえで、自社にどのような義務やリスクが生じるのかを検討していきましょう。
秘密保持契約(NDA)とは何か
秘密とは何か
秘密保持契約(NDA)は、取引などを通じて開示される秘密情報について、本来の目的外での使用や第三者への開示・漏えいを防止するために締結するものです。
秘密情報としては、「営業秘密」と、営業秘密に該当しないその他の秘密情報があります。営業秘密とは、不正競争防止法2条6項の「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」という定義に当てはまるものです。この定義に該当すれば法的な保護を受けることができるため、秘密保持契約(NDA)は補足的な意味合いで締結されるものといえます。
しかし、営業秘密といえるかどうかについて、裁判所は厳しく判断する傾向があります。そのため、営業秘密に該当しないその他の秘密情報として扱われることも想定し、秘密保持契約(NDA)によってリスクを手当てしておく必要があります。
秘密保持契約(NDA)のメリット・デメリット
秘密保持契約(NDA)を締結するメリットとデメリットは、自社が「情報を開示する側」(開示側)と「情報を受領する側」(受領側)のどちらの立場になるか(あるいは両方か)によって異なります。契約締結によって課される法的義務の内容を見極めることが重要です。
開示側
- 受領側が秘密情報を保持し、目的外に利用・開示しないよう、義務づけることができる
- 将来特許権を取得する可能性に備えることができる
- 受領側が秘密保持の約束を破ったことで損害を被った場合に損害賠償を請求できる可能性が高まる
デメリット
- 契約上、秘密情報の範囲に含まれないことになる情報が開示された場合に、漏えいや目的外利用のリスクが高まる
- 契約内容によっては、情報を開示する際のプロセスが煩雑になる場合がある
受領側
- 秘密情報を明確に定義することで、責任を負う範囲を限定できる
- 想定していた目的で情報を利用できなかったり、契約違反の状態になったりする可能性を排除できる
デメリット
- 受領した情報を適切に管理するための負担が生じる
- 情報の不適切な取扱いがあった場合に、損害賠償等の経済的損失が生じ得る
秘密保持契約(NDA)を締結するタイミングと取引場面
秘密保持契約(NDA)は、秘密情報の開示に先立って締結する必要があるため、取引をするかどうか検討するタイミング、または取引開始前のタイミングで締結します。秘密保持契約(NDA)を締結する前に打ち合わせ等が進むこともあり得ますが、重要な秘密情報が関わるビジネスであればあるほど、秘密保持契約(NDA)を締結していない状態でコミュニケーションをとることはリスクが高いといえます。
秘密保持契約(NDA)は、幅広いビジネスの場面で締結されます。一般的な商談から、個人情報の提供を伴う業務委託、共同研究開発、合併・買収、資本・業務提携までさまざまです。開示される秘密情報の量や性質に応じてリスクを検討することが求められます。
秘密保持契約(NDA)と関連する法令
秘密保持契約(NDA)と関連する主な法令として、個人情報保護法、不正競争防止法、特許法の3つがあげられます。
個人情報保護法
個人情報保護法は、企業や行政機関等が個人情報を適切に扱い、有効に活用するためのルールを定めています。個人情報取扱事業者に対しては、利用目的の特定義務、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務、従業者や委託先に対する監督義務、第三者提供の制限などが課されています。
個人情報保護法に違反した場合の法的・社会的ダメージは小さくありません。開示される秘密情報に個人情報が含まれる場合には、同法の規定を踏まえた秘密保持契約(NDA)を締結する必要があります。
不正競争防止法
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を促進するため、事業者の営業上の利益の保護と公正な競争秩序の維持に関するルールを定めています。不正競争行為の類型の1つとして定められているのが、営業秘密の侵害です。
営業秘密の不正な取得・使用・開示は同法違反となり、民事上・刑事上の法的責任を追及することができます。そのため、秘密保持契約(NDA)がなくとも、一応は法的保護を受けられることになっています。
ただし、不正競争防止法で営業秘密として保護されるには、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(有用な技術上または営業上の情報であること)、非公知性(公然と知られていないこと)の3要件をすべて満たすことが必要です。保護を受けられる場合は相当に限定されることになることから、営業秘密に該当しない秘密情報であっても法的保護を受けられるようにしておくために、秘密保持契約(NDA)を締結する必要があるのです。
特許法
特許法は、発明者に一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与するための法律です。特許法による保護を受けられる発明であるためには、産業上の利用可能性、新規性、進歩性、先願、公序良俗に反するものでないこと、という要件を満たす必要があります。
これらの要件のうちの新規性が失われないようにするために、秘密保持契約(NDA)が重要な役割を担います。新規性とは、「公然知られた発明」(公知の発明)は特許を受けられないという要件です。公知の発明とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明をいいます。つまり、秘密情報を用いた発明について特許出願をしようとしても、秘密保持契約(NDA)を締結せずに情報を開示してしまっていたら、特許取得ができなくなる可能性があります。
将来、特許出願をする可能性があるのなら、秘密保持契約(NDA)を締結しておくことが不可欠といえます。
秘密保持契約(NDA)の一般的な内容と主要条項
秘密保持契約(NDA)において規定すべき主な内容は以下のとおりです。
- 契約の当事者と目的(前文)
- 秘密情報の定義・内容、例外
- 秘密保持義務と目的外使用の禁止
- 知的財産権の帰属
- 契約の有効期限と秘密保持義務の存続
- 秘密情報の返還・廃棄
- 損害賠償
- 紛争解決
秘密保持契約(NDA)のひな形はさまざまな文献等で入手することができますが、ここでは、経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」の「(参考資料2)各種契約書等の参考例」として公表されている条項例を基に、一般的な内容と主要条項を紹介します。
ただし、これらの条項例はサンプルにすぎませんので、このまま使うと適切なリスク管理ができない可能性があります。実際に契約書を作成する際には、個別の取引内容に合った記載とすることが何よりも重要です。
契約の当事者と目的(前文)
契約の当事者を明確にし、契約を締結する目的を記載します。契約書タイトルの下に、前文として記載されるのが通常です。
秘密情報の定義・内容、例外
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
- 開示を受けたときに既に保有していた情報
- 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
- 開示を受けたときに既に公知であった情報
- 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
どのような情報を秘密情報として扱うかを記載します。場合によっては、以下のように追記するパターンもあり得ます。
- この秘密保持契約(NDA)を締結したという事実についても、秘密情報の対象とする
- 開示の形式が書面である場合に限定する
- 秘密である旨の表示が困難な形式による開示の場合の取扱いを記載する
- 秘密情報の内容を「別紙」で具体的に特定する
秘密保持義務と目的外使用の禁止
- 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
- 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
- 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。
- 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
- 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
1. 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
2. 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3. 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
秘密情報を適切に保管・管理し、目的外使用をしないことを記載しますが、上記の遵守事項は例にすぎません。
複製や第三者への開示、法令に基づく開示の際の手続などは、案件に応じてさまざまなパターンがあり得ます。役員・従業員に会社と同等の義務を課したり、開示できる役員・従業員の範囲を限定する場合もあります。また、秘密情報の保管状況について報告を求めたり、保管場所への立ち入り調査が可能となるようにするなど、より厳格な記載とすることも考えられます。
秘密情報の性質や量、秘密情報が関わる取引の内容を踏まえ、必要十分かつ運用可能なルールとなるよう、社内で相談のうえで相手方と交渉する必要があります。
知的財産権の帰属
1. 甲と乙との共同研究により取得した知的財産権の帰属は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
2. 目的物の製作に関する設計上の考案、設計図面、又は製作情報に関する知的財産権は、原則として乙に帰属する。
3. 甲又は乙は、相手方の図面若しくは仕様書により製作された目的物又はその製作方法に関連し知的財産権の出願を行う場合には、事前にその旨を相手方に申出て書面による承諾を得なければならない。この場合、知的財産権の帰属等に関しては、その貢献度に応じて甲と乙とが協議して定める。
4. 甲又は乙は、目的物に関わる知的財産権を第三者に譲渡又は実施権設定の許諾を行う場合は、相手方の書面による承諾を得るものとする。
5. 甲又は乙は、目的物につき第三者との間に知的財産権上の権利侵害等の紛争が生じたときは、相手方に書面で通知し、甲及び乙のうちその責めに帰すべき者が、その負担と責任において処理・解決するものとする。
秘密情報の開示を伴う取引において、特許等の知的財産権が発生する可能性がある場合のルールを記載します。ここでは、共同研究が行われる取引を例として、共同研究によって取得した知的財産権の帰属は両者で協議して定めることとし、製作に関する知的財産権は原則として乙に帰属するというルールとなっています。
この条項例のような記載以外にも、両者の力関係や取引の性質によって、権利の帰属や紛争対応の責任をどちらか一方に寄せるパターンも考えられます。また、この条項自体が不要な場合もあるでしょう。自社の立場と譲歩できる範囲を見極めたうえで、どのような書きぶりとするか、相手方と交渉する必要があります。
契約の有効期限と秘密保持義務の存続
1. 本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満◯年間とする。期間満了後の◯か月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに◯年間継続するものとし、以後も同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、第◯条、第◯条及び第◯条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
契約の有効期限を定めます。この条項例では自動更新となっていますが、1回限りの業務委託など、取引関係が終了した後にも秘密保持義務を負うことは適切ではない場合もありますので、第1項の記載を1文目だけとするパターンも考えられます。
秘密保持契約(NDA)が終了したからといってすぐに秘密情報を利用されては困るという場合には、第2項のように、秘密保持義務を存続させる記載とすることがあります。存続期間を「◯年間」などと具体的に記載することも考えられます。
存続期間をどのくらい長く設定するのが適切かという点は、秘密情報の性質によって異なります。時間の経過とともに古くなって価値がなくなる情報なのか、時間が経過しても重要性が変わらない情報なのか、また保管コストはどれくらいかかるのかなど、しっかり見極めることが必要です。
秘密情報の返還・廃棄
1. 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物 (以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2. 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。
契約締結の目的となる取引の終了などにより、秘密情報が必要ではなくなった場合の返還・廃棄を義務づける条項です。
電子的な秘密情報などは、実務上、本当に返還・廃棄が完了したかどうかを確認することが難しいため、第2項のように、受領側から書面を提出することを義務づける場合があります。秘密情報に重大な技術情報や個人情報が含まれるような取引において、特に必要性が高いものといえます。
損害賠償
甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は甲若しくは乙の許諾により開示を受けた第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
秘密情報の漏えいなど、秘密保持契約(NDA)に違反した場合の措置や損害賠償について定めます。ここでは抽象的な記載としていますが、賠償する損害の範囲をどう定めるかなどについて、契約交渉で折り合いがつきにくい場合もあります。また、漏えいなどが生じた場合に、この条項のみで問題が解決できるわけでもありません。そのため、損害賠償に関する条項とは別に、「違約金」について定める条項を設けておくこともあります。
紛争解決
本契約に関する紛争については◯◯地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
秘密保持契約(NDA)をめぐって紛争になった場合の第一審専属管轄裁判所を記載します。ただし、裁判になればその手続は原則として公開され、秘密情報の内容が公になってしまうというリスクは認識しておく必要があります。
秘密保持契約(NDA)をチェックする際のポイント
秘密保持契約(NDA)をレビューする場合、自社が開示側か受領側か、あるいは両方かについて整理し、具体的なリスクを想定したうえで検討しなければなりません。自社が開示側であれば、秘密情報の範囲は広く定め、受領者に厳重に管理してもらいたいと考えるでしょう。逆に自社が受領側であれば、秘密情報の範囲は狭く定め、なるべく責任を負わなくて済むようにしたいと考えるはずです。
開示側と受領側のそれぞれが着目すべき点は次のとおりです。
- 契約を締結する目的は明確か
- 秘密情報の定義や範囲は明確か
開示側
- 受領側に対して、秘密情報を保護するために必要かつ十分な義務を課しているか
- 保護すべき秘密情報が対象としてすべて含まれているか
受領側
- 契約締結の目的を達成するために必要な情報をすべて受領できる記載となっているか
- 自社に課される義務が、情報提供を受ける目的に照らして合理的なものか
- 求められている秘密情報の管理体制が、自社にとって構築・運用可能なレベルになっているか
秘密保持契約(NDA)の違反があったら
受領側が秘密保持契約(NDA)に違反し、第三者への開示や漏えいなどがあった場合、開示側は損害賠償等を請求することが可能です。しかし、情報が漏えいしたことによる損害について、損害の事実や損害額を立証することが難しい場合もあります。また、訴訟手続のなかで秘密情報が公開されてしまうリスクも考慮しなくてはなりません。そのため、秘密保持契約(NDA)違反による損害を法的措置によって回復することができるとは限らないのです。これが秘密保持契約(NDA)の限界です。
それでは、なぜわざわざ秘密保持契約(NDA)を締結するのでしょうか。そこには「情報を流用したり、漏えいしたりすると、大変なことになる」というプレッシャーを与える意図があります。秘密保持契約(NDA)が万能ではないことを理解したうえで、開示する情報を限定する、金銭的な取引条件を有利にすることでリスクを転嫁する、そして究極的には、不安な相手とは取引しないなど、ビジネス面で工夫することが求められます。
秘密保持契約(NDA)と収入印紙
秘密保持契約(NDA)は、印紙税法上の課税対象となる文書に当たらないため、原則として収入印紙の貼付は不要です。例外として、実質的に「継続的取引の基本となる契約書」と判断される内容となっているなど、秘密保持以外の事項が含まれる場合には、収入印紙の貼付が必要になり得ます。
参考文献
- 橋本裕幸・松田秀明「秘密保持契約のヒ・ミ・ツ」ビジネスロー・ジャーナル2008年9月号101頁
- 丸野登紀子「契約書審査差がつくポイント 秘密保持契約」ビジネスロー・ジャーナル2013年12月号76頁
BUSINESS LAWYERS COMPLIANCEは、わかりやすく面白いドラマ形式のオンライン研修動画でコンプライアンス研修の実効性向上をサポートするサービスです。パワハラやセクハラ、下請法違反など、企業が陥りがちな違反ケースをそろえた動画コンテンツは、すべて弁護士が監修。従業員の受講状況や確認テスト結果などの一元管理も可能です。
詳しくはこちら

弁護士ドットコム株式会社