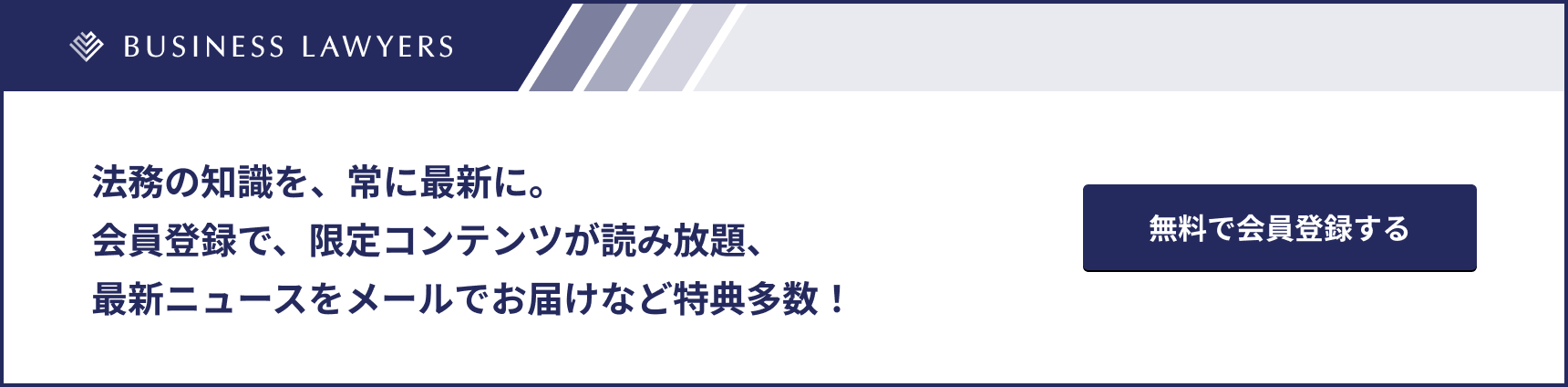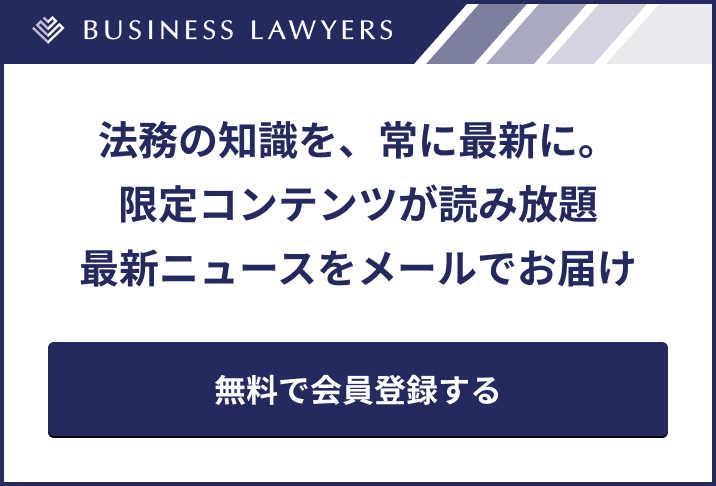パワハラとは?定義、ペナルティ、措置義務、対応の流れを解説
人事労務
目次
パワハラとは?
パワハラの実態
厚生労働省では、2012年度から「職場のハラスメントに関する実態調査」を実施しています。最新の2020年度の調査によると、過去3年間に職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)を受けたことがあると回答した労働者の割合は31.4%でした。また、2020年6月のパワハラ防止法施行後に都道府県労働局に寄せられたパワハラの相談件数は約18,000件、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数も2020年度には約80,000件にのぼっており(「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より)、職場のトラブルのなかでも特に大きな問題となっていることがわかります。
パワハラの定義となる3つの要素
パワハラとは、どのような行為をいうのでしょうか。企業にパワハラ防止を義務付けるパワハラ防止法30条の2第1項では、次の3つの要素すべてを満たす場合にパワハラになると定義されています。
- 職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 雇用する労働者の就業環境が害されるもの
「職場において行われる」については、労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます(出張先、社用車の中、在宅勤務中の自宅など)。勤務時間外の「懇親の場」等、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断にあたっては、職務との関連性、参加が強制か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。
「雇用する労働者」については、正社員だけではなく、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用するすべての労働者をいいます。派遣労働者については、派遣元事業主だけではなく、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先事業主)も、自ら雇用する労働者と同様に、パワハラ防止対策の措置を講じる必要があります。
それでは、3つの要素についてどのような行為が該当するのか、厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(パワハラ防止指針)を基に見ていきましょう。
「優越的な関係を背景とした言動」とは
1つ目の要素である「優越的な関係を背景とした」言動とは、業務遂行にあたって、パワハラの行為者に対して抵抗または拒絶することができない可能性が高いような関係を背景として行われるものを指します。
上司によるものだけでなく、同僚や部下による言動であってもパワハラに該当する場合があることに注意が必要です。
- 職務上の地位が上位の者による言動
- 同僚または部下による言動であっても、行為者のほうが知識や経験が豊富で、その協力を得なければ円滑に業務を遂行することが難しい場合
- 同僚または部下からの集団による行為で、上位者がこれに抵抗または拒絶することが難しい場合
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは
2つ目の要素である「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、その言動が明らかに業務上必要性のない、またはそのやり方が相当でないものを指します。
この判断にあたっては、行為に至る経緯や状況、業務の性質、指導としての適切性など、さまざまな要素を総合的に考慮する必要があり、どんな場合にも当てはまるような基準はないということに注意が必要です。
- 業務上明らかに必要性のない言動
- 業務の目的を大きく逸脱した言動
- 業務を遂行するための手段として不適当な言動
- 行為の回数、行為者の数等、そのやり方や手段が、社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
「労働者の就業環境が害される」とは
3つ目の要素である「労働者の就業環境が害される」とは、その言動によって身体的・精神的に苦痛を与えられ、不快な職場環境になったことで、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、無視できないほどの支障が生じることを指します。
この判断にあたっては、平均的な労働者の感じ方を基準として検討されることになります。
パワハラ以外のハラスメント
パワハラは、職場における嫌がらせ(ハラスメント)のうちの1つです。ハラスメントとしては、ほかにも次のような種類があります。
- セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)
- マタニティハラスメント(妊娠・出産・育児に関する嫌がらせ)
- パタニティハラスメント(育児休業等制度を利用しようとする、または利用した男性への嫌がらせ)
- SOGIハラスメント(性的指向や性自認に関する嫌がらせ)
- 就活ハラスメント(採用担当者等が就職活動中の学生等に対して行う嫌がらせの総称)
- カスタマーハラスメント(客の立場を利用した嫌がらせ)
- リモートハラスメント(Web会議システムを通したやり取りのなかで起きる嫌がらせの総称)
パワハラの種類とは? 6つの行為類型
厚生労働省は、裁判例などに基づき、次の6つのタイプをパワハラの典型例として整理しています(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より)。
ただし、これらに該当する行為であっても、個別の事案の状況によってはパワハラといえない場合もありますし、パワハラに当たりうる行為のすべてについて網羅したものでもありません。実際の判断にあたっては詳細な検討が必要となりますので、注意してください。
身体的な攻撃
暴行
傷害
殴る・蹴る、頭を小突くなど、体に危害を加える行為によって部下や同僚を威嚇し、従わせようとすることは、「身体的な攻撃」型のパワハラに該当します。
-
該当すると考えられる例
- 殴る、蹴る
- 相手に物を投げつける
-
該当しないと考えられる例
- 誤ってぶつかる
精神的な攻撃
脅迫 名誉毀損 侮辱 ひどい暴言
激しく怒鳴る、罵倒するといった⾏為は、「精神的な攻撃」型のパワハラに該当します。パワハラで最も多いのはこのタイプといえます。
相手を脅迫するような言動や人格を否定するような侮辱、名誉を傷つけるような言葉、ひどい暴言などがあげられます。
-
該当すると考えられる例
- 人格を否定するような言動(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む)
- 必要以上に長時間にわたって、厳しい叱責を繰り返し行う
- 他の労働者の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う
- 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を、他の労働者も宛先に含めて送信する
-
該当しないと考えられる例
- 繰り返し注意しても、遅刻などの社会的ルール違反が改善されない労働者に対して、一定程度強く注意する
- 業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする
人間関係からの切り離し
隔離 仲間外し 無視
仕事から外して長時間別室に隔離したり、集団で無視をしたり、1人だけ飲み会に誘わなかったりするような⾏為は、「人間関係からの切り離し」型のパワハラに該当します。
-
該当すると考えられる例
- 気に入らない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり自宅研修させたりする
- 1人に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
- 新しく採用した労働者を育成するために、短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
- 懲戒処分を受けた労働者が通常の業務へ戻る前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる
過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制 仕事の妨害
必要な教育や説明を行わないまま達成困難な目標を課し、未達成について厳しく叱責したり、業務とは無関係の私的な用事を強制的に行わせたり、わざと妨害して仕事の進行を遅らせたりといった行為は、「過大な要求」型のパワハラに該当します。
-
該当すると考えられる例
- 肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、業務に直接関係ない作業を長期間にわたって行わせる
- 新卒採用者に必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
- 私的な雑用の処理を強制的に行わせる
-
該当しないと考えられる例
- 育成のために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
- 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、通常時よりも一定程度多く業務を任せる
過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、または仕事を与えない
業務上そうすることが必要なわけではないのに、本人の能力や経験に見合わない、誰にでもできるような仕事しか与えないとか、そもそも仕事を振らないというような行為は、「過小な要求」型のパワハラに該当します。
-
該当すると考えられる例
- 管理職を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
- 気に入らない労働者に対して嫌がらせをするために、仕事を与えないでおく
-
該当しないと考えられる例
- 能力に応じて一定程度業務内容や業務量を軽減する
個の侵害
私的なことに過度に立ち入る
私物のスマートフォンを勝⼿に⾒たり、職場外での行動を監視したり、センシティブな事情をほかの人に暴露したりなど、プライベートな領域に必要以上に踏み込む⾏為は、「個の侵害」型のパワハラに該当します。お酒の席などで起きやすいため、特に注意が必要です。異性とのやり取りではセクハラになる可能性もあります。
-
該当すると考えられる例
- 職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露する
-
該当しないと考えられる例
- 本人への配慮を目的として、家族の状況等についてヒアリングを行う
- 本人の了解を得て、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す
パワハラと指導の違い
指導する際の注意点
部下や後輩を指導する際には、次のような点に十分に注意してください。
◯ 自分の感情を認識する(怒り、怖れ、悲しみ、焦り、妬み)
◯ 攻撃でなく「改善点を的確に指摘・指導」する
◯ 相手を見て接し方を工夫する
◯ 不要な誤解を招かないコミュニケーションを心がける
× 職場での役割や存在まで否定する
× 嫌悪感や否定的な発言により、心理的に追い込む
(厚生労働省「あかるい職場応援団」管理職向け自習用テキストより)
パワハラに該当するおそれがある言葉
具体的にはどのような行為がパワハラに該当する可能性が高いのでしょうか。厚生労働省「あかるい職場応援団」の管理職向け自習用テキストでは、改善すべきものとして次のような言動が紹介されています。
- 問題がある企画書について、書類を投げつけて修正を命じる
- 部下を叱責しながら、近くにあった物差しで頭を叩く
- 「説明してもわからないだろう」と、1人だけ打ち合わせから外す
- 仕事が終わって帰ろうとする部下に、「俺が残っているのに先に帰るのか」と言う
- やる気を引き出そうとの意図で「意欲がないなら会社を辞めるべき」とのメールを本人に送るとともに、職場の同僚もccに入れて送信する
- 明らかに納期に間に合わないとわかっていて、資料の作成を命じる
- 能力に見合わない程度の低い業務を継続的に命じる
- 「俺の若いころは、もっと厳しかったんだ。それに比べ、今の若い者は、甘やかされている」と日ごろから言う
- 個人的な趣味・嗜好について必要以上に聞く
- 特定の部下だけを、何度も同僚の前で叱責する
- 特定の同僚を仲間外れにする
パワハラの発生原因
どのような職場でパワハラが発生しやすいのでしょうか。「令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書(概要版)」では、次のような職場の特徴があげられています。
- 上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない
- ハラスメント防止規定が制定されていない
- 失敗が許されない/失敗への許容度が低い
- 従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる
パワハラ防止法の概要
パワハラ防⽌法は、正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正法であり、略して「労働施策総合推進法」とも呼ばれます。パワハラ防⽌法は、すべての企業に対して、パワハラ防⽌対策を講じる義務を課しています。大企業については2020年6⽉に施⾏され、2022年4月からは中小企業にも対象が拡大されました。
パワハラ防止法30条の2第1項は、企業が負う義務について以下のとおり規定しています。
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
パワハラ対策と防止措置
企業の義務
パワハラ防止法に基づく「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(パワハラ防止指針)では、企業が講じるべき措置として次のような項目があげられています。
| ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発 | ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発 |
| 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発 | |
| 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 | 相談窓口の設置 |
| 相談に対する適切な対応 | |
| 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 | 事実関係の迅速かつ適切な対応 |
| 被害者に対する適正な配慮の措置の実施 | |
| 行為者に対する適正な措置の実施 | |
| 再発防止措置の実施 | − |
| 併せて講ずべき措置 | 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知 |
| 相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・ 啓発 |
(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」より)
上記について、具体的な対応メニューとして整理すると以下のとおりです。
- トップのメッセージ
「パワハラはなくすべきものである」という方針を、トップのメッセージの形で明確に打ち出す。 - 社内ルールを決める
労使一体で取組を進めるために、労働協約や労使協定などで、罰則規定の適用条件や処分内容、相談者の不利益な取扱いの禁止などについて明確なルールを定める。就業規則を変更する場合は労働基準法で定められた手続に従う。 - 社内アンケートで実態を把握
対象者に偏りのない匿名アンケートを行い、正確に実態を把握する。 - 管理職向けの研修・一般社員向けの研修
管理職向けと一般社員向けに分けて研修を行う。 - 社内での周知・啓蒙
組織の方針、ルールなどとともに、相談窓口やその他の取組について、定期的・能動的に周知する。 - 相談窓口の設置、相談対応
従業員が相談しやすい相談窓口を社内・社外に設置し、できるだけ初期の段階で気軽に相談できる仕組みをつくる。 - 再発防止
行為者への再発防止研修や、社内へのメッセージ発信などを行うとともに、新たなパワハラが発生する労働環境となっていないかを確認する。
パワハラ防止研修
厚生労働省のウェブサイト「あかるい職場応援団」の「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第4版)参考資料」では、社内アンケートや各種研修資料、ポスター等のひな形が提供されています。
また、わかりやすく面白いドラマ形式のオンライン研修動画でコンプライアンス研修の実効性向上をサポートする「BUSINESS LAWYERS COMPLIANCE」では、パワハラ防止研修に便利な動画コンテンツを提供していますので、ぜひご利用ください。
望ましい取組
上記はすべての企業が必ず行わなければならない義務ですが、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(パワハラ防止指針)では、上記に加えて「行うことが望ましい取組」として、次のような内容があげられています。大企業や上場企業など、より高度なコンプライアンスが求められる企業では、これらについても対応しておくことが望ましいといえます。
- 各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備
- 職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組
- 労働者や労働組合等の参画
- 自社の労働者以外の者(就職活動中の学生等)に対するハラスメントに関する取組
- 他社の労働者や顧客等からのパワハラや迷惑行為に関する取組
パワハラ行為を行った労働者のペナルティとリスク
懲戒処分
パワハラは職場秩序を乱すものであり、就業規則に基づく懲戒処分の対象となり得ます。どのような処分内容となるかは、行為の程度・性質や、過去にあった自社内での同種事案の処分例などを基に、客観的に平等・公正なものとなるよう検討する必要があります。
処分の検討にあたっては、事実確認を十分に行い、社内ルールに則った適正な手続を踏むことが重要です。
民事責任
パワハラが民法上の不法行為に該当する場合(民法709条)には、発生した損害の賠償責任を負う可能性があります。不法行為は、次の4つの要件を満たす場合に成立します。
- 故意または過失
- 権利または法律上保護される利益の侵害
- 損害
- 因果関係
不法行為に基づく損害賠償の金額は、行為の悪質性や事案の内容によってさまざまですが、一般的には数十万円から100万円程度、被害者が自殺したなどの重大な事案では1,000万円以上となることもあるようです。厚生労働省のウェブサイト「あかるい職場応援団」では、実際に裁判で扱われたハラスメントが紹介されており、損害賠償の金額も確認することができます(「裁判例を見てみよう」)。
刑事責任
パワハラ行為自体を禁止する法令はなく、「パワハラ罪」といったものがあるわけではありませんが、悪質性が高い場合には刑事責任が生じる可能性があります。パワハラに関連する罪としては次のようなものが考えられます。
- 暴行罪(刑法208条)
- 傷害罪(刑法204条)
- 名誉毀損罪(刑法230条)
- 侮辱罪(刑法231条)
- 脅迫罪(刑法222条)
- 強要罪・強要未遂罪(刑法223条)
パワハラが発生した企業のペナルティとリスク
行政責任
企業にパワハラ防止を義務付けるパワハラ防止法では、措置義務および不利益取扱いの禁止について、企業に対して厚生労働大臣が助言、指導または勧告を行い、勧告に従わない場合に企業名を公表できると規定されています(同法33条)。公表された違反事例はまだありませんが、もし自社名が公表された場合は、レピュテーションに大きな悪影響があるものと思われます。
さらに、措置義務および不利益取扱いの禁止について、厚生労働大臣は企業に対して報告を求めることができると規定されており(パワハラ防止法36条1項)、この報告を拒否したり、虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料が発生することがあります(同法41条)。
民事責任
上記の行政処分リスクとは別に、パワハラ被害者/行為者との間で生じる労働紛争が重大なリスクとしてあげられます。パワハラが発生すると、企業は2種類の民事責任を負う可能性があります。
- 自社の労働者が業務を行ううえで第三者に損害を与えたことによる損害賠償責任(民法715条)
- 労働者の安全に配慮する義務(労働契約法5条)に違反したことによる債務不履行責任(民法415条)
厚生労働省のウェブサイト「あかるい職場応援団」では、実際に裁判で扱われたハラスメントについて、主にパワハラに関しては6つの行為類型に分類して紹介されています(「裁判例を見てみよう」)。ほかにも、企業の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例やセクハラに関する事例など、全部で14の切り口から裁判例が分類されており、どのような行為について責任が問われているのか、確認することができます。
パワハラをめぐる裁判による損失としては、損害賠償等の経済的損失はいうまでもありませんが、弁護士費用や人事・法務担当者の業務負担、他の従業員のモチベーション低下、企業名とともに紛争内容が公開されることによる社会的評価の低下、採用への悪影響などが予想され、経営に少なからぬダメージを与えることがあります。パワハラ防止に努めることはもちろん、発生した場合には適切な対応を行い、紛争化させないことが肝要です。
労働災害の補償責任
パワハラが原因となってメンタルヘルス疾患を発症した場合、それが業務上災害と認定されれば、企業は労災補償責任を負います(労働基準法第8章)。
厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の1つを満たすこととされています。認定基準の「業務による心理的負荷評価表」には「パワーハラスメント」が明示されており、職場における人間関係の優越性等に注目したうえで「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷が判断されることになります(厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」)。
パワハラ相談窓口での対応の流れとポイント
パワハラ防止法とパワハラ防止指針は、従業員がパワハラについて初期の段階で気軽に相談できる仕組みとして、相談窓口の設置を義務付けています。
相談窓口で行うべき対応としては、たとえば次のようなものが考えられます。

相談窓口の担当者が注意すべきポイントは次のとおりです。
- プライバシーを確保できる環境を準備し、秘密を厳守する
- 相談者等が不利益な扱いを受けないようにする
- 相談者と行為者の双方から話を聴く
- 行為者や第三者に事実確認を行う際には、事前に相談者の了解を得る
- 相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮しながら、丁寧に事実確認等を行う(ただし1回の相談時間は50分程度まで)
- 相談内容によっては産業医などの医療専門家等の協力を得る
- パワハラに該当するか、どのような対応が適切かなど、判断に迷ったら弁護士や社会保険労務士、都道府県労働局などの外部専門家に相談する
- 人事部等への情報共有のため、また将来の紛争化に備えて、相談の記録を残す
パワハラの相談先
自分がパワハラを受けて悩んでいる、同僚がパワハラで苦しんでいる、指導している部下からパワハラだと言われた、といった場合には、社内外の窓口や機関に相談することができます。
相談したことが知られたら不利益な対応を受けそうで不安な人もいるかもしれませんが、パワハラ防止法は、企業に対して、相談したこと等を理由にして不利益な取扱いをしてはならない旨を定め、周知・啓発することを義務付けています。
-
社内の相談先
- 同僚や上司
- 人事部
- 相談窓口(ハラスメント専用窓口のほか、コンプライアンス窓口やヘルプライン等)
-
社外の相談先
- 会社がある場所の労働局または労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
- 日本司法支援センター「法テラス」
- 法務局「みんなの人権110番」
- 厚生労働省「ハラスメント悩み相談室」
『ハラスメントの事件対応の手引き - 内容証明・訴状・告訴状ほか文例 - 』
発売年:2016年
出版社:日本加除出版
編著等:第二東京弁護士会両性の平等に関する委員会
BUSINESS LAWYERS LIBERARYで読む
『予防・解決 職場のパワハラ セクハラ メンタルヘルス マタハラ・SOGIハラ・LGBT/雇用上の責任と防止措置義務、被害対応と対処法』
発売年:2018年
出版社:日本加除出版
編著等:水谷 英夫
BUSINESS LAWYERS LIBERARYで読む
『パワハラ管理職 指導できない管理職 人事が直面する職場トラブル~ハラスメント個別対応実例集~』
発売年:2019年
出版社:第一法規
編著等:樋口 ユミ
BUSINESS LAWYERS LIBERARYで読む
『Q&A発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応』
発売年:2020年
出版社:中央経済社
編著等:布施 直春
BUSINESS LAWYERS LIBERARYで読む
BUSINESS LAWYERS COMPLIANCEは、わかりやすく面白いドラマ形式のオンライン研修動画でコンプライアンス研修の実効性向上をサポートするサービスです。パワハラやセクハラ、下請法違反など、企業が陥りがちな違反ケースをそろえた動画コンテンツは、すべて弁護士が監修。従業員の受講状況や確認テスト結果などの一元管理も可能です。詳しくはこちら


弁護士ドットコム株式会社