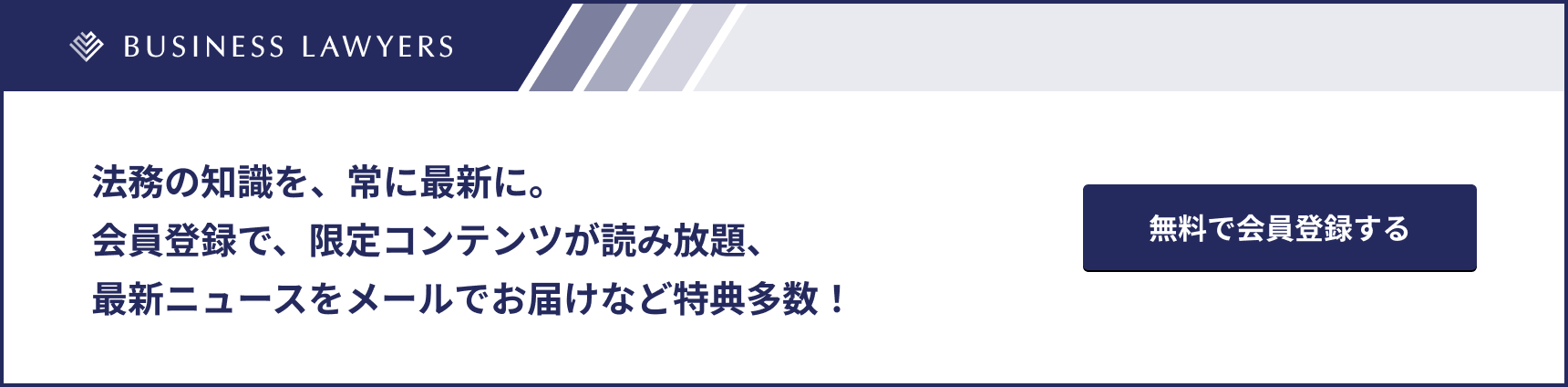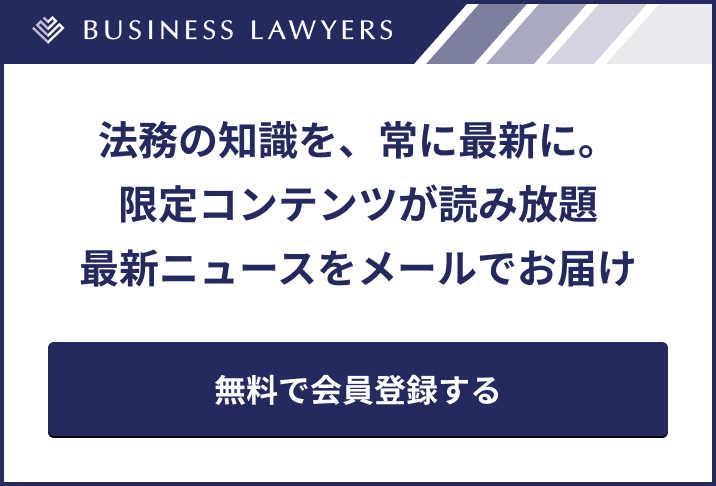株主総会受付業務における留意点について
コーポレート・M&A
※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュースNo.219」の「特集」の内容を元に編集したものです。
本年6月の株主総会は、昨年5月に新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に変更されて以降、2年目を迎え、更なる来場者数の増加が見込まれます。本特集では、株主総会受付業務において来場株主、同伴者等の入場可否判断を行う上での留意点を、近年の傾向も踏まえつつご案内します。
株主資格の確認
原則として、来場者が議決権行使書用紙を持参した場合には、議決権行使書用紙を持参した者を「株主本人」とみなして入場を認めて差し支えありません。これは、株主が議決権行使書用紙(会社が作成し、株主名簿に記録された住所あてに送付した書類)を持参し、提示することが本人確認となるという整理 1 に基づきます。
一方、議決権行使書用紙を持参しない場合については、氏名・住所等を申告(会社指定の様式に記入)してもらい、申告内容を株主名簿と照合して本人確認がなされるのが一般的です 2。
特殊対応が必要となり得るケースにおける考え方および実務の対応状況は次のとおりです。考え方は一例ですので、会社において対応方針を定める際のご参考としてご覧ください。
| No. | ケース | 考え方および実務の対応状況等 |
|---|---|---|
| 1 | 男性(女性)が女性(男性)と推察される名義の議決権行使書用紙を持参した場合 |
|
| 2 | 本人以外の名義の議決権行使書用紙を持参した場合(自己が名義人でない旨を申告された場合) |
|
| 3 | 法人名義の議決権行使書用紙を当該法人の職員が持参した場合 |
|
代理人資格の確認
代理人資格を株主のみに制限している場合
代理人資格は、次のとおり定款において「他の株主」にのみ授権を認められるのが一般的となっています。
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(全国株懇連合会「定款モデル」〔最終改正2021年10月22日〕より抜粋)
このような定款規定は、株主総会が第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を守る趣旨で、合理的な理由による相当程度の制限として有効とされています(最判昭和51年12月24日民集30巻11号1076頁)。
従って、このような定款規定が置かれている場合に、代理人の受付を行う際は、当該代理人自身も株主であるとの前提の下、まず代理人本人の議決権行使書用紙にて代理人本人が株主であることを確認し、委任状の提出を求めることが考えられます。委任状の内容に関しては、今回の総会に係るもの(会社名、開催日等)であるか、また、署名や、記名・押印等の形式要件を満たすか 6 といった確認を行うことが考えられます。
なお、委任状には、委任した株主の議決権行使書用紙を添付させることで、その真正を確認する方法が主流となっています 7。
株主ではない代理人(弁護士)の入場可否
前掲の定款規定が存在する場合に、株主ではない弁護士に代理人資格を認めるか否かについては、裁判例が分かれています 8。従って、株主ではない代理人より出席要請があった場合は、顧問弁護士とも相談の上、対応を決定することが考えられます 9。
同伴者の入場について
家族等
株主の同伴者(家族等)については、同伴者自身も株主でない限り、出席は認められないものとして、入場を拒否することが可能と考えられます。しかしながら、総会攪乱のおそれや、議事進行の妨げになるおそれがない場合など、会社の方針に応じて入場を認める場合もあります。
| 株主の配偶者は入場させる | 2.8% |
| 株主の子(中学生以上)は入場させる | 4.6% |
| 株主の子(小学生)は入場させる | 23.1% |
| 株主の子(乳幼児)は入場させる | 45.4% |
(「2023年度全株懇調査報告書」16頁より抜粋。数値は重複集計)
介助者
心身の不自由な株主の介助者については、障害者差別解消法の改正を踏まえ、株主より同伴者としての入場を求められた場合には、これを認めることが考えられます 10。
| 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)改正の概要 |
|---|
|
| 【同法第8条第2項】 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 |
通訳者
会社側で通訳者を用意しない場合に、株主から通訳者の同伴を求められたときは、コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」)の要請 11 も踏まえ、これを認めることも考えられます 12。なお、通訳者の同伴を認める場合は、通訳の発言を正式な発言として取り扱うこと、通訳として必要な範囲を超えた発言をしないこと、誤訳による不都合は株主の責任となること等を、あらかじめ株主との間で確認しておくことが考えられます。
機関投資家等の実質株主
CGコード補充原則1−2⑤では、「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議しつつ検討を行うべき」と定められており、これを受けて全国株懇連合会は、「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」(最終改正2021年8月27日、以下「本ガイドライン」)を策定しています。
本ガイドラインは、実質株主が名義株主の代理人として議決権を行使する方法(ルートA、C、D)、また、実質株主が総会を傍聴する方法(ルートB)を提示しており、その概要は以下のとおりです。
| 各ルートの概要 | |
|---|---|
| ルートA | 株主総会の基準日時点でグローバル機関投資家等が1単元以上の株式所有者となり、名義株主から名義株式に係る代理権授与を受けて総会に出席する方法 |
| ルートB | 会社側の合理的裁量に服した上で、株主総会当日に総会を傍聴する方法 |
| ルートC | 「特段の事情」13 を発行会社に証明した上で名義株主の代理人として総会に出席する方法 |
| ルートD | 会社が定款規定を変更して、グローバル機関投資家等が名義株主の代理人として総会に出席する方法 |
実質株主が総会への出席を希望する場合、一般的には、事前に会社に連絡があると考えられます。そのため、会社としては、その時点であらかじめ定めた方針があれば当該方針に沿って対応し、方針が定められていなければ、顧問弁護士その他の関係者と具体的な対応を協議し決定することが考えられます。
なお、「株主総会白書2023」106頁によれば、ルートB相当の方法を採用する会社が最多の72.8%、次いでケース・バイ・ケースで対応すると回答した会社が19.0%となっています。
三菱UFJ信託銀行
法人コンサルティング部 会社法務グループ
03-6214-7391(代表)
-
全国株懇連合会「全株懇株式実務総覧」(商事法務2022年1月)79頁。 ↩︎
-
「株主総会白書2023」(旬刊商事法務No.2344)103頁によれば、株主名・住所等を記入させ、株主名簿と照合してから入場させた会社は59.8%。 ↩︎
-
「株主総会白書2023」103頁。 ↩︎
-
定款により代理人も株主であることを要すると定めているのが一般的。詳細は「2.代理人資格の確認」ご参照。 ↩︎
-
定款の規定により、代理人を株主に限定した場合(「2.代理人資格の確認」ご参照)でも、株主である県、市、株式会社が、その職制上上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使にあたって法人の代表者の意図に反することができないようになっている職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させ議決権を行使させても、当該定款規定には違反しない(最判昭和51年12月24日民集30巻11号1076頁)。 ↩︎
-
委任状は、株式取扱規程において、署名もしくは記名、押印が求められることが一般的。
【ご参考】全国株懇連合会「株式取扱規程モデル」(最終改正2022年4月8日)第10条第3項。 ↩︎ -
「株主総会白書2023」107頁によれば、議決権行使書の添付を求める会社は57.8%。 ↩︎
-
肯定したケースとして神戸地裁平成12年3月28日判決(判タ1028号288頁)、否定したケースとして宮崎地裁平成14年4月25日判決(金判1159号43頁)など。 ↩︎
-
「株主総会白書2023」105頁によれば、弁護士の入場を認めることがあるとする会社は8.4%。 ↩︎
-
「2023年度全株懇調査報告書」16頁によれば、介助等が必要な株主の付添人の入場を認める会社は75.5%。 ↩︎
-
「少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。」(CGコード基本原則【株主の権利・平等性の確保】1.より抜粋) ↩︎
-
「2023年度全株懇調査報告書」16頁によれば、通訳者の入場を認める会社は40.4%。 ↩︎
-
「特段の事情」とは、議決権の代理行使を認めても総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれがなく、議決権の代理行使を認めなければ議決権行使が実質的に阻害されることとなる等、グローバル機関投資家等の議決権の代理行使を認めるべき事情をいう。 ↩︎