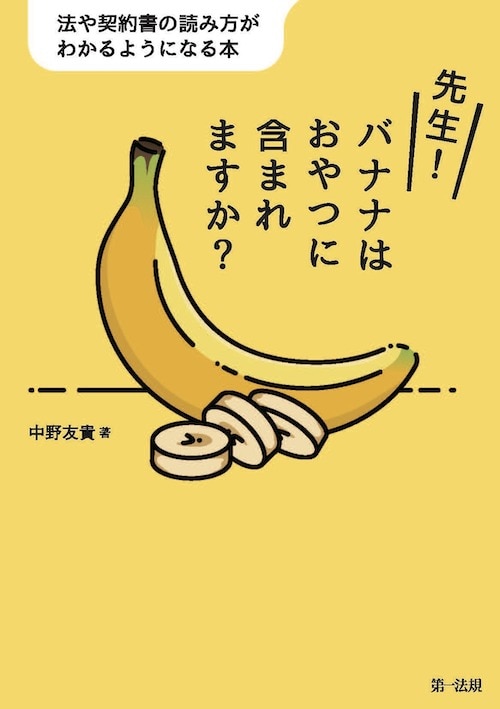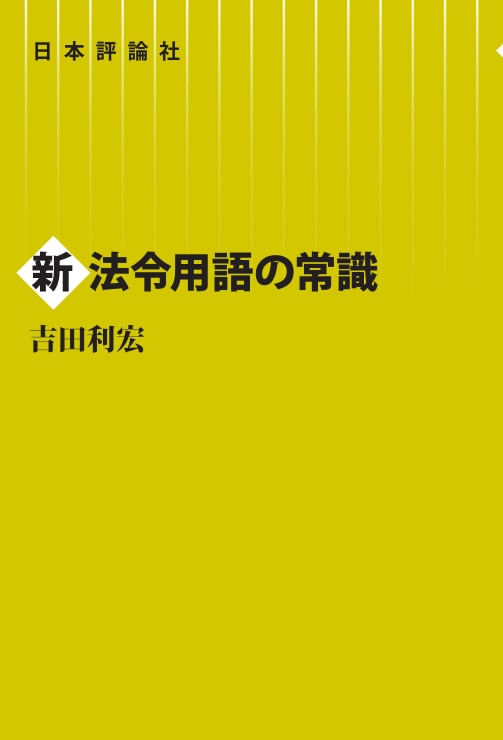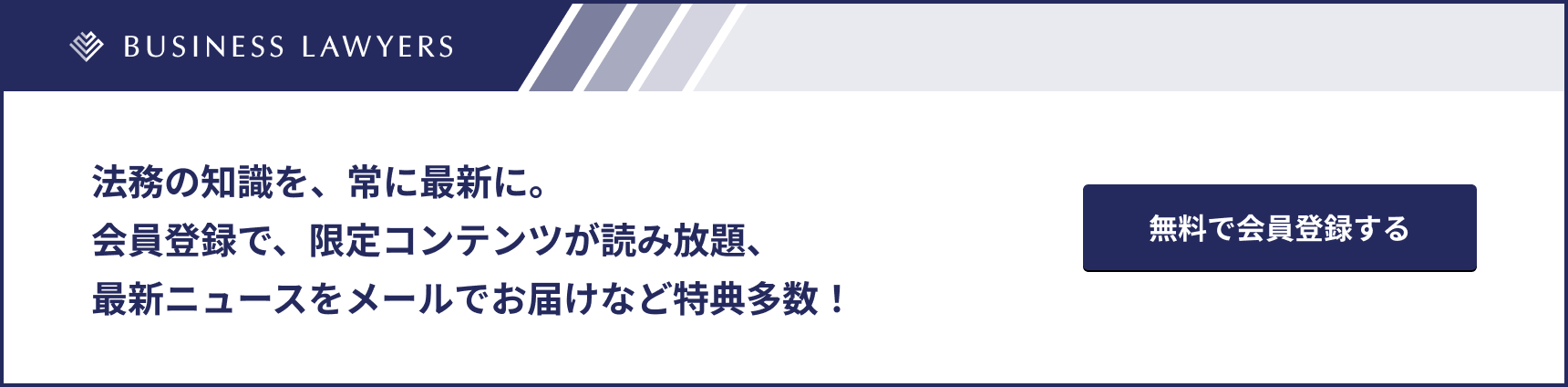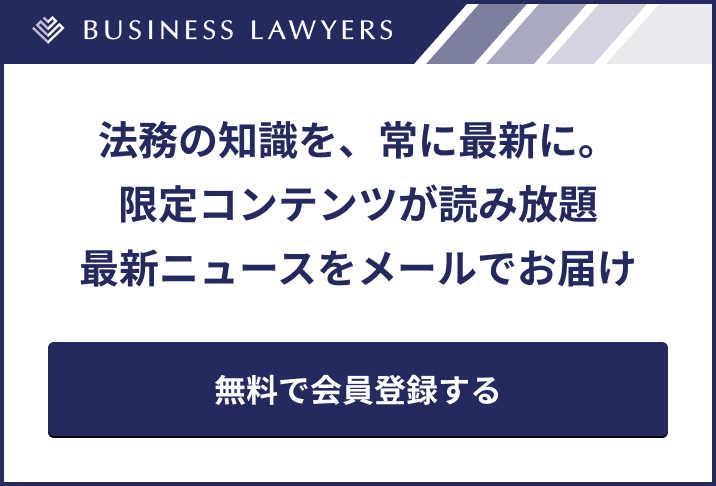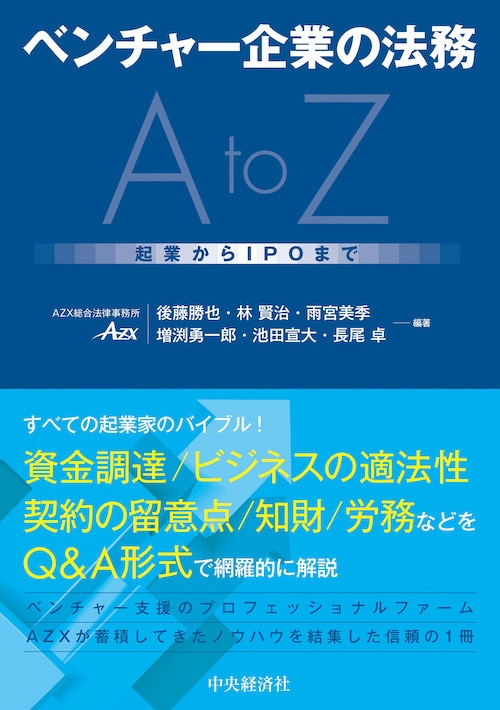新人法務におすすめの本 - Twitterでの推薦書籍と、法務の先輩2名による書籍活用のアドバイス
法務部
目次
この春から新しく法務部門に配属された方も、実務に触れる機会が増えてくる季節。参考のために書籍を読もう、と思っても「どの本を読めばいいかわからない」。そんな悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの度BUSINESS LAWYERSは、Twitterで「#新人法務におすすめの本」というハッシュタグとともに、新人法務担当者におすすめしたい本を募集しました。
本稿では、Twitterで寄せられたおすすめ書籍を一覧でまとめるとともに、上記のハッシュタグをつけて投稿いただいた2名の法務担当者の方に、書籍を選ぶ際のポイントや効果的な書籍の活用方法について伺いました。
新人法務におすすめの本、第1位は『企業法務のセオリー』
おすすめ書籍としてTwitterで最も多くあげられたのは、瀧川英雄・著『スキルアップのための企業法務のセオリー 実務の基礎とルールを学ぶ』でした。同書は、法務担当者として仕事を始める前にまず必要となる心構えから解説。また、企業法務の業務を一般化し、「企業法務遂行スキル」「典型的な法務案件のセオリー」についてもまとめており、法務部門に配属されてまず身につけるべき基本知識が体系化されています。
そのほか、法務部に配属されたら“まず読むべき入門書”としてまとめられた、藤井豊久/守田達也・編著、企業法務向上委員会・著『今日から法務パーソン』や、法解釈の技術について身近な題材を元に解説する中野友貴・著『先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―』、法律を扱ううえで身につけておくべき基本的な用語や区別が難しい用語等を紹介する、吉田利宏・著『新法令用語の常識』なども、新人法務担当者へのおすすめ書籍として複数名から投稿されています。
また、法律分野ではないビジネス書として、仕事に取り組む姿勢や具体的な行動のとり方などについて解説する岩瀬大輔・著『入社1年目の教科書』をはじめ、ビジネスマン一般として身につけるべき素養を学ぶための書籍も、数多く推薦されました。そのほか投稿されたおすすめ書籍については本稿末尾に一覧として紹介します。
『スキルアップのための企業法務のセオリー 実務の基礎とルールを学ぶ』
編・著:瀧川英雄・著
出版社:第一法規
発売年月:2013年
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『今日から法務パーソン』
編・著:藤井豊久/守田達也・編著、企業法務向上委員会・著
出版社:商事法務
発売年月:2021年
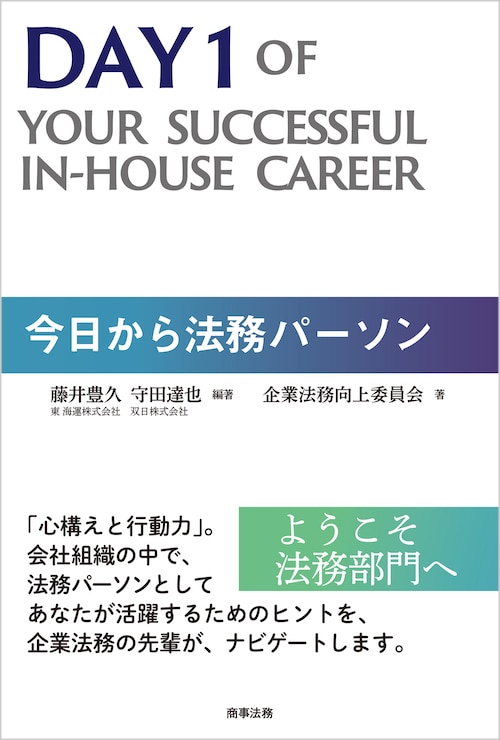
『先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―』
編・著:中野友貴・著
出版社:第一法規
発売年月:2018年
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『新法令用語の常識』
編・著:吉田利宏・著
出版社:日本評論社
発売年月:2014年
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『入社1年目の教科書』
編・著:岩瀬大輔・著
出版社:ダイヤモンド社
発売年月:2011年
法務の先輩2名が推薦する書籍と新人担当者へのアドバイス
Twitterでは数多くの書籍が推薦されましたが、法務業務では具体的にどのように書籍を活用すべきなのでしょうか。本企画についてツイートしていただいた、LAPRAS株式会社 飯田 裕子さん(@Iidasame)、itotanuさん(@itootanu)のおふたりに、実務を念頭に置いたおすすめ書籍や、新人法務担当者の方へ向けたアドバイスを伺いました。
解決したい課題を念頭に置いて書籍を読むことが大切(LAPRAS株式会社 飯田 裕子さん)
LAPRAS株式会社で法務部門責任者を務める。SIer営業、司法書士補助者、士業コンサルグループ勤務を経て、Legal&HRとして2020年4月に同社へ入社し、2020年9月より現職。現在は一人法務として業務を行いつつ、新入社員オンボーディング、Working Environment(働く環境づくり)等バックオフィスを幅広く担当している。また、法務のいいださん(@iidasame)として、法務業務での日々の学びをnote等のSNSで積極的に発信している。
日々の業務にあたるなかではどのような書籍を読まれますか。
飯田さん:
利用する書籍の種類については、大きく以下の3種類に分けられます。
- 社内外の関係者と交渉するうえで参考とする書籍
- 特定の分野について幅広く知るために用いる書籍
- 実務のなかで個別のトピックについて参照する書籍
①について、新人法務担当者の方におすすめしたい1冊は、瀧本哲史・著『武器としての交渉思考』です。
特に私が所属するLAPRASのようなベンチャー企業では、事業部側が適切にリスク把握したうえで事業判断ができるよう、法務担当者は、守るべきラインや発生するリスクを提示して、適切にブレーキを踏むことが主な仕事です。一方で、相談内容にリスクがあったとしても、「リスクがあるからすべてストップしてほしい」といったコミュニケーションでは、事業部側も今後の戦略が取れず、納得感もないため、通用しません。法務は何をリスクとして捉えているのか、その根拠は何か、事業を進めるためにそのリスクはどういうケアをすべきなのか等を説明し、事業部に次のアクションに向けて動いてもらう必要があり、法務にも交渉力が求められるのです。
同書では、開示する情報の範囲を検討したり、あらかじめ複数の交渉ルートを用意したりするなど、交渉にあたっての事前準備の方法を手厚く説明しています。また交渉の落とし所の検討法や、論理だけでは伝わらない相手の説得法といった、実践的な事項にも踏み込んで解説しており、実践的です。
この書籍を読んだきっかけは、当社の役員に薦められたことでした。事業部の人たちがどのような理論に基づいて物事を考えているかを理解できるので、彼らが読んでいるのと同じ書籍を読むことは大切だと思います。
「②特定の分野について幅広く知るために用いる書籍」についてはいかがでしょうか。
飯田さん:
ベンチャー企業に入社した法務担当者の方に1冊だけお薦めするのであれば、後藤勝也/林賢治/雨宮美季/増渕勇一郎/池田宣大/長尾卓・編著『ベンチャー企業の法務AtoZ』です。ベンチャー企業の法務担当者が扱う論点が網羅されており、まずはこの書籍の解説内容を理解できるかが、最低限身につけておくべき知識を備えているかを判断する指標になります。
そのほかAIを用いたサービスを提供する企業であれば、宇佐美誠・編「AIで変わる法と社会 近未来を深く考えるために」や、曽我部真裕/林秀弥/栗田昌裕・著「情報法概説 〔第2版〕」などもおすすめです。これらの書籍による解説内容のすべてが業務に必要な情報とは限りませんが、当該分野の全体感を把握して業務に必要な知識に漏れがないかを確認できます。
「③実務のなかで個別のトピックについて参照する書籍」のなかで、新人担当者へおすすめの書籍はありますか。
飯田さん:
年度が変わる度に通読しているのは「司法試験&予備試験 完全整理択一六法 民法」です。民法ではある条文が他の条文を準用していることが多いですが、この本ではそうした関係が図表でまとめられており、条文を行き来する必要がありません。
司法試験の範囲以上のことを実務で求められることは少ないですし、ここに載っていない事項であれば顧問弁護士に相談する、という判断基準にもしています。また新人法務の方については原典にあたることが何より重要ですので、この書籍でも条文を都度引くだけでなく、全体として条文を通読することをお勧めします。
書籍に関する情報はどのように手に入れていますか。
飯田さん:
知り合いに聞くことが多いですね。顧問弁護士の先生に案件を相談するメールの最後で、その案件に関わるおすすめの書籍を聞くこともあります。先生は私の理解度もわかっているため、それにあわせた本を教えてくれます。複数名の法務部門であれば、先輩にどの本を読んで勉強したかを聞くのもよいでしょう。
業務の知識を習得するために書籍を選ぶ基準はありますか。
飯田さん:
1冊目はとにかく薄い本を読むことで、その分野や法律の特徴、主な論点などの全体感を把握するようにしています。2冊目は具体的な条文を学ぶために逐条解説を読み、その後は業務で必要となる個別論点を解説した書籍を活用していきます。
契約実務については、条項例が入っている書籍も手元に置いてはいますが、例示されている表現に引っ張られてしまうので、最後まで開かないようにしています。
書店で書籍を選ぶ際は、どのようなポイントを確認していますか。
飯田さん:
まずは前書きを見て、最後まで読み切ることができそうな文体や表現かを判断しますね。また目次で、コラムや余談が少なく要点がまとまっているかも確認します。
また、根拠条文などについて丁寧に記載されていることも重要です。周辺知識を持たない新人の法務担当者の場合、原文にあたることができないと、根拠を聞かれた際に「その本に書いてありました」ということ以上の回答ができず、根拠として弱くなってしまいます。
書籍のなかには、解説の根拠が法律なのかガイドラインなのか、著者の意見なのかが判断できないものもあります。購入するときは書籍の特に後半の章を数ページ読んでみることで、1冊をとおして根拠についてどのように記載されているかを確認できると思います。
新人法務担当者の方へ向け、書籍の活用法についてのアドバイスをいただけますか。
飯田さん:
書籍から情報を得るうえでは、ともすると、勉強のための勉強に陥ってしまいがちです。「事業部の担当者と接点を持ちたい」「この質問に答えられるようになりたい」「特定分野の知識を広く身につけたい」など、解決したい課題を念頭に置いて書籍を読むことが大切だと思います。
『武器としての交渉思考』
編・著:瀧本哲史・著
出版社:星海社
発売年月:2012年
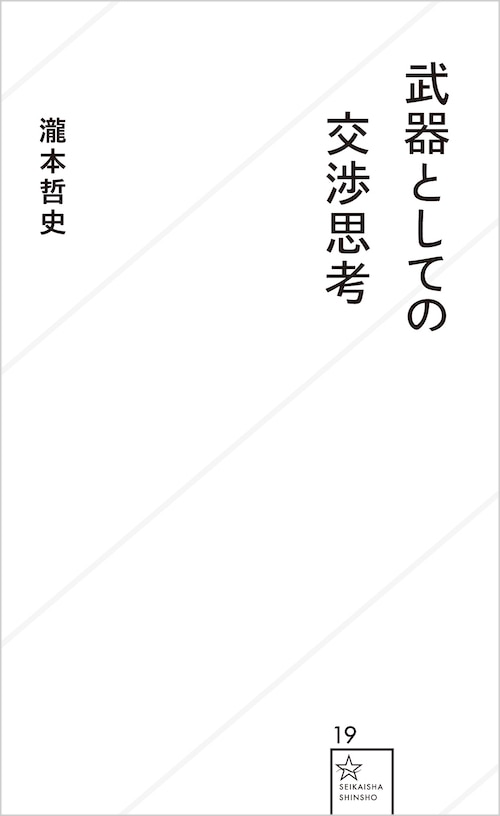
『ベンチャー企業の法務AtoZ』
編・著:後藤勝也/林賢治/雨宮美季/増渕勇一郎/池田宣大/長尾卓・編著
出版社:中央経済社
発売年月:2016年
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『AIで変わる法と社会 近未来を深く考えるために』
編・著:宇佐美誠・編
出版社:岩波書店
発売年月: 2020年
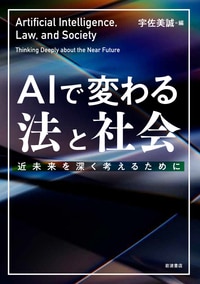
『情報法概説 〔第2版〕』
編・著:曽我部真裕/林秀弥/栗田昌裕・著
出版社:弘文堂
発売年月:2019年
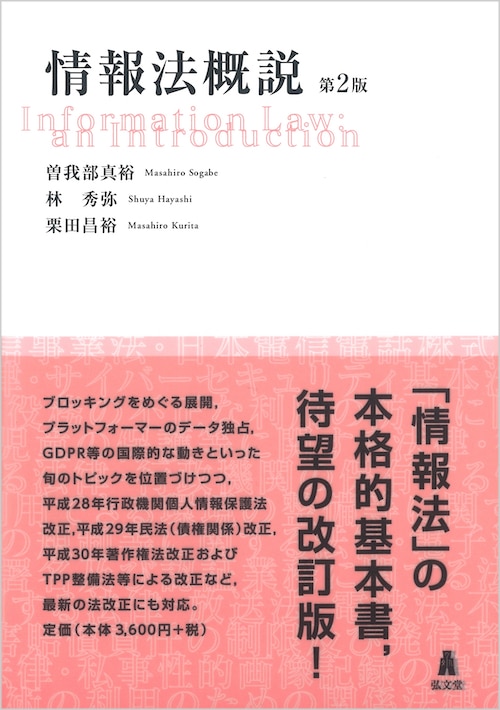
『司法試験&予備試験 完全整理択一六法 民法』
編・著:LEC 東京リーガルマインド・編著
出版社:東京リーガルマインド
発売年月:2020年
おすすめは業務で必要なところから書籍にあたり知識を身につけること(itotanuさん)
メーカー企業の法務部門で管理職を務める。大阪在住。法務関連のトピックを発信するブログ「Legal X Design」を更新している。
法務部門に新たに配属される担当者は、まずどのようなスキルを身につけるべきでしょうか。
itotanuさん:
わかりやすく情報を伝えたり、正しく聞き出したりする能力だと思います。また法務担当者に限りませんが、好奇心が旺盛であること、誠実であることも重要でしょう。
一方、法的な知識は実務を通じて少しずつ身につけていくことが可能です。法学部出身である必要はありません。法学部出身ではない先輩方も、法務分野で数多く活躍されています。
法務担当者としてもまずは一般にビジネスマンとして必要となる能力が求められるということですね。新人法務担当者の方が基礎的なスキルを身につけるうえでおすすめの書籍を教えてください。
itotanuさん:
私からは以下の4冊を紹介したいと思います。
『スキルアップのための企業法務のセオリー 実務の基礎とルールを学ぶ』
編・著:瀧川英雄・著
出版社:第一法規
発売年月:2013年
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―』
編・著:中野友貴・著
出版社:第一法規
発売年月:2018年
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『文章力の基本』
編・著:阿部紘久・著
出版社:日本実業出版社
発売年月:2009年
『図で考える。シンプルになる。』
編・著:櫻田潤・著
出版社:ダイヤモンド社
発売年月:2017年
当社の法務部門に配属された方に必ず通読してもらうのが『スキルアップのための企業法務のセオリー 実務の基礎とルールを学ぶ』です。法務に入ってまず学ぶべきことが体系的にまとめられており、図も多く平易な表現で書かれています。個人的には入門書としてこれ以上の書籍を知りません。
Twitter上でも最も多く名前があがった書籍でした。
itotanuさん:
ほかに法務の基礎知識がない方にもおすすめの書籍としては「先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―」があります。特にPART1では解釈の必要性と5つの解釈のパターンが紹介されており、法解釈の方法を知る入り口として適しています。法務での経験を積んでからも、特定の解釈の方法に偏っていないかなどを再確認するのに使えるでしょう。
またこの本は、自分であればどのように相手を説得するかを考えながら読むとよいと思います。今後、当社でも若手の担当者に、「この本を読んでバナナはおやつに含まれると思うか」を問う課題を出したいと考えています。
メンバーごとの解釈の仕方の特徴を知ることができそうですね。3冊目は文章力について解説した書籍をあげられています。
itotanuさん:
3冊目は阿部紘久・著『文章力の基本』です。法律文書の書き方を指南した良書もありますが、この本が解説するのはもう少し手前の文章の基本的な書き方です。
法務の仕事では、現場担当者から裁判官までを相手にした文章を書くことがあり、いかに少ない言葉で曇りなく物事を伝えられるかが求められますが、文章の基本に関する書籍を読んだことのある法務担当者の方は意外と多くないように思います。また法務の入門書でも、文章の書き方に気をつけるよう指南するものはありますが、具体的なポイントを解説した書籍は多くありません。
同書では、目次において文章を書くための77のヒントが示されており、気になるところから辞書的に引いて使うことができます。法律・法務に特化した文章術の書籍を読み始める前に、まずはこの本を読むことをおすすめしたいです。
4冊目の『図で考える。シンプルになる。』をおすすめいただいたのはどういった理由からでしょうか。
itotanuさん:
法務では、抜け漏れを防ぐため、取引関係者の関係図や取引のフローチャート、契約条件について場合分けするための樹形図など、図を用いて検討する場面が多いです。この書籍では、7種の図が紹介されており、図を用いて情報を伝えたり、引き出したりする方法を身につけられます。
また法務部門では、コンプライアンス教育やプレゼンテーションを行うこともありますので、そのような際にも役立ちます。
書籍に関する情報を入手するためのおすすめの方法はありますか。
itotanuさん:
先輩に聞けるのであればまずはそれが一番でしょう。また最近は若手からベテランの方まで、法務業界の方がTwitterやブログで発信していますので、そうした情報も参考になります。
ただし、必ずいい本と巡り合えるようなテクニックはないと思います。多くの本を手に取り、ときには失敗することも必要でしょう。
いろいろな書籍にあたることで自身にあうものに出会えるということですね。
itotanuさん:
はい。そのほか、同じテーマの書籍を複数読むこともおすすめです。たとえば契約実務については、よく推薦される阿部・井窪・片山法律事務所・編『契約書作成の実務と書式 - 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版』だけを読むのではなく、もう1冊類書を読むべきでしょう。自分が読んだものが少数説の可能性もありますので、考えの違う著者による書籍を選ぶことも大切です。
新人法務担当者の方へ向け、書籍を業務で活用するうえでのアドバイスをいただけますか。
itotanuさん:
法務の仕事は書籍がなければ成り立たないといっても過言ではありません。自分のお金で買った書籍は、法務分野で仕事をするうえで必ず力になります。
一方で、はじめのうちは、基本的な書籍を除き、それほど頑張って書籍を読まなくてもよいとも思います。まずは実務のなかで条文にあたることが何より大切です。目の前の案件や、そのなかで参照した書籍から情報を吸収しきる意識を持つことで成長できるのではないかと思います。
法務は幅広い分野をカバーしていかなければなりません。業務で必要となるところから書籍にあたりつつ、学んだ領域は確実に力にしていくという学び方をおすすめしたいです。
新人法務におすすめの本一覧
法務の新任担当者の方々は、本稿で紹介された書籍やその活用法も参考のうえ、今後の法務パーソンとしての1歩目を踏み出していただければと思います。
なお、Twitterで「#新人法務におすすめの本」のハッシュタグとともに推薦された書籍の一覧は以下のとおりです。まず手に取る書籍を検討する際の一助として活用ください。
Twitterで推薦された「新人法務におすすめの本」一覧(一部抜粋)
【法務】
| 書名 | 編・著 | 出版社 | 発刊年 |
|---|---|---|---|
| スキルアップのための企業法務のセオリー 実務の基礎とルールを学ぶ | 瀧川英雄・著 | 第一法規 | 2013 |
| 希望の法務――法的三段論法を超えて | 明司雅宏・著 | 商事法務 | 2020 |
| 今日から法務パーソン | 藤井豊久/守田達也・編著、企業法務向上委員会・著 | 商事法務 | 2021 |
| 条文の読み方〔第2版〕 | 法制執務/法令用語研究会・著 | 有斐閣 | 2021 |
| 企業法務入門テキスト――ありのままの法務 | 経営法友会企業法務入門テキスト編集委員会・編著 | 商事法務 | 2016 |
| 説得力が劇的に上がる 法務の文書・資料作成術! | 芦原一郎・編著 | 学陽書房 | 2020 |
| 先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本― | 中野友貴・著 | 第一法規 | 2018 |
| 法学部、ロースクール、司法研修所で学ぶ法律知識 主要10法と法的思考のエッセンス | 品川皓亮・著 | ダイヤモンド社 | 2018 |
| 法令用語の常識 | 林修三・著 | 日本評論社 | 1975 |
| 新法令用語の常識 | 吉田利宏・著 | 日本評論社 | 2014 |
| 法学の基礎〔第2版〕 | 団藤重光・著 | 有斐閣 | 2007 |
| 実践!! 契約書審査の実務 改訂版 | 出澤総合法律事務所・編 | 学陽書房 | 2019 |
| アメリカ契約法〔第2版〕 | 樋口範雄・著 | 弘文堂 | 2008 |
| ケースで学ぶ 国際企業法務のエッセンス | 森下哲朗/平野温郎/森口聡/山本卓・著 | 有斐閣 | 2017 |
| 増補改訂 財務3表一体理解法 | 國貞克則・著 | 朝日新聞出版 | 2016 |
| 法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)〔第2版〕 | 田路至弘・著 | 商事法務 | 2018 |
| 会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法 | 土井万二・編集代表、尾方宏行/新保さゆり/内藤卓/橋詰卓司/大塚至正/重松学・執筆、弁護士ドットコム株式会社/株式会社リーガル・編集協力 | 日本加除出版 | 2021 |
| 平成30年8月改訂 印紙税実用便覧 | 川﨑令子・編 | 法令出版 | 2018 |
| 民法案内1〔第2版〕 私法の道しるべ | 我妻榮・著、遠藤浩/川井健・補訂 | 勁草書房 | 2013 |
| 金融から学ぶ会社法入門 | 大垣尚司・著 | 勁草書房 | 2017 |
| 事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック | 塩野誠/宮下和昌・著 | 東洋経済新報社 | 2015 |
【ビジネス】
| 書名 | 編・著 | 出版社 | 発刊年 |
|---|---|---|---|
| 武器としての交渉思考 | 瀧本哲史・著 | 星海社 | 2012 |
| 入社1年目の教科書 | 岩瀬大輔・著 | ダイヤモンド社 | 2011 |
| コンサル一年目が学ぶこと | 大石哲之・著 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | 2014 |
| ビジネスパーソンのための契約の教科書 | 福井健策・著 | 文藝春秋 | 2011 |
| ビジネスパーソンのための法律を変える教科書 | 別所直哉・著 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | 2017 |
| 賢さをつくる 頭はよくなる。よくなりたければ。 | 谷川祐基・著 | CCCメディアハウス | 2019 |
| スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい ~8割の社会人が見落とす資料作成のキホン | 四禮静子・著 | 技術評論社 | 2020 |
| イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」 | 安宅和人・著 | 英治出版 | 2010 |
| 会社はこれからどうなるのか | 岩井克人・著 | 平凡社 | 2003 |
| しんがり 山一證券 最後の12人 | 清武英利・著 | 講談社 | 2013 |
| Tools and Weapons テクノロジーの暴走を止めるのは誰か | ブラッド・スミス/キャロル・アン・ブラウン・著、斎藤栄一郎・翻訳 | プレジデント社 | 2020 |
| サピエンス全史 | ユヴァル・ノア・ハラリ・著、柴田裕之・訳 | 河出書房新社 | 2016 |
| AIに負けない子どもを育てる | 新井紀子・著 | 東洋経済新報社 | 2019 |
「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」は、以下の特徴・機能を備えた法律書籍・雑誌の月額閲覧サービスです。
- 800冊以上の書籍・雑誌のオンラインでの閲覧(2021年6月現在)
- PCに加え、タブレット・スマートフォンによる書籍・雑誌の閲覧
- タイトル・本文について、キーワードによる書籍・雑誌の横断的な検索
新型コロナウイルスによる影響が続くなか、「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」が新しい働き方に取り組む法務ご担当者様の一助になれば幸いです。