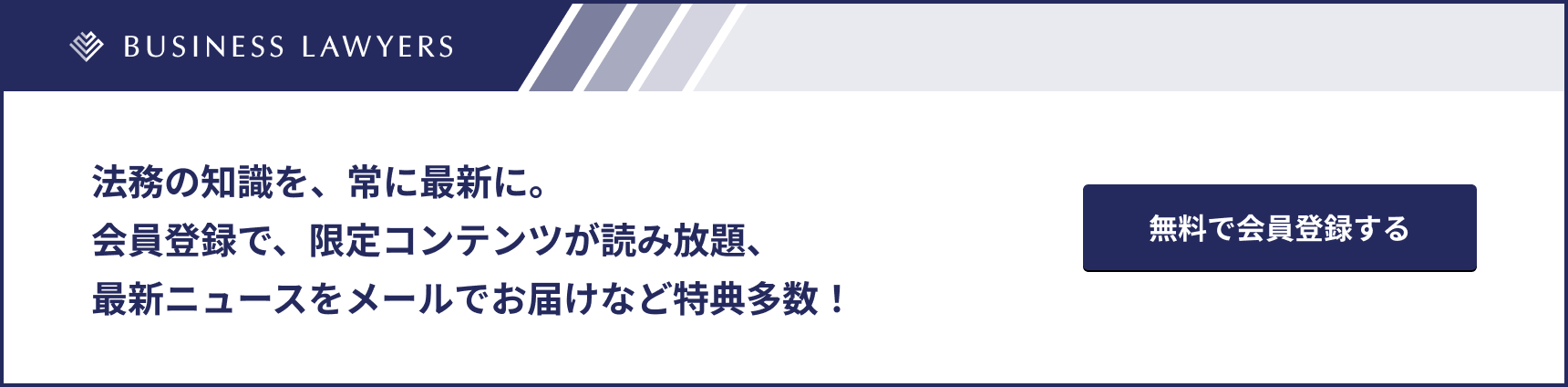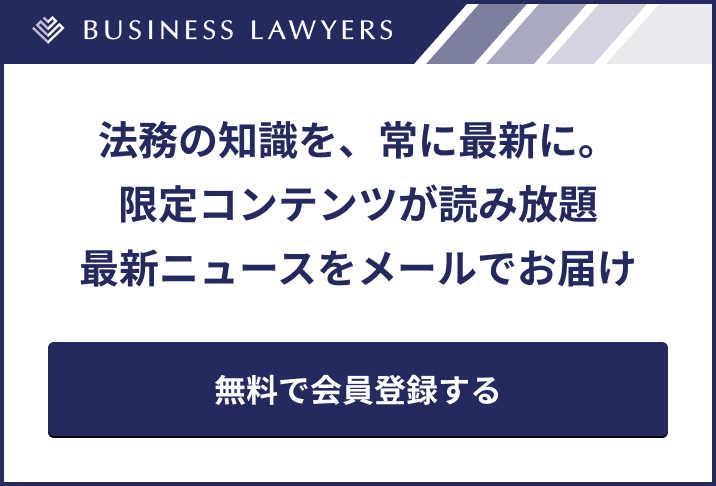リーガルリサーチとは 基本からツールの使い方まで弁護士が解説
法務部
目次
企業実務におけるリーガルリサーチでは、前提となる事実調査のほか、あらゆる法令や、ガイドラインなどのソフトロー、裁判例を調査する必要があります。そのため、以下の流れに沿ってリサーチを行い、経営者や事業部が求める回答を用意する必要があります。
- 事実のリサーチ
- リーガルフレームによる落とし込み
- リーガルリサーチ
- リーガルリサーチ結果の当てはめ
- 事業部(相談者)への回答
また、次の基本姿勢を守ることで、リーガルリサーチを効果的に進めることができるでしょう。
基本姿勢 ② 調査にかける時間を決めておく
基本姿勢 ③ アウトプットは読み手目線で
この記事では「リーガルリサーチ」について、実務で求められるリサーチの基本や進め方、役立つノウハウやツールについて紹介します。
※本稿は、2021年12月7日開催のセミナー「法律知識のアップデートはできていますか?効率的なリサーチ手法とおすすめツールを弁護士が解説」の内容をもとに編集部が構成のうえ、杉浦健二弁護士の監修により制作しています。
リーガルリサーチとは
実務で求められるリーガルリサーチとは
企業実務や弁護士実務におけるリーガルリサーチは、法務系の資格試験問題の答案作成時に求められるリサーチとは異なります。たとえば、民法の試験では「AさんがBさんに怪我をさせた。この場合、何が問題になるか」などと事例が設定されており、それに対して「不法行為である。民法709条が適用される」といったように、設問に対して適用法令をあてはめる流れで考えていきます。
試験では設問に書かれた事実はすべて真実としてみなせばよく、基本的にそれ以上の調査は不要です。「AさんはBさんに本当に怪我をさせたのか。Bさんが怪我と主張しているだけではないか。診断書はあるのか」などと考えなくて良いわけです。さらに、試験科目以外の法律を気にする必要もありません。民法の試験である場合、「ひょっとしたら傷害罪として刑法が問題になるかもしれない」「会社のなかで起きたことであれば、労災の適用が問題になるかもしれない」などと当該科目以外の法律や諸制度について考える必要はないのです。
一方、実務では、そもそも質問の前提となる事実があるのかどうかさえわからないうえに、リーガルリサーチの対象は試験科目のように限定されていません。あらゆる法令やガイドラインなどのソフトロー、裁判例が調査対象になります。
試験問題と実務のリサーチの違い

リーガルリサーチの前提:質問者へのヒアリング
さらにもう1つ気にしておかなければならないのは、聞かれた質問に対して形式的に答えるだけでは、質問者が本当に必要としている回答に辿り着けない可能性があることです。
たとえば、自社のサービスでキャンペーンを実施する際に「今回のキャンペーンが景品表示法に違反しないかどうか調べてください」という依頼を受けてリサーチしたものの、よくよく確認すると米国の消費者も含むキャンペーンで、日本の景品表示法だけを調べて解決する問題ではなかったケースであったり(この場合、米国のFTC法や州法等を確認する必要があります)、「Webサービスの利用規約をつくってほしい」と言われたが、その実態はスマートフォン向けアプリの利用規約であったりするケースなどが考えられます(この場合、各アプリストアのデベロッパー向け規約を遵守する必要があります)。
上記の例は、いずれも質問者の説明不足ではなく、あくまで回答者からのヒアリング不足が原因であると、回答を受ける立場である法務パーソンとしては捉えておく必要があります。質問者がなぜその質問をするに至ったのか、なぜいま回答が必要なのかを、たとえ質問者から面倒だと思われようが、背景事情までしっかりと食らいついて確認することが大切です。
「質問者が聞いてきた質問に(表面的には)答えられているのだから問題ない」というスタンスは好ましくありません。そのような回答者に対して、今後質問が寄せられることはないでしょう。法務パーソンとしては、質問者が置かれている立場を理解し、当事者意識を持って、一歩踏み込んだヒアリングを心がけるべきです。
リーガルリサーチの進め方
事実のリサーチ
ヒアリング不足が発生する原因の1つに、そもそも何をヒアリングするべきなのかがわからない、ということがあります。聞くべき事実を把握するためには、「リーガルフレーム」をあらかじめ準備しておくことが肝要です。ここでいうリーガルフレームとは、法的知識に裏付けられた思考と検討の枠組みと捉えてください。
今回は「顧客のデータを使ってAIを開発したい」と事業部から問い合わせを受けた法務部のケースを例に、リーガルフレームについて具体的に考えてみます。
はじめに、事業部の要望を理解するための事実のリサーチを行います。「『AIを開発』とは具体的にどういう意味か」「顧客のデータとは具体的にどのサービスの顧客のいかなる項目のデータなのか、個人データに該当するのか、すでに手元にあるデータなのか、またはこれから取得するデータなのか」などをヒアリングにより明らかにして、「『個人データに該当する、すでに手元にある既存の顧客データ』を『顧客に対する新サービス提案のために開発する機械学習モデルの学習用データとして使いたい』」といった法的なあてはめができる程度の具体的な内容まで整理します。
リーガルフレームによる落とし込み
次に、具体的に整理した質問内容をリーガルフレームにあてはめて、リサーチ対象を洗い出します。今回の事例におけるリーガルフレームは、大きく分けて「法律に反しないか」「契約に反しないか」という2つの視点から見ることが有益です。法律は、個人情報保護法や著作権法、不正競争防止法など、契約は、顧客と交わした利用規約や秘密保持契約などが対象となるでしょう。
- 個人データの利用が法律に反しないか
・個人情報保護法
・著作権法
・不正競争防止法 など - 個人データの利用が契約に反しないか
・顧客と交わした利用規約や秘密保持契約 など
このようにリーガルフレームを用いて考えていくと、たとえば「自社のプライバシーポリシー内にある顧客情報の利用目的には『商品発送のため、お問い合わせ対応のため』としか書かれていないが、個人情報を学習用データとして用いる場合、この目的もあらかじめ通知・公表しておく必要があるか」といった具体的な問いに落とし込むことができます。このような問いを得ることで、はじめて具体的なリサーチ対象が特定され、法令・ガイドライン・文献などにあたってリーガルリサーチを進めていくことができるようになります。
リーガルリサーチ(法令・ガイドライン・文献などによる具体的な調査)
調べる対象が特定できたところで、法令・ガイドライン・文献などによる具体的な調査へと移ります。ここからが狭義のリーガルリサーチにあたります。
たとえば今回の事例においてリーガルリサーチを実施した結果、『一問一答 令和2年改正個人情報保護法』という書籍で以下のような記載が見つかりました。
①当初の利用目的には該当しない場合や、該当するか判断が難しい新たな目的での内部分析を行うケース(データセット中の特異な値が重要とされる、医療・製薬分野における研究用データセットとして用いるケースや、不正検知等の機械学習モデルの学習用データセットとして用いるケース等)
佐脇紀代志 編著『一問一答 令和2年改正個人情報保護法』16頁(商事法務、2020年)
このステップ以降の当てはめや事業部への共有について説明する前提として、リサーチ結果からどのような解釈が行えるかについて簡単に紹介します。まず、大命題として、個人情報は、あらかじめ公表等している利用目的の達成に必要な範囲内でしか取り扱えないというルールがあります(個人情報保護法16条1項(令和3年改正法の施行後は18条1項、以下同じ。)。利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱おうとする場合には、本人の同意を得なければなりません。
上記の文献では、仮名加工情報の利活用例である、当初の利用目的には該当しない場合や該当するか判断が難しいケースの一例として、不正検知等の機械学習モデルの学習用データセットとして用いるケースがあげられています。
仮名加工情報とは、令和2年の個人情報保護法改正で新たに導入された制度で、個人情報を仮名加工情報に加工すれば、仮名加工情報については個人情報の利用目的を無限定に変更して利用することが可能となる制度です。逆に言えば、当初定めた個人情報の利用目的から「機械学習モデルの学習用データセットとして用いる目的、当該機械学習を経たうえで実現したい目的」が読み取れないような場合は、個人情報を仮名加工情報に加工して、利用目的を変更したうえで利活用しましょう、と文献は述べていると理解することができそうです。
とすれば、個人情報を機械学習モデルの学習用データとして用いる場合は、個人情報取得時に公表等していた利用目的において、少なくともこのような利用目的が読み取れる必要があると捉えておくのが無難ではないか、と整理することができます。
リーガルリサーチ結果の当てはめ
リーガルリサーチによって一定の見解を得ることができたら、実際に事業部(相談者)による相談内容に当てはめます。今回の事例では、顧客データ取得時に公表等していた利用目的において「商品発送のため、お問い合わせ対応のため」としか書かれていませんでしたので、この記載だけでは、「顧客に対する新サービス提案のために開発する機械学習モデルの学習用データとして利用すること」は、目的外利用と判断されるリスクが否定できません 1。ここまでが、リサーチを行ったうえでの検討事例への当てはめのフェーズです。
事業部(相談者)への回答
上記の当てはめにより一定の見解に至ったところで、その結果を事業部(相談者)に回答します。大切なのは、結論を前出しすることです。今回の事例であれば、まず冒頭で「現在のプライバシーポリシーに記載された『商品発送のため、お問い合わせ対応のため』という利用目的のままでは、顧客データを新サービス提案のための機械学習モデルの学習用データとして用いることは、個人情報保護法16条(改正後18条)1項 2 に抵触する可能性が否定できません」などと伝えることになります。
もっとも、法務パーソンとしては、「できません」という結論だけを伝えても事業が前進しないため、さらに対案を提示できるよう努めるべきです。たとえば、改めて顧客本人らから同意を取得できる余地があるのか、仮名加工情報や匿名加工情報に加工する方針は考えられないか(これらの情報に加工した場合であっても、機械学習の精度に大きな影響はないかについてもあわせて検討を依頼する)などが考えられるでしょう。
特に回答のボリュームが大きくなる場合には、法的三段論法に基づいて「前提事実」「適用法令」「当てはめ」をきちんと書いて対策を示すことが重要となります。ここまでが、リーガルリサーチの流れの一例です。
結論
現在のプライバシーポリシーで公表している『商品発送のため、お問い合わせ対応のため』という利用目的のままでは、顧客データを新サービス提案のための機械学習モデルの学習用データとして用いることは、個人情報保護法16条(改正後18条)1項に抵触する可能性(目的外利用となる可能性)が否定できない。
対策
そこで以下の方針が考えられる
①本人同意を取得する(個人情報保護法16条1項)
②匿名加工情報に加工する
③仮名加工情報に加工する
理由
(1)前提とした事実
(2)適用法令と解釈
(3)あてはめ
(4)対策
リーガルリサーチに求められる基本姿勢
ここまで説明した点に加えて重要となる、リーガルリサーチに求められる基本姿勢を3つ紹介します。
基本姿勢① リサーチが甘いことで会社が被る最大限のリスクを認識する
リーガルリサーチが甘かったり回答が誤っていたりした場合、罰則や許認可の取消、レピュテーション下落といった損害を会社が被るリスクがあることを、回答者である法務パーソンはまず認識しておく必要があります。
基本姿勢② 調査にかける時間を決めておく
時間を限定しないと際限なくリサーチをしてしまいがちであるため、あらかじめ調査に掛ける時間を決めておくことをおすすめします。特にまだリサーチに慣れていない新人の方であれば、15分〜30分単位で時間を短く区切り、「ここまでのリサーチ結果」という形でその都度簡単にアウトプットのアジェンダを作成することを繰り返していきましょう。
リサーチを任せた上司の立場からすると「いま何を調べているのか」「何合目まできているのか」「中間報告がないと不安」と感じることがあります。特に丸一日以上掛かるようなリサーチの場合は、「いまここまで調べました。これから◯◯を調べます」といった形でこまめに報告すると良いでしょう。
基本姿勢③ アウトプットは読み手目線で
2-5でも触れましたが、アウトプットは結論を前出しするようにしましょう。また「Noです」と言う場合も、可能な限り対案を付記するように努めると喜ばれます。「Yesです」という場合でも、事実関係が異なる他の事案でその回答だけが一人歩きしてしまうことを防ぐために、「この事実関係、前提条件のもとであれば可能です」といった形で、回答の射程が及ぶ前提条件をきちんと明示するよう心掛けると良いでしょう。
リーガルリサーチに役立つ知識をアップデートするノウハウ6選
リーガルリサーチを効率的に行うためには、普段から法律知識をアップデートしていくことが求められます。その際、法改正や新刊の情報などを闇雲に「集めにいく」のではなく、自然に情報が「集まってくる」体制と習慣をつくっていくことが重要です。下記では、そのノウハウの一部を紹介します。
法律雑誌を定期購読し、毎号目次だけは必ず目を通す
定期購読している法律雑誌の目次に目を通して、気になる記事があれば、その場ですぐに読むか、「後で読む」という付箋を付けて「付箋消化タイム」を週1回など定期的に設定し、まとめて読むようにします。日常生活のリズムに組み込んで習慣化することがポイントです。1人で続けていくのが難しいということであれば、複数のメンバーで協力して法律分野や法律雑誌ごとに担当を決めて行うのも良いでしょう。
メールマガジンの活用
週2回無料で配信される「商事法務メルマガ」は、新刊や法改正などの情報についてしっかりと丁寧に解説されています。BUSINESS LAWYERSをはじめとするリーガルポータルサイトのメールマガジン購読もおすすめです。
Twitterの活用
Twitterは、情報発信を目的として利用されることも多いですが、情報収集にも大変役立つツールです。弁護士や専門家の方のなかには、まだどの刊行物にも掲載されていない最新の情報や議論を積極的にTwitterへ投稿されている方もいます。そのほか、法律系出版社やリーガルポータルサイトのアカウントなどもフォローしておくと良いでしょう。
加えて、「PICK UP! 法令改正情報」という、改正法令の新旧対照表を無償で提供している新日本法規出版のアカウントもおすすめです。
Facebookページの活用
法務関係のセミナーやイベント、学会情報は、Facebookページで告知されることも多いです。重要な学会や法務グループなどの情報はトップに表示される設定にしておき、見逃さないようにすると良いでしょう。
Googleアラート
「Googleアラート」は、「個人情報保護法」「ガイドライン」など、集めたい情報のキーワードを設定しておくことで、関連トピックがメールで通知されるサービスです。自社の名前を登録しておけば、炎上の早期検知にも活用することができます。
リアル書店での書籍との出会い
現在はさまざまな電子書籍サービスが出てきていますが、リアルの書店での本との出会いも欠かせないと考えています。電子書籍サービスではレコメンド機能が働くことで、良くも悪くも興味関心がある分野の書籍に囲まれ続けることになるため、予期せぬ良書との出会いを得るためには、リアル書店への定期的な訪問は欠かせないでしょう。
リーガルリサーチに役立つ有料サービス6選
クラウドサインのリーガルメディアである「サインのリ・デザイン」が公開している「日本のリーガルテックカオスマップ2021」3 を見てもわかるように、昨今のリーガルリサーチツールの充実には目を見張るものがあります。
リーガルリサーチの肝は「検索対象を効率的に絞ってノイズを減らせるか」です。たとえば、Googleで「〇〇法」などと検索しても、作成者が不明であったりリサーチの根拠とするには不安を覚える情報も多数表示され、効率的なリサーチを進めづらくなっています。ツールを活用して、特定の分野における専門的で良質な情報にあたっていくことが重要です。下記では、リーガルリサーチに役立つツールを紹介していきます。
論文、書籍検索サービス
論文や学術誌などを検索できるデータベースサイトとしては、日本語文献の場合、「CiNii(NII学術情報ナビゲータ)」や「J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)」、英語文献の場合は「Google Scalar」が有益です。また、「国立国会図書館サーチ(NDL Search)」では、国立国会図書館をはじめ、全国の公共・大学・専門図書館や学術研究機関などが提供する資料、デジタルコンテンツを統合的に検索することができます。
全国の図書館の蔵書とその貸し出し状況を横断検索できる「カーリル」や、郵送または宅配便で複写製品を受け取ることができる国立国会図書館の「遠隔複写サービス」などを活用するのも良いでしょう。
判例検索サービス
判例検索サービスについても、様々な事業者によって提供されています。下記では、現在特に多くの組織で利用されていると思われる主流サービスをあげています。
- 「TKCローライブラリー」(TKC)
- 「D-1Law.com」(第一法規)
- 「判例秘書INTERNET」(LIC)
- 「Westlaw Japan」(ウエストロー・ジャパン)
法律書籍のオンライン閲覧サービス
「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」をはじめ、法律書籍のオンライン閲覧サービスの普及も進んでいます。こうしたサービスでは、電子書籍を通読することもできますが、監修者はどちらかというと「書籍内の情報を横串で検索するためのサービス」だと考えています。検索結果はラインナップされた法律書籍に記載された情報に絞られるため、いわば“良質な法律文献に限定したGoogle”として使うことができるでしょう。
出版社による電子版サービス
独自の電子版サービスを提供している法律系出版社もあります。商事法務の『NBL』、中央経済社の『ビジネス法務』、レクシスネクシス・ジャパンの『Business Law Journal』(現在は休刊中)などのバックナンバーを検索することも可能となっています。
外部弁護士への相談
外部弁護士への相談も有効なリサーチ手段の1つです。最近では弁護士の専門化が進み、非上場企業でも、得意分野ごとに複数の法律事務所を使いこなしているケースが珍しくありません。外部弁護士に依頼する際には、その弁護士のリーガルリサーチの進め方やノウハウを共有してもらうのも良いでしょう。
リーガルリサーチ関連書籍
リーガルリサーチについて学ぶための書籍も出版されています。ここではいくつかピックアップして監修者のコメントとともに紹介します。
- 指宿信、齊藤正彰・監修、いしかわまりこ、藤井康子、村井のり子・著『リーガル・リサーチ(第5版)』(日本評論社、2016年)
リーガルリサーチに関するあらゆる手法が紹介されています。リーガルリサーチについて網羅的に学びたい方におすすめです。 - 田中豊・著『法律文書作成の基本(第2版)』(日本評論社、2019年)
法務の文書をあまり書き慣れていない新人法務の方のみならず、若手弁護士にもぜひ読んでいただきたい良書です。 - 中村智子、五島隆文、安達知彦、森規光・著「リーガル・リサーチ基本のキ」『ビジネス法務』2021年8月号〜2022年1月号連載(中央経済社、2021年)
日本法のみならず、英米法のリサーチ手法も幅広くカバーされているリーガルリサーチに関する『ビジネス法務』の連載記事です。 - 森下国彦、村山由香里、門永真紀・著『企業法務におけるナレッジ・マネジメント』(商事法務、2020年)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所所属の先生方によるナレッジ・マネジメントの手法をベースに、ナレッジ・マネジメントの仕組みづくりやその実践方法が指南されています。
加えて、リサーチ業務に用いるための書籍を探すための情報源について、こちらも監修者のコメントとあわせて下記にて数点列挙します。そのほか、個人の方による書評ブログなども、スクリーニングされていない率直な意見が紹介されており、参考になります。
- 企業法務マンサバイバル「法務パーソンのためのブックガイド『法律書マンダラ2022』」(2022年3月27日、2022年3月28日最終確認)
法分野ごとに読むべき書籍が、レベル別(習熟度別)にマンダラ形式でまとめられています。こちらにピックアップされた書籍を読破できれば、相当な実力がつくことは間違いありません。 - BUSINESS LAWYERS「新人法務におすすめの本 - Twitterでの推薦書籍と、法務の先輩2名による書籍活用のアドバイス」(2021年7月14日)
2名の法務パーソンの方が、インタビュー形式で良書を紹介されています。現役法務部の方視点の実践的なコメントも多く、この春、あらたに法務に配属された方は、まずはこの記事に目を通されるとよいと思います。 - BUSINESS LAWYERS「弁護士が推薦、いま読むべき法律書とリーガルリサーチの心構え(前編)」(2021年2月10日)
岩﨑祥大弁護士、宇賀神崇弁護士と杉浦が、おすすめ書籍やリサーチ業務に関する鼎談をさせていただいた際の記事です。こちらは弁護士視点の記事になるため、ひとつ上の記事とあわせてご参照いただくと面白いかもしれません。
おわりに
判例検索の方法やリーガルライティングの基礎については法学部やロースクールでも教えてもらえると思いますが、実務におけるリーガルリサーチの実践的な手法やノウハウとなると、配属された組織の研修や先輩から受ける指導、そして何より現場での経験が重要になってきます。他方で、法務担当者が自分1人しかいない場合などは、いかにして外部から有益な情報や手法を得る体制を作るかが大事になってくると考えます。
本稿が、これからリーガルリサーチを学ぼうとする方の一助となれば幸いです。
「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」は、以下の特徴・機能を備えた法律書籍・雑誌の月額閲覧サービスです。
- 1,200冊以上の書籍・雑誌のオンラインでの閲覧(2022年3月現在)
- PCに加え、タブレット・スマートフォンによる書籍・雑誌の閲覧
- タイトル・本文について、キーワードによる書籍・雑誌の横断的な検索
新型コロナウイルスによる影響が続くなか、「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」が新しい働き方に取り組む法務ご担当者様の一助になれば幸いです。
-
これに対し、利用目的に「当社の新商品・サービスに関する情報のお知らせ・ご提案のために利用いたします」といった記載がある場合は、新サービス提案のために開発する機械学習モデルの学習用データとして利用することも、この利用目的に含まれていると解釈できる可能性があると考えます。 ↩︎
-
令和4年4月1日の改正法施行後は個人情報保護法18条1項。 ↩︎
-
サインのリ・デザイン「日本のリーガルテックカオスマップ2021を公開」(2020年12月15日、2022年3月3日最終確認) ↩︎