法律雑誌編集部と振り返る2019年
第2回 有斐閣、ジュリスト編集室が注目した2019年の出来事
法務部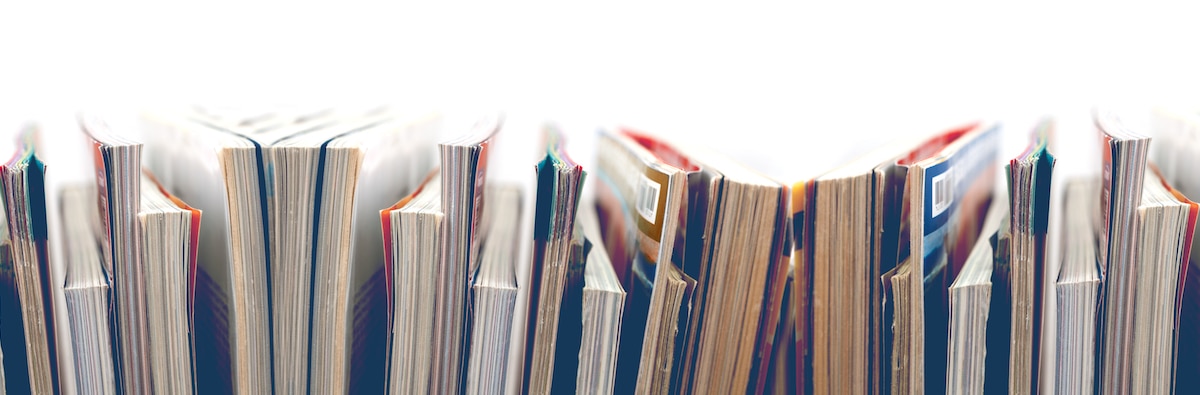
法律業界の2019年を、専門誌編集部のおすすめ記事と特集でたどる本連載。第2回は、株式会社有斐閣 ジュリスト編集室が、国内外の注目トピックを通して2019年を振り返ります。
2019年を振り返って
2019年のキーワードとして、まずあげられるのは、データ利活用の進展です。耳目を集めるAIの活用が進むことで、ビッグデータの価値がさらに高まります。その利用を阻害しない形で、どのように法規制を行うか。
次に、国際的な視点から注目されるのが、国際協調と「自国第一主義」です。気候変動など、世界が一丸となって取り組むべき喫緊の課題が山積しているなかで、アメリカを始めとして世界に広がりつつあるいわゆる「自国第一主義」。イギリスのEU脱退、日本と韓国の関係など、あちこちで起こる流れについて、国際法・国際政治学はどう捉えるのか。
最後に、国内立法で注目されるのは、今年の法改正により法曹養成の新たなルートとして新設されることになる学部3年+法科大学院2年のいわゆる「3+2」。その他の改正項目を含め、法科大学院教育の充実を図る趣旨ですが、それと同時に将来を担う研究者をどう養成するかという重要な問題も残されています。
2019年の注目特集5選
〔特集〕司法制度改革20年・裁判員制度10年
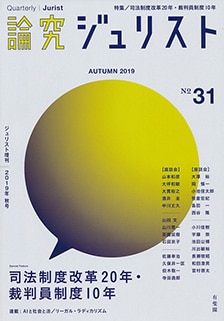
- 掲載号:
- 論究ジュリスト31号(2019年秋号・11月発売)
- 著者:山本和彦・大澤裕ほか
【選出のポイント】
2019年は、司法制度改革の開始から20年、さらに、裁判員制度の開始から10年の節目の年に当たります。これを契機とした本特集は、司法制度改革・裁判員制度のこれまでの歩みを振り返り、今後を展望する内容となっています。
第1部で司法制度改革を、第2部で裁判員制度と刑事司法改革を取り上げています。第1部の冒頭は、法曹養成をテーマとした座談会です。法科大学院の創設から現在話題となっている3+2制度についても扱い、望ましい法曹養成の在り方について積極的に議論を交わします。それに続く各論文では、司法制度改革により各法分野でどのような変革があったかを論じます。さらに、司法制度改革の実現に貢献された先生方による4本のエッセイも必見です。
第2部も冒頭に裁判員制度の10年を振り返る座談会があります。法曹三者と研究者による座談会で、裁判員裁判の実情や現場の課題につき、理論・実務それぞれの視点が絡み合う重厚な内容です。続く各論文も、研究者と実務家それぞれの立場から、刑事司法改革における重要テーマを考察します。
法曹関係者にとっては、これまでの動きを振り返り、これからの司法を考えるうえで、必読の特集です。
〔特集〕「自国第一主義」と国際秩序

- 掲載号:
- 論究ジュリスト30号(2019年夏号・8月発売)
- 著者:酒井啓亘・森肇志・西村弓ほか
【選出のポイント】
近時の国際社会においては、国際協力の実現が強調される一方、主権国家が自国の利益を優先して独自の行動をとるという現象が見られます。たとえば、2019年の米国のパリ協定離脱や日本の国際捕鯨取締条約離脱などがそれにあたります。
本特集ではこうした行動、いわゆる「自国第一主義」と国際秩序の関係につき、最近の具体的な事例をもとに、国際法学・国際政治学の多面的な視点から検討を試みます。
まず西平等論文では「自国第一主義」を理論的に整理します。続けて、小寺智史論文・小林友彦論文・中山俊宏論文がアメリカの動向を、和仁健太郎論文が中国の南シナ海問題を、深町朋子論文がロシアによるクリミア併合問題をそれぞれ論じます。EUにおける問題については、中坂恵美子論文が難民問題を、阿部達也論文が核保有国とNPTの関係を論じます。最後に、日本が関係する問題として、萬歳寛之論文と篠田英朗論文が韓国徴用工判決を、山田哲也論文が日本の国際捕鯨取締条約脱退を論じます。
今後も「自国第一主義」的な傾向が続くことが予想されるなか、これからの国際関係を考えるうえで、示唆に富む特集です。
〔特集〕個人情報保護と利活用の現在
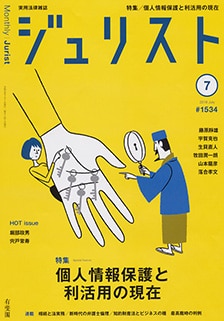
- 掲載号:
- 月刊ジュリスト1534号(2019年7月号・6月発売)
- 著者:宇賀克也・宍戸常寿ほか
【選出のポイント】
情報銀行の認定、リクナビ問題……。2019年は個人情報に係る発展性と課題が盛んに報じられました。個人情報の利活用により生活の利便性が高まる一方で、そのデータの扱い方次第では、思わぬ損害が発生する可能性もあり、個人情報の「保護」と「利活用」のバランスがますます重要になってきました。またビジネスに国境がない現代において、事業者は、GDPR等の越境規制に対しても精確な理解が求められます。
本特集では、藤原靜雄論文でGDPRをめぐる法的課題を明らかにし、特に、個人情報の保護と利活用が問題となる5分野(公的部門・宇賀克也論文、通信分野・生貝直人論文、放送分野・牧田潤一朗論文、医療研究領域・山本龍彦論文、金融分野・落合孝文論文)での保護と利活用のバランスを検討しました。
さらに、巻頭コーナーのHOT issueでは、日本の個人情報保護法研究の第一人者である堀部政男先生にご登場いただき、特定個人情報保護委員会の発足から、GDPRの十分性認定に至るまで、個人情報をめぐる現在の課題について、お話しいただきました。
個人情報保護法制のこれまでとこれからを理解するうえで必読の特集です。
〔特集〕パワハラ予防の課題
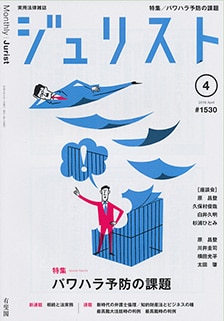
- 掲載号:
- 月刊ジュリスト1530号(2019年4月号・3月発売)
- 著者:原昌登ほか
【選出のポイント】
今年の通常国会で成立したパワハラ防止を義務づける関連法。業務とは関係のないセクハラなどとは異なり、業務上必要な「指導」との線引きは、企業等で指導者の立場にいる方々にとっては、非常に難しい問題です。この特集では、企業のみならず、今年ニュースでよく取り上げられたスポーツ界のハラスメントや学校現場のハラスメントと比較しながら、パワーハラスメントとは何なのか、どうすればそれを予防できるのかという点について、なるべく現場に近い視点から考えてみました。さらに、法的視点のみならず、組織論の視点からの検討も行っています。
パワハラ対策を迫られている企業関係者のみならず、スポーツ団体の関係者や教育関係者にも参考になる内容です。
〔特集〕ブロックチェーンと商取引
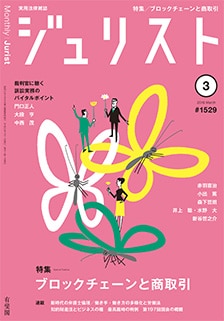
- 掲載号:
- 月刊ジュリスト1529号(2019年3月号・2月発売)
- 著者:赤羽喜治、小出篤、森下哲朗ほか
【選出のポイント】
商取引の分野において大きな注目を集めている分散台帳技術。特定の帳簿管理者を置かずに、インターネット上などで、複数の主体による分散型での台帳管理を可能とする技術のことで、その一種としてブロックチェーンがあげられます。仮想通貨に用いられる技術、というイメージがありますが、分散台帳技術の適用可能性は、金融分野にとどまらず、製造・物流といった様々な分野にも拡がりを見せています。本特集では、分散台帳技術の内容や、その技術がビジネスにどう活かされているか、またその利用によって生じ得る法的課題は何か、多方面から検討を行います。
特徴的なのは、特集の最初に分散台帳技術そのものの解説を置いたことです。次に、分散台帳技術と法制度の関係を論じます。分散台帳技術を利用することに法的な効果や有効性が認められるかという重要な論点です。さらに、実際の取引に分散台帳技術はどのように利用され得るか、金融取引・証券取引それぞれにおける分散台帳技術の適用について検討を試みる論文が続きます。最後に、分散台帳技術を利用した貿易書類の電子化について現状の取組や展望を示した論文で特集は締められます。
商取引における法制度の概念を覆す意欲的な特集です。新たなビジネスのヒントを見つけてみてください。
2020年の注目トピックス
2020年注目トピックスの1つめは、所有者不明土地問題に関する立法動向です。現在法務省法制審議会で議論がなされていますが、今年の私法学会でも取り上げられた注目のテーマで、学問的にも実務的にも大きな問題です。本誌では、4月号で特集予定です。2つめは、12月4日に国会で成立した会社法改正です。株主総会に関する手続や取締役に関する規制など、実務的にも影響の大きい改正です。本誌では、3月号で特集予定です。最後に4月に施行が迫る債権法改正です。その内容もさることながら、どこまで旧法が適用され、どこから新法が適用されるのかという点に関する経過措置は、施行の迫るこの時期、実務的には重要な問題です。このテーマについては、実務的な視点から弁護士の中井康之先生のご論考を本誌1月号・2月号に掲載予定です。是非ご一読ください。
雑誌名:ジュリスト(月刊ジュリスト・論究ジュリスト)
発行元:株式会社 有斐閣
発売日:月刊ジュリスト 毎月25日/論究ジュリスト 毎年2月・5月・8月・11月10日
定価:月刊ジュリスト 1,569円/論究ジュリスト 3,035円
URL:http://www.yuhikaku.co.jp/
定期購読はこちら
