スタートアップ起業家の「法」との向き合い方
第6回 「世界中の信用を評価し、資本主義をアップデートし続ける」小川社長が語るイノベーションを実現する規制のあり方-VALU
ベンチャー
シリーズ一覧全6件
近年、デジタルの世界にとどまっていたインターネットがリアルの世界を侵食し、UberやAirbnbといった既存産業の法規制と衝突するプロダクトが生まれている。また、ブロックチェーン技術といった既存の法律が想定していない技術革新が起き、次々と制度的な対応も迫られている。このような環境変化のなか、スタートアップの起業家は、今まで以上に法制度と対話していくことが求められるようになった。
本連載では、弁護士であり、ベンチャーキャピタリストである株式会社ドリームインキュベータの下平 将人氏がモデレーターとなり、起業家へのインタビューを通じて、スタートアップがどのように「法」と向き合っていくべきかに迫っていく。
第6回は、株式会社VALUの代表取締役である小川 晃平氏にお話を伺った。VALUは、仮想通貨を利用し、個人がブロックチェーン上に個人のトークンを発行し売買ができるサービスを提供している。
小川氏は事業会社でモバイルアプリゲームの開発を担当、シリコンバレーの支社へ赴任をした経験を持つ。帰国後、フリーランスを経て、2016年12月に株式会社VALUを設立。規制当局とコミュニケーションを取りながら、新たなビジネスを築いている小川氏に「法」との向き合い方についてお話しいただいた。
ビットコインで世の中の信用の仕組みに変革を
小川さんがVALUを立ち上げようと思ったきっかけについて教えてください。
2011年頃、大学で金本位制やドル本位制に関する講義を聞いてから、こんなに面白い世界があるのかと思って、「お金の仕組み」に興味を持ちました。翌年にはビットコインのことを知り、2015年頃に本格的に勉強し始めた時には「これは来る」という確信がありました。
その頃、フリーランスとして仕事をしていたのですが、不動産を借りようとした時に、企業に所属していないことが原因で「保証が降りなかった経験」や、クレジットカードを新規発行した時に「限度額が30万円」という経験をしました。フリーランスとして生きていくだけでなく、ユーチューバーやインスタグラマーして生計を立てることだって出来る時代なのに、銀行や社会の評価の仕組みが追いついていないと感じていたのです。
そういう思いを抱えているなかで、堀江貴文さん、PARTY社とブロックチェーンのプロジェクトについて話しているうちにVALUのアイデアが出てきました。価値を測るファンクションを持っているのに、お金とは法律の定め方がまったく違うビットコインを使えば、世の中の信用の仕組みを変えられるかもしれないと思ったのです。
改めてVALUの仕組みについて教えてください。
VALUは「VA」と呼ばれる個人のトークンをブロックチェーン上に発行して、それを売買する仕組みです。個人のトークンとは、ファンクラブの会員権のようなものです。
「VA」が仮想通貨に該当するか、事業を行ううえで何が規制されるのかを明確にすることが法的な論点です。
以前は、ブロックチェーン上に乗っているすべてのものが仮想通貨に該当するという見解を持つ人もいたので、資金決済法2条5項2号に定める「不特定の者を相手方として」「相互に交換を行うことができる財産的価値」に該当するか、という「不特定多数性」がポイントになっていました。
今では、ブロックチェーン上にいろいろなタイプのトークン、たとえばゲームなどで用いられる電子アイテムや、暗号アイテムなども出てきたので、「VA」も同じ性質ではないかという考え方も出てきています。金融庁の見解も確認していますが、明確な結論は出ていません。
グレーゾーン解消制度などを使って明確にする方法もあるかと思いますが、どのようなアクションを取られていますか。
JBA (Japan Blockchain Association)の理事として、情報収集をしています。あとは、業界内で有名な弁護士の方々との意見交換にも参加しています。
金融庁のような規制をかける側や、金融市場をコントロールする側としての使命を持っている人たちに対しては「業界団体」や「パブリックコメント」を通じて、正々堂々と議論を進めつつ、経済産業省のような経済発展を使命とする官庁には、私たちが実現してほしいことに関する意見を伝えています。
官公庁のなかには、私たちのサービスを応援してくれている人たちも、反対する人たちもいます。これは当然のことなので、1つ1つ、反対する理由の本質を理解し、サービスを改善しながら、反対する人たちの意見をオセロのように裏返していくことが重要です。

プロフェッショナルの力を引き出すコツ
弁護士の選び方や付き合い方がわからない若い起業家の方々も多いです。小川さんの弁護士選びや、付き合い方のコツのようなものがあれば教えてください。
弁護士だけでなく医師、会計士、税理士、エンジニアも同様に、プロフェッショナルの1人として付き合っています。
プロフェッショナルの方は難しい課題をお渡しすると目を輝かせて検討してくださる方が多いと思っています。しっかりとやりたいことのビジョンを共有しながら、難しい課題について一緒に考えてもらえるよう巻き込んでいくことがプロフェッショナルの方の力を引き出すコツかな、と思います。
当社の事業は新しい規制に関わるので、弁護士も面白いと感じてくれるのではないでしょうか。エンジニアが難しい課題を与えられるとわくわくするのと同じようなものです。
スタートアップに関わる弁護士や法務担当者にはどのような資質やスキル、マインドセットを求めますか。
やりたいことに対して、一緒に解決策を考えてくれる、本当に親身になって考えてくれる人が好きです。この法律があるからダメだと言うような人だときついでしょうね。そういう弁護士と付き合ったことはないですけど。
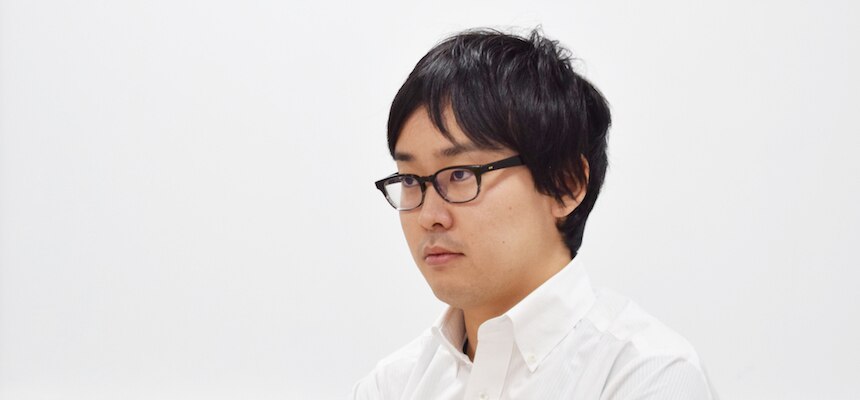
日本の規制づくりに不足しているもの
2017年に改正資金決済法が施行され、仮想通貨についての規制が設けられましたがどのように捉えていますか。
イノベーションを促進しながら、詐欺やマネーロンダリングが起こらないようなバランスを保つことがあるべき規制の姿のはずですが、現状の法律はイノベーションを阻害していると感じます。
過去の仮想通貨流出事件などで問題となった、プライベートキーの管理方法にはあまりきつい規制はかけられておらず、それほど問題になっていないところにきつい規制をかけようとしています。
原因はどこにあると思いますか。
省庁の研究会などで規制に関する意見交換会が行われていますが、技術を理解している人や、業界のことを理解している人があまりにも少ない。どのような視点で人選されているのか疑問です。自分たちの知り合いや気心の知れた人たちを呼んでいるだけなのかなと推測してしまいます。また、省庁と民間の人材の流動性が少ないことも大きな原因だと考えています。
その点、アメリカは規制改革がうまいです。リーマンショック後に次々と規制緩和がされていきました。Airbnbによって個人は保有している自宅を活用することができ、Uberは個人の運転手も営業することができるようになり、誰でもお金が稼げ、利用者は安価なサービスを利用できるようになりました。内向きな事情ではなく、国民にとって良いことをしているだけですよね。人材の流動性に関しても、Dropboxの取締役にライス元国務長官が就任したり、FacebookのCOOのシェリル・サンドバーグ氏も、ビル・クリントン大統領時代のアメリカ合衆国財務長官の下で働いていた経験があります。
人選の部分は、国内の大手企業が低迷している理由に似ていますね。ただ、そういう状況の中で小川さんがルールメイキングに関わっているのはプラスだと思います。
わからないことも多いですが、法律ができる過程に携われることは貴重な経験です。私と同年代の人間ではなかなかできることではありません。10年後、20年後に新たなイノベーションが起こったときに、経験者としてコミットできる可能性もありますよね。
規制を作る側にはどう変わってほしいですか。
国家公務員 Ⅰ 種の人たちには、給料を今の3倍くらい出してもいいのではないでしょうか。国家の税収や経済の成長に対してコミットし、インセンティブをもらえる仕組みのほうが、面白いと思います。
国も会社も仕組みはあまり変わらないので、国が成長した場合はそこに貢献した人たちの給料が上がる方がよくないですか?
今の公務員は稼げないのに、大変な仕事が多い。国家公務員Ⅰ種のブランド力も落ちてきているように見えるので、給料を含めた条件を改善して魅力を高め、国を良くするためにどんどん活躍してほしいです。
小川さんにとって法律とはどんな存在でしょうか。
自分たちにとって武器にも、脅威にもなる存在です。最近になって、法律の意味がわかってきました。法律があり、その下に規則、ガイドラインがあるという構造は面白いしうまくできています。会社に置き換えると最上位にビジョンやバリュー、行動価値などがあって、その下に就業規則や人事評価システムなどの運用ルールがある。構造が似ているんですよね。

バブル崩壊によってVALUの価値は高まる
これから金融領域ではどのような変化が起こると思いますか。
ようやく金融の規制が開いた気がしていて、金融業界もイノベーションが起こるのではないか、大きな革命が起こるのではないかと期待しています。
通貨は30年から50年の周期で白紙になると信じていて、第2次世界大戦で日本は1回リセットされ、土地の価値もほぼなくなりました。その次は1971年のニクソン・ショックによって、金本位制が終わりお金の仕組みも変わりました。
そろそろニクソン・ショックから50年が経ちます。今の通貨の仕組みを白紙にする強力なパワーがやって来るのではないでしょうか。
その時にVALUはどのようなサービスを目指しますか。
大勢の人が使っている面白いサービスを作りたいと考えています。
アメリカの行政機関に勤めている方は、スタートアップに移る例などもあり事業への理解を持っていますが、日本の行政機関の方は圧倒的に流動性が低い。そういう状況下で事業を国にも認められるにはそれしか手段がないでしょう。
事業成長のタイムスパンはどれくらいのイメージですか。
これまでの約10年間は景気が回復しているという論調でしたが、景気は後退局面に入り、早ければ今年、遅くても2、3年でバブルの崩壊が来ると思っているので、そのタイミングで成長させたいです。
バブルが崩壊すると、VALUにどのような影響があるのでしょうか。
金融の本質は評価です。人や会社を評価し、投資することでお金が儲かりますよね。たとえばIPO市場でも、会社の財務諸表などを見て、この会社は高く売れそうだと思ったら買えばいいし、この会社は駄目そうだと思ったら買いません。
今までは安定感のある株が投資の中心でしたが、バブルが崩壊するタイミングで新しいタイプの金融商品が出てくると見込んでいます。評価できるものすべてが金融商品になり得ます。そうなった時に個人を評価する仕組みである、VALUの価値が増していく可能性はあります。
面白いですね。本日はありがとうございました。
(取材・構成 BUSINESS LAWYERS編集部)
シリーズ一覧全6件
