経営者・管理職にも有益 『チェックリストでわかる 実務家・企業のためのスタートアップ法務』著者が語る法務を後回しにするリスクとはPR
ベンチャー
目次
日本経済活性化の鍵として、スタートアップ企業の台頭が期待されるなか、法務面での適切な対応の重要性も増しています。しかし、事業開発や資金調達に追われるスタートアップ企業にとって、法務やコンプライアンスへの対応は後回しにされがちなのも事実。スタートアップ企業に投資、あるいは協業等で関与する企業のリスクも増しています。
「素晴らしい新規ビジネスが法的トラブルで停滞・頓挫することも多い」。
そう語る岡本直也弁護士(弁護士法人岡本)は、このような現状を踏まえ、一般のビジネスマンでも一定の判断ができるように『チェックリストでわかる 実務家・企業のためのスタートアップ法務』(日本加除出版)を上梓しました。
本書では、創業前からイグジット(出口戦略)まで、スタートアップ企業の各成長段階で必要となる法務対応が、実践的なチェックリスト形式でまとめられています。生成AI等の新技術や働き方の多様化など最新の論点も網羅しているため、大企業における新規事業開発やカーブアウトの際にも活用できる内容です。今回は、スタートアップ法務の実務と課題について、法務担当者が知っておくべきポイントを岡本弁護士に聞きました。
岡本 直也 弁護士
弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)。学習院高等科卒業、慶應義塾大学法学部法律学科卒業、早稲田大学大学院法学研究科修了、東京大学法科大学院修了。株式会社ジェーソン(東証スタンダード上場)社外取締役(監査等委員)。 著書に『Q&A 善管注意義務に関する実務』(日本加除出版、2023年)、『Q&A 競業避止、営業秘密侵害等の不正競争に関する実務』(日本加除出版、2021年)。関連記事はこちら。
スタートアップ企業を取り巻く環境と法務の重要性
近年、日本においてスタートアップ企業への注目が高まっています。この背景についてお聞かせください。
日本の経済力が相対的に低下しているなかで、新しい産業や事業を生み出していく原動力としてスタートアップへの期待が高まっています。世界を見渡すと、アメリカのMATANA(Microsoft、Amazon、TESLA、Alphabet(Google)、NVIDIA、Apple)をはじめ、スタートアップから始まった巨大企業が経済をリードしています。しかし、日本の状況を見ると、世界時価総額ランキング(2024年)トップ50社のうちトヨタ自動車以外の企業が見当たらないのが現状です。
このような状況を打開するため、国もさまざまな支援策を打ち出しています。大企業としても、自社だけでは実現できないイノベーションを、スタートアップとの協業を通じて実現しようという動きが活発化しています。若い世代の新しい発想や技術を活用し、日本経済の活性化を図ろうという機運が高まっているのです。

昨今のスタートアップ企業にとって、法務面での対応はどのような意味を持つのでしょうか。
スタートアップ企業は、営業や事業開発に注力するあまり、コンプライアンスやガバナンスを後回しにしがちです。「とにかく走りながら考える」というスタンスは理解できますが、昨今では非常にリスクの高い選択となっています。
特に近年は、SNSでの炎上リスクも高く、一度でも不祥事を起こすとブランドイメージに致命的なダメージを受けます。商品購入・サービス利用を敬遠されたり、資金調達や人材採用など経営に大きく影響するおそれがあります。しかも、一度ついたネガティブなイメージは簡単には払拭できないうえ、情報社会においてはどこかに記録として残り続けます。IPOを目指す場合は特に、早い段階から法務面の整備が重要です。昭和の時代とは異なり、コンプライアンス違反は経営の致命傷となりかねません。
また、ビジネス慣行自体も大きく変化してきています。かつては「信頼関係があるから書面は不要」「細かいことを言わない方が取引は円滑に進む」という考え方が一般的でした。しかし今や、契約書での適切な取り決めは当然のビジネスプラクティスとなっています。特に最近は、小規模な会社が契約書での取り決めを求めても、「生意気だ」と取引を拒否されるようなことは少なくなってきました。むしろ、言うべきことはしっかり言い、書面に残すことが、健全な取引関係を築く基礎となっているのです。
契約交渉によって、少しでも優位な条件を引き出せれば、事業成長にも良い影響をもたらします。後回しにされがちですが、事業推進と危機管理の両輪を担えるのが法務といえます。
資金調達や労務管理、事業の適法性調査…スタートアップが直面する法務課題とは
法務面での準備を怠ると、具体的にどのような問題が起こりうるのでしょうか。
典型的な例として、創業や資金調達の際、投資契約や株主間契約の内容を十分確認せずに締結してしまっているケースがあります。後になって「こんな条項が入っているとは知らなかった」と問題になることが少なくありません。たとえば、M&Aを行う際に株主の承諾が必要となったり、資金調達や新規事業の展開についても株主の承諾なしには実施できないといった制約が課されていたという経験があります。こういった場合、自社株式の買戻しを検討しても、極めて高額な買取価格が設定されているケースも多いです。
特にエンジェル投資家との契約には注意が必要です。一見、単純な資金提供者に見えても、実は非常に厳しい条件を含む契約書を提示される場合があります。資金が必要なあまり安易にサインしてしまうと、人事権から経営の自由度まで、あらゆる面で制約を受けることになりかねません。
また、労働問題も重要です。スタートアップならではの働き方改革や柔軟な勤務体制を導入する際に、労働法規との整合性を十分検討せずに進めてしまい、後々問題化するケースもあります。特に最近は、偽装請負や労働時間管理の問題が厳しく問われています。IPOの際の審査でも、労務管理は重要なチェックポイントとなります。
IPOの準備には、監査やコンサルティングなど、様々な費用がかかります。上場審査に引っ掛かり上場見送りとなれば、さらに費用が嵩み事業に影響を与える可能性もあります。
新しいビジネスモデルにおける法的対応はどのように行うべきでしょうか。
最近の例でいえば、給与前払いサービスの登場が興味深いケースです。一見すると労働法や金融規制との関係で違法性が疑われるような事業でも、適切な法的スキームを組むことで適法に実現できる場合があります。
私たち弁護士の役割は、単にリスクを指摘するだけでなく、いかに適法な形で事業目的を達成できるかを提案することです。スタートアップ企業が掲げる事業には、AI等の新領域や社会課題の解決を目指すものが多い傾向にあります。しかし、素晴らしいビジネスも違法であれば元も子もありません。走り出す前に事業の適法性を確認しておくと安心感も大きいでしょう。
一方で、インバウンド関連のスタートアップが新型コロナウイルスの影響で苦境に陥ったように、予期せぬリスクに直面することもあります。そうした事態に備え、事業計画の段階からリスク分散を考えておく必要があります。法務面での準備は、そうしたリスクマネジメントの重要な要素となります。
実務で使えるチェックリストを用意。関連する行政ガイドラインや書式も多数収録
本書の特徴について教えてください。
まず、実務で使いやすいチェックリスト形式を採用していることです。スタートアップの経営者や法務担当者、また顧問弁護士の方々が、効率的に重要なポイントを確認できるように工夫しました。細かい理論や解説は他の専門書に譲り、実務において本当に必要な事項を厳選しています。

特に注力したのは、新しい論点の網羅です。生成AI、営業秘密、電気通信事業法、資金決済法など、近年注目されている分野について重点的に取り上げています。また、積極的にコンプライアンスに取り組み、ジョブ型雇用をはじめ新しい働き方にチャレンジする国内企業も出てきています。そうした最新の動向も意識して執筆しました。
また、行政のガイドラインを多く収録しているのもポイントです。実は行政機関も非常に詳細なガイドラインを公開しているのですが、Webで検索しても見つけにくいことが多いです。そうした重要な情報源を、できるだけ多く盛り込むようにしました。ガイドラインの索引も用意しているので、チェックリストで発覚した不明点・疑問点を確認するといった形で活用してもらうとよいかもしれません。ガイドラインで確認すべきポイントを絞ることで、効率的に対応できるはずです。
弁護士に依頼する際、企業法務担当者が留意すべき点はありますか?
重要なのは、早い段階から密なコミュニケーションを取ることです。問題が表面化してから相談するのではなく、事業計画の段階から法的リスクを検討し、適切な対応を取っていく必要があります。特に新規性の高い事業の場合、どの法律が適用されるのか、どの規制に注意すべきかの判断自体が難しいケースも多々あります。
相談の際は、具体的な状況や課題を明確にしていただくと、より適切なアドバイスが可能になります。本書のチェックリストをコミュニケーションツールとして活用していただき、どの部分が不安なのか整理しておけるといいでしょう。弁護士への相談内容が明確になれば、適切なアドバイスや支援が受けられます。契約書のチェックでも、単に法的な適否だけでなく、業界の慣行や相場観などを踏まえたアドバイスも得られるでしょう。
さらに、スタートアップの成長段階に応じて必要な法務対応も変わってきます。資金調達、知的財産管理、労務管理、そしてIPOやM&Aまで、各事業フェーズで重要となる法的課題は異なります。そうした変化に合わせた支援を得るためにも、弁護士との継続的なコミュニケーションが重要です。本書では、こうしたスタートアップの事業フェーズに応じた法務対応を体系的にまとめています。
また、フェーズごとに必要な書式のサンプルや実際の法律トラブル・相談をもとにしたコラムも盛り込んでいます。「こんなトラブルが本当にあるんですか?」と驚かれることも多いですが、前述したエンジェル投資家のようなトラブルも多いので、事前に読んでいただくことをお勧めします。

本書はスタートアップ企業以外の方々にとっても有用だと感じました。
スタートアップ企業に必要な法務対応は、大企業や中小企業でも必要です。特に本書では、新しい論点を多く取り上げているので、非スタートアップ企業の方々にとっても有益な情報源となるはずです。
近年、大企業でもM&Aによる買収や、社内ベンチャーの立ち上げなど、スタートアップ的な要素を取り入れる動きが活発化しています。そうした際に、スタートアップ特有の課題や、最低限押さえるべきポイントを理解する手引きとして本書を活用していただけます。
たとえば、スタートアップ企業は人材も予算も限られているなかで、どのような優先順位で法務体制を整備していくべきかという視点が求められます。これは、大企業が子会社やベンチャー投資先を支援する際にも参考になるはずです。また、カーブアウト(事業の切り出し)や新規事業の立ち上げを検討する際にも、本書のチェックリストが有効です。たとえば株式譲渡契約であれば、買主・売主双方のチェックリストを掲載しています。スタートアップに限らず、幅広い企業で活用できる設計になっています。経営陣や管理職などのリスキリングにも有益な内容になっていると思います。
事業の成長をともに支えるパートナーとして弁護士を活用してほしい
最後に、BUSINESS LAWYERS読者へのメッセージをお願いします。
スタートアップ企業にとって、事業推進のスピードは重要です。しかし、法務面での準備を怠ると、後々大きな痛手を被ることになりかねません。本書を入門書として活用し、自社の状況に応じた法務体制を整備してもらえればと思います。
特に重要なのは、弁護士の効果的な活用です。スタートアップ企業では、大規模な法務部を設置して複数の担当者を配置することは現実的ではありません。とはいえ、1人ですべての法務業務を担当するのは困難を極めます。そのような状況だからこそ、自社に合った弁護士を見つけ、実務や事業計画をよく理解してもらいながら、長期的な関係性を築いていくことが重要です。
弁護士は、単なる相談相手や問題解決の窓口としてではなく、事業成長をともに支えるパートナーとして位置づけてほしいです。抽象的な法律論だけでなく、実務に即した具体的なアドバイスを得るためには、日頃からのコミュニケーションが欠かせません。
私たち弁護士も、時代の変化に応じて新しいビジネスモデルや技術への理解を深め、クライアントのニーズに応えていく必要があります。スタートアップ企業の挑戦を法的側面からサポートし、日本経済の活性化に貢献できれば、これほど嬉しいことはありません。本書が、そうした取り組みの一助となれば幸いです。
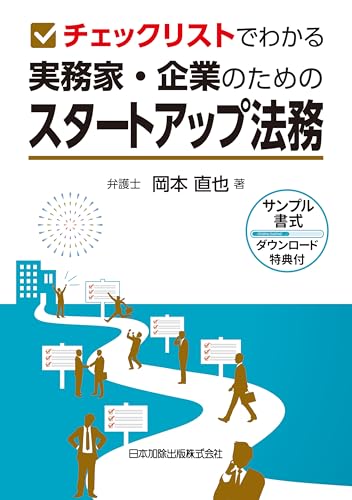
- チェックリストでわかる 実務家・企業のためのスタートアップ法務(サンプル書式ダウンロード特典付)
- 著者:岡本 直也
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発刊年:2024年
