中小企業の事業承継・事業継続に備えて読んでおきたい『中小企業のM&A』 『株主管理・少数株主対策ハンドブック』PR
コーポレート・M&A
目次
近年、中小企業の事業承継・事業継続の問題が深刻になっています。貴重な技術を保有し、従業員を雇用し、社会や経済に必要とされているにもかかわらず、後継者の不在等の理由で企業の存続が危ぶまれるケースが増えているのです。中小企業を継続させるために有効な手段として、「M&A」があります。
「かつて抱かれていたM&Aの負のイメージは、いまやほとんど消滅した」と語るのは、加藤&パートナーズ法律事務所 加藤真朗弁護士です。加藤弁護士は、中小企業の廃業による雇用や技術の喪失を防ぐため、M&Aの活用支援に取り組んでいます。今回は、加藤弁護士の編著書である『中小企業のM&A(第2版)』(日本加除出版、2023年)、『株主管理・少数株主対策ハンドブック』(日本加除出版、2022年)の特長や活用方法、中小企業の法務担当者がM&Aにおいて気をつけるべきポイントなどについて伺いました。
加藤 真朗 代表弁護士
加藤&パートナーズ法律事務所 代表弁護士、関西学院大学大学院法学研究科非常勤講師、神戸大学法学部卒業。主な取扱分野は、契約紛争、M&A、組織再編、事業承継、相続法など。訴訟については、株主代表訴訟や会社経営権をめぐる争いなど。
弁護士実務の他、会社役員の責任、コンプライアンス、内部統制、契約書、M&A、事業承継、相続などをテーマとして、大学院における講義、書籍・論文の執筆、講演・セミナーを行っている。
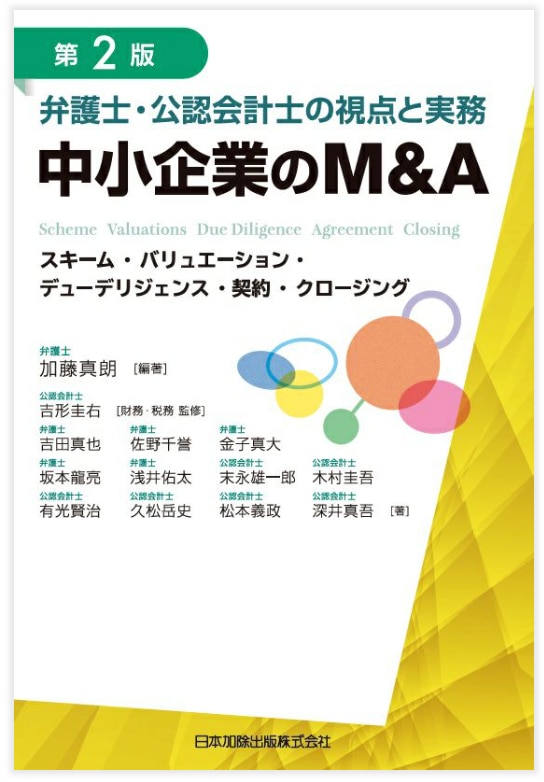
- 第2版 弁護士・公認会計士の視点と実務 中小企業のM&A
- 著 者:加藤真朗
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2023年
- 書籍の購入・詳細はこちら
- BUSINESS LAWYERS LIBRARY会員はこちら
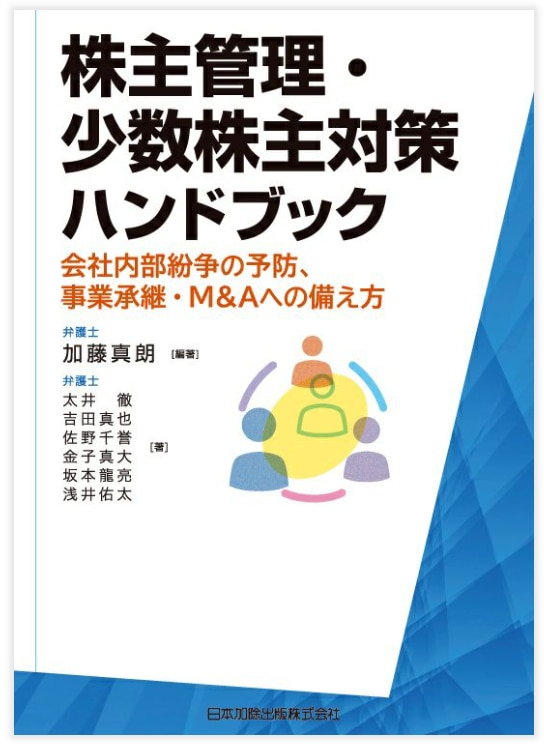
- 株主管理・少数株主対策ハンドブック
- 著 者:加藤真朗
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2022年
- 書籍の購入・詳細はこちら
事業継続の手段として広がりつつある中小企業のM&A
加藤先生が中小企業の事業継続に注力されている背景について聞かせてください。
当事務所は大阪に拠点を置いていることもあり、多くのクライアントが中小企業です。中小企業は、創業者が会社に対して強い思い入れを抱いている場合が多く、適切な後継者が見つからない事業承継問題、親族間の感情のもつれによる内部紛争など、特徴的な問題も多く生じます。
こうした問題を解決する合理的な手段の一つがM&Aです。M&Aで企業価値を向上させる買い手が見つかれば、買い手と売り手でWin-Winの関係を構築することができます。中小企業の技術や雇用を守るため、大企業だけでなく、規模の小さな会社でもM&Aがより広まってほしいという想いをかつてから持っていました。
初版発行の2018年から第2版が刊行された2023年までの5年間で変化はありましたか。
初版のはしがきでは「弁護士等の専門家でも、実際にM&Aに関与したことがあるのは少数派」と述べましたが、現在ではM&Aに対する負のイメージはほぼ消滅し、それに応じてM&Aに関与する専門家が確実に増加しています。
今後も、弁護士や税理士といった専門家がM&Aに積極的に関与する流れがより拡大していくと良いと思っています。

中小企業のM&Aにおいて気をつけるべきポイント
M&Aにおいて、大企業と中小企業の主な違いはどこにありますか。
圧倒的に大きな違いはかけられるコストです。中小企業は、大企業のようなコストをかけられないなか、どの工程を重視するか、費用対効果をどう考えるかがポイントとなります。
一方で、M&Aの知見がないにもかかわらず専門家へのアウトソーシング費用を出し渋ったために、トラブルにつながったパターンも実際にあります。M&Aの業界は不動産業界のような細かな法規制がないためリスクも大きく、一定の慎重さが求められます。
コストの検討と同時に知識も大切ということでしょうか?
M&Aについて、一通りの知識を得た上で、方向性を考えておくことは重要です。専門家やコンサルタントのアドバイスも大切ですが、「誰が本当に自社のことを考えてアドバイスをしているのか」を見分けられる程度には、自分でも勉強しておいたほうがよいでしょう。
また、正解が複数あるなかで、専門家でもベストではない提案をしてしまうこともありえます。そこに対してきちんと議論できるような知識を持っていれば、よりよいM&Aにつなげていくことができます。
M&Aでは各手続きの関連性など、全体像の把握が重要
具体的にどのような点を学ぶべきでしょうか?
全体像の把握が重要です。本書では、M&Aの全体像を提示し、株式取得の他、合併、会社分割、事業譲渡といったスキームの選択肢と、その考慮要素として従業員の承継、許認可・契約、簿外債務、税務上のポイントなどを列挙し、各手続き間の関係性や影響範囲に着目して解説しています。
バリュエーション(企業価値評価)やデューデリジェンス、契約といった工程ごとにM&Aを解説している書籍は他にも多くありますが、よりよいM&Aのためには各手続きの関連性が重要と考え、本書では意識してまとめました。
こうした全体像を把握しなければ、弁護士や税理士などとの適切な連携もできないと思います。
『中小企業のM&A』は体系的かつ網羅的にまとまった書籍であり、教科書的な位置づけとして活用するのにもよさそうです。
M&Aの書籍のなかには、上場企業だけを対象としていると思われるものも多くあります。上場企業の大型M&Aはニュースにもなりますが、日本経済全体では中小企業のほうが圧倒的に多く、中小企業のM&Aの件数は今後もますます増えていくと見られます。
そうした意味では、多くの方々に関係する書籍といえますし、M&A実務に携わる方々にテキストとして使っていただけるとうれしいですね。
第2版でアップデートされた点、なかでも特に意識された部分があれば教えてください。
近年、個人情報に対する意識が高まり、情報やデータの重要性が増している背景から、情報デューデリジェンスの項を新設して詳細に解説しています。また、働き方改革関連法および新しい裁判例を踏まえて、労務デューデリジェンスの項も大幅に加筆しました。
その他では、令和元年の会社法改正により導入された株式交付について法務・税務両面からの解説を加えるなど、法改正、税制改正、新たな裁判例を踏まえて全体的にアップデートしています。

名義株の解消、所在不明株主の株式買取りなど、トラブルになる前におさえておきたい『株主管理・少数株主対策ハンドブック』
『株主管理・少数株主対策ハンドブック』を企画されたきっかけについてお聞かせください。
中小企業のM&Aでは、株主管理も重要な要素のひとつになります。しかし、少数株主対会社、少数株主対支配株主といったさまざまな内部紛争を扱うなか、経営者における株式の重要性に対する認識があまりにも希薄であるという問題意識を持っていました。
実際、創業初期に親族や親しい友人、従業員、取引先に株式を所有してもらったものの、世代交代に伴い、初期の意図とは異なり、多くの争いごとや予想外の損失が発生することや、思いどおりの意思決定ができないという問題が生じます。
本書では株券発行会社と不発行会社の相違といった基礎的な事項の他、名義株の解消、所在不明株主の株式買取り方法、スクイーズアウト、相続人等に対する売渡請求などの具体的な実務について記載しました。
なかでも譲渡制限株式や株価の算定方法など、多くの方々が誤解されている点もあり、そのあたりの理解を深めていただきたいという思いもありました。
発刊後、読者からの評判や反響はいかがでしょうか。
高い評価をいただいており、「株主管理・少数株主対策のバイブル」とお褒めいただく方もいるくらいです。本書を読みながら実務対応を進めたという方、株主管理の必要性を感じて当事務所へ相談に来られた方もいらっしゃいますね。
専門家だけでなく企業の法務担当者にとってもわかりやすく実用的な内容
最後に、BUSINESS LAWYERSの読者に向けてメッセージをお願いいたします。
どちらの本も図表等を入れてわかりやすくまとめているので、専門家だけでなく企業の法務担当者にも役立つ内容だと思います。
『中小企業のM&A』は、買収側、被買収側に関わらず、今後増えていく中小企業のM&Aにおいて“使える”書籍になっていると思います。初版はBUSINESS LAWYERS LIBRARYにも掲載されているため、会員の方は併せてご活用ください。
『株主管理・少数株主対策ハンドブック』は、株式を100%取得している場合以外はすべての企業が関連するテーマですので、常に手元に置いていただき、まさにハンドブックとして利用してもらえたらと思っています。
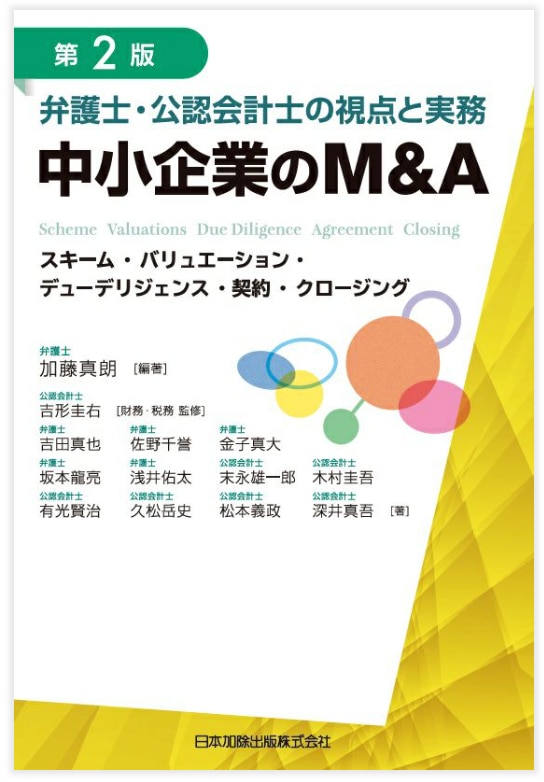
- 第2版 弁護士・公認会計士の視点と実務 中小企業のM&A
- 著 者:加藤真朗
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2023年
- 書籍の購入・詳細はこちら
- BUSINESS LAWYERS LIBRARY会員はこちら
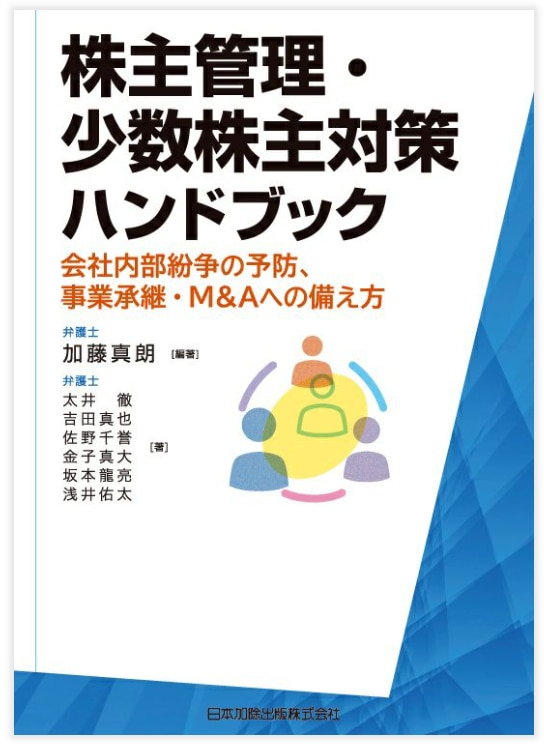
- 株主管理・少数株主対策ハンドブック
- 著 者:加藤真朗
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2022年
- 書籍の購入・詳細はこちら
