複数拠点を持つ法律事務所は書籍のオンライン閲覧サービスをどう選び、使っているか 大江橋法律事務所のBUSINESS LAWYERS LIBRARY導入・活用例
法務部
目次
「人に、社会に、時代に、『よい事務所をつくる』」という精神のもと設立された弁護士法人大江橋法律事務所。設立の地である大阪に加え、東京、名古屋、上海と複数の拠点を展開する同事務所では、リーガルリサーチやナレッジマネジメントにどのように取り組んでいるのでしょうか。リサーチの体制や書籍のオンライン閲覧サービス「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」の活用状況について、同事務所のパートナーであり図書担当を務める長澤哲也弁護士に伺いました。
国内外のオフィスで蔵書を一覧化して共有
貴所の特徴や業務領域について教えてください。
当事務所には約150名の弁護士が所属し、国内では大阪、東京、名古屋に拠点があります。大阪、東京にはそれぞれ約70名ずつ、名古屋には3名の弁護士が常駐しており、海外では上海にも日本人弁護士が所属するオフィスがあります。こうした体制から、いかに多拠点間でリサーチの環境を整えるかは、従来から重要な課題でした。
また当事務所に所属する弁護士の特徴として、個々人レベルにおいても、特定の分野に特化するだけではなく、幅広い分野を扱っている者が多いことがあげられます。そのため、日々の業務においてリサーチを行う領域が広く、多様な分野の書籍等へのアクセスを容易にすることに意を払っています。
リサーチの環境は、従来どのように整備されてきましたか。
当事務所では、誰か1人でも必要だと判断した書籍は基本的に購入しています。創設者がもともと学者志望であったこともあり、記念論文集など稀少な書籍も昔から積極的に受け入れています。他方、古い文献など大阪にあって東京にない書籍やその逆のものもあります。そのため当事務所では、各オフィスが所有する書籍の一覧をデータベース化しており、検索して読みたい書籍が見つかれば、その書籍があるオフィスの司書に連絡することで速やかに必要な情報にアクセスできる体制をとっています。
出勤頻度の低減のために書籍のオンライン閲覧サービスを導入
多拠点間での情報共有体制やデータベースも備えられているなか、BUSINESS LAWYERS LIBRARYをご利用いただいています。書籍のオンライン閲覧サービスを必要とされた背景をお聞かせください。
やはりコロナ禍がきっかけです。在宅勤務を行うアソシエイトの弁護士から「リサーチのためのツールを導入してほしい」という声が上がりました。また出勤者数を減らし、司書の出勤日も限定されることとなりました。弁護士が出勤する大きな理由の1つが「本を調べに行く」ことになりつつあったなか、出勤頻度を下げなければいけないと考えていたところで、書籍のオンライン閲覧サービスの導入を本格的に検討しはじめました。
2020年前半のコロナ禍になったばかりの時点では、サービスの利用にあたって、事務所が費用を出して利用者各自が契約する方法を取りました。BUSINESS LAWYERS LIBRARYを契約した人もいますし、他社のサービスを契約した人もいます。各メンバーによるサービスの利用が進むなか、事務所内でのニーズが高かったため、2021年2月、事務所全体として正式にBUSINESS LAWYERS LIBRARYを契約することにしました。
各社のサービスを比較検討された際、どのような点を重視されましたか。
サービスごとに特徴がありますが、まず気にしたのは収録書籍です。一方で、検討要素は、現時点で収録されている書籍の数量や中身だけではありません。どのサービスも今後収録点数は増えていくはずだと思います。最終的な決め手となったのは、サービスの使いやすさでした。
特に、リサーチのためにオンラインで検索すると最近はBUSINESS LAWYERSの記事を目にすることが多いですよね。ライトな調べ物に関して、BUSINESS LAWYERSは記事と書籍の両輪によりワンストップで応えてくれます。リサーチに関して総合的にサービスを提供しており、同じような使用感で活用できる点もBUSINESS LAWYERS LIBRARYを選択した理由の1つでした。

効率的な下調べにBUSINESS LAWYERS LIBRARYが役立つ
リサーチ業務はどのような場面で行われることが多いでしょうか。
リサーチ業務には大きく2種類あると思います。1つは、ある分野の概要を把握するための下調べとしてのリサーチ、もう1つは、当該分野・論点について最新の状況を深く調べるためのリサーチです。弁護士にとって後者のリサーチが生命線となりますが、前者の下調べを行うことも意外と多くあります。
下調べとしてのリサーチを行う際は、まずどのような情報から順に調べられますか。
手早く、効率的に、その分野の最新の全体像を知りたい、というのがライトな下調べをする際のニーズです。リサーチにかけられる時間は限られていることが多いなか、必ずしもコンメンタールや詳細な立法資料を参照することが最適とは限りません。無駄な時間をいかに減らすか、という考え方も重要です。そのため最近は、下調べではBUSINESS LAWYERS LIBRARYを使って検索をかけ、情報を得ることが多くあります。
リサーチした結果はどのように扱われていますか。
各自がまとめたリサーチ結果は事務所内の共用データベースに格納するようにしており、事務所のメンバーであればいつでも検索して閲覧できます。ある分野を深堀りして調べたいときに目を通すことが多いですね。
また、私は所内で、弁護士登録1年目の若手に対するリーガルリサーチの研修も担当しているのですが、指導のなかで「リサーチした内容は成果物としてまとめよう」と伝えています。深く調べるリサーチでは、「この論点については自分が一番詳しい」と思える程度まで調べ上げることを求めており、その成果物を文書にまとめておくことは、自分を含む後人に有益であるはずだからです。作成する成果物はパートナーへの提出資料や自身のための手控えなど形式を問いませんが、できれば論文など世に出る形にしたいものです。出版社の刊行物に掲載されることは、若手弁護士の1つの目標になっています。
検索結果は、想定外の関連トピックにも気づかせてくれる
BUSINESS LAWYERS LIBRARYは主にどのような場面で利用されていますか。
先ほどお話ししたような下調べを行う際や、リサーチの最初のとっかかりをつかむうえで、キーワード検索により表示された本を閲覧することが多いです。また「この本を読みたい」と書籍のタイトルをピンポイントに検索する場面もあります。最近では、刊行年が新しい『改正債権法コンメンタール 1』などをよく調べましたね。

もう1つ便利な使い方は、書籍内でのキーワード検索です。これにより書籍内で特定のキーワードに言及しているページを一覧で表示することができます。キーワードが載っているページを見返すために、紙で所有している書籍についてBUSINESS LAWYERS LIBRARYで検索をかけることもあります。紙の書籍にも索引がありますが、情報量が不足していることが多く、全文検索ができることは大きな付加価値となります。また、デジタルでの全文検索であれば、前後の文章も表示されますので、直感的な絞り込みもしやすくなります。知りたい内容がどのページに載っているかを漏れなく調べられるのはデジタルならではですよね。
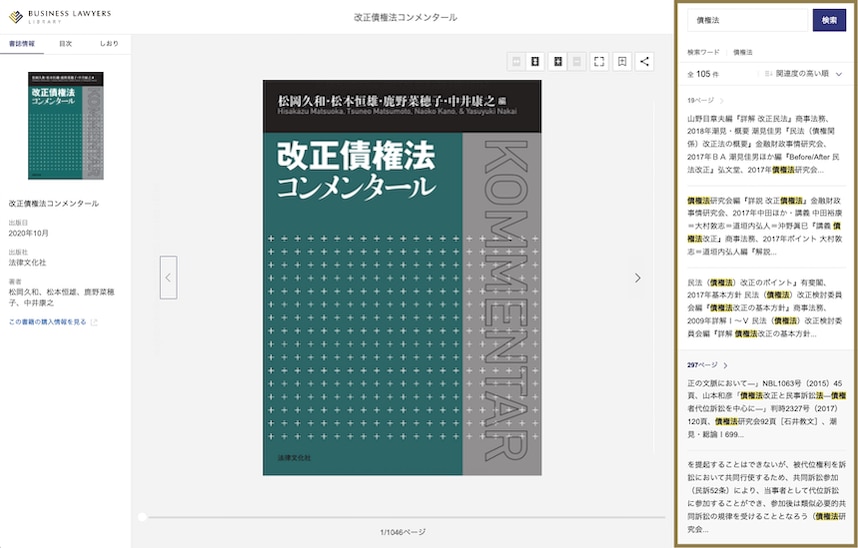
閲覧する書籍はどのように選択されていますか。
たとえば下調べとしてキーワードで検索する際であれば、ある程度絞ったうえでざっと目を通し、そのなかで1、2冊を選んで読んでいます。選ぶことが多いのは、調べたいトピックについて正確かつわかりやすく解説していそうな教科書的な書籍のなかで、刊行年が新しいものですね。「情報の鮮度」はリサーチにおいて大きなウェイトを占めます。また扱うことが少ないマイナーな分野について調べることも多いです。
そのほか、民法、民事訴訟法、刑法などの基本法について調べる場面もあります。基本法であっても普段扱わない分野もあり、最新の判例や学説の状況を十分にフォローできていないことがあります。もっとも、勘所はわかっていますから、過去の理解が今も通用しているか、最新の情報をさっと確認し、アップデートできれば十分ということも多くあります。そのような場合にもBUSINESS LAWYERS LIBRARYが役立っています。
利用開始後に感じたサービスの活用メリットなどはありますか。
ある分野についてリサーチを行うなかで、事前に想定していなかったトピックの書籍が検索結果に表示されることで、「この分野も関係するのか」と気づけることがあります。副次的に関わる分野にまで広げて調べることができるのは、リサーチにおいて有用だと思います。
また書籍の内容まで閲覧しなくても、検索結果を見ることで、どの本にどんなことが書いてあるのかを大まかに知ることができます。さっと検索するだけでも、下調べというリサーチの目的の一部は果たせています。
貴所内ではどのような方がBUSINESS LAWYERS LIBRARYをよく活用されていますか。
若手の弁護士が1番使っていますね。これは様々なトピックについて全体像を把握しないといけないことが多いためです。
特に当事務所では、若手弁護士は毎年仕事をローテーションして、扱う分野を変えています。1つの分野に担当を限定するのではなく、できるだけ幅広い分野を扱えるようにするためです。パートナーは、誰がどの分野を担当したことがないかを確認しながら、若手弁護士が経験していない分野をできるだけ減らしていきます。若手弁護士としては、毎回、扱う分野について「知らない」状態からのスタートとなるので、大まかにでも全体像を把握するニーズが高いのです。
30年にわたり蓄積してきたナレッジを一層活用していきたい
リサーチのデジタル化やナレッジマネジメントに関して、貴所として今後どのように取り組んでいきたいとお考えですか。
ナレッジマネジメントは今後も検討を続ける大きな課題です。実は当事務所は早くからデータを貯めてきており、1990年代からのデータがすべて残っています。
蓄積したデータについて、これまでは全文検索で探すことができていましたが、情報が多くなればなるほど、目的の情報に効率的かつ早くたどり着くためのスキルやツールが必要になります。契約書のひな形や一部の意見書などは分野別、種類別のタグをつけて検索しやすくしていますが、今後は取組みを他のすべての文書へと広げ、あらゆる情報を皆で効率的に共有できるようにしたいですね。
今後、BUSINESS LAWYERS LIBRARYに期待される点をお聞かせください。
BUSINESS LAWYERSとBUSINESS LAWYERS LIBRARYの連携にも期待したいです。企業法務に関する多くのコンテンツを掲載しているサイトが母体としてあるわけですから、今後は、たとえばBUSINESS LAWYERSのサイト内でキーワード検索すると、記事に加えて書籍まで横串で検索結果に表示されるようになったりすると便利だと思います。
本日はありがとうございました。
(写真:弘田 充、文:枚田 貴人、取材・編集:BUSINESS LAWYERS 編集部)
「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」は、以下の特徴・機能を備えた法律書籍・雑誌の月額閲覧サービスです。
- 1,800冊以上の書籍・雑誌のオンラインでの閲覧(2024年2月現在)
- PCに加え、タブレット・スマートフォンによる書籍・雑誌の閲覧
- タイトル・本文について、キーワードによる書籍・雑誌の横断的な検索
- AIによる参考書籍の検索アシストとサマリー作成
-
松岡久和・松本恒雄・鹿野菜穂子・中井康之編『改正債権法コンメンタール』(法律文化社、2020) ↩︎
