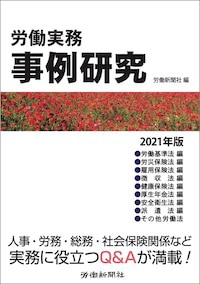労働時間と休憩・休日を労働基準法はどう定めている?
人事労務 更新当社は飲食店で、スタッフの勤務時間が長く、休日も少ないのが現状です。また、お店が混むと、休憩もなかなか取れない状況があり、一部のスタッフから不満が出ています。あるスタッフ(社員)が、「労働時間は労働基準法で決められていて、1日8時間以上働かすのは違法だ。」「休憩時間も取れていないのだから、それも労働時間になるはずだ。」と言ってきており、対応に困っています。
労働基準法では、原則として、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとしています。これを超えて労働させる必要がある場合には、使用者と従業員の過半数代表者の間で時間外・休日労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。また、休憩時間中も仕事をしているとすると、その時間も労働時間となります。
長時間労働が原因とされた精神疾患や健康被害、自殺などの報道がマスコミを賑わせています。違法な長時間労働をさせないよう、しっかりとした労働時間管理が必要です。
解説
目次
労働時間とは
労働基準法上の定義と罰則
「労働時間」とは、休憩時間を除いた実際に労働させる時間で、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことです。労働基準法32条で、労働時間は原則として1日8時間、週40時間以内と定められています。
違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労働基準法119条)。
なお、ここでいう労働者とは、「事業⼜は事務所(中略)に使⽤される者で、賃⾦を⽀払われる者のこと」のことを指し(労働基準法9条)、正社員のほか、パートタイマーやアルバイトなども労働者に該当します。
32条(労働時間)
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
労働時間についてより詳しく理解するために、以下では「法定労働時間」「所定労働時間」「実労働時間」「拘束時間」の意味や違いについて説明します。
法定労働時間とは
「法定労働時間」とは、労働基準法で定められている労働時間のことです。上述のとおり、原則として1日8時間、週40時間以内と定められています(労働基準法32条)。
なお、この法定労働時間を超過した残業を「法定時間外労働」といいます。
所定労働時間とは
「所定労働時間」とは、各事業所で定められた「労働者が働くべき時間」のことです。たとえば、ある会社で始業が9:00、終業が17:00、休憩が12:00~13:00と決まっていた場合、所定労働時間は休憩時間を除いて7時間となります。
なお、所定労働時間を超過した残業時間を「所定外労働時間」といいます。
実労働時間とは
「実労働時間」とは、休憩時間を除いた労働時間のことです。
拘束時間とは
実労働時間と休憩時間を合わせた時間は、労働者が使用者の拘束下にあるので、「拘束時間」となります。

休憩時間・休日とは
労働基準法上の定義と罰則
「休憩時間」とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間です。労働基準法34条で、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
さらに、同法35条では、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけないと定められています。
違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
34条(休憩)
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
- 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
第35条(休日)
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法が定める休憩の3原則
労働基準法には、休憩に関する基本的なルール「休憩の3原則」が定められています。これは、以下の3つの原則から成り立っています。
- 途中付与の原則:休憩は労働時間の途中に与えなければならない
- 一斉付与の原則:休憩は一斉に与えなくてはいけない
- 自由利用の原則:休憩時間を自由に利用させなければいけない
休憩時間に当たらないもの(手待ち時間)
休憩中に電話番をしたり、お店が混んだらすぐに接客したりしなくてはならないという状態は、休憩時間とは認められません。
このように、労働者が使用者の指揮命令下にあるが、現実の労働をしていない時間は、「手待ち時間」として、労働時間に当たるため、注意が必要です。
労働時間に当たるもの/当たらないものの具体例
労働時間に該当するものとそうでないものを大別すると、以下のとおりです。
| 労働時間に当たる | 労働時間に当たらない |
|---|---|
|
|
実際に労働時間に当たるかどうか判断に迷うケースも多いでしょう。以下では、実務上問題となりやすい点を中心に詳しく解説します。
手待ち時間(待機時間)
前述2-2のとおり、実際に作業をしていなくても、呼び出しがあればすぐに作業に取りかかるなど労働者が使用者の指揮命令下にある場合は、「手待ち時間」として労働時間に該当します。
たとえば、以下のようなものがあります。
- 運送業などで、ドライバーが荷物の積み降ろしを待っている時間
- 休憩時間中の電話や来客対応
- 店番の待機時間
- 仮眠時間(例:仮眠中にトラブルが生じた際に対応しなければならない場合等の夜間勤務の警備員)
始業前・終業後の時間
始業前あるいは終業後の時間であっても、以下のような場合は労働時間に当たります。
- 始業前に制服に着替える必要がある
- 始業10分前から始まる朝礼に参加義務がある
- 終業後に清掃を命じられている
始業前後の労働時間について、有名な判例がありますので、以下に引用します。
三菱重工長崎造船所事件(最高裁(一小)平成12年3月9日判決・民集54巻3号801頁)
研修時間
会社が命じる研修の受講時間も、労働時間かどうかの判断に迷うことが多いと思います。これについては、出席が強制かどうか、参加しない場合に不利益な取り扱いがあるかないか、という点が判断のポイントとなります。
出席の強制がない自由参加のものであれば、時間外労働にはならないという通達が出ています。
昭和26年1月20日基収2875号、平成11年3月31日基発168号
時間外・休日労働に関する協定(36協定)
いわゆる「36協定」とは
法定労働時間は、原則として1日8時間、週40時間以内ですから、それを超えて労働させることはできません。ただし、事業場に過半数の労働者で組織する組合がある場合には、その組合、もしくは事業場の過半数労働者の代表者が使用者側と書面で協定し、これを労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能です(労働基準法36条)。
この時間外・休日労働に関する協定は、「36協定」(さぶろくきょうてい)とも呼ばれます。
36協定書では、以下の項目について定めます。
- 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日および1日を超える一定の期間についての延長をすることができる時間または労働させることができる休日 など
時間外労働の上限
ただし、この36協定さえ締結・届出しておけば、無制限に時間外労働をさせられるわけではありません。労働基準法は、原則、1か月について45時間以内かつ1年について360時間以内の「限度時間」を超えない時間に限ると定めています(36条3項・4項)。
この限度時間の例外として、「特別条項付き 36協定」があります。原則は、1か月45時間以内かつ1年について360時間以内までですが、「特別条項付き 36協定」を締結することにより、年6回までは1か月45時間を超え、また年360時間を超えて上限を設定することが可能です。
「特別条項付き 36協定」を締結した場合は、月100時間未満、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させてもよいのは1年につき6か月までとされています。また、2~6か月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内に収まるようにしなければなりません。また、あくまでも「通常予⾒することのできない業務量の⼤幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合」に限りますので、具体的な事由(決算期の対応等)が必要です。
36条(時間外及び休日の労働)
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
- 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲- 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ。)
- 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
- 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
- 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
- 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
- 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
- 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
- 使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間2時間を超えないこと。
- 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間100時間未満であること。
- 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間80時間を超えないこと。
- 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
- 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
- 行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
- 前項の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。
- 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。
【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】
『トップ・ミドルのための採用から退職までの法律知識〈十四訂〉』
発売日:2013年09月13日
出版社:中央経済社
編著等:安西愈
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『労働実務事例研究 2021年版』
発売日:2021年06月14日
出版社:労働新聞社
編著等:労働新聞社
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『労働法[第2版](日評ベーシック・シリーズ)』
発売日:2019年02月20日
出版社:日本評論社
編著等:和田肇、相澤美智子、緒方桂子、山川和義
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

フェリタス社会保険労務士法人