新卒採用する外国人の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する際に必要な期間
人事労務当社では、日本の大学を卒業予定の外国人留学生を正社員として採用したいと考えています。外国人留学生が所持する在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する際、企業の規模等によって申請から処理にかかる期間が異なると聞いたのですが、詳しく教えてください。
新卒採用を予定している外国人留学生の在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更するにあたって、出入国在留管理庁では、申請を行う企業を、その規模等に応じて4つのカテゴリーに分類し、個別の対応を行っています。申請の処理に要する期間はカテゴリーによって異なります。主に上場企業が該当するカテゴリー1、上場していないがそれに準じる企業にあたるカテゴリー2では、申請の処理日数が短縮されているほか、必要書類も削減されるなど手続の迅速性が増しています。
解説
はじめに
現在、多くの企業から外国人従業員の在留申請が出入国在留管理庁になされていますが、申請する企業規模に応じてカテゴリー分けが行なわれ、それぞれ異なる扱いがなされています。原則として上場企業や大企業では提出資料が大幅に省略されていますが、中小企業や新設会社では従来通りすべての提出資料が求められています。
特に教育機関を卒業予定である外国人留学生を採用する場合には、多くの場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければなりません。その際にも企業規模に応じたカテゴリー分けにより対応が異なるので、まずは自社がどのカテゴリーに分類されるかを確認することが大切です。
また、この際の在留申請は、外国人従業員が自分で行う方法が原則となりますが、「申請取次制度」を活用すれば雇用企業の担当者が外国人従業員に代わりに申請を行う事も可能となります(出入国管理及び難民認定法施行規則6条の2第4項、59条の6第2項)。そのほかには、行政書士などの専門家に依頼することも可能ですので、自社に適した方法を検討する必要があります。
雇用企業のカテゴリー
出入国在留管理庁では、新卒採用する外国人留学生の在留資格について、「技術・人文知識・国際業務」への変更許可を行おうとする企業を、その規模に応じてカテゴリー1から4に分類したうえで、各企業の申請に対して、それぞれ個別の対応を行っています。各カテゴリーの分類は以下の通りです。
雇用企業のカテゴリー
| カテゴリー1 | (1)日本の証券取引所に上場している企業 (2)保険業を営む相互会社 (3)日本または外国の国・地方公共団体 (4)独立行政法人 (5)特殊法人・認可法人 (6)日本の国・地方公共団体の公益法人 (7)法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) (9)一定の条件を満たす企業等 |
|---|---|
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
| カテゴリー3 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
出典:法務省ウェブサイト(2020年3月13日最終閲覧)
各カテゴリーに該当するのは、一般的に以下のような企業となります。
| カテゴリー1 | 上場企業 |
|---|---|
| カテゴリー2 | 上場していないがそれに準じる企業 |
| カテゴリー3 | 中小企業 |
| カテゴリー4 | 新設法人など |
申請処理に要する日数
カテゴリー1 および 2
在留資格の変更申請に要する期間はどれくらいでしょうか。カテゴリー1および2の企業からの申請については、「申請受理日から10日程度を目途として申請を処理する」と、比較的短い期間が示されています 1。また、カテゴリー1および2の企業については、在留資格の変更申請の審査に必要とされる添付資料についても大幅に削減されています。よほどの事情がない限り証拠書類の提出等を求められることもなく、審査はほぼ申請書の記載内容のみで行われます。
カテゴリー3 および 4
一方、カテゴリー3および4の企業からの申請については、特に処理に要する期間の目処は示されていません。しかし、法務省から在留審査処理期間(日数)が公表されており、参考になります。令和元年7月から9月許可分の「技術・人文知識・国際業務」における在留資格変更においては平均41.8日とされています 2。
とはいえ、案件によっては処理に2か月から3か月程度かかることもあります。そのため、在留資格を変更する場合は、できる限り早めに申請することが重要となります。さらに、申請の際に必要な添付資料については、原則としてほとんどの場合に主張に対する立証資料が求められます。たとえば、翻訳・通訳の業務内容で外国人従業員を採用する場合には、その雇用契約書や業務内容の説明、取引先企業との契約書、業務量を客観的に判断できる資料、外国人従業員が翻訳・通訳としての能力を有することが判断できる資料などが求められることになります。
さいごに
いずれのカテゴリーにおいても、在留資格の変更申請とは、手続さえすれば必ず許可される、というものではありません。要件を満たしていない場合などには当然に不許可となることがあります。申請は、本人または代理人が最寄りの出入国在留管理局、支局、出張所などに提出することができ、在留資格変更許可の手数料として収入印紙4,000円が必要となります。
在留資格の申請は、外国人従業員が自分で行うことが原則ですが、そのためには出入国管理及び難民認定法に関する一定の理解が必要です。とはいえ、同法は分量が多いうえ、他の法律との関連性も問われるため、日本人であってもそのすべてを完全に理解することは非常にハードルが高いと言えます。仮に本人任せで申請を行った後に問題が発覚した場合、一度主張した内容を覆すことは難しく、取り返しがつかないケースが多くあります。そのため、外国人従業員に手続をすべて任せるのではなく、企業の人事担当者や専門家が適切にサポートすることが重要となります。
また、外国人留学生を新卒採用する際のスケジュールについては「外国人留学生の新卒採用スケジュール」をご参照ください。
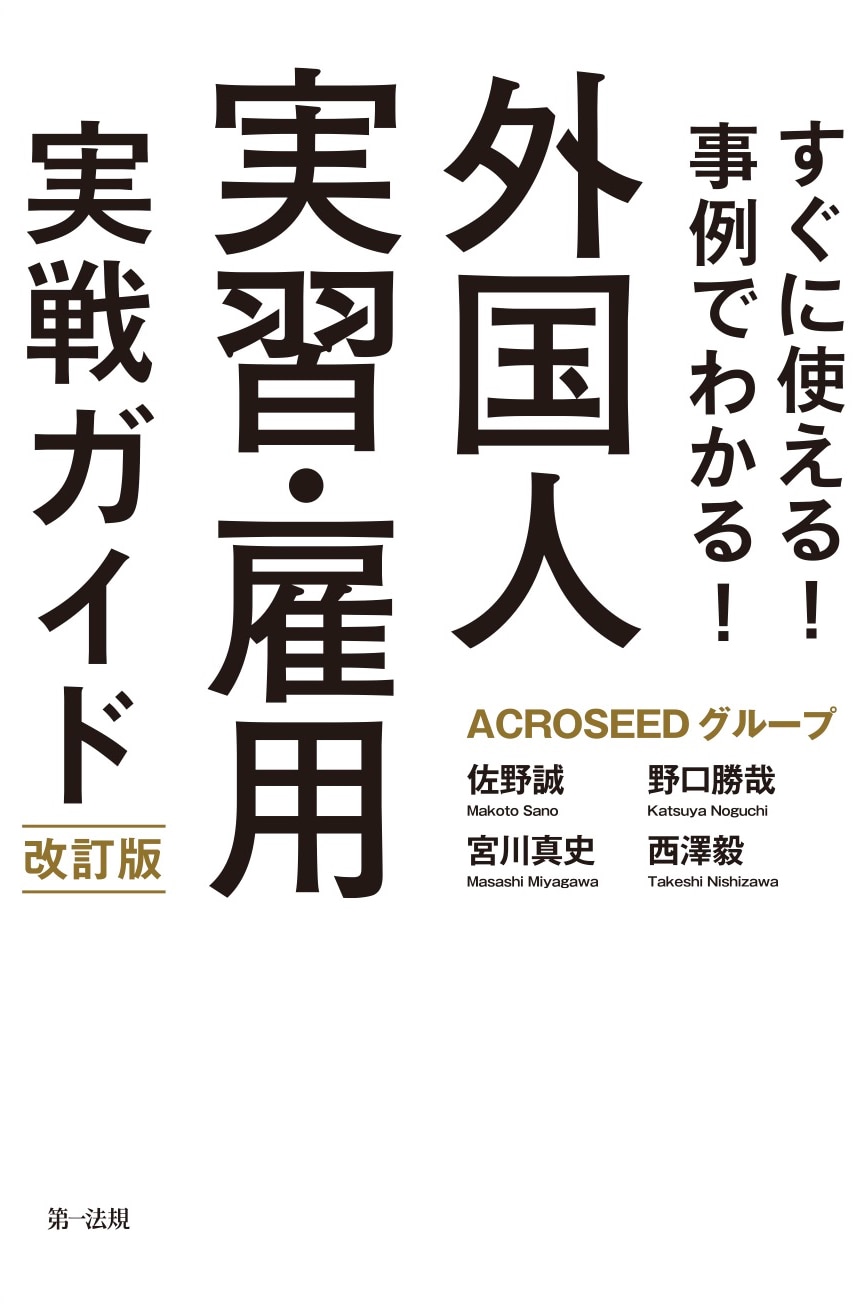
- 参考文献
- すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版
- 著者:佐野誠、宮川真史、野口勝哉、西澤毅
- 定価:本体3,600円+税
- 出版社:第一法規
- 発売年月:2018年7月
-
法務省入国管理局「カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請手続の取扱いについて」(平成27年3月) ↩︎

株式会社ACROSEED