研修・技能実習制度を活用して外国人を受け入れる際の留意点
人事労務当社はステンレスの製造加工を行うメーカーです。昨今の求人難を受けて、初めての外国人雇用を考えています。「技能実習」の在留資格での受入れを検討していますが、技能実習制度について詳しく説明してください。
研修・技能実習制度とは、18歳以上の外国人を日本に受け入れ、日本での産業上の技術や技能、知識などを習得させ、本国で活用してもらうことにより、人材育成を通じた国際貢献を行うための制度です。この研修制度は日本が経済成長の波に乗った1960年代に基礎ができ上がりました。
当時、多くの日本企業が海外進出を果たした結果、世界中に日本企業との合弁会社や現地法人が設立され、業務を円滑に行うためにも現地で雇用された外国人社員の研修が大きな課題となりました。なかでも精緻な技術を必要とする製造業では、外国人社員を日本に招へいし自社の工場などで直接、必要な知識・技術・技能を教える必要がありました。そのため、多くの企業からの要望を受ける形で外国人研修制度が発足しました。当時は企業単独での受入れのみが規定されていましたが、1990年に行われた改正により、組合を通じての受入れが可能となりました。さらに93年には、より実践的な技術や技能を習得させるため、受入機関との雇用関係の下に成立する技能実習制度が実施されるようになりました。
しかし、実務研修については、外国人研修生を実質的な低賃金労働者として扱う不正な受入れが目立つなど様々な問題が起きたため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が制定され現在に至っています。
解説
目次
研修とは
在留資格「研修」とは、日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動をいいます(出入国管理及び難民認定法 別表第一の4)。ただし、「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」および「留学」の在留資格に該当する活動は含まれません。そのため、この在留資格で行うことができる研修とは、海外生産拠点の現地社員を日本に呼び寄せて行う社内研修や工場見学、実務研修をまったく伴わない研修、国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修などに限定されます。
技能実習とは
「技能実習」とは、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的とし(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「技能実習法」)1条)、1年目から労働者として在留する外国人技能実習生に与えられる在留資格です。この在留資格の特徴としては技能実習生が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護を受けられるよう、原則として雇用契約に基づいた技能等の修得をする活動を行うことが義務付けられている点です(技能実習法2条4項)。従来は労働者として認められていなかった技能実習生にも労働基準法が適用されるため、受入れ側の機関は最低賃金や残業代、夜間の割増賃金などを支払わなければなりません。
さらに在留資格「技能実習」は、「活動内容」と「受入形態」により4種類に分類されます。
① 活動内容による分類
| 「技能実習」1号 | 「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」 |
| 「技能実習」2号 | 技能実習1号の活動内容に従事し、技能等を修得した者がその技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動 |
② 受入形態による分類
| 「技能実習」イ | 海外にある合弁企業など事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型) |
| 「技能実習」ロ | 商工会などの営利を目的としない団体の責任および管理の下で行う活動(団体管理型) |
技能実習生は、技能実習1号終了時に技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けることで、技能実習2号へ移行することができます。技能実習2号への移行対象職として、81職種145作業 1 が定められています。
技能実習1号から技能実習2号へ移行する場合、滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
技能実習の受入れ方法
技能実習生の受入れには様々な方法がありますが、大きく分けると企業単独型(技能実習イ)と団体管理型(技能実習ロ)の2つに分類されます。
企業単独型とは、海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤職員を日本の企業などが研修生として受け入れる場合が該当します。受け入れることができる研修生の数は、原則として、受入れ企業の常勤職員20名につき研修生1名となります。
一方、団体監理型での受入れの場合には、日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人などが責任を負い、その指導・監督のもとに会員・組合員企業などが研修生を受け入れる場合が該当します。
事業協同組合等の中小企業団体が受け入れる場合には、原則として、受入れ企業の常勤職員が50名以下の場合には研修生3名の受入れが可能です。このような人数枠の基準があるため、常勤職員を多数抱える大企業が企業単独型で受け入れるケースが多く見られます。常勤職員数が少ない小規模の企業の場合は、中小企業事業協同組合などを通して団体管理型の受入れを行うケースが多くなります。
技能実習制度のなかでも団体管理型(技能実習ロ)の場合には、コンプライアンス意識が高い事業協同組合を選別することが重要です。複数の組合に足を運び、技能実習の現場を自身の目で見ておくことは非常に有効です。制度の趣旨をきちんと理解し、営利最優先ではない運営を行っているパートナーを見つけることが技能実習を成功させるポイントとなります。
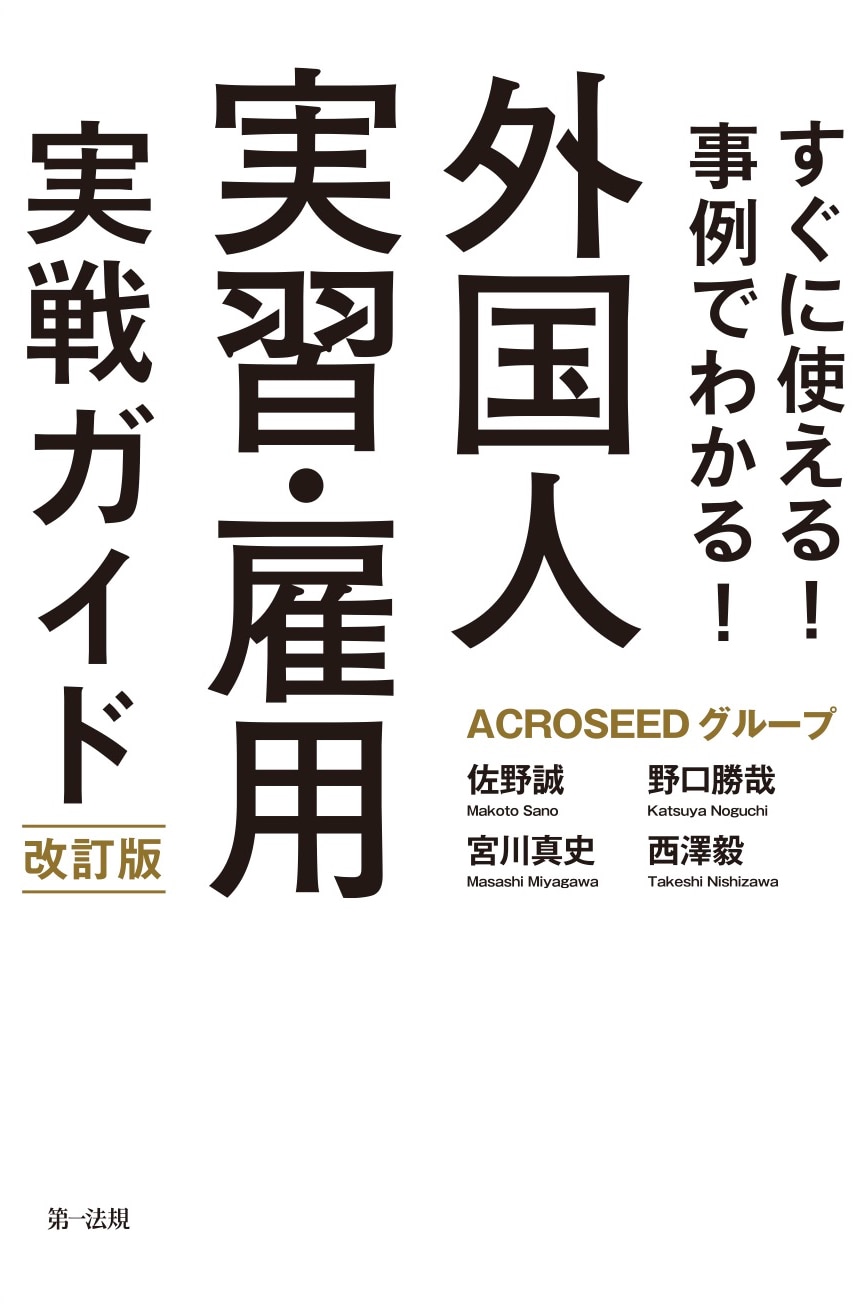
- 参考文献
- すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版
- 著者:佐野誠、宮川真史、野口勝哉、西澤毅
- 定価:本体3,600円+税
- 出版社:第一法規
- 発売年月:2018年7月
-
厚生労働省「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(81職種145作業)」(令和元年11月8日時点) ↩︎

株式会社ACROSEED