外国人を雇用する際に守るべき法令(入社から退職まで)
人事労務当社では外国人を雇用することを検討しています。外国人労働者を雇用した際に、入社後に行うべきことや、守るべきルールなどはありますか?
自社で外国人労働者を雇用する際は、厚生労働省が公表している「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が参考になります。この指針には、外国人雇用に関わる法律、採用募集、労働条件の決定・周知の方法などのほか、外国人労働者が入社した後に行うべき実務の要点が整理されています。外国人雇用に取り組む際には、この指針を参照しながら業務を進めていくとよいでしょう。
解説
外国人を雇用する際に守るべき法令
外国人を雇用する際に事業主が講ずべき必要な措置を定めているのが、厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年8月3日、平成29年11月1日最終改正、以下、「指針」といいます)です。この指針には、外国人労働者を雇用する際に守るべき法令やルールがあげられています。本稿では、外国人労働者の入社後に事業主が行うべきことを中心に、指針に沿いながら実務のポイントを解説していきます。
外国人労働者の募集から入社までに行うべき実務の要点については、「外国人を雇用する際に守るべき法令(入社から退職まで)」をご参照ください。
労働安全衛生
事業主が外国人労働者に対して安全衛生教育を実施する場合には、特に業務上使用する機械設備、安全装置または保護具の使用方法等が確実に理解されることに留意します(指針 第4 3−1)。通訳やマニュアルなどを使用して外国人労働者がその内容を理解できる方法で行うことが重要です。
事業主には、外国人労働者が労働災害防止のための指示が理解できるように、必要な日本語や基本的な合図などの習得に努めることと同時に、工場内などの労働災害防止に関する標識や掲示においては、イラストなどを用いて外国人労働者が理解できる方法を採用することが求められています(指針 第4 3−2, 3−3)。
多くの企業では、空港などで利用されているユニバーサルデザインと呼ばれるイラストが利用されています。その他にも、仕事道具は色分けされた箱に収納する、敷地内の危険地帯を赤の斜線で覆うなど、様々な工夫がなされています。
労働安全衛生法等の定めにより、日本人労働者と同様に、外国人労働者に対しても健康診断を実施します。その際、事業主は、健康診断の目的や内容を外国人労働者が理解できる方法で説明するよう努めなければなりません(指針 第4 3−4)。また、産業医や衛生管理者など活用して外国人労働者に対して健康指導や健康相談を行うよう努めることも求められています(指針 第4 3−5)。
さらに、労働安全衛生法等関係法令の定めにより、外国人労働者に対して、その内容を周知することが求められています。周知にあたってはマニュアルなどを用いることで外国人労働者が十分に理解できるよう配慮することが必要です(指針 第4 3−6)。
現在では、マニュアル作成用のアプリなども広く活用されており、写真を撮りながら簡単な説明を加えるだけで作成できるようなサービスを活用することも有用です。さらに、翻訳に関してもウェブサイトの翻訳サービスを活用して作成し、最終的には外国人労働者に1つひとつ訂正してもらう方法も多く取られています。
保険関連の適用
事業主は、雇用時に外国人労働者に対して、以下の労働・社会保険に関する法令や給付に関する請求手続きについて理解できるように説明し、必要な保険関係手続きを行わなければなりません(指針 第4 4−1)。
- 雇用保険
- 労災保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
外国人労働者の離職時には、雇用保険被保険者離職票の交付など必要な手続を行い、失業給付などの受給に必要となるハローワークの窓口を案内するなど、必要なサポートに努めます。また、労働災害が発生した場合には労災保険給付の請求に必要となる援助をすることも同様です。厚生年金保険の加入期間が6か月以上ある外国人労働者が帰国する場合には、脱退一時金に関する案内を行い、年金事務所等の窓口などについての情報を伝えることが求められます(指針 第4 4-2)。
やがて母国に帰国することが前提である外国人労働者にとって、脱退一時金による還付は非常にありがたいものです。日本で働いた期間により金額は異なりますが、1か月分以上の給与に相当する額が還付されることも珍しくありません。外国人労働にとって帰国後の貴重な収入となりますので、積極的に周知するようにしてください。
人事管理、教育訓練、福利厚生など
外国人労働者が職場に適応し、評価や処遇に納得しつつ就労することができ、多様な人材が能力発揮しやすい環境の整備に努めるために、事業主は以下の点に留意する必要があります(指針 第4 5-1)。
- 職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化
- 職場における円滑なコミュニケーションの前提となる条件の整備
- 評価・賃金決定
- 配置等の人事管理に関する運用の透明化 など
また、事業主には、外国人労働者が日本社会へスムーズに適応できるようにするため、外国人労働者に対して日本語教育や日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行などについて理解を深めるための指導を行うとともに、生活上または職業上の相談に応じるようにすることも求められています(指針 第4 5-2)。
日本語教育においては、市区町村で開かれている外国人のための日本語教室などの公共サービスを活用することも一案です。また、在日外国人をサポートするボランティア団体などと提携することで、雇用企業の負担を最小限に抑えながら教育を実施する例も見られます。
在留資格の範囲内で、外国人労働者が自分の能力を有効に発揮しながら就労できるように、事業主は、外国人労働者に対して適切な教育訓練を実施したり、その他の必要な措置を行うように努めます。苦情や相談体制の整備、母国語での導入研修の実施など働きやすい職場環境の整備などがこれにあたります(指針 第4 5−3)。
外国人労働者から相談を受けた場合には、日本人以上のケアを行う心構えが必要です。生活から就業に至る様々な点について、外国人労働者が率直に相談できるような関係づくりを常日頃から意識しておくことが、外国人雇用を成功させるための鍵となります。
福利厚生については、外国人労働者のために宿泊施設を確保するように努め、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、日本人労働者と同様に外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めなければなりません(指針 第4 5-4)。
外国人社員と日本人社員を差別することは、もちろん避けなければなりません。しかし、外国人だからこその配慮も必要となります。在留手続きやそれに伴う職務内容、食生活や宗教上の理由による働き方の違いなどがそれにあたります。日本人従業員の側から見ると、「外国人を特別扱いしている」と映ることもあるようです。両者に対して十分な説明を行い、働き方のバランスをうまくとりながら、全従業員に納得してもらうことを心がけましょう。
外国人雇用に関して不可欠となるのが在留手続きです。外国人労働者の在留期間が満了する際には、事業主は雇用関係を終了させ、帰国のための諸手続に関する相談やその他の必要なサポートに努めなければなりません(指針 第4 5−5イ)。外国人労働者の在留資格の変更時や在留期間の更新時にも、勤務時間の配慮やその他必要な援助により、外国人労働者が、それらの手続を行えるように援助することが求められます(指針 第4 5−5イ)。
在留手続きを行う際は、入国管理局へ出向いて申請を行うことになります。申請手続きについて、勤務時間の扱いとするか、有給休暇の扱いとするかといった点は、事前に明確化しておくことが重要です。以下のように誰が在留手続きを行うかについても、検討すべきポイントとなります。
- 外国人労働者本人が在留手続きを行う
- 雇用企業の人事担当者などが申請取次制度を活用して代理申請する
- 行政書士などの専門家に任せる
在留手続きに対する雇用企業の対応は様々です。大切なことは、最初に明確な方針を決定したら、以降はその方針に沿った対応を貫くことです。むやみにルール変更を行うと、外国人労働者の理解が得られず、思わぬトラブルに発展することがあるため注意してください。
事業規模の縮小を行う場合であっても、外国人労働者に対して安易な解雇等を行うことは認められません。やむを得ず解雇を行う場合には、再就職を希望する外国人労働者については、関連企業へのあっせん、教育訓練などの実施、求人情報の提供など、在留資格に応じた再就職ができるように必要な援助を行うことが求められています(指針 第4 6)。
外国人の場合には、在留資格取消制度の適用があります。この制度の概要とは、現在与えられている在留資格に該当する活動を3か月以上行わないと、在留資格が取り消されるというものです(出入国管理及び難民認定法22条の4)。そのため、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の場合には、退職後3か月以内に再就職できないと帰国を余儀なくされる可能性が生じます。外国人労働者にとって、退職は日本人以上に非常に深刻な問題となり得るため、やむを得ず解雇等を行うときは、最後まで再就職を支援することが、トラブル回避のためにも重要です。
雇用状況の届出と雇用管理責任者
新しく外国人労働者を雇用した場合やその外国人労働者が離職した場合には、事業主は以下の事項を、原則として在留カードの提示によって確認します(指針 第5 2)。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期間
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき事項
(職種、賃金、住所など)
※雇用保険被保険者資格がない場合、または2007年10月1日の時点で現に雇い入れている場合は、①~⑥までとなります。
確認した上記の事項は、雇入時は原則として雇い入れた日の属する月の翌月10日まで、離職時には原則として離職した日の翌日から起算して10日以内に雇用先企業を管轄する公共職業安定所に届け出なければなりません(指針 第5 3)。さらに、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者の雇用管理に関する責任者である「雇用労務責任者」を選任することが必要です(指針 第6)。
技能実習生
技能実習生についても外国人労働者に含まれます。そのため、上記の事項に加えて、法務省、厚生労働省「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針」(平成29年4月7日)に規定されている施策にも留意し、実効性ある技術や技能等の修得が図られるよう取り組むことが求められます。
技能実習生は、初めて来日する場合が多く、日本の法令や労働ルールに関する知識を持たないケースが大半です。そこにつけ込んだ悪質な企業が、劣悪な労働環境下で技能実習生を半強制的に働かせているような事案も伝えられています。たとえば、技能実習生に対して最低賃金以下の給与しか支払わず、残業代も支払っていなかったケース 1 など、一部の悪質な企業の実態が報じられています。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の施行に伴い、現在では法令違反時の通報窓口や労働基準法違反時の教育などの体制整備が求められています。しかし、ハラスメント行為などによって、技能実習生に通報をためらわせるような企業が存在するのも事実です。技能実習生を雇用する事業主は、法令に照らして適切な雇用環境を提供することに留意しなければなりません。
行政機関の援助と協力
職業安定機関や労働基準監督機関、その他の関係行政機関の必要な援助と協力を得て、事業主はこの指針に定められた事項を実施しなければなりません(指針 第8)。
さいごに
以上、外国人労働者を雇用する際のルールとなる「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の内容を確認しました。
技能実習生や外国人留学生のアルバイトに対しても、当然に労働基準法が適用されるため、日本人と同等な待遇をしなければなりません。最近では、外国人労働者もユニオン等に加盟し、違法な就業を強いる事業主に対して、泣き寝入りすることなく、法的手段に訴える事例も目立ちます。「外国人だから安く使おう」「外国人だから(違法なことをしても)わからないだろう」といった考え方は通用しません。
劣悪な労働環境での強制的な雇用は人権侵害につながり、雇用企業はもちろんのこと、技能実習制度の存続の是非に影響を及ぼしたり、日本社会の国際的地位の低下を招いてしまうといった、重大な事態につながりかねません。事業主には、外国人労働者に対し、日本人労働者と同等のフェアな精神で接することが求められています。
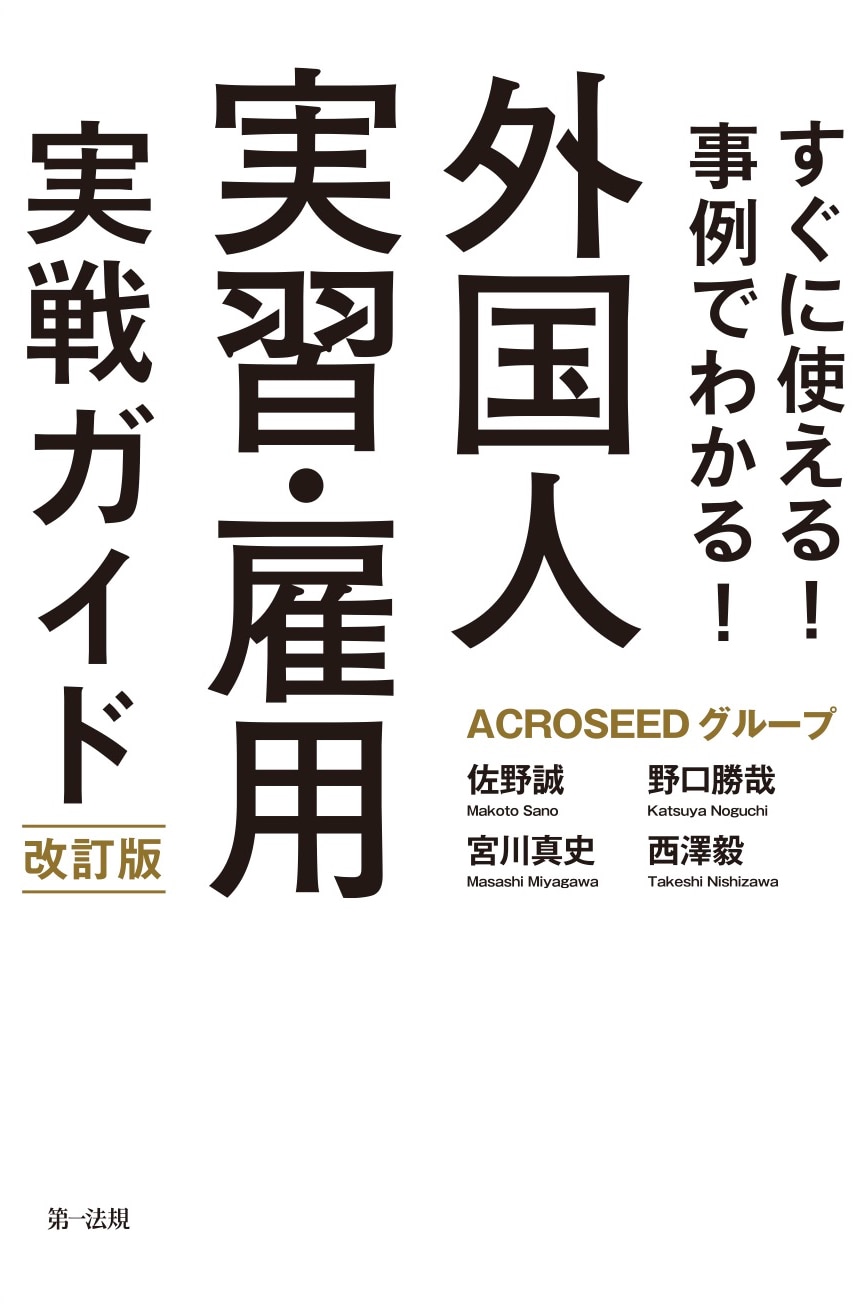
- 参考文献
- すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版
- 著者:佐野誠、宮川真史、野口勝哉、西澤毅
- 定価:本体3,600円+税
- 出版社:第一法規
- 発売年月:2018年7月
-
朝日新聞デジタル「技能実習生に給料未払い・過重労働 複数社の処分検討」(2020年1月17日、2020年1月27日最終閲覧) ↩︎

株式会社ACROSEED