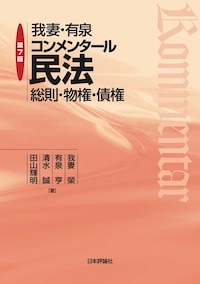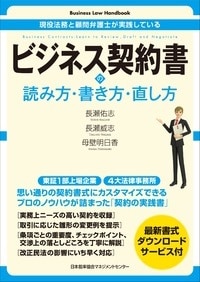債権譲渡に関する民法改正の主なポイント
取引・契約・債権回収 更新- 改正民法の下では、旧民法とは異なり、譲渡制限特約が付された債権であっても、原則として譲渡が有効になると聞きましたが、その詳細について教えてください。
- 改正民法の下では、債権譲渡の際の、債務者による「異議をとどめない承諾」の制度が廃止されたと聞きましたが、その詳細について教えてください。
- 改正民法の下では、債権譲渡と相殺に関するルールが整理されたと聞きましたが、その詳細について教えてください。
- 旧民法では、譲渡制限特約が付された債権の譲渡は無効と解されていましたが、改正民法では、譲渡制限特約が付されていても、これによって債権譲渡の効力は妨げられない(有効である)とされました。もっとも、債権の譲受人が譲渡制限特約について悪意または重過失である場合には、債務者は、譲受人に対する債務の履行を拒むことができます。
- 旧民法は、債務者が異議をとどめないで債権の譲渡の承諾をしたときは、債務者は譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができないと定めていましたが、改正民法は、異議をとどめない承諾の制度を廃止し、債務者が有する抗弁の切断については、抗弁を放棄する旨の債務者の明確な意思表示を必要とすることにしました。
- 旧民法の下では、債権譲渡の際に債務者が譲渡人に対する反対債権を持っていた場合の相殺権の行使の可否について明確な規定が置かれておらず、ルールが不明確でしたが、改正民法は、債権譲渡の対抗要件が具備される前に債務者が取得した債権等一定の債権について、これを自働債権として相殺できる旨のルールが整理・明文化されました。
解説
※本記事の凡例は以下のとおりです。
- 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法
- 旧民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正前の民法
譲渡制限特約の効力
改正の内容
旧民法466条は、1項で債権譲渡自由の原則を定めながら、2項で「当事者が反対の意思を表示した場合」は、この原則を認めない旨を定めており、一般的に譲渡制限特約が付された債権の譲渡は無効だが、例外的に譲渡制限特約について善意・無重過失の譲受人に対しては特約の存在を主張できないと解されていました(物権的効力説)。
もっとも、このような解釈には、譲受人の主観により債権譲渡の有効・無効が決まるのは債権取引の安定性を欠く、また、中小企業等の資金調達を妨げるといった批判がなされていたことから、改正民法は、譲渡制限特約が付されていても、これによって債権譲渡の効力は妨げられないと明記しました(改正民法466条2項)。そのうえで、譲渡制限特約につき悪意または重過失の譲受人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができると定め(改正民法466条3項)、旧民法における原則と例外を逆転させました。

旧民法と改正民法の相違点については、下表もご参照ください。譲受人の主観面について、債務者に立証責任が転換された点も、実務的に影響がある部分です。
譲渡制限特約について旧民法と改正民法の対比
| 旧民法 | 改正民法 | |
|---|---|---|
| 効力 | 物権的効力説 | 債権的効力説 |
| 原則 | 譲渡制限が付された債権の譲渡は無効 | 譲渡制限が付された債権の譲渡は有効 |
| 例外 | 譲渡制限について善意・無重過失の譲受人に対しては特約の存在を主張できない | 譲渡制限について悪意・重過失の譲受人に対しては履行を拒むことができる |
| 立証責任 | 譲受人の善意・無重過失につき譲受人が立証責任を負う | 譲受人の悪意・重過失につき債務者が立証責任を負う |
預貯金債権にかかる譲渡制限特約の効力
改正民法の下でも、預金口座または貯金口座に係る債権(預貯金債権)については、譲渡制限特約につき悪意または重過失の譲受人との関係では、債権譲渡は無効であるとされました(改正民法466条の5)。
預貯金債権について異なる取扱いをする理由としては、金融機関は大量の預貯金債権につき迅速な処理が求められるため、債権者を固定化する必要性が高いこと、預貯金債権の譲渡による資金調達は一般的には行われておらず、譲渡を有効とすべき必要性に乏しいこと等があげられます。
異議をとどめない承諾の扱い
旧民法468条1項は、債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾した場合には、譲渡人に対して対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することはできないと定められています。
しかしながら、債務者が債権譲渡があったことを認識した旨を告げただけで、あらゆる抗弁を喪失させる効果を生じさせるのは債務者にとって酷にすぎる等の理由から、改正民法は、異議をとどめない承諾の制度を廃止しました。
そのため、譲受人が債権譲渡後に債務者から予期せぬ抗弁の主張を受けることを防ぐためには、債務者より、明示的かつ積極的な抗弁権の放棄の意思表示を得る必要がありますが、そのような意思表示を得るにあたっては、公序良俗や信義則違反により無効にならないように慎重に債務者の意思を確認する必要があります。
債権譲渡と相殺
旧民法の下では、債権譲渡の際に債務者が譲渡人に対する反対債権を持っていた場合において、譲受人に対して相殺権を行使できるか否かについて明確な規定が置かれておらず、解釈論に委ねられていました。改正民法はこの点を整理し、債権譲渡があった場合に債務者が譲渡人に対して以下の反対債権を有している場合には、債務者は当該債権と譲渡債権の相殺を譲受人に対抗できる旨明記しました(改正民法469条)。
(2)債権譲渡にかかる対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権(同条2項1号)
(3)譲渡債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権(同条2項2号)
(1)については、債務者が債権譲渡の対抗要件具備前に取得した債権であれば、両債権の弁済期を問わず、債務者は相殺権を主張することが可能です。
(2)については、たとえば債権譲渡の対抗要件具備前に締結されていた賃貸借契約に基づき対抗要件を具備した後に発生した賃料債権等がこれに該当し、債権譲渡の対抗要件具備前に債権の発生原因が生じている以上、相殺の期待も生じていることが通常であることから、このような相殺権の主張が認められています。
(3)については、将来債権が譲渡された場合を想定した定めで、同一の契約から生じた債権債務について、特に相殺の期待が強いことに基づくものです。
経過措置
債権譲渡に関する改正の内容は、改正民法の施行日以後に債権譲渡の原因となる法律行為がされた場合に適用されます(民法附則22条)。すなわち、譲渡される債権の発生日や債権譲渡の効力発生日等が基準になるわけではなく、債権譲渡契約の締結日が基準となり、債権の発生原因となる締結済みの契約に譲渡制限特約が付されていても、実際の債権譲渡契約が改正民法施行日後に締結されれば、債権譲渡に関して改正民法の規律が適用されますので、注意が必要です。
【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】
『我妻・有泉コンメンタール民法[第7版] 総則・物権・債権』
発売日:2021年04月01日
出版社:日本評論社
編著等:我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『改正債権法コンメンタール』
発売日:2020年10月05日
出版社:法律文化社
編著等:松岡久和、松本恒雄、鹿野菜穂子、中井康之
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『Business Law Handbook ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』
発売日:2017年06月24日
出版社:日本能率協会マネジメントセンター
編著等:長瀨 佑志、長瀨 威志、母壁 明日香
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
2020年4月2日:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に伴い「現行民法」の記載を「旧民法」に改めました。

DT弁護士法人