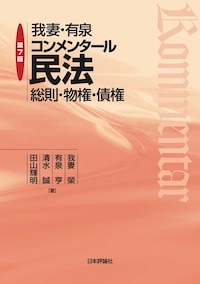相殺に関する民法改正のポイント
取引・契約・債権回収改正民法により、相殺が認められる範囲は変わりましたか。その他相殺に関する改正民法の主な内容を教えてください。
改正民法は、①相殺制限特約、②不法行為等により生じた債権による相殺の禁止、③差押えを受けた債権による相殺の禁止、④相殺の充当について改正を行っています。このうち、②および③は相殺が認められる範囲について、従来と異なる定めをしていますので、特に留意が必要です。
解説
目次
※本記事の凡例は以下のとおりです。
- 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法
- 旧民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正前の民法
不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
不法行為債権:全面禁止から悪意の場合のみ禁止へ
旧民法509条では、不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権(相殺する側から見て債務)とする相殺を全面的に禁止しています。その心は、①金銭を払ってもらえないことの腹いせとして不法行為を行うような事態を未然に回避し(違法行為の未然防止)、②不法行為の被害者には現実に金銭賠償を受けさせるべき(被害者救済)という政策的配慮にあるとされていました。
しかしながら、単なる故意や過失による不法行為には①のような配慮は必ずしもあてはまらないことや、②の観点で果たして不法行為の被害者に限って特別に現実の弁済を受けさせる必要性があるのか(安全配慮義務違反のときなど、債務不履行の被害者にも場合によっては現実の弁済を受けさせるべき場合があるのではないか)といった点に疑義が呈されていました。
そこで、改正民法509条1号では、まず①の点に関し、相殺禁止の対象となる不法行為に基づく損害賠償債権(受働債権)を「悪意による不法行為に基づく」ものに限定しました。ここでの悪意とは単なる故意では足りず、積極的な害意まで必要とするものであるとされますので、この意味において旧民法よりも相殺禁止の対象を狭めているものといえます。
人の生命・身体の侵害による損害賠償債務による相殺禁止(新設)
他方、②の点に関しては、改正民法509条2号は、むしろ相殺禁止の範囲を広げる規定を定めています。つまり、不法行為に基づく損害賠償債権か債務不履行に基づく損害賠償債権かにかかわらず、「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」を受働債権とする相殺を禁止することとしました。なお、過失による不法行為も人の生命または身体の侵害の場合には、改正民法509条2号にて相殺禁止の対象になります。
例外
上記改正民法509条1号および2号には共通の例外があり、債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは(つまり、悪意の不法行為の被害者等が損害賠償債権を第三者に譲渡した場合)、たとえ悪意による不法行為や人の生命または身体侵害に基づく損害賠償債権であっても債務者は相殺可能とされています。このような債権の譲受人には現実の弁済を受けさせる必要性が必ずしもないからです。
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
無制限説の明文化
旧民法511条では、第三債務者は差押え「後」に取得した債権(自働債権)による相殺を差押債権者に主張しても、差押えを甘受しないといけない(つまり、反対債権があっても差押債権者への支払いを強いられる)こととされており、この規定は改正民法でも維持されています。
逆に、差押え「前」に取得した債権による相殺については、旧民法は明文の規定を設けておりませんでしたが、最高裁の大法廷判決(最高裁昭和45年6月24日・民集24巻6号587頁)により、自働債権と受働債権の弁済期の前後を問わず、差押え前に取得した債権による相殺は無制限に認められることとされてきました(いわゆる無制限説)。改正民法511条1項は、この無制限説を明文化し、「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる」と規定しました。
差押え後に取得した、差押え「前に生じた原因」による債権との相殺許容
さらに、改正民法は、差押え後に取得した債権による相殺についても、一定の場合に差押債権者に対抗できることとし、相殺の担保的機能をより保護する明文を設けました。すなわち、改正民法511条2項本文は、「前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる」としました。
ここでのポイントは、「前に生じた原因」です。前に生じた原因による相殺を相殺禁止の例外としている破産法72条2項2号等の解釈を参考にすると、差押え前に債権の発生原因がある場合には、相殺への合理的期待があり、かかる相殺は原則として差押債権者に対抗できるものと考えられます。どのような場合に合理的な期待があるといえるかは今後の事例の集積によりますが、たとえば、差押えよりも前に締結されていた賃貸借契約に基づき差押え後に発生した賃料債権については、前に生じた原因によるものとして、相殺が認められるものと考えられます。
例外
もっとも、いかに差押え前に生じた原因に基づく債権であっても、「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したとき」は、差押債権者に相殺を対抗することができないものとされます(改正民法511条2項ただし書)。差押え後にわざわざ第三者から債権を譲り受ける場合には、相殺に対する合理的期待を有していたとは考え難いからです。
まとめ
以上のとおり、改正民法は、不法行為等の損害賠償債権を受働債権とする相殺禁止の範囲を変更し、差押えを受けた債権を自働債権とする相殺と差押えとの優劣関係について実質的な変更を行いました。その他相殺を制限する特約は、悪意重過失の第三者に対抗できるとした点(改正民法505条2項)、相殺の充当に関し当事者間の充当順序に関する合意の有効性等を規定した点(改正民法512条1項)もあわせてご確認ください。
【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】
『我妻・有泉コンメンタール民法[第7版] 総則・物権・債権』
発売日:2021年04月01日
出版社:日本評論社
編著等:我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『改正債権法コンメンタール』
発売日:2020年10月05日
出版社:法律文化社
編著等:松岡久和、松本恒雄、鹿野菜穂子、中井康之
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『新プリメール民法3 債権総論〔第2版〕』
発売日:2020年04月15日
出版社:法律文化社
編著等:松岡 久和、山田 希、田中 洋、福田 健太郎、多治川 卓朗
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『民法(債権関係)改正法の概要』
発売日:2017年08月24日
出版社:一般社団法人金融財政事情研究会
編著等:潮見佳男
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『民法改正で変わる!契約実務チェックポイント』
発売日:2017年03月18日
出版社:日本加除出版
編著等:野村 豊弘、虎ノ門南法律事務所
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

弁護士法人大江橋法律事務所