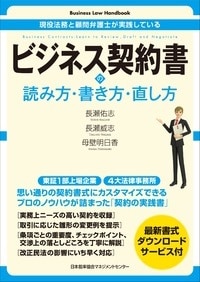契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い 民法改正による変更点
取引・契約・債権回収 更新2020年4月に施行された民法(債権法)改正によって、売買における売主の瑕疵担保責任の規定が大幅に見直されたとのことですが、具体的にどのように変わったのでしょうか。
民法改正により、「瑕疵」という文言は使われなくなり、「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められ、これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものは、「契約不適合責任」と呼ばれるようになりました。
また、民法改正により、担保責任の法的性質について、契約(債務不履行)責任であると整理された結果、契約不適合責任の規定が特定物・不特定物を問わず適用され、契約不適合の対象は原始的瑕疵(契約締結時までに生じた瑕疵)にかぎられないこととなりました。加えて、買主のとり得る手段として、これまでの解除、損害賠償に加え、追完請求、代金減額請求も認められました。さらに、損害賠償請求には、売主の帰責性が必要になりました。
解説
目次
-
※本記事の凡例は以下のとおりです。
- 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法
- 改正前民法:上記改正前の民法
契約不適合責任とは何か
契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(改正民法562条1項)に売主が買主に対して負う責任をいいます。たとえば、商品が不良品であった場合に売主が買主に対して負う責任などがこれにあたります。
法的性質に関する見解の整理
改正前民法における瑕疵担保責任の法的性質については、法定責任説と契約(債務不履行)責任説の見解の対立がありました。
特定物売買の場合には売主は目的物をそのまま引き渡せば債務の履行としては足りるところ、民法上の瑕疵担保責任は債務不履行責任とは別に法が特に定めた責任であると考える見解。
契約(債務不履行)責任説
売主は瑕疵のない目的物を引き渡す義務を負っており目的物に瑕疵がある場合には債務不履行となるところ、民法上の瑕疵担保責任は売買における債務不履行の特則であると考える見解。
改正前民法下では、法定責任説が有力な見解といわれていましたが、改正民法は、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を、契約(債務不履行)責任と整理しました。
このことが改正前民法(本記事では、法定責任説を前提とします)と改正民法におけるさまざまな帰結の違いをもたらすことになります。
「瑕疵」から「契約不適合」への表現の変更
改正前民法570条は、「瑕疵」という表現を用いていましたが、改正民法では、「瑕疵」という文言は用いられず、代わりに「契約の内容に適合しないもの」(以下、「契約不適合」といいます)という表現が用いられています。
特定物・不特定物を問わない
改正前民法における法定責任説のもとでは、瑕疵担保責任の対象は特定物にかぎるとされていましたが、改正民法下では、特定物・不特定物を問わず契約不適合責任の規定が適用されることになります。
契約不適合責任の対象は契約履行時まで
改正前民法における法定責任説のもとでは、瑕疵は原始的瑕疵(=契約締結時までに生じた瑕疵)にかぎるとされていましたが、改正民法下では、契約の履行時までに生じたものであれば契約不適合責任を負うことになります。
契約不適合の場合に買主がとり得る手段の違い
改正前民法における法定責任説のもとでは、買主がとり得る手段は、解除(契約した目的を達成できない場合)と損害賠償だけ(改正前民法570条・566条)でしたが、改正民法下では、追完請求(改正民法562条)、代金減額請求(改正民法563条)もできるようになりました。
瑕疵担保責任(法的責任説)と契約不適合責任について、買主がとり得る手段の違いは以下のとおりです。
買主がとり得る手段の比較
| 瑕疵担保責任(法定責任説) | 契約不適合責任 | |
|---|---|---|
| 追完請求 | 不可 | 可 |
| 代金減額請求 | 不可(数量指示売買を除く) | 可 |
| 解除 | 契約をした目的を達成できない場合のみ可 | 可(ただし、不履行が軽微である場合、不可) |
| 損害賠償 | 可(信頼利益に限定) | 可(履行利益まで可) |
追完請求(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)
改正前民法における法定責任説のもとでは、修補等による追完請求は認められないとされていましたが、改正民法下では、契約責任と整理されたことの帰結として、追完請求ができるようになりました(改正民法562条)。
追完の方法は、第一次的には、買主が選択できることとされています(同条1項本文)が、買主に不相当な負担を課するものでないときは、売主は、買主が請求した方法と異なる方法で追完することが可能です(同条1項ただし書)。
なお、契約不適合が買主の帰責事由による場合には、追完請求はできないこととされています(同条2項)。
代金減額請求
改正前民法下では、数量指示売買 1 を除き、代金減額請求は認められていませんでしたが、改正民法下では、代金減額請求ができるようになりました(改正民法563条)。
代金減額請求は、履行の追完を催告し、催告期間内に履行の追完がない場合にすることができます(同条1項)。ただし、追完が不可能である場合(1号)など、改正民法563条2項各号に該当する場合には、催告は不要です。
また、契約不適合が買主の帰責事由による場合に請求ができない点は、追完請求の場合と同様です(同条3項)。
解除
改正民法では、契約責任と整理された結果、損害賠償および解除については、債務不履行の一般規律に服することとなりました(改正民法564条)。したがって、解除を行うためには、原則として履行の追完の催告が必要となります(改正民法541条)2。
そして、改正前民法下の瑕疵担保責任(改正前民法570条・566条)においては、解除の要件として「契約をした目的を達することができない」ことが求められていましたが、改正民法では、債務不履行の一般規律に服する結果、催告解除(改正民法541条)においては、契約目的達成が可能である場合に、不履行が軽微であるときを除いて解除できる余地が生じることとなりました 3。したがって、民法改正によって、“契約目的達成は可能であるが軽微でない” 場合も解除できることになり、解除できる場面が広がったといえます。
また、「隠れた」4 瑕疵であることが要求されなくなった結果、買主の善意・無過失は解除の要件ではなくなりました。
損害賠償
改正民法下では、上記のとおり、損害賠償についても債務不履行の一般規律に服します。そのため、売主の帰責事由が不要であった改正前民法と異なり、損害賠償には売主の帰責事由が必要となりました(改正民法415条1項ただし書)。
また、改正前民法における法定責任説のもと、信頼利益(履行の準備のためにかかった費用など、契約が有効であると信じたことによって失った利益)までとされていた損害賠償の範囲は、履行利益(転売利益など、契約が履行されていれば得られたであろう利益)まで含まれることになりました(改正民法416条)。
買主の善意・無過失が損害賠償の要件でなくなった点は、解除と同様です。
契約不適合を理由とする権利行使の期間制限
改正前民法下では、瑕疵を理由とする損害賠償請求等の権利行使は、買主が事実を知ってから1年以内にしなければならないとされていました 5(改正前民法570条・566条3項)。これに対し、改正民法では、種類または品質に関する契約不適合を理由とする権利行使については、買主が契約不適合を知った時から1年以内に「通知」6 をすれば足りるとし、また、数量や移転した権利に関する契約不適合を理由とする権利行使については期間制限が設けられていません(改正民法566条本文。ただし、改正民法166条1項によって消滅時効にかかる可能性はあります)。
なお、売主が契約不適合につき悪意または重過失であった場合には、上記1年の期間制限にはかかりません(改正民法566条ただし書)。
契約不適合責任の規定の適用範囲
これまで物の売買を念頭に説明してきましたが、契約不適合責任は、売買の目的が物ではなく権利の場合にも適用されます(たとえば、貸付金債権という権利の売買で、貸付金債権の実際の残高が売買契約で合意した内容と異なることが判明すれば、売主には契約不適合責任の責任が発生します(民法565条))。
また、契約不適合責任の規定は、改正前民法における瑕疵担保責任の規定同様、請負契約など、売買以外の有償契約にも、その性質がこれを許さないときを除き準用されます(民法559条)。
さらに、商人間の売買においては、商法526条が適用されます。
もっとも、これらは、強行法規に反しないかぎり、当事者の合意により修正が可能です。契約不適合責任に関する契約条項のポイントについては以下の関連記事をご覧ください。
【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】
セカンドステージ債権法Ⅰ 契約法[第3版]
発売日:2020年04月25日
出版社:日本評論社
編著等:野澤正充
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『改正債権法コンメンタール』
発売日:2020年10月05日
出版社:法律文化社
編著等:松岡久和、松本恒雄、鹿野菜穂子、中井康之
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『Business Law Handbook ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』
発売日:2017年06月24日
出版社:日本能率協会マネジメントセンター
編著等:長瀨 佑志、長瀨 威志、母壁 明日香
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
-
改正前民法下でも、数量指示売買の場合には、代金減額請求を認めていました(改正前民法565条、563条1項)。改正前民法は、瑕疵担保責任と数量指示売買を区別していましたが、改正民法では「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」として、統一的に規定されることになりました(筒井健夫=村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』(商事法務、2018)(以下、「一問一答」という)275頁参照)。 ↩︎
-
一問一答280頁。 ↩︎
-
一問一答236頁参照。 ↩︎
-
瑕疵についての善意無過失と解するのが判例です(一問一答281頁参照)。 ↩︎
-
判例(最高裁平成4年10月20日判決・民集46巻7号1129頁)は、「具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある」としていました。 ↩︎
-
「通知」は、損害額の算定の根拠まで示す必要はないものの、不適合の内容を把握することが可能な程度に、不適合の種類・範囲を伝えることが必要と考えられます(一問一答285頁参照)。 ↩︎

隼あすか法律事務所
- コーポレート・M&A
- IT・情報セキュリティ
- 人事労務
- 知的財産権・エンタメ
- 事業再生・倒産
- 危機管理・内部統制
- ファイナンス
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
- ベンチャー

かなめ総合法律事務所
- コーポレート・M&A
- IT・情報セキュリティ
- 人事労務
- 知的財産権・エンタメ
- 事業再生・倒産
- ファイナンス
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
- 不動産
- ベンチャー