外国人を雇用する事業主が採用前、採用後に行う実務と手続
人事労務当社では今後、外国人材を積極的に採用していきたいと考えています。様々なセミナーなどにも参加し、採用にあたって在留資格の制限があることなどを理解しました。しかし、断片的な情報が多く、採用から活用に至るまでの流れがつかめません。採用前と採用後に雇用企業がやるべきことなどを教えてください。
外国人従業員の採用を検討する場合には、まず募集の前に在留資格の要件となる、雇用企業の条件面(職務内容・待遇など)を確認したうえで、応募者の学歴・職歴を明確にしておきます。採用後には、①在留資格の手続、②在留カードの届出、③外国人雇用状況の届出などが必要となります。
解説
募集前に行う在留資格の確認
外国人従業員を雇用する場合には、採用後に在留資格を取得する必要があるため、在留資格の要件に該当する人材を採用しなければなりません。しばしば問題となるのが、いわゆる「人物重視」で採用を進めてしまうケースです。求人に応募してきた外国の方の経験や人柄などに魅力を感じて、すぐさま採用を決め、本人に通知した後に、就労可能な在留資格が取得できないことが判明し、雇用をあきらめざるを得ないといった事態も起こり得ます。
そのため、外国人従業員を募集する前には、在留資格の要件を確認・明確化しておくことが重要となります。
外国人従業員の採用後に行う手続
外国人従業員を採用した後に行う主な手続は次の3つです。
- 在留資格の手続
- 在留カードの届出
- 外国人雇用状況の届出
在留資格の手続
外国人の出入国を管理するため、日本では「在留資格制度」が採用されており、在留資格にはそれぞれ日本国内で行うことができる活動の内容と期間が定められています。日本に滞在する外国人は、あらかじめ在留資格で定められた制限の範囲内で日本に滞在することが可能になります。
在留資格には、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。
- 雇用関係などを基礎とする在留資格
雇用企業との契約や学校への入学などが在留の基礎となる。 - 身分関係を基礎とする在留資格
国際結婚などの身分事項が在留の基礎となる。
このうち、手続面などで企業としての対応を求められるのが、①雇用関係などを基礎とする在留資格です。
雇用関係などを基礎とする在留資格
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日または15日 |
| 教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年または3月 |
| 芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年または3月 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年または3月 |
| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年または3月 |
| 高度専門職(1号) | ポイント制による高度人材 | 5年 |
| 高度専門職(2号) | 無期限 | |
| 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月または3月 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年または3月 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年または3月 |
| 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年または3月 |
| 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年または3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年または3月 |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年または3月 |
| 介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年または3月 |
| 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月または15日 |
| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年または3月 |
| 技能実習(1号) | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲) |
| 技能実習(2号) | 法務大臣が個々に指定する期間 (2年を超えない範囲) |
|
| 技能実習(3号) | 法務大臣が個々に指定する期間 (2年を超えない範囲) |
|
| 文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月または3月 |
| 短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間 |
| 留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校等の学生・生徒 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
| 研修 | 研修生 | 1年、6月または3月 |
| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
| 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表(平成30年8月現在)」
在留カードの届出
在留カードとは、在留資格を取得して日本に中長期間滞在する外国人を対象に交付され、外国人が適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。
在留カードには次の事項が記載されています(出入国管理及び難民認定法19条の4))。
- 氏名・生年月日・性別・国籍等
- 住居地
- 在留資格・在留期間・在留期間満了日
- 就労の可否
- 在留カードの番号・交付年月日・有効期限満了日
- 就労制限の有無
- 顔写真 等
銀行口座の開設や携帯電話の契約、アパート・マンション等の賃貸借などの重要な契約の際に本人確認書類として提示が求められることが多い在留カードは、外国人従業員にとって社会生活を送るうえで必要不可欠な書類と言えます。
在留カードは新規入国者などに対して、日本に上陸した一部の主要な空港や港などで交付されます(出入国管理及び難民認定法19条の6)。在留カードの交付を受けた中長期滞在者は、居住地を定めてから14日以内に市区町村に届け出なければなりません(出入国管理及び難民認定法19条の7第1項)。なお、上記以外の空港や港で上陸した場合には、上陸許可の際に在留カードは交付されず、入国後14日以内に市区町村に居住地の届出を行った後に、在留カードが住居宛に郵送されます。
在留カードに関する届出は外国人労働者本人の義務となりますが(出入国管理及び難民認定法19条の7第1項)、届出義務を怠った場合には、実務上では在留資格手続が不許可となったり、出入国在留管理局から雇用企業として説明を求められることなどが考えられます。そのため、在留カードの手続については、雇用企業の側でもしっかりと管理することが望ましいと言えます。
外国人雇用状況の届出
外国人雇用状況の届出は、外国人の雇入れ・離職の際に事業主に義務付けられている届出です。外国人雇用状況届出書(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定および職業生活の充実等に関する法律施行規則10条に関する様式3号)の記載事項は次のとおりです。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期間
- その他厚生労働省令で定める事項
事業主は、雇入れ・離職の場合ともに、これらの事項を翌月末日までにハローワークに届け出る必要があります(雇用対策法28条)。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、助言、指導または勧告の対象になるだけでなく、30万円以下の罰金が科されます(雇用対策法33条、40条1項2号)。
届出の記載内容の正確性は、一義的には事業主が担保することとなります。パスポートや在留カード等でしっかりと確認したうえで、届け出なければなりません。
外国人雇用状況の届出は正規雇用の場合はもちろん、以下の場合にも必要となります。
- アルバイトの場合
- 派遣労働者の場合
- 雇用契約を締結しない場合(ダンサー、歌手、楽器演奏者、プロスポーツ選手等で使用従属性があると認められる場合)
さいごに
そのほか、外国人従業員の採用時には、就業規則等の重要事項について、外国人従業員本人が理解できる言葉で説明することも重要です。もし日本語で十分な理解が得られない場合には、外国語に翻訳するなどの雇用企業側の配慮が求められます。
日本人を雇用する場合と比較して、外国人を雇用する企業にはより多岐にわたる実務や手続が求められるため、慎重に対応することが必要です。
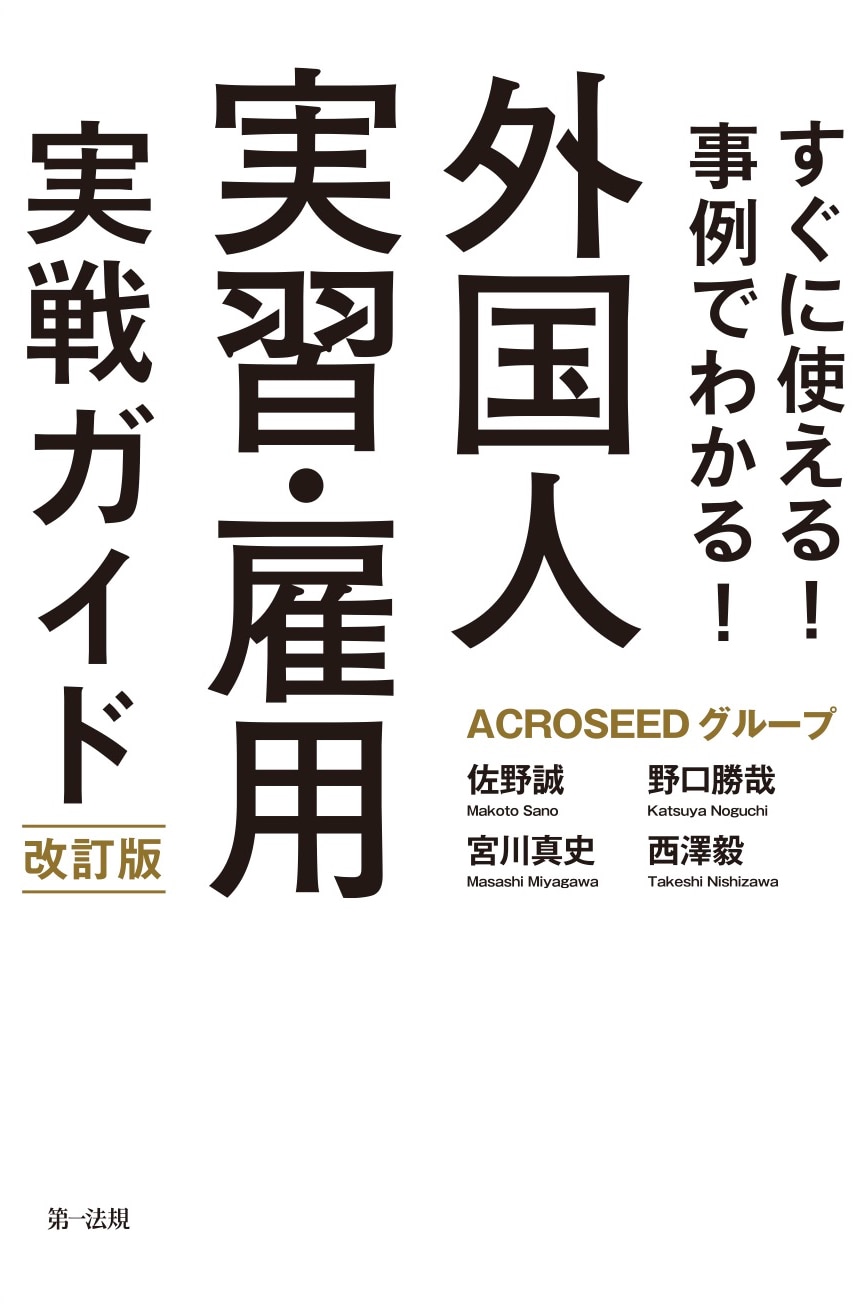
- 参考文献
- すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版
- 著者:佐野誠、宮川真史、野口勝哉、西澤毅
- 定価:本体3,600円+税
- 出版社:第一法規
- 発売年月:2018年7月

株式会社ACROSEED