インターンシップで外国人学生を受入れる際の手続きと留意点
人事労務製造業を営む当社は、将来の正社員としての外国人採用を見据えて、まずはベトナムからインターンシップで大学生を受け入れようと考えています。その後、当社に適した人材については一度帰国して大学を卒業してもらったうえで、入社してほしいと考えています。前段階となるインターンシップの受入れ手続きについて注意する点などはありますか。
インターンシップとは、あくまでも大学教育の一環として実施するものであり、採用活動とインターンシップは切り離して考えるケースが一般的です。インターンシップの滞在期間は、「1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること」が求められます。海外の大学に在学する学生を受け入れる場合は、企業側がビザ手続きを行う必要があります。
報酬は有償・無償を問いませんが、取得する在留資格によって制限があるため注意が必要です。また、滞在日数も在留資格によって異なります。
インターンシップの内容と学生の専攻との間に合理的な関連性が認められない場合には、不許可となるケースもあります。
解説
外国学生のインターンシップとは
インターンシップとは、大学等の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度です。日本企業での就労体験を通して学生の視野を広げ、職業意識の向上に資するのが目的です。一方、サマージョブ(サマーインターンシップ)もインターンシップとほぼ同様ですが、夏季休暇等の期間を利用して行われ、通常は教育課程の一環とはみなされない点が異なります。
とはいえ、いずれも大学と企業の契約に基づき企業等で就業体験を行う点においては相違ありません。人材採用のグローバル化に伴い、在学中の優秀な外国人留学生や外国学生などに自社をアピールする、日本人社員のグローバル化の一環として受け入れるなど、人事戦略の一環としても利用されています。
海外の大学に在籍する学生を受け入れるケースでは、日本企業が海外の大学と契約を結び、授業の一環として学生を受け入れます。海外の一流大学を卒業予定の「高度人材」と言われる学生が対象となることが多く、プログラマーやエンジニアなどの技術職が多くみられます。ビザ手続きなどは、受入れ企業が行う必要があります。
インターンシップのメリット
インターンシップには以下のようなメリットがありますが、あくまでも大学教育の一環として実施するものです。そのため、就職や採用を前提とした活用は好ましくなく、採用活動とインターンシップは無関係とするケースが一般的です。
- 優秀な学生に就業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげる
- 外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てる
- 語学対応、マネージメント能力など、社員教育の一環として役立てる
- 報酬を得ながら外国である日本での生活や文化に触れることができる
- 将来の就職先となるかもしれない
- 学生のうちから社会人としての常識、教養を身につけることができる
インターンシップ受入れ期間
インターンシップの滞在期間は、「1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること」とされています(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(令和元年法務省告示第40号))修業年限とは大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最低期間のことを指し、2年制の大学なら1年間、4年制の大学なら2年間となります。また、1年を超えない期間となっていますので、一度のインターンシップでは最長でも1年の滞在となります。仮に4年制の大学であれば、本人が一度帰国したのち、別の機会でもう1年間インターンシップとして来日することができます。
インターンシップと報酬
インターンシップは、外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本企業との間の契約に基づき実施されます。学生は企業で実際に就業することとなりますが、この就業に対する報酬は有償でも無償でも構わず、具体的な金額についても制限は設けられていません。そのため、なかには学生に対して高額な報酬を払うケースもありますし、無償で実施しているケースも見られます。
とはいえ、学生は海外から日本に学びに来ているため、渡航費用や滞在費などは必要となります。本人の自己負担とすることも考えられますが、一般的には受入れ企業がすべて負担したうえで、最終的に報酬をいくらに設定するのか、という点で落ち着く例が多いようです。
インターンシップと在留資格
海外の大学からインターンシップを受け入れる場合には、在留資格の取得が必要となります。在留資格は滞在期間と報酬の有無によって異なり、以下は主にインターンシップで利用される例です。
| 在留資格の種類 | 短期滞在 | 特定活動 | 文化活動 |
|---|---|---|---|
| 滞在日数 | 90日以内 | 90日以上 | 90日以上 |
| 報酬の有無 | 報酬なし | 報酬あり | 報酬なし |
出典:ACROSEEDが作成
インターンシップの注意点
インターンシップでの受入れは通常は数か月間の短期間となるため、大きなトラブルが生じるケースは多くはありません。しかし、企業での就労が含まれるため、通勤中の交通事故、オフィス内での転倒によるケガなどの労働災害などが生じた際の責任の所在が問題となります。
インターンシップでも、正社員の4分の3以上の就労がある場合には社会保険加入の対象となり(平成28年5月13日保保発0513第2号)、労災保険の適用は雇用とみなされるかどうかにより異なります。状況によりますが、公的な保険が適用されない場合には民間の保険を活用してリスクをカバーすることも検討すべきです。
このほかには、学生側の責任として、以下のようなケースが想定されますが、受入れ時に誓約書を取るなどして防止するケースが多いようです。
- 情報漏えい
- 備品の破損
- 従業員や顧客への暴行・けが
- ビジネスの妨害による売上損失 など
インターンシップ制度は、成長途中の学生に国際的な視野を与え、将来の成長に貢献する重要な制度です。しかし、一部では単純労働の受け皿の1つとして悪用される例もあるため、労働法関連、大学の専攻との関連性などについて審査が行われます。実務上では、学生がその企業で直接生産活動などに従事した結果、利益効果が企業に帰属し、かつ企業と学生の間に使用従属関係が認められる場合には労働者と考えられるケースが多いようです。
また、インターンシップの内容とその学生の専攻との関連性についても審査がなされ、合理的な関連性が認められない場合は不許可となるケースも見られます。当然ですが、風俗営業などに従事するものは認められません。インターンシップでは、受入れ企業がインターンシップ本来の趣旨を理解したうえで適正な受入れを行うことが求められます。
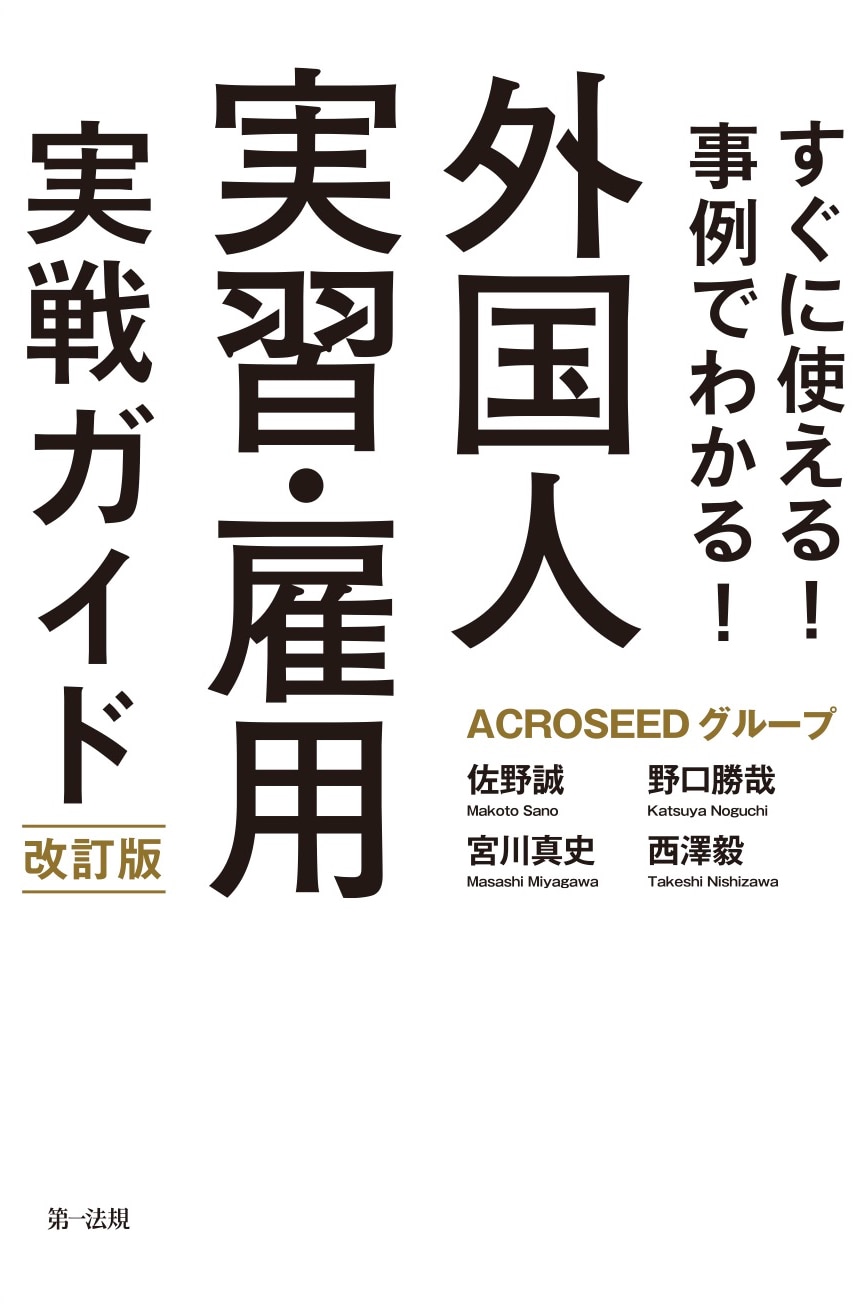
- 参考文献
- すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版
- 著者:佐野誠、宮川真史、野口勝哉、西澤毅
- 定価:本体3,600円+税
- 出版社:第一法規
- 発売年月:2018年7月

株式会社ACROSEED