法人税の所得はどのように計算するのか
税務法人税の所得金額はどのように計算するのでしょうか。
法人税は各事業年度の所得に法人税率を掛けて算出します。法人税の対象となる課税所得とは、企業会計上の利益である「収益−費用」ではなく税法上の所得金額「益金−損金」のことをいいます。
この益金と損金とは、法人税法上に規定される調整を、各事業年度ごとの会計上の収益と費用に行ったものになります。
日常的な会計処理を企業会計とすると、法人税計算のための税務会計は、その企業会計による数字を調整して計算される別のものと考えるとわかりやすいでしょう。
具体的には、損益計算書に記載されている当期利益に一定の調整(税務調整)を加えて、法人税の申告書の別表四という表を使って所得金額を計算します。
解説
目次
課税所得とは
法人税法では、その法人の「各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする」と明記されています。「控除(引き算)した金額」を課税所得といいます。
会社のお金の出入りを決められた方式で計算し、決められた形にまとめることを会計といいます。法人税を計算し、申告書のもとになる数字をまとめるのも会計です。益金、損金、所得という言葉は、税金計算で使う用語です。益金とは、企業会計上の収益とほぼ同じもので、売上や雑収入などの収入のことです。収益≒益金と考えられますが、イコール(=)ではないという点を覚えておきましょう。損金とは、やはり企業会計の費用とほぼ同じといえますが、費用≒損金の方がより違いが大きくなっています。費用と損金の認められる範囲が違うと考えてください。所得とは、益金から損金を引いたもので、企業会計上の収益-費用、つまり利益に該当するものです。前述した法人税法の条文は、法人税は、「利益に対して課税されるのが原則」だといっているわけです。
正確には、益金とは「収益に法人税を算出するための特別ルールで修正を加えた後の金額」、損金とは「費用に法人税を算出するための特別ルールで修正を加えた後の金額」、所得とは「利益に法人税を算出するための特別ルールで修正を加えた後の金額」となります。 次にもう少し、この内容をわかりやすく説明していきます。
法人税算出のための会計(税務会計)と企業会計
企業に関係する会計には、法人税算出のための会計(税務会計)の他に、企業会計があります。同じ「会計」という言葉を使っていても、2つの会計の中身は違います。

企業会計は、会社の実際の姿をできる限り正確に表わすことを目的としています。それに対し、税務会計は、公平な課税を誰もが納得できる形で算出するのが目的になっています。そもそも、会計の目的が違うのです。したがって、会計のルールも税務会計と企業会計とでは違います。
先ほど、益金、損金、所得の説明で出てきた収益、費用、利益とは、前述したとおり企業会計で使う言葉です。
企業会計では、企業が営業活動をして得たお金(これを企業会計では、「資本取引を除いた企業活動によって得たお金」といいます)を収益、そのお金を得るために使ったお金を費用、収益から費用を引いたお金を利益と呼びます。
話を税金に戻しますと、結局、益金、損金、所得とは、企業会計上の収益、費用、利益に法人税法上の特別ルールで修正を加えて算出したものということになります。
税務調整とは
税務会計と企業会計では、会計のルールがどのように違うのでしょうか。ここでは、基本的な考え方だけ説明します。企業会計は、会社の実態をできる限り正確に表わすのが目的です。したがって、企業会計のルールも会社の実態をできる限り正確に表すために策定されています。また、株主や投資家、債権者などの利害関係者が会社の実態を評価するために必要とするデータについては、企業会計による基準で作成するのが基本中の基本です。会社の実態を正確に知りたいという場合は、企業会計のルールで作成する損益計算書(会社が1年間の事業活動で得たお金と支払ったお金のデータ)や貸借対照表(会社の財産をまとめたデータ)を参照しなければなりません。
一方、税務会計は、会社の実態を知る必要があることはもちろんですが、税金を算出するために、「税収の確保」と「税の公平性」という観点も加味しなければなりません。
ここまで説明すれば、もうわかると思います。会計のルールの違いとは、税務会計には、基本中の基本である企業会計のルールの他に「税の確保」と「税の公平性」を加味する必要があるということなのです。
つまり、まとめるとこうなります。税務会計とは、企業会計で算出した収益、費用、利益に「税収の確保」と「税の公平性」という面からの修正を加えることなのです。この修正を加えることを税務調整と呼びます。
「税の確保と公平性を加えて修正する」ことの基本的な考え方は以下のとおりです。
収益、費用、利益には入れるが、益金、損金、所得から除外する修正
以下のような観点から修正を加えます。
(1)社会通念上、課税になじまない支出や収入
たとえば、公益法人の法人税は、営利活動によって得た利益以外は課税されません。つまり、公益の仕事をして利益を得た場合は、その利益を益金という概念に入れる必要がないのです。これは、公益法人が非営利を目的としている法人であるため、その儲けに課税すべきでないという配慮が理由になっています。
(2)政策的な理由から課税になじまない支出や収入
社会通念上、課税すべき支出としては、オーナー企業などが役員(家族)に多額の賞与を支払った場合があります。会社の利益を個人(家族)に渡したと考えることもできるため、税法上は損金扱いできません。
政策的な理由から課税すべき支出としては、寄付金の一部がこれにあたります。寄付金は、社会貢献のひとつで、無償で金品を提供するものです。損益計算書上では、全額を費用扱いできますし、社会貢献という意味からも税金を掛けるべきではないとも考えられますが、税収の確保といった面から、一部しか損金扱いできないのが原則です。
収益、費用、利益には入れないが、益金、損金、所得には入れる修正
以下のような観点から修正を加えます。
(1)社会通念上、課税すべき支出や収入
たとえば、会社が役員に無償で土地などを提供した場合などがあてはまります。企業会計では、収益に入るわけがないのですが、税務会計では、土地をいったん、有償で役員に譲渡したものとみなし、土地代金も役員から受け取ったものと考えます。つまり、会社に益金が発生していると考えるのです。そして、その土地代金をさらに役員に無償で譲渡したとみなします。
(2)政策的な理由から課税すべき支出や収入
たとえば、欠損金の繰越控除がこれにあたります。
こうしてみると、わかると思いますが、税務会計は、国の「都合」が入る余地がかなりあるといえます。実際、企業会計のルールが厳格な経済の法則に則っている一方で、税務会計は、論理的には理解し難い内容も入っているのです。
決算調整と申告調整がある
税務調整には、決算の際に調整する決算調整と、申告書の上で加減して調整する申告調整とがあります。法人税法では、その法人の「各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする」と規定していますので、法人税の所得は、ゼロから「益金」と「損金」を集計するのではなく、企業会計上の確定した決算に基づく「利益」をもととし、「申告調整」を行って求めることになります。
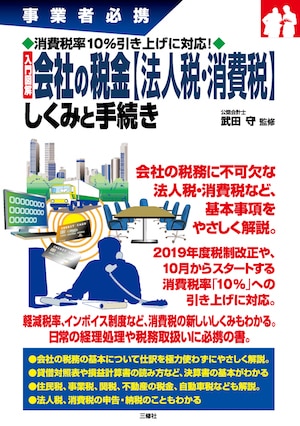
- 参考文献
- 事業者必携 消費税率10%引き上げに対応! 入門図解 会社の税金【法人税・消費税】しくみと手続き
- 監修:武田 守
- 定価:本体 1,900円+税
- 出版社:三修社
- 発売年月:2019年5月

武田公認会計士事務所