現地で採用した外国人社員を研修のために日本に呼び寄せる方法
人事労務当社は東京で機械部品の製造業を営んでおり、ベトナムにも支店を設けて現地での生産を行っています。今度、現地採用したベトナム人社員を日本に呼び寄せ、日本での製造研修を実施しようと考えていますが、どのような方法がありますか。
現地採用社員の研修にあたっては、「企業内転勤」、「技能実習」、「研修」、「短期滞在」などのさまざまな方法があります。日本での研修内容に応じて的確な手段を選ぶことが重要です。
解説
企業研修での外国人社員の呼び寄せ方法
現地採用社員に製造業の研修を日本で行う場合、その職務内容、日本での滞在期間などにおいて、その手段が異なってきます(出入国管理及び難民認定法別表第1および出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2)。
企業研修で利用される受入れ方法
| 在留資格 | 就労の有無 | 滞在期間 | 該当する職種 |
|---|---|---|---|
| 企業内転勤 | 可能 |
長期間(更新あり) (入管法施行規則別表第2) |
主に事務職 (入管法別表第1の2) |
| 技能実習 | 可能 | 最長5年まで (入管法施行規則別表第2) |
主に現業系職種 (入管法別表第1の2) |
| 研修 | 不可 | ケースにより1年程度 (入管法施行規則別表第2) |
見学・聴講など (入管法別表第1の4) |
| 短期滞在 | 不可 | 最長90日 (入管法施行規則別表第2) |
見学・聴講など (入管法別表第1の3) |
「企業内転勤」での受入れ
「企業内転勤」には学歴要件がなく、原則として現地での採用から1年以上が経過している外国人社員の日本への呼び寄せが可能です。給与の支払いも現地と日本のどちらでもよく、使い勝手がよいため多くの企業で活用されています。しかし、日本で行う業務内容は、他の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」で定められる職務内容に限定されます。これは主に事務職などが該当し、工場内での作業などに従事することはできません。そのため、主たる業務が何であるかにより、活用できるかどうかが異なります。
「技能実習」での受入れ
次に「技能実習」ですが、これは大きく分けると技能実習1号と2号、さらに企業単独型と団体管理型の組み合わせで、合計4パターンに分かれます(技能実習は優良管理団体の場合には3号まで受入れが可能ですが、本稿では割愛します)。
技能実習の4つのパターン

技能実習1号
技能実習1号は、入国後1年目の技能等を修得する活動であり、最大1年間の滞在となります。原則として業種に制限はありませんが、日本の優れた生産等の技術移転であることが十分に立証されなければなりません。
技能実習2号
2年目以降は、2・3年目の技能等に習熟するための活動である技能実習2号に移行することになりますが、2号に以降できる職種(移行対象職種)はあらかじめ決められており、業務内容がこれに該当すれば移行することも可能です。そのため、自社で行おうとする研修内容が、移行対象職種に含まれるかどうかを事前に確認しておくことが必要です。
企業単独型
企業単独型は、自社が受入れ機関となり技能実習生の研修計画の作成から住居の手配などをすべて行う方法です。すべて自社内で完結するので、すべての実務をコントロールできますが、その分、社内で行う事務作業のボリュームが増えるため、どちらかというと大企業が活用する例が多いようです。
団体管理型
団体管理型では、まず技能実習制度を扱う事業協同組合に加入します。事業組合を第一次受入れ機関として技能実習生を受け入れ、自社は第二次受入れ機関として技能実習生を受け入れることになります。呼び寄せに必要な事務作業などは、原則として事業協同組合がすべて行ってくれるため、自社は本来の目的である研修業務に専念できます。こちらは主に中小企業を中心に活用されていますが、自社の現地採用社員などの特定の人物を受け入れるためには、現地送出し機関との調整などが必要となるため、実現が難しいケースも多くみられます。そのため、今回のケースでは企業単独型での受入れが適しているといえます。
「研修」での受入れ
「研修」での受入れも選択肢の1つです。しかし、「研修」では企業の生産活動に携わることができず、主に工場の見学や聴講などがメインとなります。機械操作の習得という目的で工場内に入ることも可能ですが、「研修」の場合は、企業が行う生産活動と完全に切り離された状態、つまり、別工場や別ラインで研修活動を行わなければならず、活動の結果として製造された製品等はすべて廃棄するなどの処置が求められます。後述する「短期滞在」と似ていますが、「研修」日本に滞在できる期間が比較的長期間となるため、6か月から1年程度の研修で活用される例が多く見られます。
「短期滞在」での受入れ
「短期滞在」は、滞在中の活動内容は「研修」とほぼ同じですが、滞在期間が90日以内と定められています。そのため、比較的短期間の研修に用いられています。また、相手国が査証免除協定国であれば現地の日本大使館などで査証(ビザ)を取得する必要もなく、最も手軽に行える方法といえます。設例のケースは、ベトナムからの呼び寄せのため該当しませんが、長期的な他の在留資格を取得するケースよりも比較的簡単に実施できるのが「短期滞在」の特徴です。
さいごに
以上、日本で現地採用社員の研修を行う場合の代表的な方法を挙げました。いずれの方法にもメリットとデメリットがあり、国内でどのような研修を行うのかにより、選ぶべき方法は異なります。まずは目指すべきゴールを設定し、そこから逆算して手段とスケジュールを決定していくことが推奨されます。
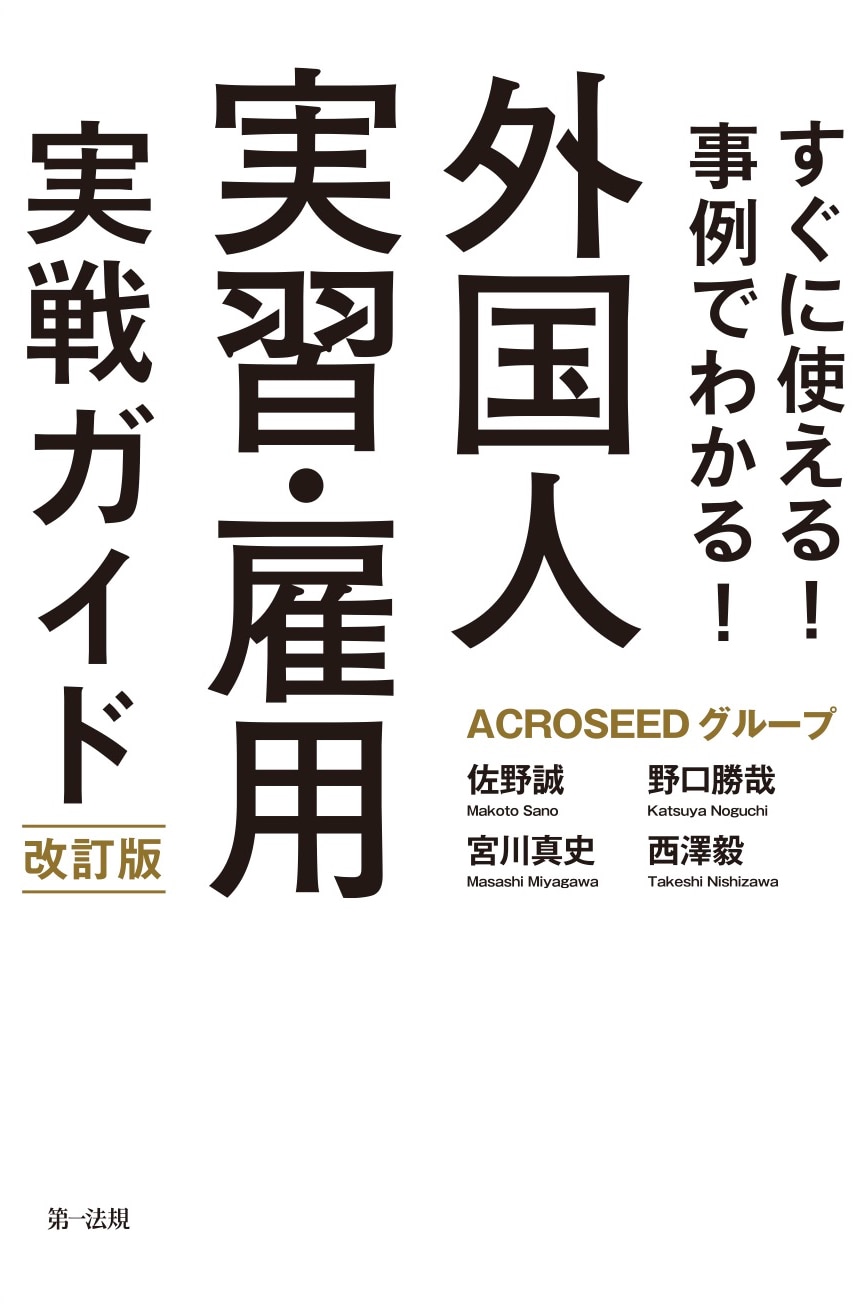
- 参考文献
- すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版
- 著者:佐野誠、宮川真史、野口勝哉、西澤毅
- 定価:本体3,600円+税
- 出版社:第一法規
- 発売年月:2018年7月

株式会社ACROSEED