61〜90件を表示 全90件

第一線の研究者が多分野にまたがる事業承継問題を縦横に論じる。重要判例・学説を漏れなく解説しながら、最新の実務と留意点を簡潔に紹介する理論実務書。手に取りやすい文体や体裁を意識し、各章冒頭に要旨を、章末に参考文献を付す。
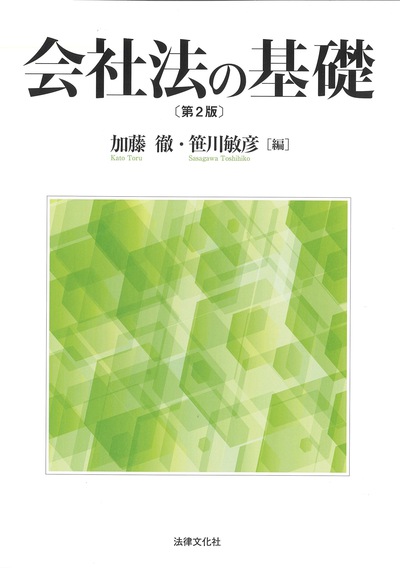
はじめて会社法に接する学生のため条文と通説、重要判例に基づき平易・簡潔に法の基礎を概説する。令和元年の会社法改正、令和2年の会社法施行規則等改正を踏まえてアップデート。
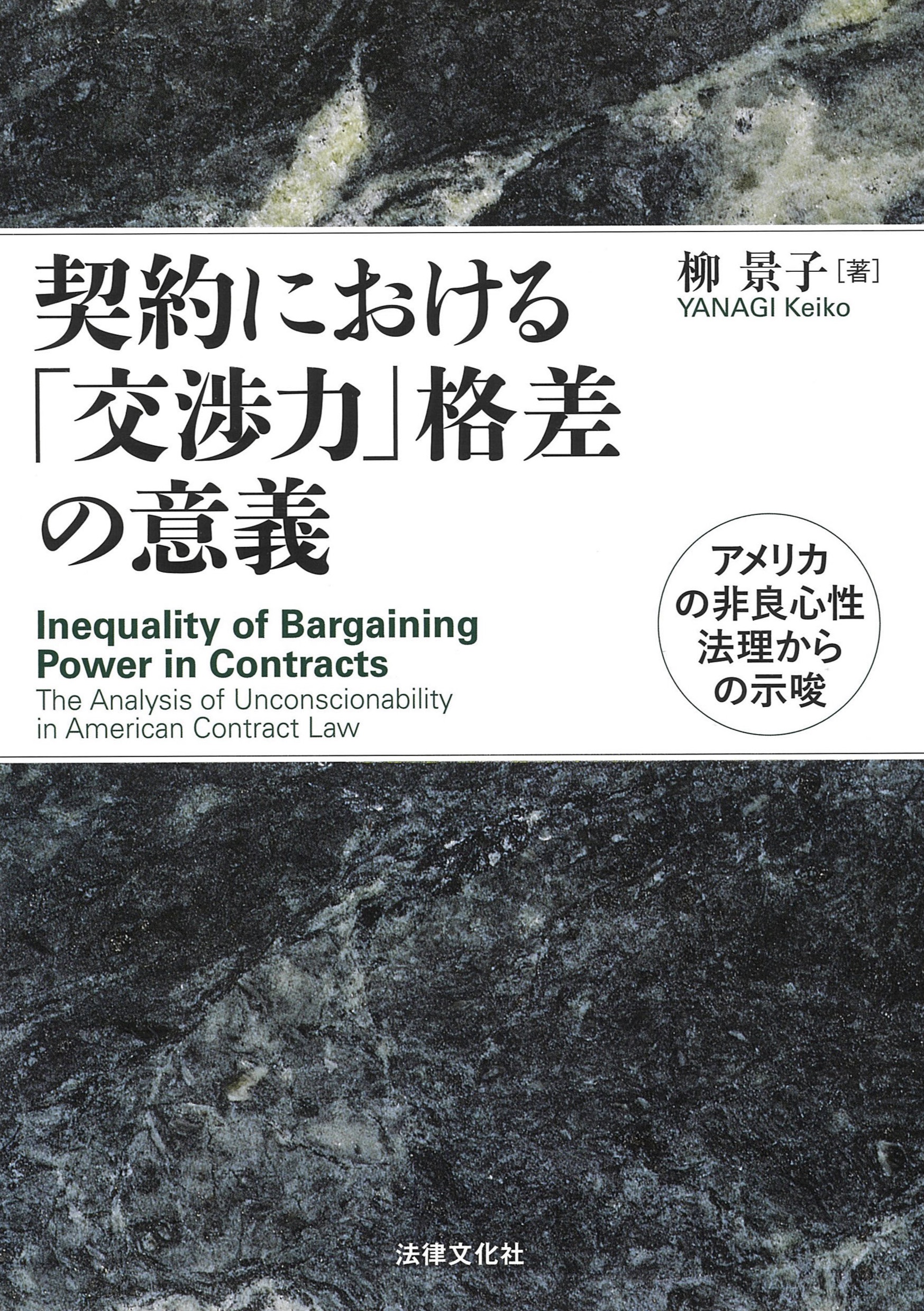
契約自由の原則にもかかわらず、成立済の契約内容を司法介入で無効とする例外とは。本書はこれをアメリカ契約法の非良心性法理から検討し、「バーゲニング・パワーの不均衡」概念が左右すると示す。さらに日本法における「交渉力の格差」概念の再定義を行う。
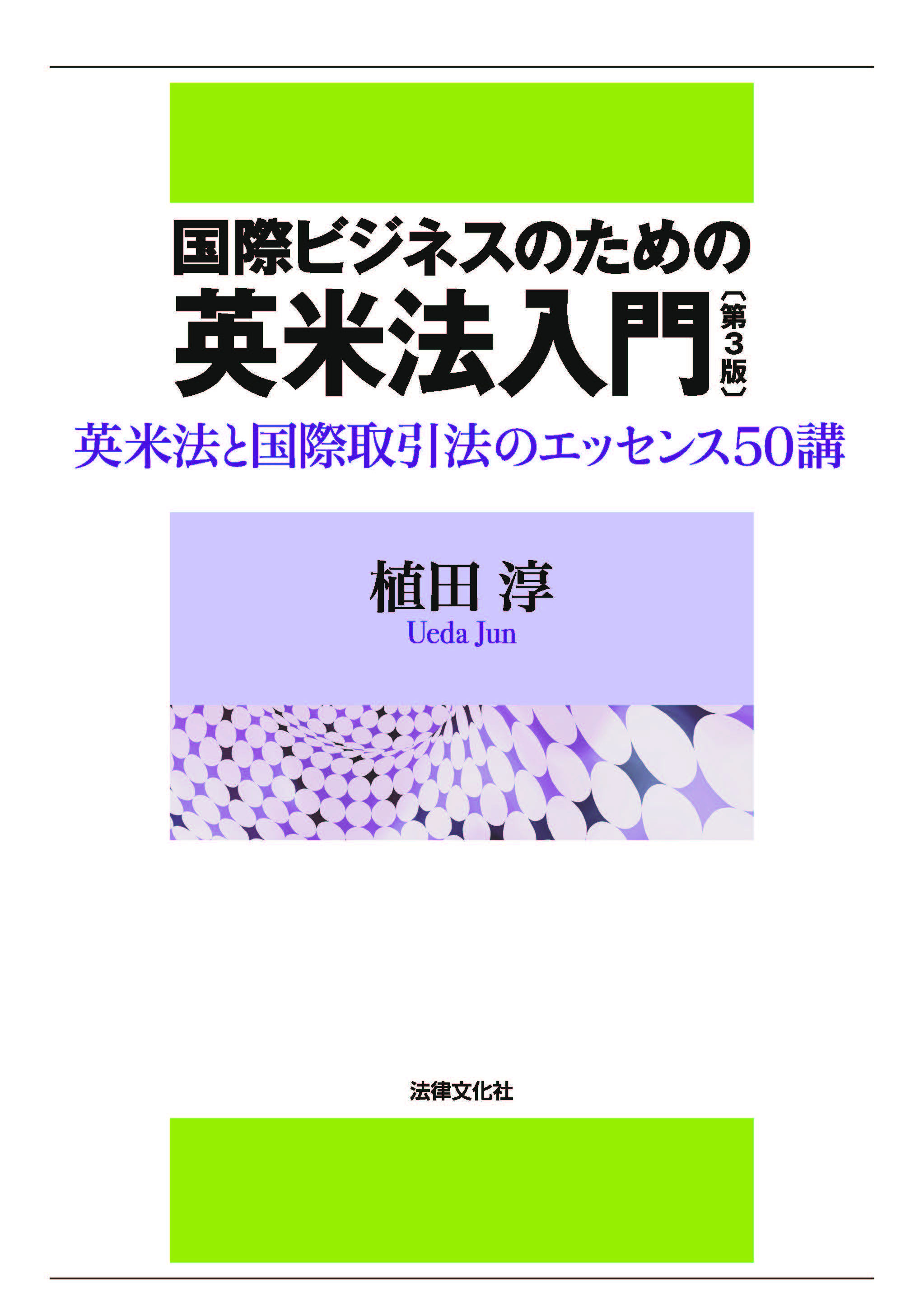
第2版刊行(2012年)以降の、米国特許法の改正や、日本のWTO貿易円滑化協定受諾といった国際取引法分野における動向をあらたに盛り込んだ最新版。国際租税法の項目を加筆・修正することでより実務に対応した。
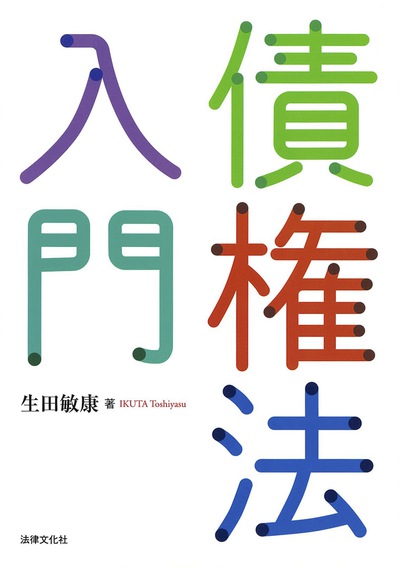
債権法が1冊で学べる初学者向けテキスト。判例・通説をふまえたオーソドックスな内容で、債権法全般のエッセンスを簡潔かつわかりやすく解説。「契約」「債権」「不法行為ほか」の3部構成、理解のしやすさから「契約」から始める。

判例分析とイギリス倒産法との比較を通じて、破産手続における多数当事者の債務関係の取扱いを考察。判例の問題点を検討、日本の債権調査確定手続や求償権者の権利行使、主債権者の権利行使の制約について新たな示唆を試みる。
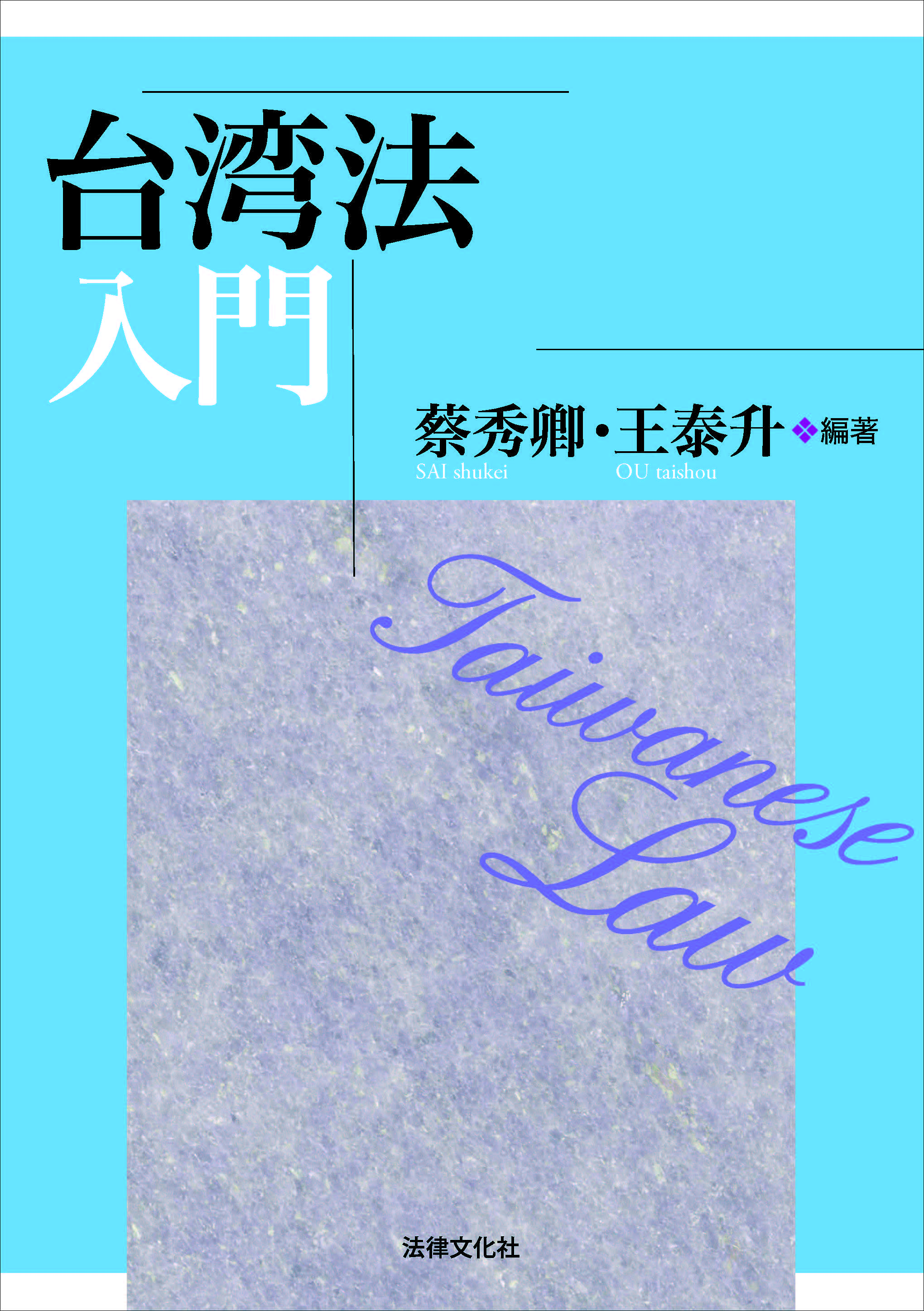
本邦初の台湾法のテキスト。日本との異同を意識し、比較法研究として重要な分野・テーマを取り上げる。各法分野では「歴史」「構造の特徴」「原理原則」「判例」を解説し、法的地位や法教育にも論及する。
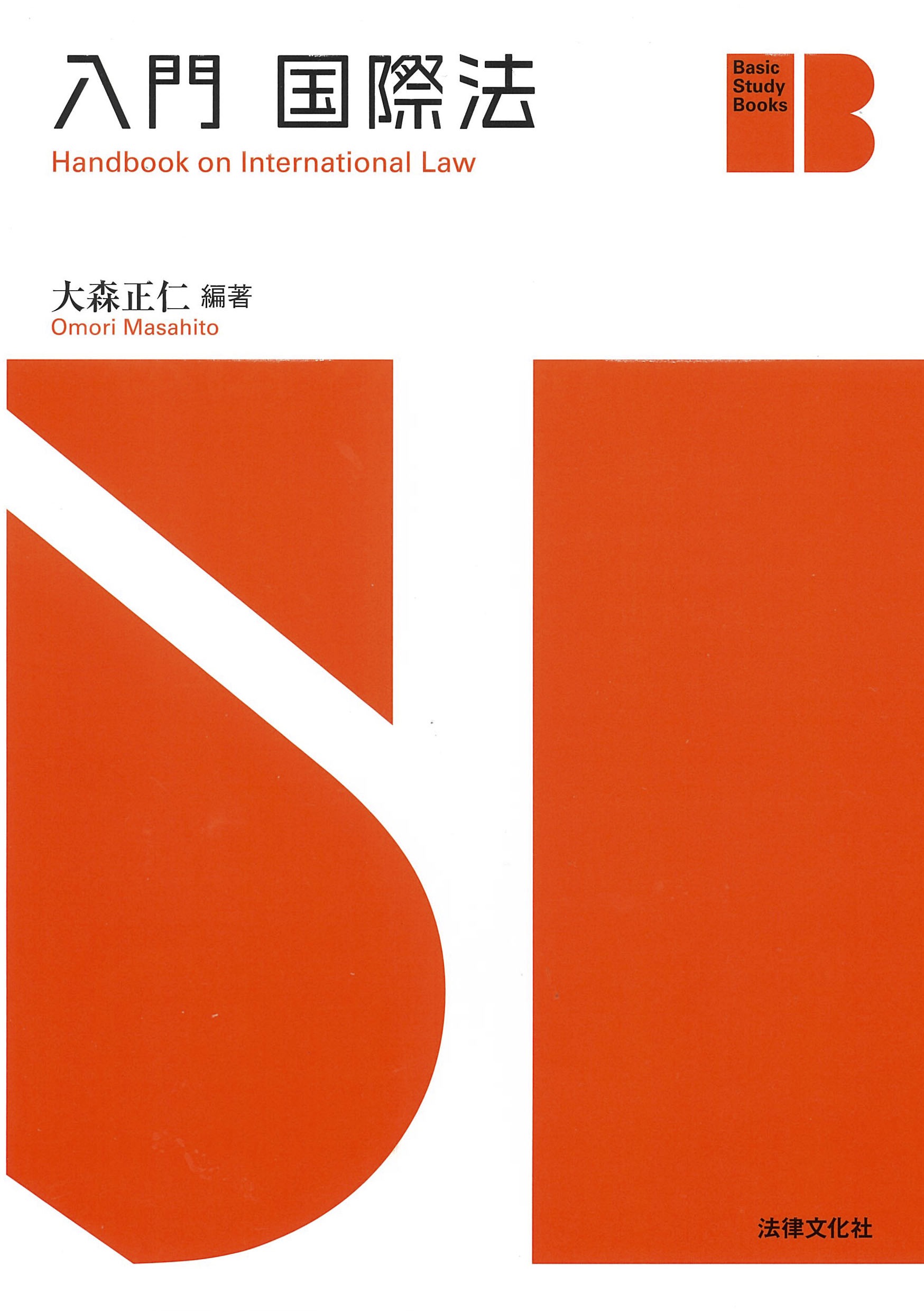
世界中で起きる事柄で国際法に関わる事例は枚挙に暇がなく、その重要性は非常に高くなっている。本書では、現在の国際法を巡る様々な問題を考慮に入れ、総論と各論という2部構成を採用することにより,取り上げることのできなかった新しい問題への対応を可能にし、最新の情報を踏まえてわかりやすく解説する。
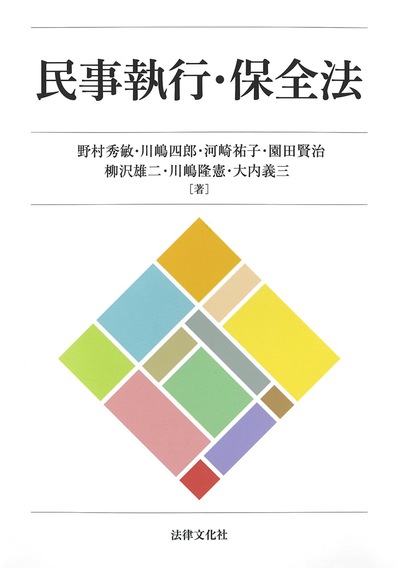
初めて民事執行・保全法を学ぶ人の入門書。司法書士試験の必修科目であり、法曹や企業実務の現場で権利実現の最終段階に位置する重要な法制度を、最新の判例と研究成果を踏まえて解説。理解を深めるコラム、書式例も掲載。

契約不適合責任制度論をめぐる議論を整理のうえ、理論的観点から分析する。ドイツ法およびEU法の最新の理論動向を踏まえた比較法的考察から重要論点につき解釈論の提示を試みると同時に、日本法への示唆を明示する。
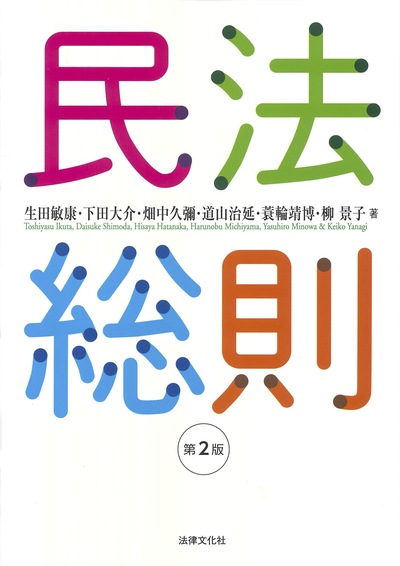
民法総則をはじめて学ぶ人のためのコンパクトな入門書。抽象度が高く難解な民法総則を、体系にそってわかりやすく解説。複雑な制度は図表やイラストを用い理解を助ける工夫をした。成年年齢引下げに伴う関連規定の改正など最新の動向に対応。
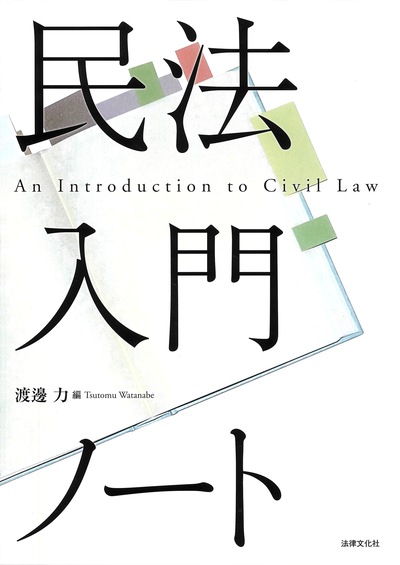
“騙されて結んだ契約はどうなる?” “相手が契約を守らなかったら!?” “交通事故に巻き込まれてしまったら!?” 数々の身近な問題にひきつけて民法の果たす役割をよみとく。各テーマ2頁読み切り。穴埋め問題と巻末練習問題で理解度確認もできる。
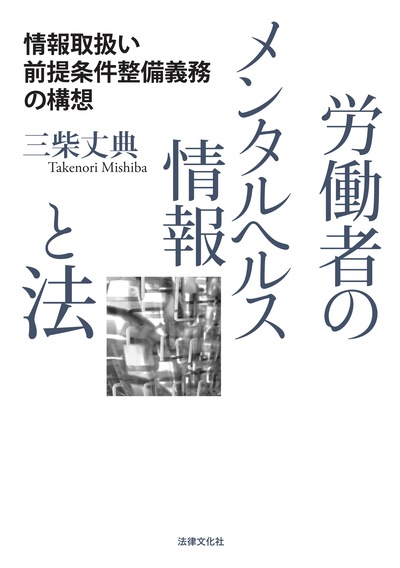
労働者のメンタルヘルス情報の取扱いをめぐる諸問題について関係法規および法理・学説を整理し、諸問題を理論的に解明。メンタルヘルス情報の取扱い適正化のための法理論構築へ向け、論証を試みる。
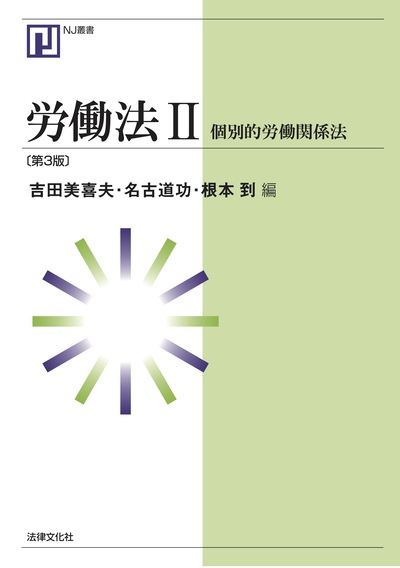
個別的労働関係法および労働紛争の解決手続に関する体系的教科書。基本事項はすべて網羅し、重要な判例・法理論は批判的な吟味も含め踏み込んで解説。旧版刊行(2013年)以降の法改正や「働き方改革」に伴う立法動向をふまえ改訂。
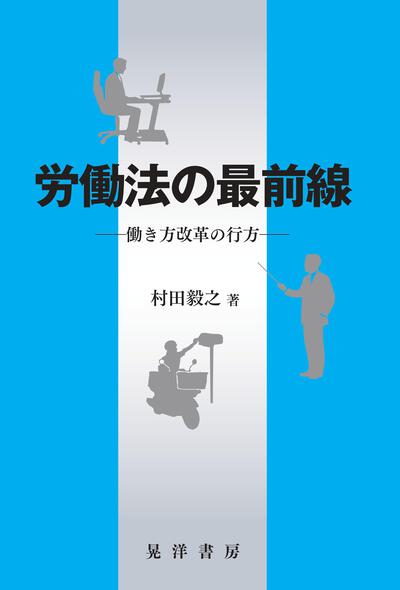
働き方改革関連法の本格的稼働の時を迎え、長時間労働の是正や正規・非正規労働者間の格差、ハラスメント対策等、課題山積の労働法について、判例理論や学説をも踏まえて、労働基準法を中心とする個別的労使関係法を検討する。最前線にある現実の姿を確認する。
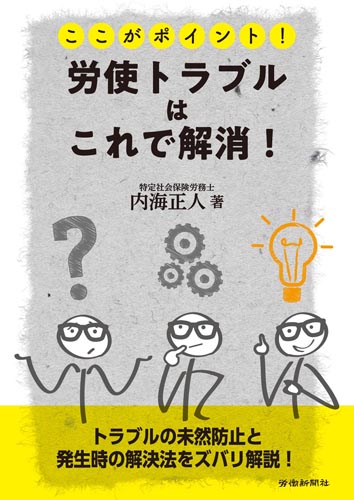
会社と社員の間での労務管理で、「あれ?」「こんなときはどうするのか?」という細かい疑問から経営の根幹を揺るがす問題まで、類似の判例等を交えて、「なぜ労使トラブルとなってしまったのか?」「裁判等ではどのように判断されるのか?」をわかりやすく解説。著者の人気メルマガの内容を厳選して掲載しています。
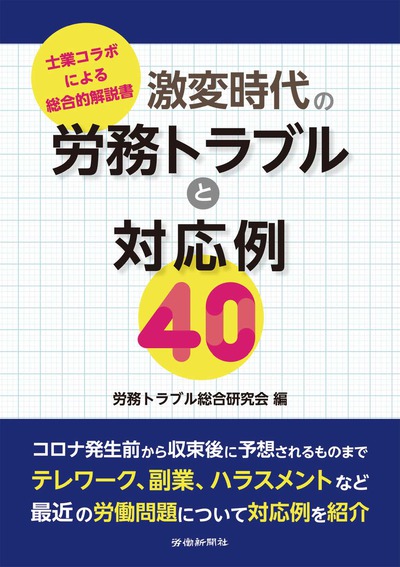
新型コロナの感染拡大で雇用環境が大きく変化したため、それまでは労使間の信頼関係などからトラブルとならなかった事がらについても従業員と軋轢が生じ、労務問題が顕在化している状況といえます。本書は労務トラブル回避のために経営者が最低限知っておくべき法律に関するポイントを理解しやすいようトラブル事例を40挙げて対応例を紹介しています。経営者の方や人事担当者に是非お読みいただきたい一冊です。
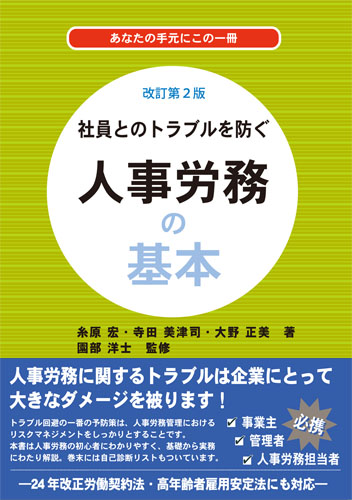
本書は、人事の勉強に時間を割けない中堅・中小企業の人事労務担当者、実務経験の浅い方や初めて人事労務の管理職になった方を対象に、最低限知っておくべき人事労務の知識を取り上げて解説しました。第2編の各章末にある「こんなときどうするQ&A」では実務対応が理解でき、第3編の人事労務診断チェックリストを使用することで、自社の現状と改善点が分かるようになっています。平成24年改正労働契約法・高年齢者雇用安定法に対応した改訂を発行。円満な労使関係構築に欠かせない1冊です。
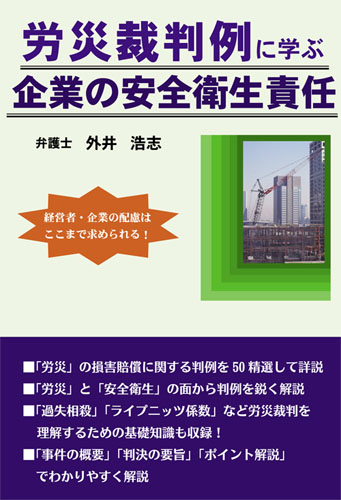
労災裁判の第一人者である筆者が、弊社発行「安全スタッフ」に連載した記事から50の判例を精選。各事件につき、詳細に解説をしています。労災事故はなぜ発生し、企業の安全衛生責任がどのように問われたのかを判例を通じて理解できます。 第1章では、労災裁判を正しく理解するうえで欠かせない知識(不法行為責任、予見可能性、過失相殺、ライプニッツ係数など)をわかりやすく解説。 企業の安全衛生責任の正しい理解に欠かせない一冊です。

実務家が相談活動の実践のために利用できる労働相談マニュアル。1995年初版発行から広く活用された労働弁護士のバイブルを5年ぶりに全面改訂、2021年12月24日発刊。単なる労働法の解説に留まることなく、最新の判例や法令を紹介しつつ、労働者が労使紛争に対処するための実践的な道筋を具体的に示している。また、各分野の法的判断の枠組みを解説するだけではなく、労使紛争に対処するために必要となる様々な制度や手続にも言及している。
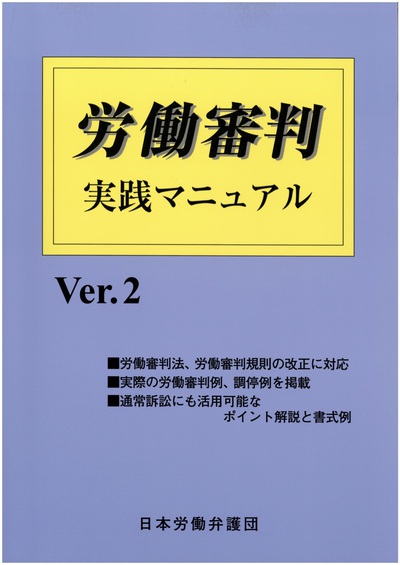
労働審判制度の仕組みと活用方法をわかりやすく解説。申立類型ごとの書式付。個別労使紛争の迅速かつ適正な解決に役立ちます。労働審判制の意義とその特徴、申立に際しての留意点、労働審判手続の流れ、労働審判の効力、他の紛争解決手段と労働審判制との選択など、実務運用をふまえて徹底解説。労働相談や労働問題の実務に携わる方々に必携の1冊。

これからのグローバル競争やAI革命を勝ち抜くための企業活動において、真に価値ある人材を計画的・継続的に育成していくエッセンスについて、具体的な事例も交えて解説します。人材開発に関する理論を理解し、その実践的手法を身につけるとともに、具体的な方策の立案にご活用いただけます。

本書は就業規則を新規に作成または改定する際の参考モデルとして使用していただくために、多くの一般的な実例規定とともに解説しています。今回、働き方改革関連法の成立・施行、労働契約法の改正、育児・介護休業法の一部改正など、個々頻繁に行われた労働法制の改正をふまえて改定しています。

企業経営を効率的・組織的に展開していくうえで、社内における規程は極めて重要です。本書は実際に使用されている模範的な規程を紹介し、社内の規程の作成および見直しの参考として、すぐに利用できるように構成しています。最近の法改正や企業経営を取り巻く環境変化を反映した改訂です。
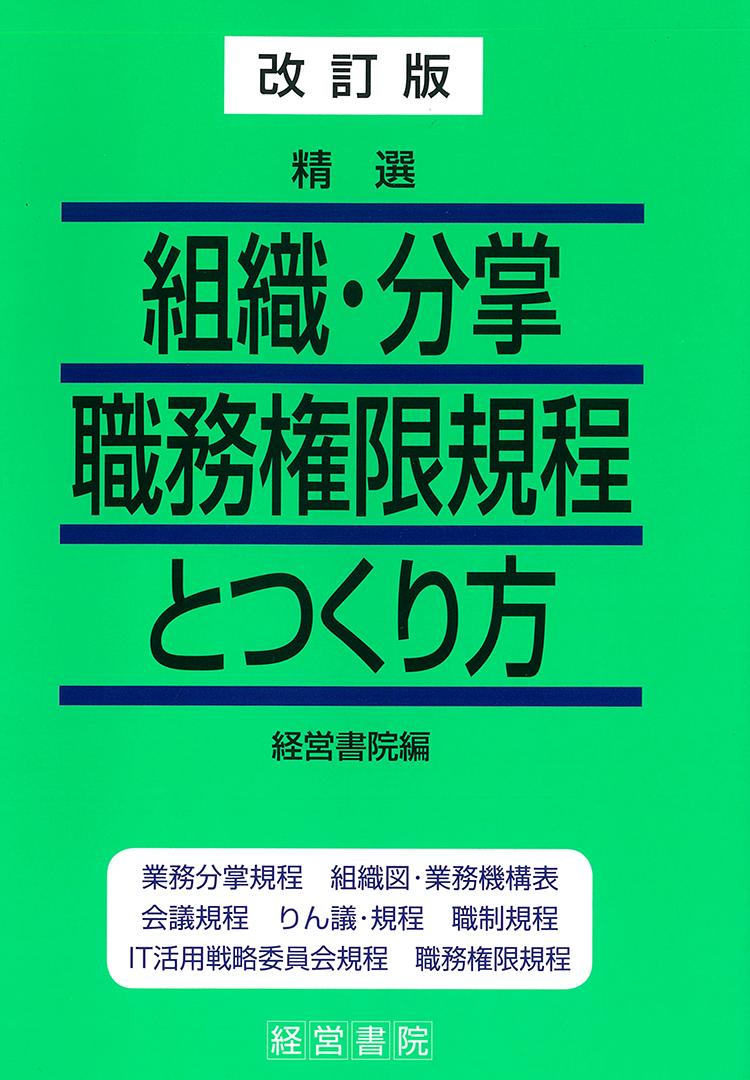
業務分掌と職務権限は、組織の中核部分に関して、その上下、左右、奥行きを決める重要な規程である。会社の組織づくりに役立つ組織、分掌、職務権限規程のつくり方をくわしく解説。
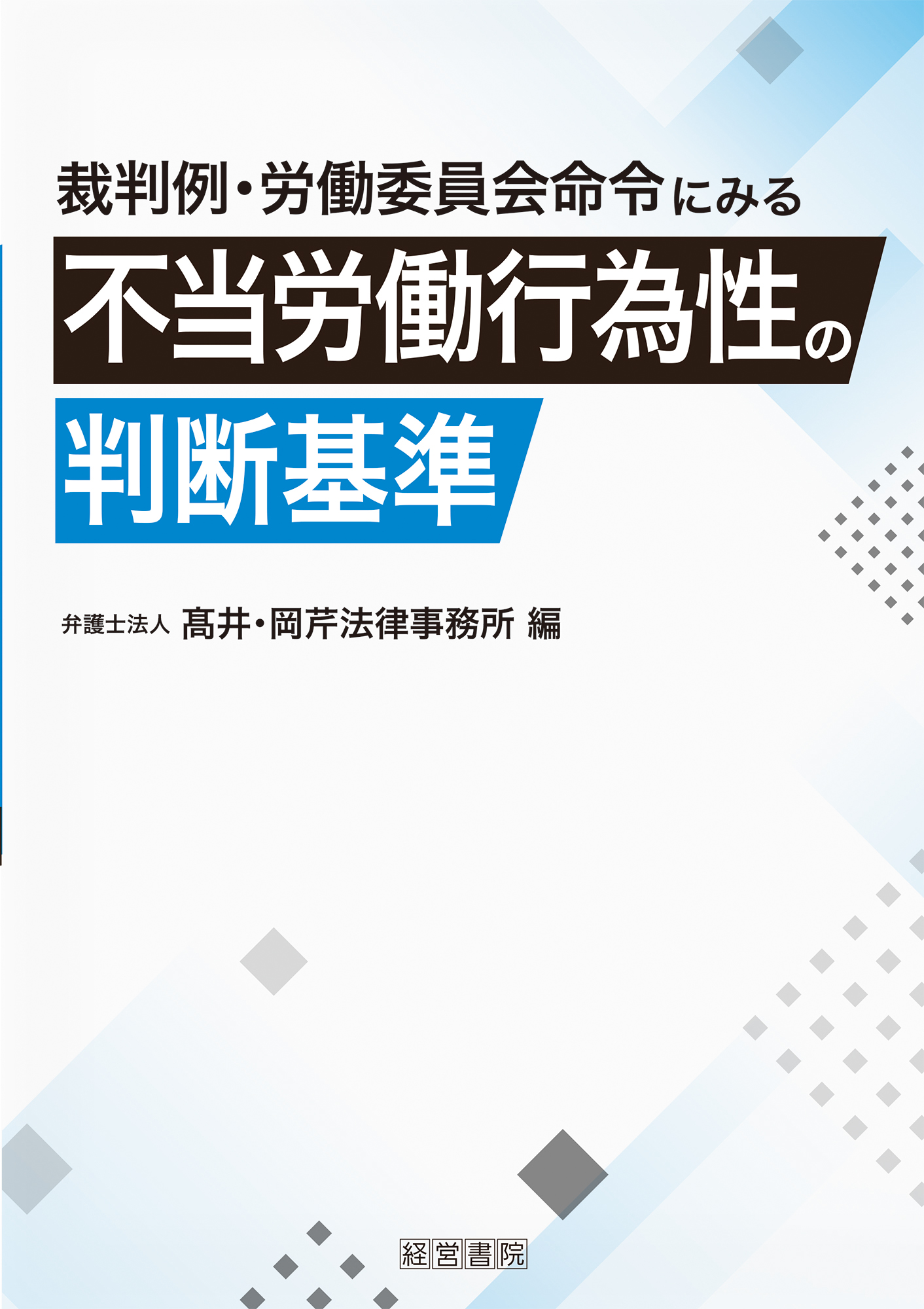
本書は、過去の裁判例・労働委員会命令のすべてを検証したうえで、労使紛争の中での使用者の言動を具体的に分類し、裁判所や労働委員会で不当労働行為と判断された事例、そうでなかった事例の双方を紹介することにより、不当労働行為性の判断基準を明らかにするものです。本書で紹介した先例を参考に、使用者の言動が不当労働行為に当たるか否かの判断を、より正確に、効率的に行うことで、労働問題における不必要な労使紛争やトラブルを避けることができます。
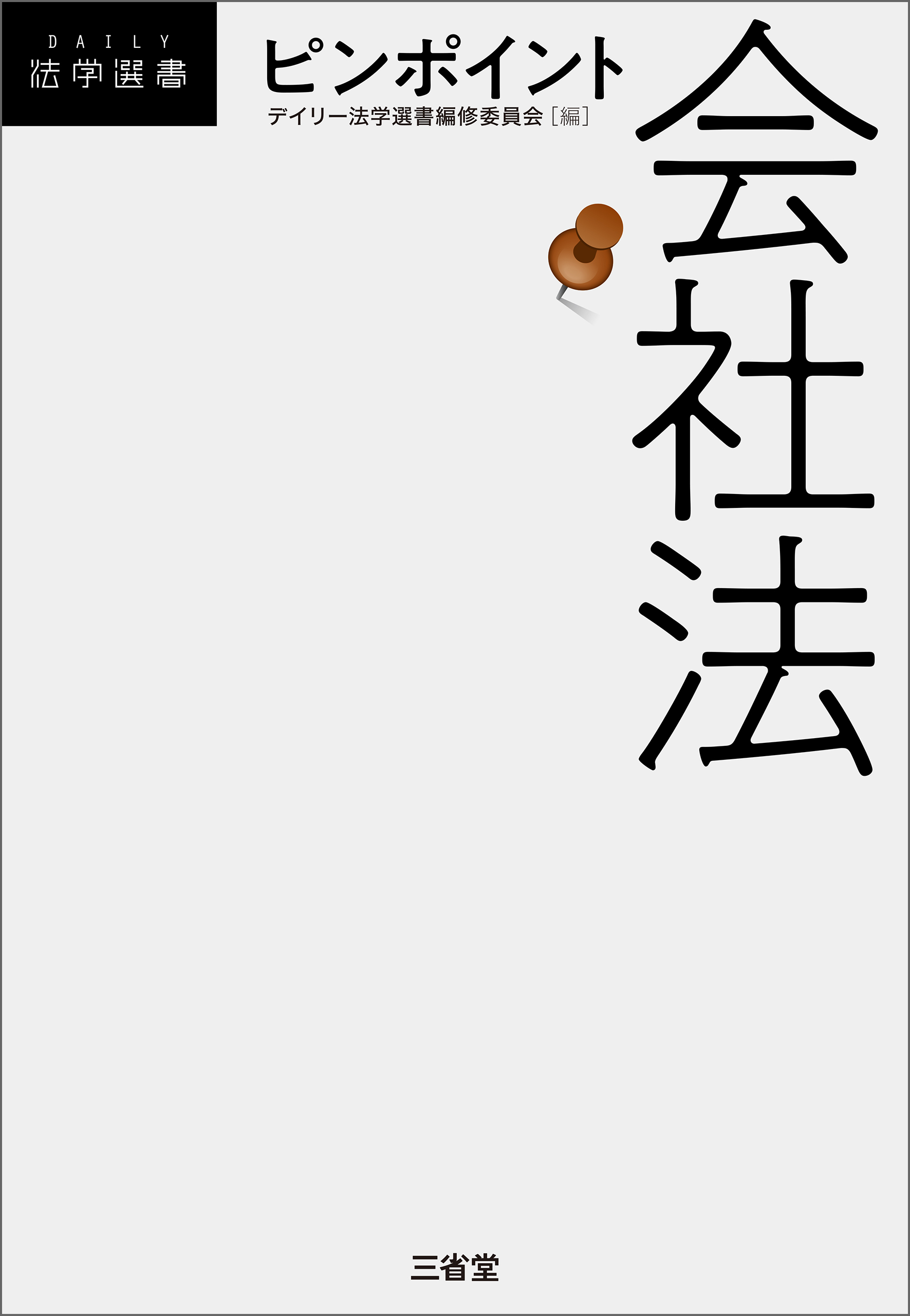
法学部生・ビジネスマン・一般読者向けの最新法学教養シリーズ。基本法中最も難解な会社法の中核をバッサリとわかりやすく解説。法学部の試験対策にも最適。
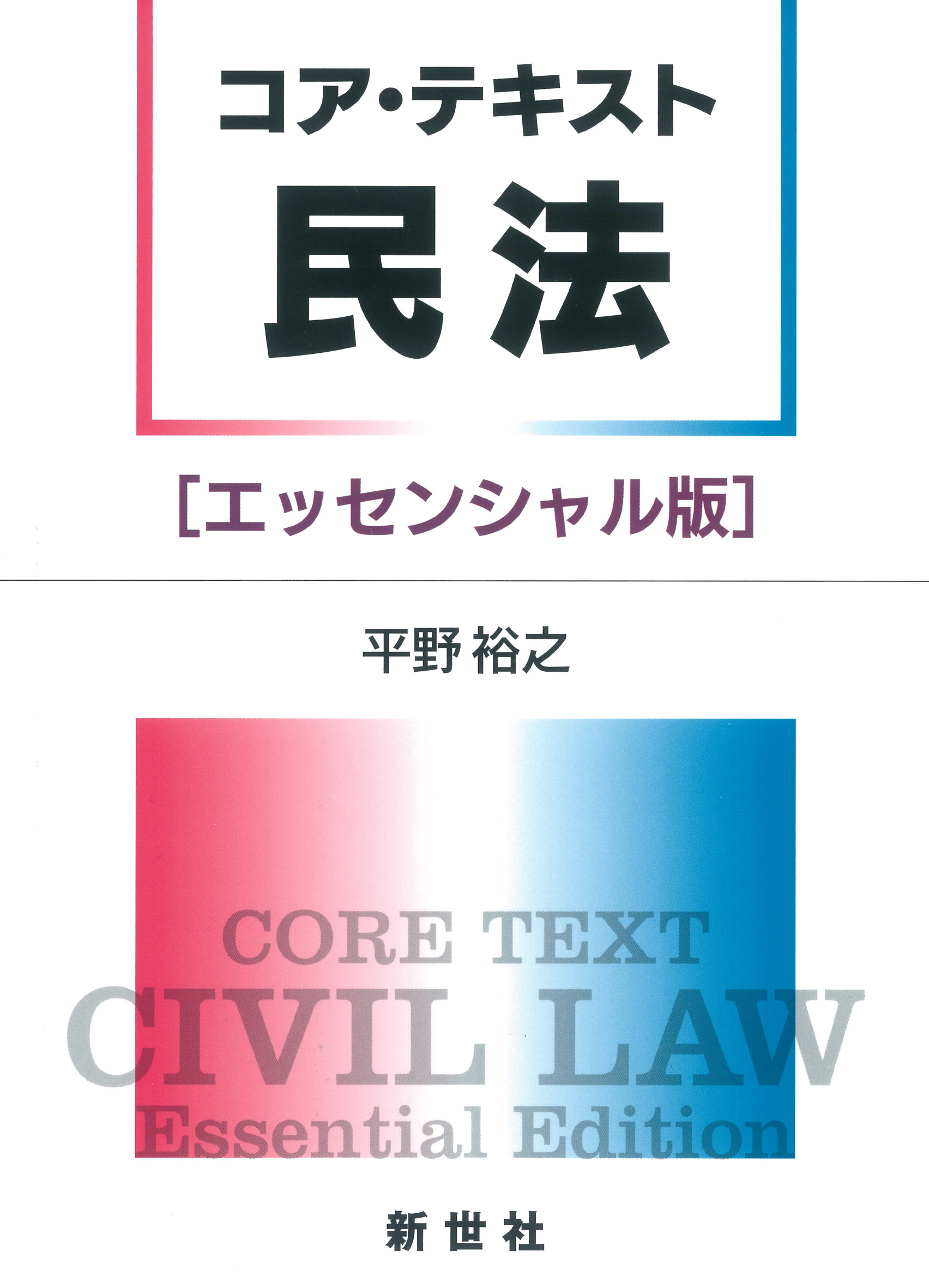
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト。民法全体を鳥瞰し、各領域の要所を的確に解説する。法学部学生の学修における参照用、予備試験・司法試験受験前に必要な知識の確認、公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の対策に最適。また、実務家が近時の法改正・判例を確認し、民法の最新情報を取得するのにも有用。
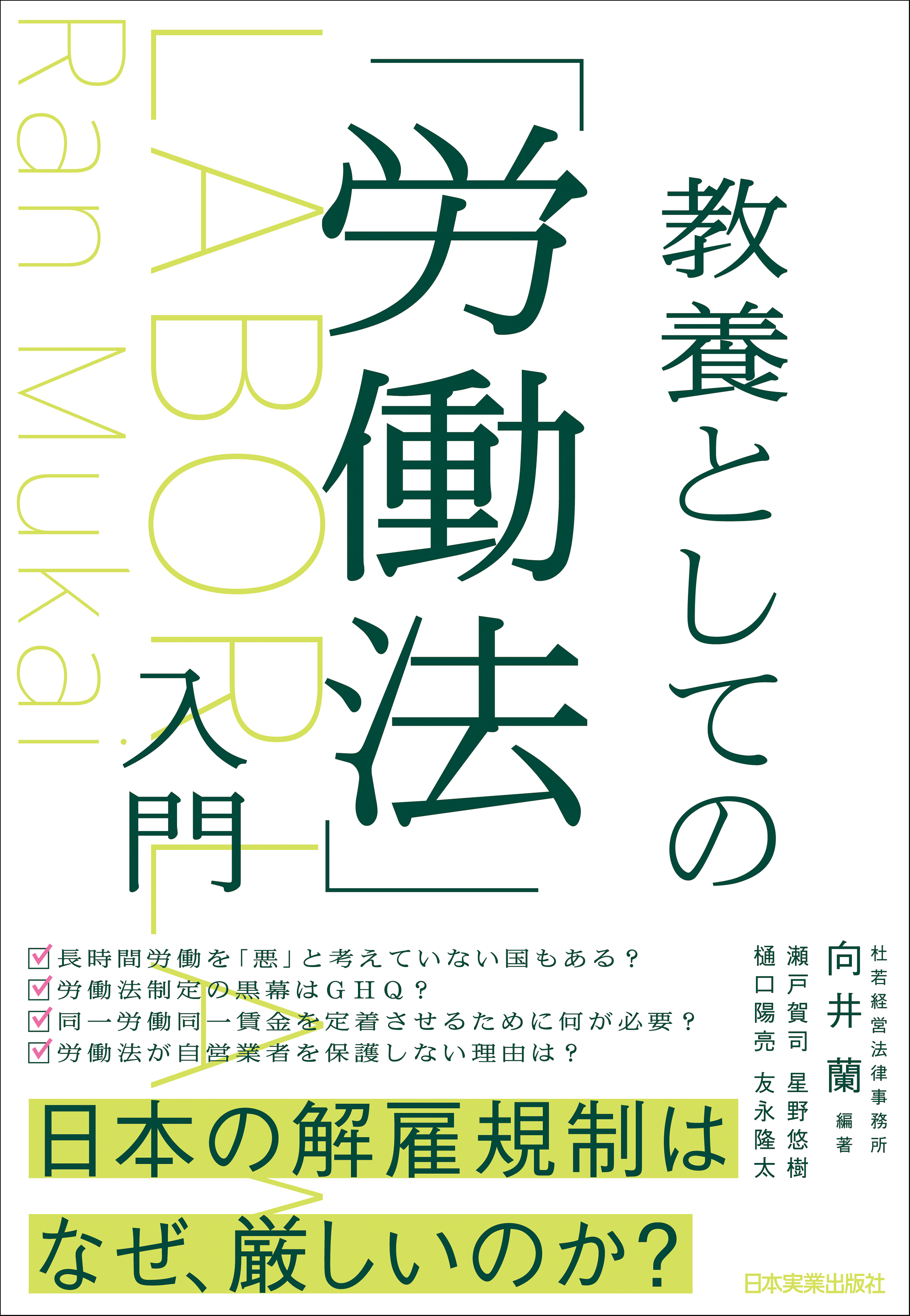
労働法制の歴史や世界の労働法制との比較をしながら、労働時間、休暇、配転、解雇などの労働法が定めるルールを解説。直接、実務や試験には役立たないかもしれませんが、多様な働き方が求められる今後の社会で生じる課題を解決する上でのヒントが満載です。
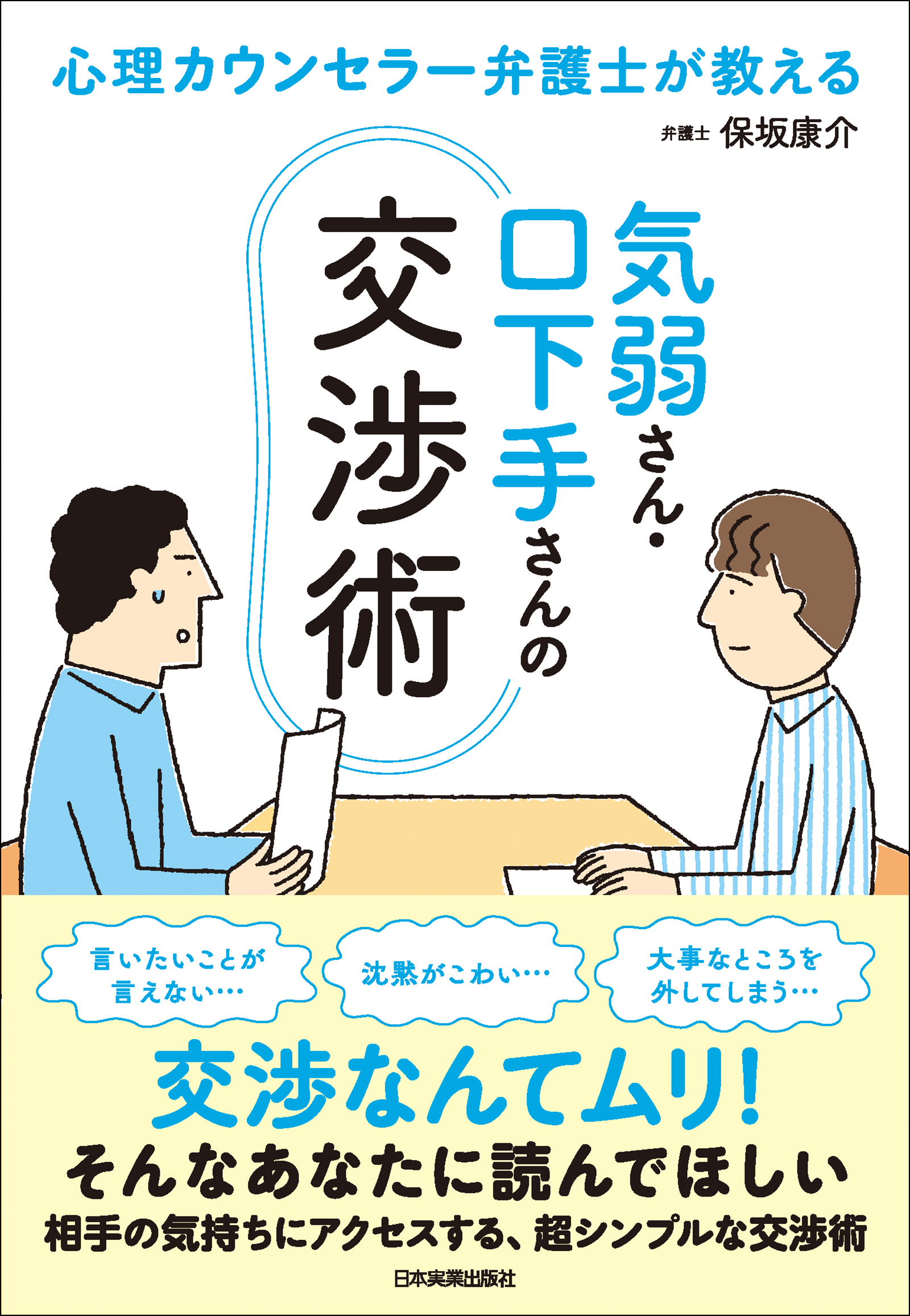
何らかの交渉をする機会は沢山あります。でも押しが弱いし話すのも上手くない…できれば避けたい方も多いでしょう。本書はそんな人でもあらゆる場面で使える交渉術を紹介。心理カウンセラー資格をもつ弁護士で、口下手な著者だからこその実践的ノウハウです。