法務部と情報システム部が一体となり導入した電子契約サービス 運用成功の秘訣は相談しやすい文化にあり – カルビー株式会社
法務部
目次
新型コロナウイルス感染症の影響で加速した「脱ハンコ」の流れ。電子契約サービスの導入を進めた企業も多く見られます。
スムーズなサービスの導入、効果的な運用には部門間の連携が欠かせません。今年7月に電子契約サービス「クラウドサイン」を導入した、カルビー株式会社法務部の宮本 博史氏は「部門を超えて同じ方向を向くことが大切」と言います。宮本氏と共に同社で「クラウドサイン 」導入の旗振り役を担った、法務部の芦澤 良平氏、情報システム部の田中 良氏に導入の経緯と部門間の役割について伺いました。
社内からの評判も良い電子契約 テレワークで進んだ検討の経緯
「クラウドサイン」はどのように利用されていますか?
芦澤氏:
取引先の理解をいただければ、法令上の規制のない限り、業務や契約の種類にかかわらず利用しています。
宮本氏:
グループ全体に電子契約サービス導入の案内をしたところ、子会社から取締役会議事録、監査役会議事録の承認、保管などに使えないか、と質問がありました。当初想定はしていなかったのですが、これから利用を考えているところです。
子会社の方も関心を持っていただけたのですね。電子契約サービスを検討されたきっかけや検討期間を伺えますか。
芦澤氏:
1年以上前から電子契約を含めたリーガルテックサービス全般について検討していました。当時検討していた時の目的は主にコスト削減と時間短縮です。
そのような中、コロナの影響によって原則テレワークになり、電子契約に検討のフォーカスを絞りました。今年の4月から6月まで本格的に検討を進め、7月の導入に至ります。
宮本氏:
1年以上前の検討開始時は、煩雑な印紙税の判断を解決したいと考えていましたね。
本格的な検討をされてからはスピーディに導入されたのですね。現在はどの程度テレワークされているのですか?
芦澤氏:
私は3月の上旬以降、5か月ほど出社しませんでした。在宅期間の間はずっと宮本さんと電子契約の話をしていて。
宮本氏:
家族より芦澤さんと話す時間の方が多かったです(笑)。
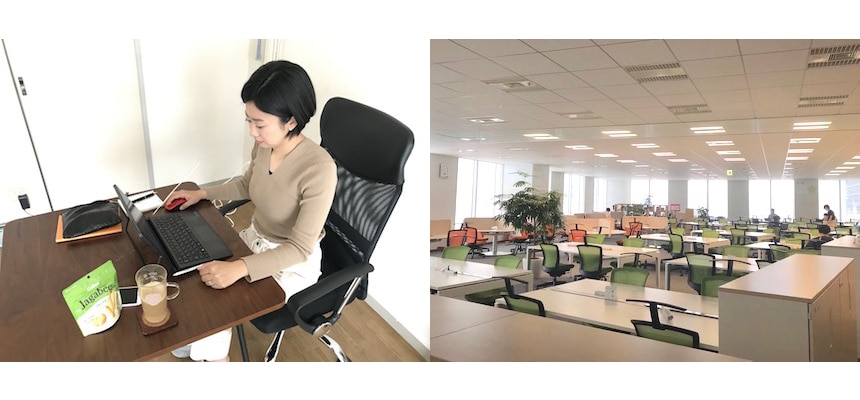
ITによるさらなる業務効率化を推進している(ペーパーレス化の拡大等)
法務部と情報システム部が同じ方向を目指し、導入を決定
田中様は電子契約サービスの導入にどう関わられたのですか。
田中氏:
昨年から全社で情報基盤の見直し、デジタル化のプロジェクトが立ち上がり、間接部門も電子化を進めようと動いていたところ、電子契約サービスのセキュリティチェックの依頼が情報システム部に寄せられました。
私はCSIRTの責任者としてチェックをしていたのですが、セキュリティ上の判断をするだけではなく、業務を全体的にシステム化する方法を法務と相談しながら進めました。
情報システム部(以下、「情シス」)と法務部の方が、コミュニケーションをとりながらプロジェクトを進めていくことは以前にもあったのでしょうか。
田中氏:
情シスから法務に相談する機会は多かったです。知財関係のワークフローを見直したこともありましたね。
芦澤氏:
サービスの導入にあたって情シスの方は積極的に背中を押してくれます。最近は私たちからも「こういうことできない?」と相談する機会がかなり増えてきました。
田中氏:
情シスからは、法務の業務がかなり大変に見えていて、早く電子化したい、セキュリティ面でのハードルさえクリアすればどんどん進めていきたい、と考えていました。
他社の方からは情報システム部門と法務部門の距離が遠い、という意見を伺うこともあります。お互いに協力していくためのアドバイスをお願いします。
田中氏:
情シスと法務の距離が遠いという感覚はないですね・・・。前は席も近かったし、お世話になることも多いから物理的にも精神的にも距離感はないです。私たちのところに新入社員が入ったときは必ず法務に挨拶に行っていますよ。
芦澤氏:
弊社はフリーアドレスを早くから導入していて、慣れ親しんだ人が常に隣にいる状況ではない中で働いていましたので、自分で情報を取っていく、自分で調べる人間が多い風土です。
なので、情シスに限らず気軽に他の部署の方に相談しますし、我々も相談されます。当たり前のことですが、適宜適切な部署に相談することが大切、という文化が醸成されています。
当社の文化が部門を超えた協力となり、意思決定の早さや、導入の早さにも繋がったのではないかと感じています。
宮本氏:
向いている方向が同じかどうかも大切だと思います。大きな方向性が共有できいていれば部門を超えた協力がしやすいのかなと思います。
特に今回は新型コロナウイルスの影響もあり、業務を簡素化し、リモートワークへの対応を大急ぎでやらなければ、という思いも共有しやすい状況でした。
田中氏:
確かに。本社のスタッフとして同じ方向を向いているかどうかは、私も重要だと思います。
ルールづくりと徹底した準備で事業部から得た好評価
電子契約サービスを検討する際、重視した点についても伺えますか。
芦澤氏:
まずはユーザビリティを重視しました。実際に利用する取引先さま、弊社の事業部門が使いやすくなければ導入した意味がありません。
そのほか、ポイントになったのはシェアや認知度の高さです。どういうサービスかイチから説明するのと、「CMもやっていて話題になっているあのサービスです」という説明では受け手に理解いただくまでのスピード感が違います。
宮本氏:
導入までのスピードも重要でした。意思決定をしてから2か月ほどで導入できたのですが、他のサービスと比べてもかなり早いイメージでした。
運用開始までの進め方についても教えてください。
芦澤氏:
まずは総務部門と運用方法について話を詰めました。
当社では契約書の製本、押印、保管は基本的に部署ごとに実施しており、総務部門が取りまとめています。法務は契約書のドラフトチェック、稟議、社長印の押印に関与します。
総務と法務で役割分担されているのですね。特にどのような点に考慮しましたか。
芦澤氏:
現行の紙とハンコによる運用と差をできるだけ作らない、利用しやすい方法を考えました。机上の空論に終わらないよう、いくつかの部門でテスト的に「クラウドサイン」を利用してもらってから全社に展開しました。
宮本氏:
承認フローの仕組みづくりは情報システム部門の協力も多く得ながら、芦澤さんが主に取り組んでくれました。たとえば申請システムのメニューに、電子契約で締結する文書か、紙で締結する文書か選択できるようになっています。どうしても紙で締結する文書が一部分残ってしまうので。
芦澤氏:
ルールづくりは一番時間がかかりましたね。便利なサービスであるが故に、適切な承認フローを経ないで利用されるリスクも考慮しました。たとえば、「クラウドサイン」の「承認機能」を活用して、社内決裁の得られていない契約書が無断で締結されないようにしています。
利用してみて良かった点があれば教えてください。
芦澤氏:
社内の人たちからは「すごく簡単だね」という意見をもらえています。社内営業を行って利用を促した甲斐がありました(笑)。
宮本氏:
締結の便利さ、印紙代の負担がないことは大きな変化です。一度「クラウドサイン」 を使った部署は、続けて使ってもらえる傾向が強いですね。
事業部の方に利用を促進した秘訣はありますか。
芦澤氏:
マニュアルを整備し、取引先向けのメールテンプレートや資料は用意しました。担当者向けの説明会は8月中に4回実施し、トータルで100名くらいの方に参加いただきました。
入念に準備されたのですね。否定的な声はありませんでしたか?
芦澤氏:
一部には懐疑的な声もありましたが、丁寧にメリットや、削減できる効果を説明しました。テスト環境を使って説明会の場で使用感を体験するコーナーを設けたのは良かったです。私が司会をしながら一緒にやってみたら「こんなに簡単なんだ」とか「やってみたらできそうな気がしました」など非常に前向きな意見が多かったです。1回使えば懸念はだいぶ減るものですね。
取引先の方にも利用いただくために工夫されていることがあれば伺えますか。
芦澤氏:
法的観点で懸念がある場合に提出する資料なども準備しています。宮本さんや私が直接対応する場面もありますね。
宮本氏:
高額な印紙代がかかる案件で試しに利用したケースもあります。おそらくコストメリットを感じていただけたと思います。

社内から社会へ 電子契約を将来のスタンダードに
見えてきた課題、今後の展望についてお聞かせください。
芦澤氏:
紙で締結していた契約の運用も曖昧だった実態が明らかになり、ルールの周知方法などを考えるきっかけになりました。また、電子契約サービスで締結した契約書の保管方法については、より効率的な運用を検討中です。
展望という点で言えば、今後はグループ会社にも展開したいですし、取引先さまの理解を得ていく方法はさらにブラッシュアップが必要と考えています。
宮本氏:
もっと社内手続きが簡素になるような仕組みは田中さん、芦澤さんはじめ社内のメンバーと一緒に考えていきたいです。
田中氏:
契約書関連の業務、情報のやりとりにはまだアナログな部分、非効率な部分が残っていて、一連の流れをデータ化・デジタル化して、効率的に回せるようにしたいですね。
ただ、私個人がまだ電子契約サービスを1回も使っていないので、まずはそこからかな(笑)。
宮本氏:
社内だけでなく、電子契約が将来のスタンダードという認知が社会全体に浸透したら良いですね。
芦澤氏:
「クラウドサイン」を導入するちょっと前のことなのですが、ある方が紙の書類にハンコを押しているのを見て、「電子契約ってどう思いますか?」と軽く聞いたら「押印をしないと、契約締結した気分にならないんだよ」と言っていました。
また、「クラウドサイン」を導入した後にいろいろなお話を聞いていると、「メリットはわかるけど違和感がある」「やっぱり落ち着かない」そういう人がけっこういます。紙文化、ハンコ文化の築いてきた歴史があるからですよね。
だからこそ、今後もより一層、社内・社外を問わずに丁寧に説明を繰り返し、1件でも多く実績を積み上げることが、将来につながっていくと思います。地道に取り組まないといけませんね(笑)。
カルビー株式会社
所在地:東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22階
設立:1949年4月30日
資本金:12,046百万円
代表取締役社長 兼 CEO:伊藤 秀二
従業員数:(連)4,053名 (単)1,765名
※2020年3月31日現在
プロフィール
宮本 博史(みやもと・ひろし)
カルビー株式会社 法務・リスク統括本部 法務部 部長
法務部にて契約関係、商標管理等の業務を担当。
電子計測器メーカーを退職後、2005年カルビー入社。コンプライアンス部門にて社内規程管理、法令遵守啓蒙等の担当を経て現職。
芦澤 良平(あしざわ・りょうへい)
カルビー株式会社 法務・リスク統括本部 法務部 法務課
印刷メーカーを経て、2019年カルビー入社。法務課にて契約関係を中心に、法務関連業務に従事する傍ら、電子契約を含む、法務関連業務のIT化の推進も担当。
田中 良(たなか・りょう)
カルビー株式会社 情報システム本部 情報システム部 部長
大学卒業後、外資系コンサルティング会社を経て2005年カルビー入社。IT企画部門にて、営業改革・商品情報統合・サーバークラウド化・ERP刷新プロジェクトなどでリーダーを歴任。2020年4月より現職
(取材・編集:BUSINESS LAWYERS 編集部)
