景気後退局面におけるクロスボーダーM&Aの代金支払メカニズム
コーポレート・M&A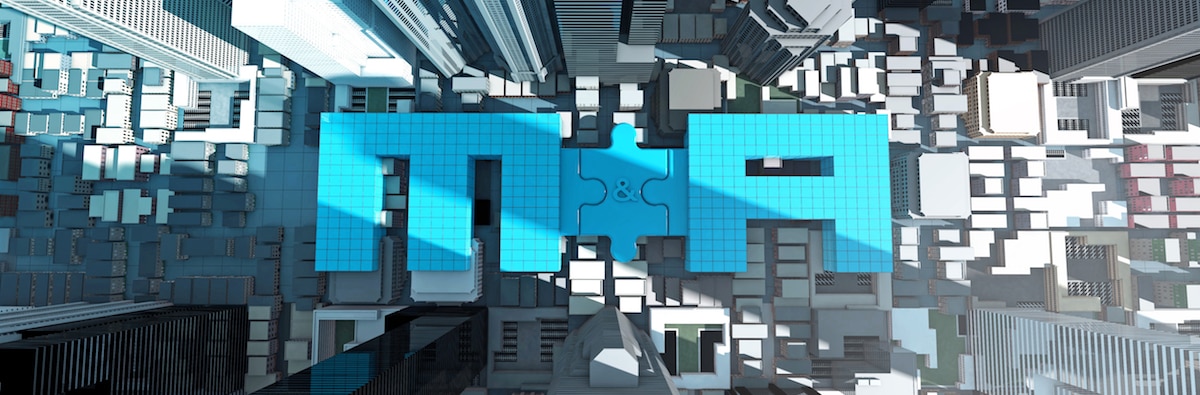
目次
はじめに
新型コロナウイルス(COVID-19)の流行により、世界的に景気の後退局面に入っています。このような状況下でM&Aを行う場合、買収対価額の決定や支払メカニズムについて特別の配慮が必要になる場合があります。買主としては、対象会社の価値評価ひいては買収対価額の決定に慎重となる場合があるでしょう。他方、売主としても、価値が不当に低く算定される事態を避けたいところでしょう。
景気の後退局面ではM&Aに及び腰となる企業も少なくありませんが、オークション案件などでは、潜在的な買い手候補者が少なくなるため、買主としては平時よりも割安で買収が実行できる場合もあります。また、ターンアラウンド型のM&Aは増加することが予想されます。
本稿では、当事者双方にとって有意義なM&Aを推進するため、景気後退局面において、リスクを適切に軽減、分配するための契約メカニズムを紹介します。
買収価格調整
Completion AccountsとLocked Box
M&Aでの買収価格は、通常Cash Free、Debt Free、Normalised Working Capitalを前提とした Enterprise Valueを基に決定します。実際の対象会社の財務状況を反映させたEquity Valueを確定させるにあたり景気後退局面で重要なる交渉ポイントの1つは、買収価格決定の基準時をいつにするかという点です。
日本国内のディールや小規模なディールでは、契約書上、その計算根拠や算出の基となったのがいつ時点の財務諸表であるかに特に言及せず、単純に確定額を買収代金として記載し、事後的な買収代金の調整を行わない例が少なくありません(Fixed Price方式)。しかし、景気の後退局面では、買収価格を契約時点で確定させることに買主は躊躇する場合が多いと考えられます 1。
そこで、国際的なM&Aや大規模なディールにおいてはCompletion Accounts(米国ではClosing Accountsともいいます)方式で行うか、Locked Box方式で行うかが分水嶺となります。景気後退局面においては、このいずれを採用するかで当事者のリスクは大きく異なってきます。
Completion Accounts方式は、Completion時点、すなわち買収取引の実行日(クロージング日)における対象会社の財務状態を基準にして最終的な買収価格を確定させます。クロージング時点の財務状態はクロージング後にならないとわからないため、代金額を契約締結時点に確定させることは不可能です。そこで、クロージング日には、クロージング時点で予想される財務状態を基に暫定的な買収価格を買主が支払い、クロージング後に、クロージング時点での実際の財務状態を基に価格調整を行います。
クロージング時点の財務状態の確定プロセスは買主が主導するのが通常であり、クロージング時点での実際の財務状態を基に事後調整ができることから、Completion Accountsは一般に買主に好まれるプロセスであるといえます。国・地域ごとの傾向としては、米国ではほとんどのディールでCompletion Accountsが用いられます。American Bar Association(ABA)の集計データによると、2018年度と2019年第一四半期に締結または実行された米国の非公開会社をターゲットとするM&A 151件のうち、95%のディールがCompletion Accounts方式を採用していたようです 2。これと対照的に、ABAの集計データによると、2017年度と2018年に締結または実行された欧州(英国を含みます)の非公開会社をターゲットとするM&A 122件のうち、Completion Accounts方式が採用されたものは32%にとどまっています 3。
欧州でより一般的に採用されているのはLocked Box方式で、上記のABAの集計データによると、64%のディールがLocked Boxを利用しています。Locked Boxは、原則として、契約の締結よりも前の時点(たとえば、契約サイン前の直近事業年度末日時点)の財務状態を価格決定の基準日とします。こうした基準日のことをLocked Box Dateと呼びます。契約締結時からクロージングまでの間に、買主が許容した以上の売主への価値の流出(leakage)があった場合には、その流出分をクロージング後に補償する形で調整を行うのが一般的です。評価の基準時は原則として契約締結前の時点であるため、買収対価は契約締結時点において確定します。また、Leakageは売主に対する価値の流出ですので、売主がある程度コントロールできる立場にあります。そのため、プライベート・エクイティ・ファンドなど、買収価格を早く確定させてしまいたい売主に特に好まれます。Locked boxは、買収価格の事後的な調整を原則として行わないため、メカニズムがシンプルで済み、契約の義務履行コストが抑えられる点や、代金額を巡る紛争に発展しづらいという点にメリットがあります 4。
Completion Accountsの場合、対象会社のビジネス上のリスクおよびアップサイドはクロージング時点を境として買主に移転します。これに対して、Locked boxの場合は、経済的なリスクおよびアップサイドはLocked Box Dateに遡って移転します。しかし、クロージングまでの間は売主が事業運営を行うため、Locked boxの場合は、リスクを負担する者と事業運営を行う者が別となり、インセンティブの歪みとそれに伴うモラルハザードが起きやすい構造が生じます。そこで、買主としては、売主が配当その他の方法で価値を流出(leakage)させないよう、Leakage防止のためのコベナンツを入れる必要があります。これには、配当の制限はもちろん、売主が派遣している取締役に対する報酬等を、事前に合意した金額を超えて支払わないことや、売主が支払った取引費用を対象会社に償還させないことなどが含まれます。
一方、売主としては、買主の利益のために事業運営を行うという側面が生じるため、Locked Box Dateからクロージングまでの期間についての買収代金額に対する利息を要求する場合があります。実際、筆者らの所属事務所が独自に集計した統計によると、英国におけるLocked Box案件では半数ほどがこのような利息を付しています。
景気後退局面におけるCompletion Accountsの有用性
一般論として、Completion AccountsとLocked Boxはいずれか一方が他方よりも優れているといったものではなく、当事者の交渉力・ポジションの強さ等に応じて事案ごとにどちらが妥当か検討されるべきものです。もっとも、景気の後退局面においては、Equity Value評価の基準時が後の時点である方が、対象会社の財務状況が悪化している可能性が高く、買収価格が低廉になりやすいことを考慮する必要があるでしょう。また、契約締結時点ではクロージング時点の財務状態を予想しにくい場合も多いでしょう。買主は、COVID-19の影響で世界的にビジネスの先行きが不透明になっているような現状のもと、できるだけ最新の財務状態を反映させて買収代金を調整することを希望する傾向が強くなると思われ、基準時が後になるCompletion Accountsの採用を提案する場合が増える可能性があるでしょう。一方で、売主にとっても、価値評価の基準時を後ろ倒しにすることを受け入れることで、買主に安心感を与えることができるため、ディールメイクという観点からはCompletion Accountsが双方にとって有益となり得ます。
COVID-19の影響で欧州の実務がどこまでCompletion Accountsにシフトしていくかどうかはまだわかりませんが、買主の交渉力が強い案件ではCompletion Accountsの採用が増えていく可能性があります。実際、筆者らの知る限りでも、英国の売主のオークション案件で、一般的には売主に不利とされるCompletion Accountsを売主が自ら提案するケースが既に出てきています。これは英国のプラクティスからするとかなり珍しいケースです。
景気後退局面におけるLocked Box − ハイブリッドLocked Box
このように、景気後退局面ではCompletion Accountsが望まれる場合が増える可能性があります。しかし、欧州でのプライベート・エクイティ・ファンドなどによるオークションに日本企業が参加する場合、株式譲渡契約のオークションドラフトが、Locked Box方式になっていることが引き続き多いことも予想されます。
クロスボーダーM&Aでは、クロージングの前提条件に競争法当局のクリアランスが規定されることが通常ですが、これらのクリアランスも、COVID-19の影響により、より時間がかかることが予想され、クロージング日がより先になる可能性があります。このように、Locked Box Dateからクロージング日までの期間が平常時よりも長くなってしまう可能性があるため、買主にとってLocked Box方式はより受け入れがたくなるでしょう。だからといって、Locked Box方式からCompletion Accountsに変更する旨を買主が提案すると、ディールの根幹を覆す提案となり、オークション案件では売主に嫌がられてしまい他のオークション参加者(買主候補者)と比べて不利になってしまう場合があります。そこで、以下では、売主がLocked Boxを提案してきた場合に、買主として基本的にそれを受け入れながら、そのリスクを軽減するための1つの方法としてHybrid Locked Boxについて説明します。
まず、上記のとおり、Locked Box方式を使用するには、Locked Boxのベースとなる財務諸表の確実性が重要になります。監査済の財務諸表であれば、より正確性に自信がもてるでしょう。しかし、直近の年度末の監査済の財務諸表は、クロージング日よりもかなり前の時点のものになってしまう可能性があります。その分、買主のリスクも高まります。
そこで、Locked Boxの期間を極力短くするために、よりクロージング日に近い日をLocked Box Dateにすることが検討されることがあります。具体的には以下の図表のとおりです。
Hybrid Locked Boxの一例

通常のLocked Boxでは契約締結時にLocked Box Accountsが既に確定しており、買主は契約締結前にその内容を精査する時間と機会が与えられていることが理想的です。しかし、契約締結時にはまだできあがっていないLocked Box Accountsを利用したい場合やAccountsが作成されていたとしても監査が完了していないものを利用したい場合があります。そこで、暫定的にLocked Box Accountsよりも過去の財務諸表を基に買収価格を仮決めし、その後Locked Box Accountsが確定した段階で調整を行い最終的な価格を決定する方法をとることがあります。このような方法をHybrid Locked Boxと呼ぶことがあります 5。Hybrid Locked Boxの場合、Locked Box Accountsを確定させるために、Completion Accounts方式の場合と同様、予想値から(または監査前財務諸表から)のCash、Debt、およびWorking Capitalなどの調整を行う場合が多いため、Completion Accounts方式の場合と同様に当事者間で合意できなかった場合の確定方法等が定められます。
Hybrid Locked Boxの場合でも、Locked Box Accountsが確定してからは通常のLocked Box同様、Leakageに対する補償以外は原則として調整がなされないため、クロージング日の買収価格は契約締結時点では確定していなくてもクロージングまでには確定できるため、売主にとっては一定の確実性が担保できます。また、買主にとってもLocked Box Dateとクロージング日の間隔を狭められるので、リスクが軽減できることになります。ただし、Locked Box Accountsを確定するプロセスが必要になるので、Completion Accountsの場合と同様に、一定の費用と確定のための交渉が必要になります。また、売主にとってのメリットの1つである「オークションでの複数の買主からの買収条件の提案内容の比較検討が容易である」という点に関して、通常のLocked Boxほどメリットが得られなくなるので、売主が同意してくれない可能性もあります。
しかし、特に欧州のプライベート・エクイティ・ファンドなどが売主となる場合はCompletion Accountsを使うことは伝統的にかなり稀です。そのため、Completion AccountsよりはHybrid Locked Boxを希望するという場合もあるでしょう。筆者らの関与する案件でも、Hybrid Locked Boxを利用したケースがいくつかあります。また、筆者らの所属事務所が独自に集計した、2019年の非上場会社を対象としたM&A案件の統計によると、英国における案件では45%が従来型のLocked Boxを利用したのに対し、16%はLocked Box Dateを先延ばしたり、Locked Boxを採用しながらクロージング後の調整を入れるなどしたHybrid Locked Box方式を採用していました。Hybrid Locked Boxは、今後景気後退を背景としてさらに増えていく可能性があると考えられます。
景気後退局面におけるその他の注意点
Completion Accounts方式が採用されるか、Locked Box方式になるかは交渉次第ですので、両方の価格決定メカニズムにおける景気後退局面での注意点につきまとめました。
Completion AccountsとLocked Boxの選択上の注意点
買主の注意点
| Completion Accounts | Locked Box |
|---|---|
|
|
売主の注意点
| Completion Accounts | Locked Box |
|---|---|
|
|
アーンアウト
アーンアウトの意義
対象会社の将来の業績が不透明な状況下では、買主として確定額をクロージング時に一括で支払いたくないという場合があります。そのような不透明さに対処する方策として国際的なM&Aでしばしば検討されるメカニズムの1つにアーンアウト(earn-out)があります。
アーンアウトは買収後の一定の期間中(earn-out period)における、対象会社の収益その他の財務指標の達成度合いに応じて、クロージング後に追加の買収代金を支払うものです。日本国内のディールでアーンアウトが利用されるケースはまだ多くありませんが、英国や欧州、米国のディールや国際的なM&Aではしばしば利用されています。
たとえば、前述のABA調査によると米国においては、アーンアウトは調査対象となったディールの27%で採用されています。筆者らの所属事務所が独自に集計したデータによると、英国および欧州でも米国と同じくらいの割合でアーンアウトが利用されています。COVID-19の影響により、一時的にアーンアウト条項の利用が促進されることも予想されます。
アーンアウトには、予想される将来収益などから割り引いて算出される対象会社の現在価値についての買主と売主との間の認識のギャップを埋める機能があります。売主は将来キャッシュフローを大きく見積もり買収金額を高くしたいところですが、買主は将来の見通しを保守的に見積もり買収金額を低く抑えたいというインセンティブが働きます。その場合、クロージング時点での買収金額を確定額で合意することは困難となる場合があり、価格ギャップが大きい場合には折り合いがつかずディールができないということになりかねません。
将来の収益力等のパフォーマンスが見通せず、それ故にvaluationが困難で将来収益等から割り戻した現在価値について当事者間で合意できないという場合は、買収対価決定の基準時をいつにするかという問題ではないため、Completion Accountsを採用したからといって解決できるわけではありません。このような場合は、買収代金の一部を後払いする、とりわけクロージング後の財務成績が明らかになった時点で、その達成度合いに応じて追加代金を支払うといったメカニズムが当事者間の意見のギャップを埋めるのに役立つ場合があります。
アーンアウトの条項例
アーンアウトの内容は事案によって大きく異なり、標準的なひな形などは存在しませんが、売上やEBITDAを基準にするものが比較的一般的です。下記では買主の総売上高に連動させて一定の上限額のもとに追加代金を支払う、といった場合のシンプルな記載例を紹介します。
Buyer will pay to Seller, for each of calendar years 2021, 2022 and 2023, an amount(the "Earn-Out Payment")equal to two percent(2%)of Buyer's calendar year aggregate gross sales in excess of twenty million dollars($20,000,000)for each such year. The maximum aggregate Earn-Out Payments required to be made by Buyer to Seller for such three(3) calendar years shall not exceed two million dollars ($2,000,000). Any Earn-out Payment owed by Buyer to Seller for any calendar year will be paid in cash by Buyer to Seller within one hundred twenty(120)days of the close of such calendar year.
アーンアウトはうまく機能すれば当事者双方に有効な仕組みとなり得ますが、メカニズムが複雑になりがちです。また、規定内容に不明確な点があると、後日紛争になることもあります。そのため、支払義務発生の要件と支払手続を詳細かつ明確に規定することが重要です。たとえば、アーンアウト期間中に対象会社がさらに売却された場合は支払がaccelerateされるのか等考えておく必要があります。
アーンアウトに関連して検討すべきコベナンツ
アーンアウトは契約締結時点における価値評価の不一致の問題を将来に先送りする性質があり、買主にとって「払い過ぎ」のリスクを回避する有用な手段となります。他方で、売主としても、買収後の事業のパフォーマンスがよければ、それに応じて買収対価が増額するという「うまみ」があります。もっとも、クロージング後の事情によって受け取れる代金額が変わるという不確実性ゆえに、確実性を重視する売主の場合はアーンアウトに反対する場合があります。特に、クロージング後は、対象会社の運営権限が売主から買主に移転するため、買主の事業運営の巧拙次第で、受け取れる金額が変化することに不安を覚える場合もあるでしょう。
たとえば、買主が、アーンアウトの支払を避けるために、アーンアウト期間中に大規模な設備投資を行ったり、リストラクチャリングを行うなどして費用をかさ上げすることでアーンアウトのトリガーを恣意的に妨げたり、アーンアウトの額を低く抑える等の人為的な操作をすることも理論的にはあり得ます。
そこで、売主としては、買収後の買主による事業運営について何らかの縛りを設けることを検討する場合があります。たとえば、過去のプラクティスと一貫する形で事業運営をすることや、事業価値を最大化するように事業運営をすること等のコベナンツを要求することが考えられます。もっとも、ABA調査によると、米国では前者のようなコベナンツを設けた例は全体の10%、後者のようなコベナンツを設けた例は全体の17%であり、いずれも比較的少数派です。買主からすると、買収後に売主から事業運営のあり方について口出しされたくないという背景に基づくものと考えられます。そこで、逆に「買主はアーンアウトのメカニズムが採用されていることに関係なく、その裁量(discretion)によって事業運営をすることができる」旨を契約上明記するケースもあり、ABA調査では調査対象となった米国のディールのうち29%のディールで買主のdiscretionが明記されています。
アーンアウトが採用される場合の買主の事業運営に関する条項例としては以下のようなものが考えられます。
アーンアウトが採用される場合の事業運営に関する条項例
Subject to the terms of this Agreement, subsequent to the Closing, Buyer shall have [sole/reasonable] discretion with regard to all matters relating to the operation of the Company; provided, that Buyer shall not, directly or indirectly, take any actions in bad faith that would [reasonably be expected to] avoid or reduce any of the Earn-Out Payments hereunder. [Notwithstanding the foregoing, Buyer has no obligation to operate the Company in order to achieve any Earn-out Payment or to maximize the amount of any Earn-out Payment.]
上記の条項例においては、アーンアウトの規定がある場合に、買主がクロージング後、その裁量により事業運営を行える旨を規定するとともに、アーンアウトの支払を阻害したり額を減少させたりする行為を意図的に行うことを禁止することで上記のような当事者双方の懸念に配慮しています。かっこ書きの部分は、ディールに応じて交渉ポイントとなる表現の例示で、これらの取捨選択によって買主有利あるいは売主有利のいずれかに傾きます。アーンアウトに関する契約条項は定型化しづらく、複雑化する傾向があるため、M&Aに精通した弁護士と共に慎重に検討する必要があります。
景気後退局面でアーンアウトを利用する場合の注意点
景気後退局面で対象会社の将来の業績が不透明な状況下では、上記に述べた通り、アーンアウトを利用することにより、売主と買主との間のValuation Gapをある程度埋めることができるため、双方にとって有用な手段になり得ます。このような状況下でアーンアウトを利用する場合の注意点をいくつか記載します。
景気後退局面におけるアーンアウトの利用の際の注意点
| 売主の注意点 | 買主の注意点 | |
|---|---|---|
| アーンアウト期間 | 対象会社のクロージング後の運営は買主が行うため、売主が先行きを見通すことは困難である。そこで、長期に亘るアーンアウト期間を設定することは避けるのが無難な場合が多い。もっとも、買主グループとのシナジーや景気回復への期待が強く、中長期的なパフォーマンスの向上が期待できる場合は長めの期間でも合理的といえる | アーンアウト期間中は、契約上、売主が経営に対する一定の影響力を持ち続ける場合があるため、買収後のグループ再編やリストラ等が制約されないか注意が必要。したがって、長期にわたるアーンアウト期間の設定は避けるのが無難な場合が多い。もっとも、クロージングの時点での払いすぎリスクを低減する観点から支払時期をできるだけ後ろ倒しにすることが理に適う場合もある |
| トリガー事由とターゲット数値 | 買主がリストラや資本的支出を行いコストを前倒し計上するなどしてアーンアウトのトリガーを妨げたり、利益を低く抑えたりするなどの恣意的な操作がなされないような契約メカニズムを検討する必要がある。また、買主が再譲渡を行ったり、買主の支配権の異動が生じたりした場合にアーンアウトをaccelerateさせるかも要検討。 | 今後のビジネス動向の予測が困難であるため、特にアーンアウト期間が長い場合は、クロージング後の景気回復の動向次第ではターゲット数値を大きく上回る可能性もあるため、支払額に上限を設ける必要がないか要検討 |
| 計算式からの除外項目 | 買主は、一定の業績改善については、アーンアウトの計算上は無視するように要求してくる場合があるため、このような除外項目が適切かどうか、慎重にレビューする必要がある | 本来、買主に帰属するべき業績改善の結果が「棚からぼたもち」として不当に売主に分配されないようなメカニズムを検討する必要がある。たとえば、買主グループ傘下に入ったことによるシナジー効果、会計基準の変更、マネジメントの変更等に起因する変化はアーンアウトの計算上は無視するように合意するか、あるいは契約締結時点で予定されている業績改善があれば、あらかじめそれを織り込んでターゲット数値を設定する必要がある |
| 買収対価に対するアーンアウトの割合 | 確実性や流動性の観点からは、アーンアウトの対象となる割合を最小限に抑え、クロージング日の支払割合を大きくすることが望ましい | 将来的な業績の悪化の可能性を考慮すると、アーンアウトの対象となる割合を大きくすることが望ましい |
おわりに
本稿では、景気後退局面におけるCompletion Accountsの有用性やHybrid Locked Boxの利用を中心に買収価格調整メカニズムを検討し、また、アーンアウトの利用により買収代金の一部の支払を後ろ倒しにするメカニズムについて検討しました。COVID-19の影響で多くの業界は厳しい状況にありますが、当事者ひいては社会全体にとって有益なM&Aは景気後退局面でも存在します。本稿がそうしたM&Aを促進するための一助となれば幸いです。
※本稿の執筆にあたっては、同僚である神山達彦弁護士から貴重なコメントを頂きました。もっとも、本稿に記載の見解は筆者らの個人的見解であり、筆者らが所属する法律事務所その他の組織・団体の見解ではありません。
-
例外として、①小規模なディールである場合、②対象会社の既存株主であり事業内容や財務状態を既に把握できている場合、または③契約締結から買収取引の実行日(クロージング)までの期間が短い場合、または④買収の主目的が技術・人材の獲得にある場合などは買主として固定価格でも構わないということもあります。 ↩︎
-
2019 Private Target M&A Deal Points Study published by American Bar Association, Business Law Section, Mergers & Acquisitions Committee, M&A Market Trends Subcommittee and available for registered members at https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/deal_points/2019_private_study.pdf ↩︎
-
2019 European Private Target M&A Deal Points Study published by American Bar Association, Business Law Section, Mergers & Acquisitions Committee, M&A Market Trends Subcommittee and available for registered members at https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/deal_points/2019_eu_private_study.pdf ↩︎
-
ただし、近時はLocked Box方式を取りながらクロージング後の代金調整を行うハイブリッド型の方式を採用するケースも存在します。 ↩︎
-
なお、Locked Boxの方式を取りながらもクロージング後の代金調整を行う方式もあり、このような方式もHybrid Locked Boxと呼ばれることがあります。 ↩︎

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
- コーポレート・M&A
- IT・情報セキュリティ
- 人事労務
- 事業再生・倒産
- 危機管理・内部統制
- 競争法・独占禁止法
- ファイナンス
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
- 不動産
- 資源・エネルギー
- ベンチャー

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
- コーポレート・M&A
- 国際取引・海外進出
- 不動産
- 資源・エネルギー
- ベンチャー
