HRテックの導入で働き手に選ばれる企業へ 広がる働き方改革の可能性 - HRテック導入支援を行うポライト社会保険労務士法人
人事労務
目次
大企業のみに先行して適用されていた時間外労働の上限規制が、いよいよ2020年4月から中小企業にも適用される。これまで、時間外労働の上限規制は法律で定められておらず、行政指導がなされるのみだった。しかし、働き方改革関連法によって法的強制力を持つようになり、違反した企業には罰則が科されることになる。
複雑な労務管理への対応が急務となった人事労務部門の救世主として、今、脚光を浴びているのが人事労務管理をテクノロジーによりサポートする「HRテック」だ。クラウド型サービスの台頭もあり、活用する企業が増加している。
だが、「HRテックを活用したいが、何から手をつけたらよいのかわからない」という人事労務担当者も少なくない。そこで、企業を対象にHRテックの導入・運用支援を行うポライト社会保険労務士法人のマネージング・パートナーで特定社会保険労務士の榊 裕葵氏にHRテック導入のポイントを聞いた。
人事労務業務を効率化・高品質化するクラウド型ITサービス
HRテックとは具体的にどのようなものですか。
「HR」とは英語のHuman Resources(人材、人的資源)の頭文字を取った略語で、「HRテック」とはHRとテクノロジーを組み合わせた造語です。私はHRテックを「人事労務業務を効率化・高品質化するクラウド型ITサービス」と定義していますが、最大のポイントは、「クラウド型」というところにあります。

これまでにも人事労務業務をサポートする給与計算ソフトや表計算ソフトなどはありましたが、それらはあくまでも専門知識を持つ人事労務担当者のパソコンにインストールして使用される「インストール型」でした。しかし、HRテックと呼ばれるものは、特別な専門知識を持たなくても操作が可能な「わかりやすいインターフェース」を備え、「全従業員が使用する」ことが大きな特徴です。代表的なサービスとして、SmartHR社の「SmartHR」やヒューマンテクノロジーズ社の「KING OF TIME」、freee社の「人事労務freee」などがあげられます。
HRテックによって企業は何を実現できるのでしょうか。
従業員が新たに入社する場合を例に説明しましょう。従業員が入社すると、これまでは、入社情報や履歴書の情報、雇用保険番号などを人事労務担当者がパソコンで入力し、人事マスタを作成したり、社会保険の加入書類を作成したりするといった作業がありました。これらの作業は人事労務担当者のデスクトップ上でしか行えませんでした。
しかし、たとえばSmartHRであれば、入社情報などを入力するウェブページへのリンクを記載したメールを従業員のメールアドレス宛に送信し、従業員が直接、住所や氏名、マイナンバー、雇用保険番号などを入力すると、そのまま人事マスタへの登録が完了します。
また、社会保険に関しては年金事務所に、雇用保険に関してはハローワークに書類を提出しなければなりませんが、クラウド上に保存された人事マスタをベースに、入社時の人事労務手続書類を自動的に作成してくれます。電子申請にも対応しているため、役所への申請も簡単な操作で済んでしまいます。
このように、単なる情報収集や管理にとどまらず、企業の人事労務業務全体を効率化できることがHRテックの特徴であり、最大の強みといえます。
働き方改革関連法への対応で、人事部門の業務負担は増える一方です。労務管理やコンプライアンスの面で、人事労務担当者の負荷を軽減してくれるような機能はありますか。
たとえば時間外労働の上限を超えてしまいそうな従業員がいるときに人事労務部門にアラートが飛んだり、どの従業員がどれくらいの時間の残業をしているか、誰が有給休暇を5日以上取っていないか、といったことを一元的に把握できるようになります。
タイムカードを使用して労働時間を管理していると、翌月になって集計して初めて、ある従業員の労働時間が時間外労働の上限を超えていたことがわかった、といったことが起こりがちです。しかし、中小企業に時間外労働の上限規制が適用される2020年4月以降はもう、「気づかなかった」では済まされなくなります。HRテックの導入は、人事労務業務の効率化だけでなく、労務管理の質の向上やコンプライアンスの強化にもつながります。
最初に導入すべきサービスは勤怠管理・給与計算・人事労務手続
人事労務部門の業務は多岐にわたり、それぞれの業務をサポートしてくれるHRテックサービスも様々です。導入を検討している企業はどのようなポイントに気をつけるべきでしょうか。
まずは会社の規模に応じて、どの業務領域から導入していくかを検討することをお勧めしています。会社の規模の目安は、最初に中小零細企業を含めたすべての企業、次に従業員数50人以上の企業、最後に大企業となります。すべての企業が導入を検討すべきシステムは、導入の第1段階と呼ばれる「勤怠管理」「給与計算」「人事労務手続」です。これらはどの企業にとっても不可欠で、取り組まなければ違法となります。
段階別HRテクノロジーのまとめ図
| 段階 | 対象 | HRテクノロジーの領域 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 全企業 | 勤怠管理 | 電子的方法で打刻された出退勤記録がクラウド上で自動集計され、1か月の所定労働時間や残業時間などが自動で表示される |
| 給与計算 | 給与規程や従業員情報などの初期設定を行い、勤怠情報をインポートすれば、機能的に対応できない部分を除き、給与計算が自動で完了する | ||
| 年末調整 | 年末調整に必要な各種情報をクラウド経由で社員から効率的に収集する | ||
| マイナンバー管理 | クラウド経由で社員のマイナンバーを安全に回収し、クラウド上のセキュアな環境にマイナンバーを保管する | ||
| 人事労務手続 | クラウド上に保存された人事マスタに基づき、入社退職、算定基礎届などの人事労務手続書類を自動作成する。電子申請に対応しているソフトもある | ||
| 第2段階 | 50名以上 | 健康管理 | 健康診断結果の管理やストレスチェックをクラウド上で行ったり、社員が健康相談を行えるチャット機能が利用できたりする |
| 採用 | 効率的に求人を出したり、応募者を管理したりすることができる | ||
| タレントマネジメント | 社員の人事異動や人事考課を効率的に行ったり、風通しの良い社風を作ったりするのに役立つ | ||
| 第3段階 | 大企業 | AI・ビッグデータ | AIやビッグデータを用いて、採用の判断や精神疾患の予兆のある社員の抽出等、単なる効率化にとどまらない高度なHRテクノロジーを導入する |
出典:榊 裕葵「日本一わかりやすいHRテクノロジー活用の教科書」(日本法令、2019)
勤怠管理を例にあげて説明しましょう。従業員のITリテラシーが比較的高い企業であれば、従業員のスマートフォンにアプリをインストールしてもらい、それを使って勤怠管理を行うのも効率的です。また、飲食店などでは、店舗に設置されたタブレット端末に従業員が笑顔を向けると出退勤が記録されるというシステムを導入しているケースもあります。ご年配の従業員が多い企業であれば、紙のタイムカードに近い感覚で、カードをセンサーにかざして出退勤を記録するといったような方法もあります。
我々のクライアントの多くは中小企業ですが「このシステムさえ導入すれば完ぺき」ということはありません。その企業の状況や勤怠等の管理方法をヒアリングし、クライアントに合ったサービスを導入することが重要だと考えています。
勤怠管理に加えて、給与計算や人事労務手続までを一元的に管理できるサービスはありますか。
たとえば「人事労務freee」は元々、給与計算の効率化を目的に開発され、そこに勤怠管理や人事労務手続の機能が追加されたサービスです。しかし、勤怠管理の機能に限定した場合、「KING OF TIME」や「ジョブカン勤怠管理」などの勤怠管理特化型のサービスと比較すると機能面で劣る部分があることは否めません。企業の状況や導入済みのシステムに合わせ、サービスに求める機能の幅や深さを検討する必要があります。
導入した場合のコストはどの程度でしょうか。
導入の第1段階である「勤怠管理」「給与計算」「人事労務手続」のサービスは従量課金制のものが多く、費用は1か月あたり「社員数×数百円」程度がほとんどです。そのため、導入時にコスト面が大きな障壁になるケースは多くありません。
企業がHRテックサービスを選ぶ際のポイントを教えてください。
たとえば、勤務時間は朝の9時から夕方の5時、休日はカレンダー通りといった企業であれば、特に勤怠管理の機能を重視する必要がありませんので、給与計算や人事労務手続まで、業務分野を広くカバーできるサービスを選ぶのが便利でしょう。
しかし、シフト制や変形労働時間制といった多様な勤務体系を採用している企業の場合は、勤怠管理や給与計算など、それぞれの業務分野に特化したサービスを組み合わせて利用することも有効ですね。その点は、業種や規模によって柔軟に検討していく必要があります。

使いたいサービスに合わせて就業規則を変える柔軟さを
企業が実際にHRテックを導入する場合、どのようなところに相談すればよいでしょうか。
HRテックサービスを展開する各事業者が導入支援を行っています。また、社会保険労務士が導入支援を手がけているような場合もあります。ただ、サービスを開発した事業者はITには強いものの人事労務の法律に弱い、社会保険労務士は人事労務の法律に強いもののITに弱い、といった傾向もあります。IT知識と法律知識の双方を兼ね備えた人材が少ないことが、HRテックがなかなか普及してこなかった1つの理由かもしれません。
企業の側で導入後の初期設定を行うことは可能ですか。
HRテックは、導入企業の側で初期設定を行うことを前提としています。その前提で、サービス事業者も、インターフェースを工夫したり、ヘルプページやカスタマーサポートを充実させたり努力をしています。しかし、たとえば様々な労働時間制度を採用している企業では、勤怠管理の初期設定を自力で行うことはなかなか大変ですし、法令への適合の面で正確さも求められます。自社で行う場合には、それなりにマンパワーを割く覚悟が必要になります。自社内のリソースだけで初期設定が難しそうな場合は、サービス事業者が提供している初期設定代行オプションや、ITに強い社労士に相談をしてみるのも良いでしょう。
HRテックのサービスが自社の就業規則に合わないケースがあるとも聞きます。
自社に合いそうなサービスが見つかったものの、「就業規則に適合しない」という理由で導入をあきらめたり、エクセルなどを併用して“だましだまし”従業員の勤怠を管理している企業もあります。イレギュラーな形でHRテックを運用して「きちんと集計や計算ができているのだろうか」と不安になった人事労務担当者が、あらためて手作業で確認し直すといった事態も起こっています。せっかく高い意識を持っているにもかかわらず、非常に残念なケースですよね。
このように、既存の就業規則にこだわりすぎて、「就業規則ありき」でサービスを導入しようとして、「結局、どのサービスも導入できない」という企業は、実際のところ少なくありません。そのような袋小路に陥らないようにするためには、自社に適したサービスを決めるのと並行して、そのサービスを利用できるように就業規則を変えていくという柔軟さが求められます。HRテックの導入と就業規則の改定は「車の両輪」だというイメージを持ってください。
「就業規則を変えなきゃだめですか」というクライアントに対して私は、「今変えておかなければ、今後の運用で矛盾や不合理が発生しますよ」と説明しています。我々も、求められれば就業規則の変更に伴う従業員説明会の資料作成などのサポートを行っています。HRテックの導入を検討中の企業には、「自社の就業規則に合うHRテックは何だろうか」ではなく、「こんなHRテックがある。これに合うように就業規則を変えてみよう」という歩み寄りの意識を持ってもらいたいですね。
HRテック導入で生まれたリソースの活用で「攻めの人事」へ
HRテックの導入によって業務が効率化されれば、これまでやりたくてもできなかった業務に取り組む余力が生まれそうです。
かつての人事労務担当者の1日は、勤怠の集計や行政への申請書類などの事務作業だけで終わってしまうという状況でした。しかし、HRテックの導入によって、その状況は劇的に変わりました。
また、毎年12月は、月次の給与計算に加えて賞与や年末調整の手続が加わるため、人事労務部門は超繁忙期です。そのため、社内の労働環境の維持・改善を担う人事労務担当者自身が、法令違反の働き方を強いられるという、本末転倒な事態が続出していました。ところが、HRテックの導入をきっかけに、繁忙期であっても定時で仕事を終えられる担当者が増えているようです。
自社の36協定はどうなっているか、フレックスタイム制を採用しているものの労使協定を締結できていたかなど、前向きな業務に充てる時間が増えたとおっしゃるクライアントは多いです。従業員の適材適所への配置や福利厚生の充実など、人事労務部門が本来取り組むべきテーマに注力できるようになった、という声もよく聞きますね。
一方で、HRテックの導入を「コスト」と考える経営者も少なくないようです。
たしかに、働き方改革を実現しようとすると業務を分担するために従業員を増やさなければならず、その分だけ人件費が増加し、コストが増えると考える経営者もいます。一方で、働き方改革を、生産性を上げ、労働環境を改善し、ひいては働き手を確保するためのきっかけと考える経営者もいます。
これまでは企業が働き手を選ぶという傾向がありましたが、労働力が不足している現状では、働き手に選ばれる企業でなければなりません。残業が多かったり、有給休暇を取得できなかったりすることで、労働環境が劣悪であると判断されてしまうと、働き手を集めることは困難です。実際に人手不足による倒産も増えています。
また、多様な働き方を実現することにより、たとえば大規模な自然災害などの発生時も、リモートワークの活用などで業務を継続できるケースもあります。何があっても出社し、長時間働いている従業員が賞賛される時代ではありません。働くときは働き、休日は家族との時間を大切にするなど、バランスを取ることが、現在における「強い会社」になるための1つの条件ともいえます。HRテックは、企業と従業員が新しい働き方に出会うための大きなきっかけになるはずです。

(写真:弘田 充、取材・文・編集:BUSINESS LAWYERS 編集部)
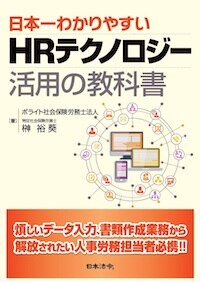
- 参考文献
- 日本一わかりやすいHRテクノロジー活用の教科書
- 著者:榊 裕葵
- 定価:本体2,300円+税
- 出版社:日本法令
- 発売年月:2019年4月

ポライト社会保険労務士法人
