ストーリーでわかる特許制度の全体像
第2回 特許として認められる発明とは?
知的財産権・エンタメ
シリーズ一覧全5件
特許制度がなぜ現在のような形になったのか、前回の「特許制度の神髄とは?」をご覧の皆様でしたら、よくご理解いただけた事と思います。
え、まだ読んでいない?
特許制度が生まれたといわれるヨーロッパの王宮の会話を想像し、特許制度とは、「発明を世の中に開示する代償として独占権を与える」制度であり、そのときに付与される独占権が「特許権」である。という特許制度の神髄を解説した、あの記事をまだ読んでいないとは・・・。
ここで読むのを止めて1話に戻ろうとした方もいるかもしれません。安心してください、今述べた事が大体のあらすじです。本連載では固い話を抜きにして、特許制度の全体像をストーリー形式でわかりやすくお伝えしていきます。
第2話のテーマは「どんな発明でも特許にしてよいのか?」です。あらゆる発明を「特許」としてしまったら、他の人は発明ができなくなって世の中が混乱してしまいます。では、一体どういう発明を「特許」とするべきなのでしょうか。
舞台は明治時代の東京へ、地下足袋商の主人と番頭が何やら話をしています。
都に特許がやってきた
主人:今日もいい天気だのう。富士の山がよく見えるわ。先代が東海道の旅人のために地下足袋を売り始めて30年、我が駿府商会も安泰だ(※2)。
番頭:そうは言っても時代は動いておりまして、このたび、新橋から横浜に湯気を出して走る「キカンシャ」という車ができるとか。地下足袋を履いて旅行する時代も終わりが近いのではないでしょうか?
主人:馬鹿者。機関車が家の前まで来てくれるか!新橋の駅まで裸足で行くわけにはなるまい。
番頭:それはそうですね。やはり地下足袋の商売は安泰ですね。それはそうと、このたび「トッキョ」とかいうけったいな名前のきまりができるとか。「トッキョ」を取ると、自分だけが「トッキョ」を取った品物を売れるそうなのです。
主人:それはつまり、我々が地下足袋の「トッキョ」をとると、品川宿では駿府商会しか地下足袋を売れなくなるということか?
番頭:品川宿だけではなく、東京あるいは日本国中で我々だけしか地下足袋が売れなくなるかと…
主人:けったいな制度だな。しかし、駿府商会は今のままでも商売繁盛。東北道、北陸道、その土地土地の地下足袋小売がいることが旅人には大事なことなのだ。
番頭:それでは…
主人:「トッキョ」なるものは駿府商会には関係ない。
(※1) 今の京浜急行北品川商店街のあたり、東海道五十三次の宿場の一つ。東海道の第一宿です。
(※2)この事例は特許解説のためのフィクションであり、実在の商品・会社とは一切関係ありません。
この会話を見てどう思いましたか。なんとなくおかしいと感じた方、その感覚は正しいです。
駿府商会は先代の頃から30年以上、地下足袋を販売しています。おそらく、同業の地下足袋商は全国各地にいることでしょう。そういう状態で誰かに特許が付与されると、既存の地下足袋商は廃業に追い込まれます。明らかに特許制度が目的としている「産業の発達」に反します。
とはいえ、「特許を取ると、自分だけが特許を取った品物を売れる」という彼らの理解はさほど間違っていないようです。では、一体なにが問題なのでしょうか。
地下足袋に特許が取られたら
番頭:ご主人様、大変です。あのサヤマ商会が地下足袋のトッキョを取った、今後、地下足袋はサヤマ商会だけが販売できるので、我々に地下足袋を売るな、と文句をつけてきました(※3)。
主人:またサヤマ商会か。あいつらどうも業界の調和を乱しがちだな。心配するな。なんでも、トッキョの元締めの「トッキョチョウ」という役所は隣村の高橋旧家倅の清さんがやっとるそうな。いざとなったら、話をつけてくる。
(※3)こちらも実在の商品・会社とは一切関係ありません。
さて、駿府商会のライバル会社であるサヤマ商会が地下足袋の特許を取ったと言ってきたようです。本当に特許が取れたのだとしたら駿府商会は地下足袋を売れなくなってしまいます。
ご主人が話を聞きに向かったのは隣村の清さんという方ですが、一体誰だかわかりますか?
答えは、高橋是清です。高橋是清は初代特許庁長官だったのですね。1884年(明治17年)に商標登録所長、1885年(明治18年)には専売特許所長を兼務しています。「特許庁 初代特許庁長官高橋是清について」
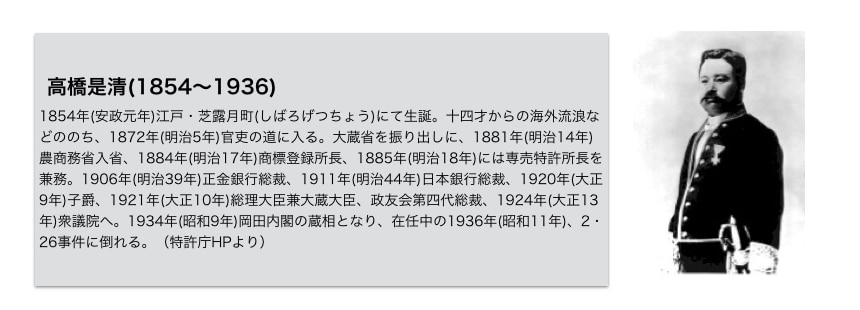
高橋是清と直に話ができるなんて、このご主人は何者なんだ・・・という野暮なツッコミは置いておいて、どんな会話がされたのか見てみましょう。
是清:これはこれは、駿府屋さんのご主人。特許制度の趣旨は「発明の奨励」「産業の発展」で、すでに販売されている物に特許は取れないし、取ったとしても効力が及ばないのです(※4)。なんせ、「新しい発明を公開する代償」として、与えられるのが特許ですから。
主人:と言いますと?
(※4)日本での特許制度は、専売特許条例が施行された1885年(明治18年)7月1日から始まったとされています。同条例施行時は、無審査主義(実体的な審査を経ずして特許を付与する主義)だったので、すでに販売されている地下足袋にも特許が付与されたということは十分に考えられます。
しかし、これは効力を伴わない特許になります。
もちろん、この会話はフィクションなのですが、初代特許庁長官から直々に特許制度を説明してもらいました。どうやら駿府商会は地下足袋の販売を続けられるようですね。
すでに第1話で述べたとおり、特許制度は「発明を公開する代償として特許権を付与する」制度ですが、その発明はどんな発明でもいいわけではなく、「新規な発明」でなければなりません。「新規な発明」が世の中に公開され、さらに改良されることで技術の進歩速度が飛躍的に高まるからです。
逆に、新規ではない発明に特許を付与してしまうと、上記のとおり、既存の事業者は事業継続ができなくなり、著しく不当な結果となってしまいます。このように、発明であればなんでもかんでも特許になるわけではなく、制度趣旨との関係で、特許とすべき条件が規定されており、これを「特許要件」といいます。
ここで議論になっているのは「新規性」という特許要件です。新規性は特許法29条1項各号に定められていますが、平たく言うと、下記の2つの要件を両方具備する場合は「新規性を有しない」発明となり、特許を受けることができません。
①守秘義務を有しない者が、②その発明を技術的に理解しうる状態にあること。
(関連条文)特許法29条1項各号
(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
新規性を喪失した状態とは
たとえば、装置の内部構造に関する発明をして、この装置を展示会で展示したら新規性を喪失した状態となるのでしょうか。
この場合、展示会に来る参加者には守秘義務がないことが通常ですから、①の要件は具備すると考えるべきです。しかし、装置を展示するだけでは装置の内部構造は見えませんので、②を具備することはありません。
ここで、展示会の参加者から質問があった場合に、内部構造の詳細技術について説明する用意がされていた場合は②も具備するため、新規性を喪失した状態となります。
それでは、発明品を外注試作してもらう場合はどうでしょうか。この場合、試作の受託者は発明を技術的に理解しなければ試作できないでしょうから、②の要件は具備します。そこで、新規性を喪失した状態にしたくなければ、受託者と守秘義務契約を交し、①の要件具備を回避することが正しいこととなります。
「新規性の喪失」に関する①②の要件は、発明について何らかの形で告知・公表する場合に重要な判断基準となります。
代表的な特許要件
なお、特許要件は新規性のみではありません。以下に代表的な特許要件を列挙します。
②先願主義:発明が先に出願された明細書(クレーム、図面を含む)に記載されていないこと(※4)。
③実施可能要件:発明が当業者をして容易に実施できる程度に明細書に記載されていること。
④サポート要件:クレームされた発明にかかる課題と解決手段が明細書に記載されていること。
⑤明確性:クレームに記載された発明の範囲が十分に明確であること。
⑥冒認:特許を受ける権利を有する者以外の者による特許出願であること。
(関連条文) 特許法29条2項(進歩性)、特許法36条(実施可能要件、サポート要件、明確性要件)、特許法49条(拒絶理由)
(※4)クレームに記載された発明と同一の場合を狭義の先願といい(特許法第39条)、クレーム以外の明細書、図面に記載された発明と同一の場合を拡大された先願といいます(特許法29条の2)。先行技術が公開されている場合は、新規性/進歩性が優先適用されます。
おわりに
いかがでしたでしょうか。普段、当たり前のように秘密保持契約などを結ばれている方も多いかもしれませんが、この契約を結ぶのは、特許制度の根底に流れる「産業の発展」という目的、そして「新規性」という特許要件があるからなのです。
無機質な秘密保持契約書も、特許制度が生まれた頃の明治日本に思いを馳せると、先人たちの思いや苦労が透けて見えてくる。そんな気がしませんか?
シリーズ一覧全5件

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
- IT・情報セキュリティ
- 知的財産権・エンタメ
- 訴訟・争訟
- ベンチャー
