株式対価M&Aの利用は広がるか、産業競争力強化法の改正と法整備の動向
コーポレート・M&A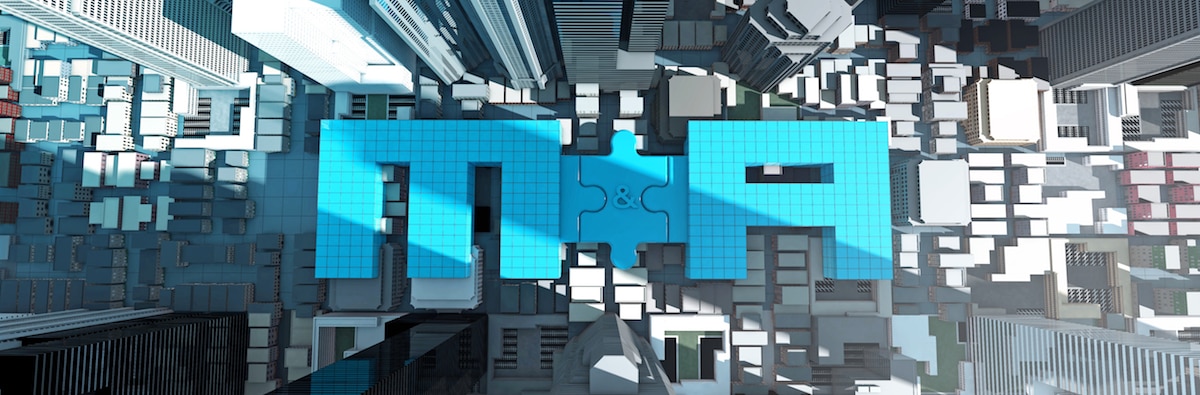
目次
はじめに
近年、IoTやビッグデータ、人工知能など、ICT (Information and Communication Technology)の分野における急速な技術革新の進展により、産業構造や国際的な競争条件が著しく変化しています。この変化に対応し、世界に先駆けて「生産性革命」を実現させるべく、政府は、平成29年12月に「新しい経済政策パッケージ」を取りまとめました。その中には、「企業の収益性向上・投資促進による生産性革命」の一環として、「大胆な事業再編を行う際の株式対価M&Aの促進に必要な措置を講じる」と明記されています。
本稿では、株式対価M&Aを促進させる措置の一つとして本年(平成30年)に導入された、産業競争力強化法における会社法および税法の特例について、その活用が想定される例を交えて概説し、今後利用拡大が期待されている株式対価M&Aに関する法整備の状況をご紹介します。
株式対価M&Aの意義と産業競争力強化法改正の経緯
株式対価M&Aの意義
株式対価M&Aとは、文字通り、買収会社が自社の株式を買収対価として実施するM&Aのことをいいます。株式対価M&Aには以下の利点があります。
- 買収会社は、買収資金(の全部または一部)を調達せずに、買収対象となる会社(以下「対象会社」といいます)の株式の買収が可能となるため、大規模なM&Aや手元資金に余裕のない新興企業によるM&Aを行いやすくなる。
- 対象会社の株主は、買収後の買収会社の株式を保有することとなるため、買収によるシナジー等の利益を享受することができるようになる。
さらに、欧米の大規模なM&Aでは、現金対価のM&Aよりも対価の全部または一部として株式が用いられる方が多いという統計があります。そのため、日本においても、株式対価M&Aが促進されれば、大胆な事業再編の促進、ひいては企業の収益性向上や投資促進による生産性革命に資すると考えられています。
<株式対価M&Aのイメージ>

日本における法制度上の課題
しかしながら、日本の法制度上、以下の課題があったため、日本では株式対価M&Aは必ずしも積極的に利用されてきませんでした。
(1)会社法上の課題
現在の日本の会社法において株式対価M&Aを実施する手法としては、株式交換(株式交換完全子会社がその発行済み株式の全部を他の会社に取得させること)を用いる方法および現物出資(買収会社が、対象会社の株式を現物出資財産として対象会社の株主に対して株式を発行すること)を用いる方法が考えられます。
しかし、株式交換は、対象会社が外国会社である場合や、対象会社を完全子会社とすることまでを企図していない場合には、利用できません。
また、現物出資については、以下のような制限があります。
- 原則として検査役の調査が必要であり、時間・費用が発生する(会社法207条)
- 引受人である対象会社の株主・発行会社である買収会社の取締役等が財産価額塡補責任を負う可能性がある(同法212条、213条)
- 買収会社による株式の発行等にあたり、対象会社株式の価格にプレミアムを上乗せした比率を設定する場合、当該株式発行等は、有利発行となり得るため、買収会社が公開会社であっても募集事項の決定に株主総会の特別決議が必要となるおそれがある(同法199条2項、3項、201条1項、309条2項5号)
こうした会社法上の制限が、日本企業において現物出資による株式対価M&Aが積極的に活用されてこなかった一因として指摘されていました。
(2)産業活力再生特別措置法による特例の課題
上記の会社法上の課題に対応すべく、平成23年には、産業活力再生特別措置法(いわゆる産活法)が改正され、認定を受けた事業再編計画に従って、自社の株式を対価とする公開買付けを実施する場合には、上記現物出資規制、有利発行規制等は適用されないこととする会社法の特例が創設されました(同法廃止後は、この特例が産業競争力強化法に引き継がれました)。しかし、同特例は、「公開買付け」により対象会社株式を取得する場合に適用範囲が限定されており、それ以外の方法による買収(非上場会社の買収等)には利用できないものでした。こうした適用範囲の狭さもあったためか、同特例を用いた株式対価M&Aは一度も実施されませんでした。
(3)税法上の課題
加えて、株式対価M&Aを実施した場合における、対象会社の株主に対する課税繰延べ措置が設けられていなかったことも、株式対価M&Aが積極的に活用されてこなかった原因の一つといわれています。
改正後の産業競争力強化法の概要
以上のような状況を踏まえ、産業活力再生特別措置法の上記特例を引き継いだ産業競争力強化法の改正が議論され、平成30年5月16日、通常国会において「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立、同年7月9日に施行されるに至りました。
参照:経済産業省「生産性向上特別措置法及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律」
この産業競争力強化法の改正(以下「本改正」ともいいます)により、以下のとおり、会社法上の現物出資規制、有利発行規制等の適用を回避できる会社法の特例の適用要件が緩和され、対象会社の株主に対する課税繰延べに関する規律(特別事業再編計画)が創設されました。
事業再編計画による特例の要件緩和(会社法の特例の拡充)
平成23年産業活力再生特別措置法改正で導入した会社法の特例では、上記のとおり、認定を受けた事業再編計画に従って「公開買付け」により対象会社株式を取得する場合に適用範囲が限定されていたところ、本改正により、認定を受けた事業再編計画に従って「譲渡」により対象会社の株式を取得する場合であれば、特例を利用できるようになりました。
すなわち、公開買付け以外の方法による上場会社株式の取得や非上場会社の買収等にも、現物出資規制、有利発行規制等を回避できるという会社法の特例の適用範囲が広がりました。
また、本改正前は、対象会社を買収会社の「関係事業者にしようとする場合」(「外国関係法人としようとする場合」を含む)にしか特例は利用できませんでしたが、改正により、すでに関係事業者(※)または外国関係法人である会社の株式を対象とする場合(子会社株式の買増し等)でも、特例を利用できるようになりました(以上につき、産業競争力強化法32条)。
※関係事業者とは、「事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう」(産業競争力強化法2条8項)とされ、たとえば、①50%以上株式等を保有する場合、②40%以上・50%未満株式等を保有し、役員等を50%以上派遣している場合等がこれに該当します(産業競争力強化法施行規則3条1号、2号)。
特別事業再編計画の創設(税法上の特例の創設)
さらに、事業再編計画のうち一定の要件を満たすもの(下記4-2参照)について、特別事業再編として認定する制度が創設され、特別事業再編計画の認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延べが認められるようになりました。
事業再編計画および特別事業再編計画の主な認定要件は以下のとおりです。
【事業再編計画および特別事業再編計画の主な認定要件】
| 要件 | 事業再編計画 | 特別事業再編計画 |
|---|---|---|
| 計画期間 | 3年以内(大規模な設備投資を行うものに限り5年) | |
| 生産性の向上 (事業部門単位) |
計画開始から3年以内に次のいずれかの達成が見込まれること。 ①修正ROA 2%ポイント向上 ②有形固定資産回転率 5%向上 ③従業員1人あたり付加価値額6%向上 |
計画開始から3年以内に次のいずれかの指標の達成が見込まれること。 ①修正ROA 3%ポイント向上 ②有形固定資産回転率 10%向上 ③従業員1人あたり付加価値額 12%向上 |
| 財務の健全性(企業単位) | 計画開始から3年以内に次の両方の達成が見込まれること。 ①有利子負債/キャッシュフロー≦10倍 ②経常収入>経常支出 |
|
| 雇用への配慮 | 計画に係る事業所における労働組合等と協議により、十分な話し合いを行うこと、かつ実施に際して雇用の安定等に十分な配慮を行うこと。 | |
| 事業構造の変更 | 次のいずれかを行うこと。 ①合併 ②会社の分割 ③株式交換、株式移転 ④事業または資産の譲受け、譲渡 ⑤出資の受入れ ⑥他の会社の株式・持分の取得 ⑦会社の設立 ⑧有限責任事業組合に対する出資 ⑨施設・設備の相当程度の撤去 等 |
他の会社の株式・持分の取得を行うこと(以下の①〜③すべてを満たすことが必要) ①他の会社を関係事業者とすること ②対価として自社の株式のみを交付すること ③対価として交付する株式の価額(対価の額)が余剰資金の額を上回ること ※余剰資金の額=現預金運転資金上記以外の買収に要する資金の額加えて左の①〜⑨等を実施することも可能。 |
| 前向きな取組 | 計画開始から3年以内に次のいずれかの達成が見込まれること。 ①新商品、新サービスの開発・生産・提供⇒新商品等の売上高比率を全社売上高の1%以上 ②商品の新生産方式の導入、設備の能率の向上⇒商品等1単位あたりの製造原価を5%以上削減 ③商品の新販売方式の導入、サービスの新提供方式の導入⇒商品等1単位あたりの販売費を5%以上削減 ④新原材料・部品・半製品の使用、原材料・部品・半製品の新購入方式の導入⇒商品1単位あたりの製造原価を5%以上削減 |
|
| 新事業活動 | ー | 次のいずれかにあたる新事業活動を行うこと ①著しい成長発展が見込まれる事業分野における事業活動 ②プラットフォームを提供する事業活動 ③中核的事業へ経営資源を集中する事業活動 |
| 新需要の開拓 | ー | 新需要の開拓計画開始から3年以内に新たな需要を相当程度開拓することが見込まれること 売上高伸び率≧過去3事業年度の業種売上高伸び率+5%ポイント等 |
| 経営資源の一体的活用 | ー | 申請事業者と関係事業者となる他の会社がそれぞれの有する知識、技術、技能等を活用することにより、商品または役務の開発、資材調達、生産、販売、提供等において協力すること |
(参照:経済産業省「産業競争力強化法における事業再編計画の認定要件と支援措置について」5頁)
上記、「⽣産性の向上」要件の数値算式は以下のとおりです。
有形固定資産回転率=売上高/有形固定資産の帳簿価額
従業員一人あたり付加価値額=(営業利益+人件費+減価償却費)/ 従業員数
事業再編計画等の活用が想定される例
事業再編計画について
事業再編計画に基づく会社法の特例は、上記の要件緩和に伴い、利用を検討できるケースが大幅に増加しました。
まず、公開買付けによらない場合にも、事業再編計画に基づく会社法の特例の利用範囲が拡充されたことにより、今後、非公開会社である中小企業等を対象会社とする案件において、事業再編計画に基づく株式対価M&Aが活用されることが想定されます。
また、すでに関係事業者である会社の株式を対象とする場合でも、会社法の特例を利用できるようになったことにより、たとえば関係事業者に該当する子会社の株式を買い増す取引において、事業再編計画に基づく株式対価M&Aが活用されることが想定されます。
なお、対象会社が公開会社であっても、すでに関係事業者である対象会社の株式を買い増すだけであれば、公開買付け規制の対象とはならない場合があります。本改正により、公開買付け規制の対象とはならず、かつ、すでに関係事業者である公開会社の株式を買い増す場合にも、事業再編計画に基づく会社法の特例を利用できるようになりました。そのため、公開会社を対象会社として本特例を活用し得る場面も、本改正によって拡充したといえます。
本改正前は、事業再編計画に基づく会社法の特例を利用できるのは、公開買付けによる場合に限定されていましたが、M&Aの案件のうち公開買付けを実施する案件はほんの一部に過ぎないところ、本改正により、特例利用の検討対象となるM&Aの絶対数が大幅に増加すると考えられます。
なお、本稿の公開時点において、株式対価M&Aについての事業再編計画(特別事業再編計画を含みます)の認定例はまだありません。もっとも、武田薬品工業株式会社がアイルランドの製薬会社シャイアーを約6兆8000億円で買収する事例において、武田薬品工業株式会社は買収対価の一部として、自社の株式を用いることを発表しているところ、同社が、本改正後の事業再編計画を用いた株式対価M&Aの実施第1号になる見通しであると報じられており、注目が集まっています。
特別事業再編計画について
他方、特別事業再編計画による税法の特例が活用できる場面は、事業再編計画による会社法の特例を活用できる場面が大きく広がったことと比較すると、かなり限定されています。特別事業再編計画の認定要件のうち、事業再編計画の認定要件と比較して特徴的な点としては、以下の四点があげられます。
(1)対価として交付する株式の価額が余剰資金を上回ることが要件とされている
現金を対価として対象会社の株式を買収することができるほどの余剰資金がある場合には、特別事業再編計画の認定を受けることはできません。買収会社が対象会社を買収するだけの余剰資金を有しないケースにおいて、対象会社の株主に、買収会社の株式を買収対価とすることを受け入れてもらうのは、必ずしも容易でないでしょう。
(2)対象会社を買収会社の「関係事業者にしようとする場合」(「外国関係法人としようとする場合」を含む)にしか特例は利用できない
すでに関係事業者に該当する子会社等の株式を買い増す場合には、特別事業再編計画の認定の対象となりません。
(3)対価として自社の株式のみを交付することが要件とされている
対価として、自社の株式とその他の財産(金銭等)を組み合わせる場合には特別事業再編計画は利用できません。
(4)新事業活動を行うことが要件になっている
以下の三種類のいずれかに該当する新事業活動を実施するためのM&Aでなければ、特別事業再編計画は利用できません。
(新事業活動の種類)
| ― | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 著しい成長発展が見込まれる事業分野における事業活動 | 対象会社の革新的な技術または事業の実施の方式を活用して行う事業活動であって、国内外の市場において著しい成長発展が見込まれる事業分野におけるもの。 | 自動車部品メーカー(自動運転)、メガベンチャーなど |
| プラットフォームを提供する事業活動 | 対象会社の経営資源を活用して行う事業活動であって、相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品または役務に係るもの | 電子商取引のプラットフォーム提供など |
| 中核的事業へ経営資源を集中する事業活動 | 対象会社の経営資源を活用して行う事業活動であって、中核的事業の売上高等の割合が相当程度増加すると見込まれる場合における当該中核的事業に係るもの。 | 事業ポートフォリオにおけるコア事業の売上高等の割合を増加させることを目指している多角化している大企業、大規模業界再編を行う企業など |
以上のように、特別事業再編計画は、①買収会社が現預金を対価として対象会社の株式を買収することができるほどの余剰資金を有していない状況において、②対象会社を新たに関係事業者にしようとするために、③買収会社が自社株式のみを対価として対象会社の株式を買収し、④対象会社の技術、経営資源等を活用して新事業活動を実施するような場合でなければ、認定を受けることができません。
この高いハードルを乗り越えて、本改正により創設された特別事業再編計画を用いて株式対価M&Aを実施するには、買収実行後の新事業の成功(ひいては、買収会社の株式価値の上昇)を強く期待できる事業計画を、買収会社と対象会社(およびその株主)が一体となって描くことが何より重要となることはいうまでもありません。
他方で、株式対価M&Aの積極的な利用促進という観点からは、本改正により創設された特別事業再編計画の今後の活用状況や、会社法上の組織再編に適用される適格税制とのバランス等を踏まえ、より広範な税制繰延べ措置(余剰資金に関する要件の緩和や対象とする事業活動の拡大等)を講じることが期待されます。
今後の株式対価M&A
以上のとおり、今般の産業競争力強化法の改正により、株式対価M&Aの活用可能性が広がったことは事実です。
とはいえ、会社法の特例および税法上の特例を受けるには、それぞれ事業再編計画・特別事業再編計画に係る主務大臣の認定を受ける必要があり、他のM&Aの手法と比較して、余分な手間やコストが生じることは否めません。特に、特別事業再編計画については、認定要件のハードルが高いため、今後、どの程度活用されるのか、認定に関する運用の蓄積が待たれます。
株式対価M&Aについては、法制審議会の会社法制(企業統治等関係)部会が平成30年2月14日に発表した「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」において、「株式交付」制度を導入することが検討されています。産業競争力強化法は、あくまで会社法の特例であり、平成32年までの時限法である一方、「株式交付」制度は、株式対価M&Aの一般的な規律として会社法に盛り込むことが検討されています。
「株式交付」が会社法に導入される場合には、組織再編の一種として位置づけられる予定であるところ、当然、その利用に事業再編計画における主務大臣の認定のような手続は必要ありません。ゆえに、「株式交付」が導入されれば、株式対価M&Aの使い勝手は現在に比べ一層向上すると考えられます。
合わせて、「株式交付」を利用する場合に対象会社の株主への課税を繰延べる税制が整備されれば、株式対価M&Aの活用可能性はさらに大きく広がることになります。
政府が掲げる「企業の収益性向上・投資促進による生産性革命」に関する措置の一環として、上記のような法整備が加速度的に進む可能性があるため、今後の改正動向には注視を要します。

弁護士法人大江橋法律事務所
- コーポレート・M&A
- 人事労務
- 危機管理・内部統制
- ファイナンス
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
- 資源・エネルギー
- ベンチャー

弁護士法人大江橋法律事務所
