【イベントレポート】法の"グレーゾーン"を登ってみる -法の「余白」で遭難しないために-(前編)
知的財産権・エンタメ
目次
「文化活動を支援するためのNPO」として2004年に設立されたArts and Lawが主催する「法の"グレーゾーン"を登ってみる -法の「余白」で遭難しないために-」が10月24日、東京都文京区のシェアオフィス&イベントスペース「ハーフハーフ」で開催された。
現行の法制度がキャッチアップできていない「法のグレーゾーン」が、文化表現活動や、ビジネスの分野で問題となるケースを目にすることも多い。
このような「法のグレーゾーン」に対して、「クリエイティブで、懐の広い社会であるために、法ができることは何か」をテーマに、いずれも弁護士であり、Arts and Lawのメンバーでもある、早稲田リーガルコモンズ法律事務所の永井 靖人氏、長島・大野・常松法律事務所の小松 隼也氏、株式会社ドリームインキュベータの下平 将人氏、シティライツ法律事務所の水野 祐氏の4名が、各々の専門分野について持論を展開した。
前半はそれぞれのプレゼンテーション、後半は4名によるトークセッションが行われた。当日の模様を2回にわたってレポートする。
同人誌におけるグレーゾーン
まず始めに発表したのは早稲田リーガルコモンズ法律事務所の永井 靖人弁護士だ。身近な方が同人誌の創作活動をされていることを交え、同人誌と著作権法の間に広がるグレーゾーンについて語った。
同人誌と著作権
同人誌は著作権法における複製権や、翻案権と関わってきます。複製権は著作権者だけがコピーできる権利、翻案権は、他人が自分の著作物を使って勝手に創作した時に「やめてください」と言える権利ですね。
裁判等で争われている著名なものとして、いわゆるパロディと呼ばれるものがあります(パロディモンタージュ事件(最高裁昭和55年3月28日判決・民集34巻3号244頁、東京高裁昭和51年5月19日判決))。
パロディとは、すでに存在する表現物の一部を改変して別のものとして出す作品のことです。
この事件は、ある写真家が撮った写真、スキーヤーがシュプールを描きながら往復している写真(写真左)なのですが、別の方がこのように改変しました(写真右)。
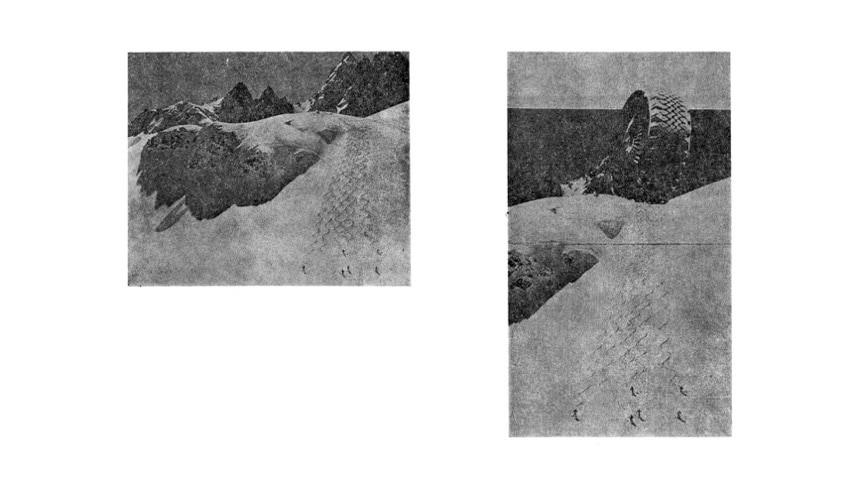
この結果、元の写真を撮影した方が改変した方を訴えた事件ですが、改変した方は、これは「引用」だと主張しました。
著作権者は様々な権利を専有していますが、ある一定の場合には著作権者以外の人もそれを利用することができ、その一つが「引用」です(著作権法32条1項)。たとえば、論文を書く時に「あの論文の著作者はこう言っているけれども、私はこう思う」という時の、「あの論文の著作者はこう言っている」の部分が引用なわけです。実際に引用かどうか認められるためには、①元の著作物と明瞭に区分されていること、②元の著作物に対して主従の関係があること、という要件があります。
パロディモンタージュ事件の場合、最高裁は著作権上違法という結論を下しています。
パロディと引用の共通点は、「元の作品を活用して別の作品を作る」ことで、それはまさに同人誌でも行われています。
同人活動をしている人の感覚は「私的利用」に近い
私の知り合いで同人活動をしている人がいて、あくまで身内で楽しんでいるだけですけど、今回のテーマである「グレーゾーン」についてどう思うか訊いてみました。すると、「自分の存在自体がグレーゾーンだ」と言うわけです。自分がやっていることは何かまずいことかも、という感覚はあるんだなと。
「作品を広く発信したい、作品が認められたい、という感覚を持っていない?」と訊くと「それは違う」と言うわけです。
「ドラえもんだったらこういう道具があったらいいよね、みたいな議論を仲間内ですることはあるでしょう。それをたまたま作品という形で表しているに過ぎないです」という話だったんです。
同人活動をしている人も様々で、自分の趣味や思想を身内だけで共有して楽しんでいるだけのものもある。その楽しみが妨げられたらいやだけれども、権利を手に入れて発信をしたい、認められたい、というわけではないのです。
同人文化について法律的な議論をする時、「引用」かどうか、という視点で考えられることが多いですが、私が聞いた範囲だと、「引用」よりも「私的利用」に近いのではないかと思いました。
私的に利用する範囲であれば他人の著作物は自由に利用することができるわけで、自分の権利をもとに何かをしたいというよりは、そこで楽しみたいだけの感覚なのです。

現代アートの訴訟から、日本へのフェアユース導入を考える
続いて発表したのは長島・大野・常松法律事務所の小松 隼也氏。自身もアートコレクターというバックグラウンドを基に、アメリカの現代美術における訴訟を紹介し、日本における引用とグレーゾーン、そしてフェアユースに対する考えを語った。
アメリカの「フェアユース」と訴訟
アメリカの現代美術には、アプロプリエーションという手法で作られた作品があります。簡単にいうと、すでに存在している他人が作ったイメージを意図的に流用、コピー、変容などをして作る作品です。
大量消費の時代、テレビや雑誌といったマスメディアが流行った時代のポピュラーアイコンを別の作品として転換することで、時代性に対する批判や皮肉を込めるという手法ですが、非常に有名な例としては、アンディ・ウォーホルが挙げられます。
アプロプリエーションによって作られた作品が著作権を侵害しているかどうか、アメリカだとフェアユース(Fair Use)という著作権法の制限規定の概念に当たるかが問題となります1。フェアユースの考慮要素は色々とあるのですが、表現が「変容的」(Transformative)といえるかどうか、新しい表現と言えるかどうかという概念で判断するという点がポイントになっています。
アプロプリエーションという表現手法は今の時代に必要だから認めてあげたほうが表現の幅は広がるよね、という発想があり、裁判所も変容的であれば著作権侵害にはあたらないという判断をしています(たとえば、Blanch v. Koons, District Court, S.D. New York. 396 F. Supp. 2d 476(2005))。
アメリカにリチャード・プリンスという現代美術の作家がいるのですが、彼はアプロプリエーションを用いた作品を発表し、常に訴訟の対象になっています。
2007年にニューヨークで発表された『Canal Zone』という作品を例にあげて紹介します。これはリチャード・プリンスが、フランス人の写真家パトリック・カリューの写真集を拡大コピーし、その画像を切り貼りして作ったものです。
パトリック・カリューの作品は、6年間ジャマイカの宗教的思想集団であるラスタファリアンというグループと一緒に生活しながら撮影した写真をまとめたものなのですが(写真左)、リチャード・プリンスの作品はこのように変容されています(写真右)。

著作権侵害でパトリック・カリューに訴えられたリチャード・プリンスは、「元の作品に対する批判ではなくて、この表現が俺の作品には必要だった。世界が崩壊した後の男女という性がなくなったジェンダーレスな中でのカオスな音楽を奏でたかったんだ」と言うんですね。裁判所はそのリチャード・プリンスの発言を聞いて、「変容的ではない」、「元の作品に対する批判的な要素は全くない」と判断し、ニューヨークの第一審はリチャード・プリンスを敗訴としました。
ところが、高裁ではその判断がひっくり返り、リチャード・プリンスが逆転勝訴となります。裁判所の結論を手短にいうと、「作家の主観は問題ではなく、客観的に新しい表現になっていればフェアユースを認める、条文上も批判が求められるなんて書いていない」ということです。
実際に裁判所は個別の作品1点1点について「これはフェアユース」「これはよくわからない、差し戻して再度判断すること」などと判断していますが、裁判所の言う客観的に新しい表現、これはグレーゾーンなわけです。
日本でのフェアユースの動向
日本では、「フェアユース規定を著作権法に入れ、著作物の利用を認める、認めないという判断を裁判所に投げる」のか、それとも「具体的にこういう使い方をした場合であったら他人の著作物を利用していても、例外的にOKですよ」という細かい法律を作るのか、議論されています。
アメリカがフェアユース規定を最初に作った後に、韓国やイスラエルがフェアユースの規定を入れたのですが、日本は否定的な流れが続いていて、未だにフェアユース規定は入っていません。
平成24年の著作権法改正で、インターネットやデータマイニングの必要性から、著作権法の中に、「こういう場合は他人の著作物を使っていい」という権利制限規定を4つ追加していますが(参考:文化庁「平成24年通常国会 著作権法改正について」)、それではまだ全然足りない。人工知能や画像認識ソフトをビジネスとして使っている会社からすると、現行の著作権法の枠組みの中だと、データを複製したらすでに著作権侵害という発想があって、それだとビジネスができないわけで、変えて欲しいという話があります。
とはいえ、元のデータを持っている業界団体のような権利者側の立場からは、フェアユースを入れてしまうと、カオスな状態になるのではという懸念もありますし、先ほどのリチャード・プリンスの例のように、判断基準がよくわからない規定を入れられても、かえって他人の著作物は使えないという萎縮効果が高いのではという発想もあったりします。
そのような流れの中で、今まさに、柔軟性を高める規定を入れたほうがいいのか、それとも権利制限規定を細かく定める規定にしたほうがいいのかという個別具体的な議論がなされています(参考:文化庁「文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会 平成28年度「新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」(第6回)」)。おそらく近いうちにフェアユースに関する一つの方向性が示されるのではないでしょうか。
ただ、アメリカほど抽象的にはならず、今までの著作権法のように細かく定めるわけでもない、中間的な規定になっている可能性が高いので、どのように改正されるのか、そして出来上がった規定を裁判所がどのように運用を行っていくかというところに注目が集まるでしょう。

起業家のグレーゾーンの歩き方
3人目の発表者は株式会社ドリームインキュベータでベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー投資や投資先の経営支援を専門としている下平 将人氏。法律事務所、事業会社での経験や起業家と接する中で感じた「法のグレーゾーン」への向き合い方について語った。
グレーゾーンは経営課題
いきなり感覚的な話になりますが、事業はマラソンみたいなもので、ランナーである起業家は、市場の選択として、高地で走るのか、海沿いで走るのかをまず決め、走る場所を決めたら、横目で競合ランナーを意識しながら、顧客満足に向けて駆け抜けていきます。
B/S(貸借対照表)とは、骨や筋肉から成る体そのもので、走った実績がP/L(損益計算書)の形で営業成績の形となって現れる。C/F(キャッシュフロー・ステートメント)により残存体力を確認し、時々水分補給(資金調達)を行いながら、自信が理想とするビジョンの実現を目指すというようなイメージを持っています。
事業と法律の関係性をマラソンに例えると、法律は道路のガードレールや標識のような役割を果たしている思います。どこまで走っていいのかガイドしてくれる存在です。
法律のグレーゾーンとは、霧みたいなもので、霧があると、ガードレールや標識がどこにあるか分からず、どこまで走っていいかがわからなければ、怖くて誰もその道路を走らなくなりますよね。ですので、ランナーである起業家にとって、グレーゾーンは大きな経営課題なのです。
今日は、このグレーゾーンに対して起業家や経営者がどのように対峙していくべきか、これをグレーゾーンマネジメントと勝手に呼びたいと思いますが、グレーゾーンマネジメントについてお話しできればと思います。
グレーゾーンマネジメントは、大きく3つのプロセスからなると考えています。①判定、②意思決定、③歩み方というプロセスです。
まず、①判定です。
起業家が霧に対峙したとき、まずその霧が白・黒・グレー、どの色か的確に判定することが重要です。
法的にグレーというのは「目の前にある事象に対してある法律が適用されるかよくわからない」という状況ですね。適法であっても社会倫理や社会感情的にNGなものについても、グレーゾーンといえるかもしれません。
起業家にとって、クリティカルに重要となるのが、法的判断のパートについて誰に相談するかです。企業法務は業務分野ごとに専門性が細分化されていますので、”土地勘”を持つ”真の専門家”に相談することが重要で、土地勘がなさそうであれば、セカンド、サードオピニオンを粘り強く取りに行くことが重要だと思っています。真の専門家は弁護士に限らず官公庁も含まれてきます。電話で相談すると匿名でもいろいろ教えてくれたりします。
真の専門家の探し方としてお勧めなのは、適切な紹介をしてくれる”ハブ”となる弁護士を見つけて付き合っていくことです。弁護士の腕・スキルは、弁護士同士でしか判断できなかったりするからです。
弁護士は依頼されたら、門外漢でもやりきろうとする職人気質のところがありますが、”土地勘”を身に着けるのには時間と修練が必要で、自分の門外漢の案件については、所内外の詳しい人にふってしまうことの方が、正確さとスピードが出て、クライアントにとって本質的な価値が出ることが多いように思います。社内法務や社内弁護士(インハウス)も同様です。紹介した側の弁護士は、案件に横で混ぜてもらって土地勘を持っている人から土地勘を学んでいけば良いのです。
グレーゾーンの判断基準
次に、②意思決定についてです。色の判定をしたらグレーゾーンだった、という時に何を判断基準とすべきでしょうか。一番重要なのは、お客様やステークホルダーにとって本当に価値があるのか、事業としての志があるのかだと思っています。言い方を変えると、サービスが炎上した時に、「そのサービスがなくなってほしくない」と言ってくれる人がどれだけいるかです。
たとえば、1980年くらいにレンタルレコードが急拡大したのですが、レンタルによってレコードの売上が減少しました。当時は貸与権等もなく、レンタルレコードは民事的に見たら不法行為に当たるかもしれないグレーなサービスだったかと思いますが、普及していったわけです。業界団体やレコード会社は訴訟を提起したのですが最終的には和解し、その和解案をベースとして著作権法が改正され、レコード製作者に対して貸与権や報酬権が付与されました。
グレーとも思える中、レンタルレコード会社が事業を進められたのは、「レンタルであれば安く音楽が入手できるようになり音楽を聴くことがより普及するので社会的・文化的な意義が大きい。レコード会社から刺されても、きっと聞き手である消費者が味方してくれるだろう」という判断があったからできたはずです。
グレーゾーンでの歩み方
次に、③歩み方についてです。経営判断として「これはグレーだけど進めましょう」となった時に、どう動くべきか。スタンスとしては、できるだけアジャイル2に少しずつ、世の中の反応を見ながら歩み始めること。いざ歩み始めたら機能面やオペレーションを改善しながら、ホワイトな方向に向けて走っていくことが重要だと思います。グレーゾーンという霧の中で走るのはしんどいじゃないですか。
一方で、法的な見解・判断や世の中の価値観って結構コロコロ変わるんですね。今までグレーとか適法だったサービスが、ある日グレーやブラックになることもあります。そういう変化も見ていくべきです。
たとえば、グーグルは以前Gmailの中身を解析していたのですが、ユーザーのプライバシー意識や感情の高まりを察知して、解析を止めており、社会感情面でのホワイト化をうまく進めているわけです。
サービスマネジメントやグロースハックといったテーマの中に、”グレーゾーンをどうマネジメントするか”という視点が入っていて、グレーとも思える部分を攻めながら引き際もしっかりと見極めることができている。経営トップがそこにコミットできている。グーグルの強さはそこにもあるかなと思っています。
話をまとめると、グレーゾーンは事業というマラソンを走るにあたっては霧のようなもので、霧に巻き込まれた時にどうマネジメントしていくかという視点がとても重要です。ポイントは、真の専門家を見つけて、黒か白かグレーなのか、その色をしっかり見極めながら、突き進む価値があるのか判断することで、グレーの中で事業をやるのであれば、小さく始めて、ホワイト化を進めること。霧のない、景色がより良いところを目指すべきだと思います。

わいせつ表現とグレーゾーン
シティライツ法律事務所の水野 祐弁護士からはわいせつ表現の規制について、最近の裁判の動向、展示における規制と対応を巡るグレーゾーンが紹介された。
裁判所はわいせつ表現をどのように判断したか
わいせつ表現の判断については、「チャタレイ夫人の恋人事件」の最高裁判決3(最高裁昭和32年3月13日判決)の中で示された、①いたずらに性欲を興奮または刺激すること、②普通人の正常な性的羞恥心を害すること、③善良な性的道義観念に反すること、という3つの要件を社会通念に従って判断する考えが、今でも一応先例とされています。
その後、「悪徳の栄え事件」という最高裁判決4(最高裁昭和44年10月15日判決)があって、わいせつかどうかは作品の一部ではなく全体で判断するという考えが示されています。
わいせつを扱った最高裁判決の中で比較的最新のものとしては、「メイプルソープ事件」5(最高裁平成20年2月19日判決)があります。
最高裁は、作品の一部について「いずれも性器そのものを強調し、その描写に重きを置く」写真であると認定しました。そのうえで、①メイプルソープは現代美術の第一人者として美術評論家から高い評価を得ていた、②メイプルソープの作品は写真芸術や現代美術に高い関心を持つ者に購読、鑑賞されることを予定していた、③写真集全体に対して、性器を写した写真の占める比重が全384ページ中19ページと低かった、という事実認定をしています。③の判断は悪徳の栄え事件の判決を踏襲しているものと考えられます。
最終的には、この写真集には芸術性など性的刺激を緩和させる要素が存在した事や、写真集を全体として見た場合、見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難として、関税定率法上の「風俗を害すべき図画ではない」、つまり「わいせつではない」と判断しました。
メイプルソープ事件は研究者によって様々な評価がされているのですが、「芸術性を持つ事が違法性を若干緩める」とも読める判断は、過去の判例の解釈を変更しているのではないかという評価もなされています。
他にも事例を紹介しますと、現在上告中の「ろくでなし子」さんの事件があります6(東京地裁平成28年5月9日判決、東京高裁平成29年4月13日判決)。
問題になったのは、『デコまん』という彼女の性器をデコレーションした作品と、彼女の性器の3Dデータで、東京地裁、東京高裁共にこの2つを分けて考えています。
まずデコまんの方に関して、裁判所は「ポップアートの一種と捉えることが可能で、わいせつ物にあたらない」というかなり思い切った判断をしています。そして、「性的刺激が緩和され」るとも判断しています。おそらく、言葉遣いからもメイプルソープ事件を意識しているのでしょう。
一方で、クラウドファンディングのリターンとして、彼女の性器の3Dデータを送信したことや、CD-Rに焼いて配布したことについては、わいせつ電磁的記録頒布にあたると判断しています。
近年の判例・裁判例をみると、芸術性がわいせつ性を一定程度減退させることを認めているように読める判決が出ていますが、そもそも芸術であることが、わいせつ性を低めるという判断を本当にしていいのか。裁判官、裁判所が芸術性の高さ・低さを判断できるのか。これは先ほどのリチャード・プリンスの作品が、フェアユースかどうか、表現に新しい価値が付与されているか否かを裁判所が判断できるのか/してよいのかの是非、みたいな議論とも近いと思います。
展示における「わいせつ」と美術館の対応
鷹野隆大さんという写真家が愛知県立美術館で開催した、「これからの写真」展(2014年8月)の中の一部の展示が、わいせつ物の陳列にあたるということで県警から指摘を受けました。美術館側は鷹野さんを交えて協議して、写真に白い布をかけたり、写真全体にシートを被せたりという対応をしたのですが、美術館側の対応の是非や、そもそも「わいせつって今の時代ナンセンスなんじゃないの?」という様々な議論が巻き起こりました。
森美術館で開催された、会田誠さんの「天才でごめんなさい」展(2012年11月)は、主に女性、幼い女性や幼児を扱う残虐または性的な表現が問題になったんですが、開催時には事前に美術館側から「性的表現を含む刺激の強い作品が含まれています」というコメントの掲示や、過激な表現をしている作品は18歳未満の入場を規制するというゾーニングがされていました。
もう1つ性表現での重要な分野に児童ポルノがあります。フランスの画家バルテュスが死ぬ間際に撮影していた、少女の裸体が写っているポラロイド写真の作品について、日本では三菱一号館美術館が頑張って公開(2014年6月)したのですが、ドイツの美術館では開催できませんでした。海外の方が児童ポルノに対して厳しい目線があるのです。
わいせつに関する判断基準はどこに
これは私なりのまとめで、わいせつに当たるかどうかには、主に3つくらいの基準があるのではと総括しています。
1つ目が、性器にフォーカスしているかどうか。2つ目が、人単体ではなく、絡みを連想させるかどうか。複数で写っている場合に親密な空気感が出ると性的な表現を連想させる。3つ目は、適切なゾーニングをしているかどうか。この辺を総合的に判断して警察が運用していると言われているのですが、やっぱりよくわからない、グレーゾーンだと言われます。
わいせつを巡る裁判や警察の関与、性表現規制など様々な国内の事例を集めたArts and Lawが協力したウェブサイトがあります。これも、もし興味があればご覧ください。
参考:東山アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)「芸術判例集 美術表現に関わる国内裁判例25選」(監修:Arts and Law)

(取材、構成:BUSINESS LAWYERS編集部)
-
主にアメリカの著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つ。表現の使用の目的がニュースの報道、批評、解説、学校教材、調査、研究などである場合には著作権侵害には該当しない。同国の著作権法107条によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準(①利用の目的および性質、②元の表現の性質、③使用された部分の量、④元の表現の潜在的利用または価値に対して与える影響)を総合考慮し、公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。 ↩︎
-
『すばやい』『俊敏な』という意味で、イテレーションと呼ばれる短い開発期間単位を採用することで、リスクを最小化しようとする開発手法の1つ。 ↩︎
-
イギリスの作家D・H・ローレンスの作品『チャタレイ夫人の恋人』を日本語に訳した作家伊藤整と、版元の小山書店社長小山久二郎に対して刑法175条のわいせつ物頒布等罪が問われた事件。2人の有罪判決が確定している。 ↩︎
-
フランスの小説家マルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』を日本語に翻訳した澁澤龍雄(筆名・澁澤龍彦)と、版元の社長石井恭二に対して刑法175条のわいせつ物頒布罪が問われた事件。2人の有罪判決が確定している。 ↩︎
-
米国の写真家ロバート・メイプルソープの写真集を日本の税関が「わいせつ図画」に当たると判断し、没収した行為の妥当性を巡り没収処分を受けた出版社社長の男性と日本国政府が争った事件。 ↩︎
-
クラウドファンディングの支援者に自身の性器の3Dデータを配布した事が電磁的記録等送信頒布罪などに問われ、自身の女性器をかたどり、着色するなどした石膏作品(「デコまん」)を東京都内のアダルトショップに陳列したとするわいせつ物陳列罪に問われた事件。 ↩︎
