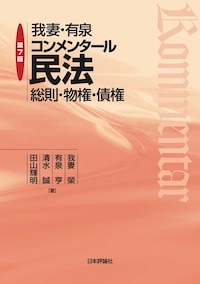民法改正(債権法改正)と不動産取引への影響
第1回 売買契約に関連する民法改正のポイント
取引・契約・債権回収 更新
シリーズ一覧全11件
目次
民法改正(債権法改正)のポイントとその概要
2017年5月26日に、民法(債権法)の改正法案(以下「改正民法」といいます)が成立し、2020年4月1日に施行されることになりました。この改正は、民法制定以来約120年ぶりに債権部分を抜本的に見直すもので、改正項目は約200項目に及びます。
不動産取引その他のビジネスにおいて用いられている契約書は、現行の民法を前提に作成されていますが、改正民法には、現行民法とは大きく異なる規定が多数存在しています。そのため、今後は、現在使用している契約書の各条項について、改正民法でどのように変わるのかを確認したうえで適切に見直すことが必要不可欠となります。
本項においては、改正民法のほか、法務省の公表している「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明(平成25年7月4日補訂)」(以下「補足説明」といいます)なども踏まえて、不動産売買契約に関連する改正民法のポイントについて、その概要を説明します。
次回は、不動産取引契約において改正民法を踏まえてどのような点に注意すべきか、『不動産売買契約の注意点』について説明する予定です。
参考:民法改正を踏まえた不動産取引の実務対応ガイド・売買契約書のサンプル付き
売買契約における契約不適合責任
契約不適合責任の概要
(1)現行民法下における瑕疵担保責任の法的性質(法定責任説)
現行民法では、売買の目的物に欠陥・不具合(瑕疵)があった場合、当事者が特定の物の個性に着目して取引する場合(特定物売買)とそれ以外の場合(不特定物売買)を分け、特定物売買の場合には瑕疵担保責任(現行民法570条等)、不特定物売買の場合には債務不履行責任(現行民法415条)が適用されるものとされてきました。
その根拠として、特定物売買における売主の義務は、その目的物の所有権を買主に移転することに尽きるため、たとえ目的物に欠陥があっても売主に欠陥のないものを引渡す義務はなく、債務不履行責任は生じないという考え方がありました(「特定物のドグマ」と呼ばれています)。
そのうえで、売主が債務不履行責任は負わないとしても、そのままでは買主の信頼が裏切られてしまうため、買主の信頼保護のために特に法律で定めたものが瑕疵担保責任であるという考え方が通説とされてきました(「法定責任説」と呼ばれています)。
もっとも、法定責任説に対しては、これまで批判的な見解も多く存在していました。
(2)改正民法における契約不適合責任
このような背景のもと、改正民法では、現行民法の瑕疵担保責任は廃止され、特定物売買か否かで分けることなく、目的物が契約内容から乖離していることに対する責任(以下「契約不適合責任」といいます)が新たに規定されました。契約不適合責任は、これまで通説とされていた法定責任ではなく、債務不履行責任として整理されることになり、契約一般についての債務不履行責任との関係では、売買の場合についての特則として位置づけられることになります。
以上のように、改正民法では、これまでの瑕疵担保責任の考え方とは根本的な違いがあるため、様々な違いが生じます。たとえば、現行民法では、目的物の欠陥に関する買主の救済手段としては損害賠償請求と解除の二つの選択肢しかありませんでしたが、改正民法では、追完請求や代金減額請求が可能となります(詳細は後述します)。
売買契約における現行民法の瑕疵担保責任と改正民法の契約不適合責任の相違のポイントは、以下の表のとおりです。
【売買契約における現行民法の瑕疵担保責任と改正民法の契約不適合責任の相違】
| 現行民法 | 改正民法 | |
|---|---|---|
| 法的性質 | 法定責任(通説) | 債務不履行責任 |
| 対象 | 隠れた瑕疵 | 契約の内容に適合しないもの |
| 契約解除 | 契約の目的を達成できない場合、可 | 催告により、可 不履行が軽微である場合、不可 |
| 損害賠償請求 | 無過失責任 信頼利益に限られる |
売主の帰責事由が必要 履行利益も含まれる |
| 追完請求 | 不可 | 履行可能であれば、可 買主の責めに帰すべき場合、不可 |
| 代金減殺請求 | (数量指示売買を除き、)不可 | 催告により、可 買主の責めに帰すべき場合、不可 |
| 権利行使の保全方法 | 知ってから1年以内に 損害賠償等の請求が必要 |
知ってから1年以内に 契約不適合の事実の通知で足りる |
契約不適合責任の要件
(1)「契約の内容に適合しないものである」こと
改正民法では、契約の内容についての解釈は、「合意の内容や契約書の記載内容だけでなく、契約の性質(有償か無償かを含む。)、当事者が契約をした目的、契約締結に至る経緯を始めとする契約をめぐる一切の事情につき、取引通念を考慮して評価判断されるべきものである」とされています(補足説明・第8「債権の目的」(89~90頁)参照)。
もっとも、このような考え方は、従来、「瑕疵」の概念について議論されてきた主観的瑕疵・客観的瑕疵の内容と大きく異なるものではありませんが、今後、民法の文言が変わることにより、裁判所の判断が変わっていく可能性は否定できず、「契約の内容」の解釈を巡って争いになる可能性があります。
(2)不特定物売買への適用
現行民法と異なり、改正民法では、特定物・不特定物の区別はなく、引渡された目的物が「種類、品質及び数量に関して契約の内容に適合しないもの」であるときに、売主が契約不適合責任を負うことになります(改正民法562条~564条、補足説明・第35「売買」3項「売主の義務」(397~398頁)参照)。
(3)要件の有無の判断時期
従来、「瑕疵」かどうかの判断時期については、法定責任説の立場から、契約締結時点までに生じた瑕疵に限られると解釈されていましたが、改正民法では「契約の内容に適合しない」か否かは契約締結の前後で区別せず、引渡し時までに発生した場合も含むことになると考えられています。
(4)契約不適合が「隠れた」ものであることは不要
改正民法においては、売買の目的物について買主が欠陥を認識していたり外形上明らかな欠陥があった場合でも、「契約の内容に適合しない」場合がありうることから、従来のように「隠れた」ものである必要はないことになります。
(5)損害賠償請求には売主の帰責性(過失)が必要
現行民法における瑕疵担保責任は、売主の無過失責任(売主の帰責性は不要)であると解されていますが、改正民法における契約不適合責任は、債務不履行一般の損害賠償請求のルールに従うことになります。したがって、契約不適合があっても、「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は、損害賠償請求をすることはできないことになります(改正民法415条1項ただし書)。
契約不適合責任における買主救済手法の多様化
上記のとおり、買主の救済方法について、改正民法は、債務不履行責任に関する売買の特則として整理され、契約不適合の状態に応じて、①追完請求権(改正民法562条1項)や②代金減額請求権(改正民法563条1項、2項)が規定されました。瑕疵担保責任として現行民法でも認められていた解除や損害賠償についても、③契約の解除(改正民法564条、541条、542条)や④債務不履行による損害賠償(改正民法564条、415条)として規定されています。
以下、それぞれについて説明します。
(1)追完請求権(代替物の引渡し、補修請求権)(改正民法562条)
改正民法では、売主が契約の内容に適合しない目的物等を引き渡した場合には、履行が不能である場合等を除き、買主には当然の結果として追完請求権(代替物または不足分の引渡請求権および修補請求権)が認められることになりました(改正民法562条1項)。

追完請求のうち、履行の方法が複数ある場合には買主に選択権がありますが、「買主に不相当な負担を課すものではないとき」は、売主は買主の請求とは異なる方法での履行の追完をすることが可能とされています。このことは、次項の代金減額請求権についても同様です。
- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 - 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
改正民法565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
(2)代金減額請求権(改正民法563条)
改正民法では、売主が契約の内容に適合しない目的物等を引き渡した場合には、買主の責めに帰すべき場合を除き、新たに代金減額請求権が認められました(改正民法563条1項、2項)。

代金減額請求権は、履行の追完を催告したにもかかわらずこれがない場合に、「不適合の程度に応じて」代金の減額を請求することができるものです。
- 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
- 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(3)損害賠償請求権(改正民法564条、415条)
現行民法の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は、信頼利益に係る損害(その契約が有効であると信じたために発生した実費等の損害)であるといわれていますが、これに対し、改正民法の契約不適合責任に基づく損害賠償は、債務不履行一般と同様に損害の範囲に履行利益(その契約が履行されていれば、その利用や転売などにより発生したであろう利益)に係る損害を含むことになると考えられます。
- 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 - 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
改正民法564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
(4)契約の解除(改正民法564条、541条)
現行民法では、債務不履行を理由とする解除の要件として、債務者の責めに帰すべき事由の存在が必要であるとされていましたが(現行民法543条ただし書)、改正民法における契約不適合責任に基づく解除の要件としては、債務者の責めに帰すべき事由は必要とされていません。
不動産の買主が契約から解放されたいと考える場合、催告による契約解除(改正民法541条)ができることになります。

この場合、現行民法において瑕疵担保責任に基づく解除をする際に求められるような「契約をした目的を達成することができない」ことは要件とされませんが、追完の催告期間経過後に債務の不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合」には契約解除ができないこととされました(改正民法564条、541条ただし書)。ここにいう「軽微である場合」と「契約をした目的を達成することができない場合」とは、必ずしも同一の場合を指すものであるとは限らないため、注意が必要です。たとえば、契約目的は達成できるが、軽微とは言えない欠陥が存在した場合、現行民法では解除できなかったものが、改正民法では解除できることになりうるということです。
他方で、債務の履行が不能である場合や、その他、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき等)には、催告によらずに契約を解除することができます(改正民法542条)。
もっとも、債権者(不動産の買主)の責めに帰すべき事由によって債務不履行が生じた場合には、買主から契約解除することはできないことが明らかとされています(改正民法543条)。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
改正民法542条(催告によらない解除)
- 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
- 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
改正民法543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者 は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
買主による権利行使のための通知期間制限
(1)契約不適合を知った時から1年間の通知制限期間
現行民法においては、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求等について、瑕疵を知ってから1年間という権利行使の期間制限(現行民法566条3項等)が存在しましたが、改正民法では、「種類又は品質」に関する契約不適合を認識したにもかかわらず1年間売主に対してその旨の「通知」をしない場合に、買主が失権することとされました(改正民法566条)。
この点について、1年間の通知期間の始期が「不適合を知った時」とされているため、現行民法において、担保責任を追及しうる程度に確実な事実関係を認識した時点を始期とする考え方と比較すると、失権しやすくなったという指摘があります。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(2)契約不適合を知った時から5年間等の消滅時効
上記の「種類又は品質」に関する契約不適合に対し、「目的物の数量」や「権利移転」に関する契約不適合については、改正民法566条の対象とはならず、一般的な消滅時効の定めに従うものとされています。
消滅時効について、現行民法は「権利を行使することができる時から進行」(現行民法166条1項)し、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」(現行民法167条1項)ものとされています。これに対し、改正民法においては、「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から「5年間」行使しないとき、または「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から「10年間」行使しないときは、時効によって消滅することとなりました(改正民法166条1項)。
- 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
- 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(3)買主の権利を保存するために必要な通知
現行民法の下において、消滅時効の完成を防ぐための権利の行使は、裁判例により「売主に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示す」必要があるとされています(最高裁平成4年10月20日判決・民集46巻7号1129頁)。これに対し、改正民法566条においては、不適合についての「通知」を行うことで足りることとされました。
この「通知」は、商法526条2項の「通知」と同様に、瑕疵・数量不足の種類をその大体の範囲を明らかにすれば足り、損害賠償の額の根拠まで示す必要はないとの指摘があります。
なお、商人間の取引等において商法526条の適用がある(引渡人から6か月以内の通知が求められる)場合があることには注意が必要です。
(4)消滅時効の障害事由(時効の更新と完成猶予)
改正民法においては、現行民法における時効の「中断」と「停止」の呼び方が、「更新」と「完成猶予」という呼び方に置き換えられました。
| 「中断」⇒「更新」 | 進行していた時効期間を“ゼロにリセット”する |
| 「停止」⇒「完成猶予」 | 時効期間の進行が“いったんストップ”する |
改正民法においては、現行民法のように「中断」「停止」(改正民法の「完成猶予」「更新」)ごとに該当する事由を列挙するのではなく、「裁判上の請求」「強制執行」「仮差押え」「催告」等の類型ごとに、それぞれ「完成猶予」または「更新」について規定する方法に改められました(改正民法147条~151条、補足説明・第7「消滅時効」6項「時効期間の更新事由」(78~82頁)、7項「時効の停止事由」(82~87頁)参照)。
特に、現行民法において、裁判例上認められている裁判上の「催告」の概念が明文化されたほか(改正民法150条)、当事者者間で係争債権に関する「協議を行う旨の合意」がなされた場合にも一定範囲に完成猶予の効力が認められることとなったこと(改正民法152条)などが注目されます。
| 改正民法の条項 | 内容 |
|---|---|
| 改正民法147条 | 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 |
| 改正民法148条 | 強制執行等による時効の完成猶予及び更新 |
| 改正民法149条 | 仮差押え等による時効の完成猶予 |
| 改正民法150条 | 催告による時効の完成猶予 |
| 改正民法151条 | 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 |
| 改正民法152条 | 承認による時効の更新 |
売買契約における売主の表明保証責任
表明保証とは、契約当事者の一方が、他方当事者に対し、契約の目的物等に関連する一定の事項について真実かつ正確であることを表明し、その表明した内容を保証するものであり、表明保証条項が規定される場合には、通常、一方当事者により表明保証された事項が真実かつ正確ではなかった場合の損害補償義務等が定められます。
上記のとおり、売主の契約不適合責任が債務不履行責任として位置付けられたことから、表明保証条項を債務不履行責任と考える従前の考え方に、改正民法における契約不適合責任が近接したかのようにも思われます。
ある表明保証事項に反する事実が判明した場合において、現行民法では当該表明保証違反が「瑕疵」とまでの評価を受けないものであっても、表明保証事項が「契約の内容」(売主の給付義務の内容)を画するものと解され、当該事実をもって「契約の内容に適合しない」(現行民法562条等)と評価されることにより、結果的に売主の契約不適合責任を生じさせる余地があるとの指摘もあります。
改正民法の影響と不動産取引契約の見直しの必要性
以上のとおり、現行民法と改正民法では、売買の目的物に欠陥があった場合の売主の法的責任の内容に大きな変更が生じうることになります。とはいえ、単純に法文の書きぶりが変わったから、法的効果もそのとおりに変わるとは限りません。
たとえば、上記のとおり、現行民法では信頼利益に限られた損害賠償の範囲は、改正民法では履行利益にまで拡張されることになりますが、瑕疵担保責任における損害賠償の範囲が信頼利益であると解釈されていたこれまでの裁判例実務においても、修補請求相当額の費用、支払代金と瑕疵があるために下落した価格の差額など、履行利益の損害賠償を認めたのと同様と評価できる結論がとられるケースも見られたことなどから、事案の性質や損害の内容によっては、民法改正により損害賠償の範囲が大きく変わるとはいえないという指摘もあります。
しかし、これは、実際に訴訟となって裁判所の判断が出された後に判明することであり、結果的に従前の実務と同様の結論に至る論点はあるとしても、本当にそうなるかどうかの予測はこれまでよりも難しくなると言わざるを得ません。そのため、今後、改正民法下において、できる限り紛争を予防し、不測の損害を被る事態を防ぐためには、上記のような変更点を十分に意識したうえで慎重な検討を行い、売買契約の各条項について見直しを行うことが必要不可欠となります。
さいごに
以上のとおり、不動産取引(売買契約)に関連する改正民法のポイントについて、その概要を説明しました。
次回、不動産取引契約において、“改正民法を踏まえてどのような点に注意すべきか”という点について、土壌汚染地取引などのケースを例に挙げて、『不動産売買契約の注意点』を説明します。
【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】
『我妻・有泉コンメンタール民法[第7版] 総則・物権・債権』
発売日:2021年04月01日
出版社:日本評論社
編著等:我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『改正債権法コンメンタール』
発売日:2020年10月05日
出版社:法律文化社
編著等:松岡久和、松本恒雄、鹿野菜穂子、中井康之
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
『民法改正で変わる!契約実務チェックポイント』
発売日:2017年03月18日
出版社:日本加除出版
編著等:野村 豊弘、虎ノ門南法律事務所
BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む
2018年1月9日(火)14:30:「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成29年政令309号)の公布により、内容面を一部修正いたしました。
シリーズ一覧全11件

牛島総合法律事務所
- コーポレート・M&A
- 知的財産権・エンタメ
- 競争法・独占禁止法
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
- 不動産

牛島総合法律事務所
- コーポレート・M&A
- IT・情報セキュリティ
- 知的財産権・エンタメ
- 危機管理・内部統制
- 訴訟・争訟
- 不動産