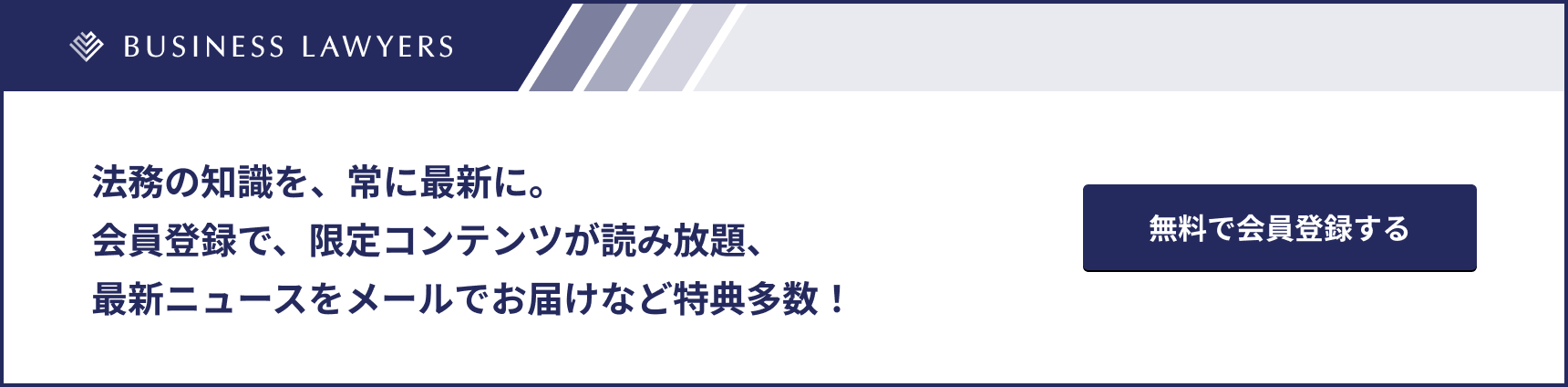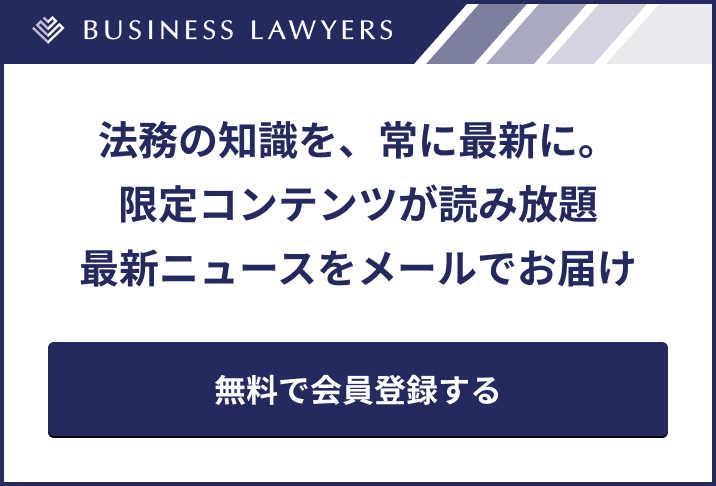下請法改正はイノベーション創出につながる ミクロ経済学の視点で語る「経営者に伝えたい」改正のポイント
競争法・独占禁止法
2025年5月16日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(改正下請法)が可決・成立し、2026年1月1日から施行される。
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、通称:取適法)への名称変更をはじめ、企業の実務において重要な改正が多く予定されているが、本質は「イノベーションの創出」と駒澤大学の岡室博之教授は語る。
改正に向けた議論を重ねた企業取引研究会に、ミクロ経済学の立場から参加した岡室教授は「今回の改正は経営戦略の問題と受け止めてほしい」と思いを込める。
岡室教授に研究会での議論内容、改正の趣旨・目的を聞いた。
※改正法の詳細な内容については「令和8年1月施行!改正下請法(中小受託法/取適法)の概要と企業に必要な対応」をご参照ください。
下請法改正がイノベーションを促進する
まずは、下請法改正の背景となった経済環境の変化についてお聞かせください。
今回の下請法改正の背景には、日本経済が経験した「失われた30年」からの脱却という考えがありました。
長期デフレを解消し、今後の経済発展、ひいてはイノベーションを推進することが企業取引研究会での議論の出発点です。
研究会には法学を専門とされる先生方が多く参加されていましたが、私はミクロ経済学の立場から参加しました。過去に、日本とドイツの自動車産業における下請取引の研究をしたので、この経験も活かしたいと思いました。
研究会での議論はどのように進んだのでしょうか。
「特定の市場や業種で常識と見なされてきた慣習が生産性向上と賃上げを阻み、デフレを助長している」という共通認識がありました。
そのため、「経済合理性がない慣習を見直す必要がある」という点から議論が始まったのです。
製造業だけでなく、物流やサービスなど多岐にわたる取引が検討の対象となりました。グローバルな視点でビジネスのあり方が変化する中で、日本の規制やルールの枠組みは高度経済成長期のまま、という点が問題として指摘されています。
私は、専門分野であるイノベーションや新たな企業・事業の創造といった観点から、「自由で公正な競争を通じて、取引関係の中からイノベーションが生まれ、そこに新たな企業が参入できるようなルールを構築すべき」という持論をお伝えしました。

具体的に、取引関係におけるどのような慣習がイノベーションを阻害してきたとお考えでしょうか。
研究会において特に繰り返し指摘された問題が「買いたたき」です。この行為自体、非常に問題ですが、その前提には「ずっと同じ企業と取引をする」という一般的な前提があります。
買い手側を「親事業者」と呼ぶこと自体、その取引が固定化されていることを前提としているわけです。このような固定的取引関係は、イノベーションを阻害し、経済発展を鈍化させる原因になっていると私は考えています。
買いたたきを防止することで、競争原理が働いて取引自体も活発になるという理解でよいでしょうか?
その通りです。現行の下請法の買いたたき規制の他に、新たな行為類型を創設すべきという議論もありましたが、私は「どのような業種であれ、常に新規参入があり、健全な競争圧力が働くような取引の枠組みを構築すべきだ」と主張しました。
下請取引をこれ以上厳しく具体的に規制すると、かえって新たな企業が参入しにくくなり、イノベーションを起こしにくくなるおそれがあります。「イノベーションを促し新規参入を可能にするような、オープンな取引環境を作る必要がある」と議論したのです。
もちろん、同じ企業と取引を続けることには、安定的な取引を通じて信頼関係が構築され、Win-Winの関係を築きやすくなる側面もあります。しかし、技術や経済環境が急激に変化する中で、従来の取引関係を維持できなくなったり、購入していた製品やサービスが不要になったりする場合があります。そのような場合には、状況の変化に合わせて取引関係を見直し、柔軟に組み換える必要があります。
そのため、下請法の中で厳しく規制したり、交渉方法を指示したりすることは避けるべきであり、自由な戦略や健全な競争の余地を残すべきなのです。
具体的にはどのような場面を想定されていますか?
たとえば、固定価格契約のような形態は、原料単価や人件費の変動に弱い下請事業者には不利に見えますが、見方を変えれば、下請事業者側がプロセス・イノベーションを起こし、製造コストを下げれば利益が上がる余地も生まれます。
実際、親事業者との価格交渉において、下請事業者側が製造工程の内訳などを開示せず、工程を削減して収益を確保する戦略を取ることもあります。
今回の改正は親事業者に法令遵守の徹底を求めるものというより、親事業者・下請事業者双方にとってフェアな競争を促し、イノベーションのきっかけを作るものと理解してよいでしょうか。
私自身は研究会全体の趣旨をそのように理解しています。私たちは何かを上から一方的に決めつけるのではなく、取引関係は基本的に自由なものであるという認識を持ち、そこでイノベーションや新規参入が起こる可能性を高めたいと考えています。

下請法改正を経営者・法務担当はどのように受け止めるべきか
企業の経営者や法務担当者は、今回の議論や下請法改正の趣旨をどのように受け止めるべきでしょうか。
今回の下請法改正への対応は企業経営の問題、特に競争戦略の問題です。これから企業をどう舵取りするのか、どのように競争力をつけるのかという観点から、取引のあり方について企業のトップによく考えていただきたいです。
経営者の皆様は目線を上げて、これからの日本経済にとって何が必要かを考えていただきたいのです。
それは自由で公正な取引環境の構築であり、イノベーションに繋がるような環境です。新たな取引先を開拓する際にも、買いたたきや下請いじめといった慣行があれば、イノベーティブな下請事業者は現れなくなってしまいます。既存事業者に弊害があるだけでなく、新規参入も阻害することになります。
突き詰めて考えると、下請法という枠の中では解決できないサプライチェーン全体の問題につながります。優越的地位の濫用という観点、独占禁止法も含めた競争法全体の問題として捉える認識が必要です。
足下の取引関係に目を向けるだけでなく、日本経済全体、グローバル経済の中でサプライチェーン全体をより効率化し、よりイノベーティブにするという観点を経営者の皆様に認識していただきたいですね。
法務担当者としては、下請法がどのような趣旨で改正されたのか改めて理解しておく必要があるでしょう。
事業部の方に対して「何々をしてはいけない」という指示を伝えるだけでなく、「下請事業者に対して不当な取引をしていたら新しい取引先が入ってこないし、イノベーションも起きない。長期的には発注側も行き詰まってしまう」という認識を持って、社内でコミュニケーションを取っていただくことを願っています。
参考:「令和8年1月施行!改正下請法(中小受託法/取適法)の概要と企業に必要な対応」
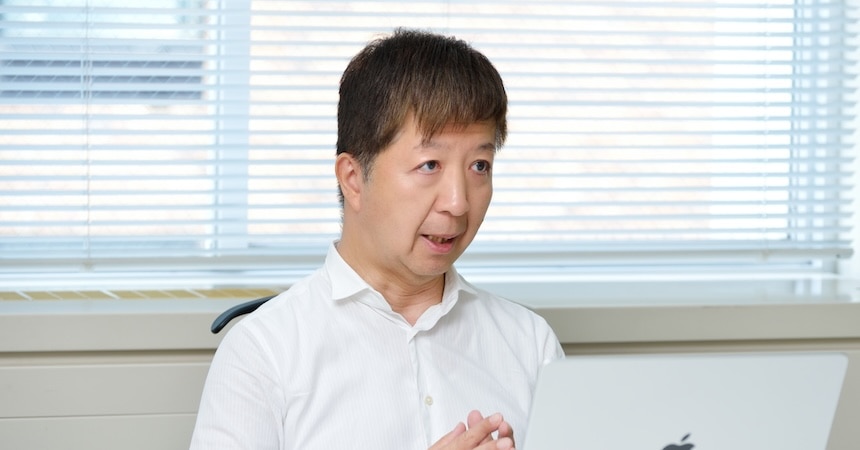
積み残しになった、物流と知的財産権の問題
今回の研究会で議論が持ち越された重要な課題や、今後の展望についてお聞かせいただけますでしょうか。
十分に議論が深められていない、重要な課題の1つが物流の問題です。
荷物を受け取る企業(着荷主)の都合で運送事業者を待たせたり、運転手に荷役作業を任せたりする現状は、私の想像を超える問題を抱えていました。
特に驚いたのは、着荷主が、最終的に荷物を運んでくる運送事業者を把握していない状況があることです。これは物流における多重下請けから生じる問題です。
さらに驚いたのは、着荷主と最終的な運送を担う事業者との間に契約がないため、取引の実態が存在しないこととなり、独占禁止法や下請法を適用できないということです。
「両社間に取引があることにしたらどうですか」と素人じみた発言をしてしまうくらい、物流業界の問題は私の知らない世界でした。
多重下請けには効率性や専門性といった経済合理性がある場合も考えられますが、まずはその実態をきちんと調査し、適切な法的措置を講じる必要があるという議論になりました。
物流問題は喫緊の課題であり、速やかな対応が必要となるでしょう。
もう1つの重要な積み残しの課題は知的財産権の問題です。中小企業の技術が大企業に不当に侵害されたり、ノウハウや技術が様々なルートを通じて盗まれたり、流出したりするケースが指摘されており、これはイノベーションへの取り組みを損なう深刻な問題です。
日本だけでなくグローバルに発生している問題ですが、これまで十分な取り組みがなされてこなかったため、今後の重点課題の1つになるでしょう。
最後に、今回の研究会全体を振り返っての所感をお聞かせください。
今回の研究会の画期的な点は、公正取引委員会と経済産業省(中小企業庁)が合同で研究会を開催したことです。
今後、各業種の監督官庁によるガイドライン作成や、実態調査につながる流れは非常に重要です。
これまで産業を保護する側面が強かった監督官庁が、自由で公正な競争を通じてイノベーションを促す方向に動く、大きな変化だと感じています。
今回の下請法改正を契機として、企業の経営層が、自社や産業の発展、さらには日本経済全体の発展を視野に入れ、サプライチェーン全体をより効率化し、イノベーティブにするという観点から、経済合理的に行動してほしいと願っています。
研究会で積み残しとなった問題を解決するためには、様々な分野からの学術的な意見も重要です。今後、より幅広い意見が問題解決に向けた議論に反映されることを期待しています。

岡室 博之教授
1962年大阪生まれ。1986年一橋大学経済学修士号、1992年ドイツ・ボン大学経済学博士号。1993年から32年間、一橋大学の専任講師・助教授・准教授・教授を歴任し、2025年3月に定年退職して4月から駒澤大学経済学部教授、一橋大学名誉教授・特任教授。専門分野は企業経済学・産業組織論、特に研究開発・イノベーションと創業の政策支援。主著に『研究開発支援の経済学』(有斐閣、2022年、西村淳一と共著、第63回エコノミスト賞受賞)など。
(写真:岩田 伸久、取材・編集:BUSINESS LAWYERS編集部)