“通商法戦国時代”の羅針盤『国際通商法実務の教科書』 伝統的な国際ルールや米中対立など、主要分野を網羅した実務家必携の一冊PR 著者・宮岡邦生弁護士に聞く通商法実務のこれまでとこれから
国際取引・海外進出
米中対立の深刻化、経済安全保障の重要性の高まり、各国による人権・環境の観点からの規制強化、そして第二次トランプ米政権の発足…。かつて自由貿易を前提としていた国際ビジネスの世界は、大きな転換点を迎えています。関税、輸出管理、投資管理、経済制裁など、国際通商に関するルールや制度への対応が企業経営に大きな影響を及ぼし、一歩間違えば刑事罰や巨額の制裁金、さらには外交問題にまで発展しかねない時代となりました。そのなかで企業法務に携わる実務家は、どのような視点で国際通商法と向き合っていけばよいのでしょうか。
10年ほど前まで「専門的でニッチな分野」だった国際通商法が、なぜ今、多くの企業にとって避けて通れない課題となったのか。『国際通商法実務の教科書』(日本加除出版)の著者である森・濱田松本法律事務所外国法共同事業の宮岡邦生弁護士に、激変する国際通商法の現在地と、企業法務担当者が押さえるべきポイントについて聞きました。
宮岡 邦生 弁護士
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー。2007年東京大学法科大学院修了、2008年弁護士登録(第二東京弁護士会)、2009年森・濱田松本法律事務所外国法共同事業入所。2013年米国コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)、2014年ニューヨーク州弁護士登録。同年から経済産業省 通商政策局 参事官補佐(~2016年)、2017年から世界貿易機関(WTO)上級委員会事務局 法務官(~2020年)を歴任。2020年に同所に復帰し、2022年から現職。
自由貿易から規制貿易へ、激変する国際通商法の現在地
本書を執筆した背景について、お聞かせください。
本書を執筆した最大の背景は、国際通商法(以下:「通商法」)実務の急拡大です。私自身、10年前に通商法の分野に携わり始めた頃は、日本で通商法を専門とする弁護士は数えるほどしかおらず、専門的かつニッチな分野という印象を持っていました。当時は自由貿易が全盛の時代であり、WTO協定やEPA・FTAといった国際的な枠組みに基づき、各国が協調して規制を緩和し、ビジネスを可能な限り円滑に進めることを目指す世界観が主流でした。弁護士の業務においても、輸出入の手続きや関税、TPPなどのEPA対応、あるいは、アンチダンピングといった例外的に許容される規制措置の取り扱いが主だったのです。
しかし、この状況が2017年の第一次トランプ米政権の発足を機に一変します。「米国第一主義」の下、戦略的競争相手と定めた中国からの輸入品に対する関税賦課に始まり、2021年に発足したバイデン政権下でも対中強硬政策は継続。こうした流れは日本を含む主要国にも波及し、各国で、経済・技術分野における覇権維持や経済安全保障の観点から、輸出管理、投資管理、経済制裁をはじめとする規制が強化されてきました。一言でいえば、「自由貿易×国際ルール重視」の世界から、「規制貿易×覇権主義」の世界への転換です。2025年1月に発足した第二次トランプ政権は、この傾向をさらに先鋭化させています。
そうした変化のなかで、企業法務の実務にはどのような影響が出ているのでしょうか。
企業が国際ビジネスを行ううえで、各種規制への対応が不可欠になってきています。対応を誤れば、単なる法律違反にとどまらず、外交・政治問題にもなりかねない。通商法対応は、まさに喫緊の経営課題となっているのです。
たとえば、最近相談を受けた事例として、問題なしと判断した海外企業に産業機械を輸出したところ、その製品が転売され、ロシアで販売されていたというケースがありました。2022年2月以降、日本政府はロシアによるウクライナ侵攻を受け、同国への広範な経済制裁措置を打ち出しています。この事案では、潜在的な制裁違反のリスクだけでなく、最悪の場合には輸出した製品が軍事転用され、戦場で人の殺傷に使われる可能性もありました。こうした規制への対応は、単なるコンプライアンスの問題を超えて、企業の信用失墜や多額の制裁金など、最終的には企業の存続を脅かすリスクをもたらします。

具体的にどのような分野での対応が求められているのでしょうか。
軍事転用可能品目や先端技術分野で事業を行っていれば輸出管理、国境を越えるM&Aを検討していれば投資管理、ロシアやイランといった高リスク国でビジネスを展開していれば経済制裁など、国際情勢の変化に伴い各国の規制対応が重要な課題になっています。また、よく見落とされがちなのが貿易実務や関税の分野です。これらは地味な印象を持たれがちですが、日々の業務でもあまり勉強する機会がないまま、「わかったつもり」になっていることが多いトピックです。特に、第二次トランプ米政権の発足も踏まえ、関税や原産地規則に関する基礎知識は、今後の国際通商環境への対応という意味でも重要性を増しています。
さらに、アンチダンピングなどの貿易救済分野も、最近は様相が変わってきています。これらは、例外的な条件の下で自国産業を保護するための貿易制限措置として古くから使われてきましたが、最近では、重要産業分野における覇権争いのツールとして、政治的・戦略的に使われる傾向も強まっています。WTO協定など「貿易自由化」を前提とする国際ルールが相対化・弱体化し、各国がそれぞれの思惑で独自の政策や規制を導入する。そうした「通商法戦国時代」ともいうべき変化を念頭に対応を進めていく必要があります。
重要なのは分野ごとの“オーバービュー” わかりやすく正確に主要トピックをカバー
本書ではどのような工夫をされているのでしょうか。
まずは通商法実務の全体像を示すという観点から、「実務で遭遇する主なトピックをこれ一冊でカバーする」ことを目標としました。具体的には、前半では貿易実務、輸出入通関・関税、EPA・FTA、アンチダンピングなど伝統的な通商実務を、後半では輸出管理、投資管理、経済制裁、人権・環境など、昨今のレギュレーションを中心に解説しました。
各章の記載で最も留意した点は、「わかりやすさ」と「正確性」の両立です。たとえば、輸出管理や経済制裁の分野は非常に専門性が高く、単に法律の条文を確認するだけでなく、政令、省令、告示に至るまで詳細に精査しなければ規制の内容を正確に把握することはできません。本気で解説しようとすれば、それだけで数冊にわたる解説書が必要になるほどの複雑さを伴います。
ただ、企業法務担当者にとって重要なのは、むしろ分野ごとのオーバービューです。「この規制があって、法律の建て付けや大きな構造はこうなっている」という全体像をつかんでもらう。そのうえで、必要に応じてさらに詳細な内容を深掘りするか、あるいは専門家に相談するかを判断してもらう形が有効だと考えています。
米中対立を例にしても、単に「両国が規制を掛け合っている」という一般的・抽象的な理解では、実務や経営上の適切な判断を行うことは困難です。それぞれの国でどのような法制度や条文が存在し、実務はどのように実運用されているのか。これらの具体的なファクトを理解したうえで判断することが、コンプライアンスの基本であり、欠かせない姿勢です。

本書の執筆過程で特に意識されたことはありますか。
執筆当初は、各章の分量が今よりもはるかに多く、50〜60ページに及ぶ章もありました。しかし、読者目線を意識して、簡潔でわかりやすくなるよう何度も推敲し、エッセンスを抽出する作業を重ねました。最終的には、各章30〜40ページほどに収まり、より読みやすいと同時に、実務で遭遇する重要ポイントの多くをカバーすることができたと考えています。
本書の具体的な活用方法についてアドバイスがあれば教えてください。
まずは、日々の業務で直面している課題に関連したトピックから読んでいただくのがおすすめです。1章あたり30分〜1時間程度で読めるので、通勤時間やスキマ時間を活用した学習にも適していると思います。
そのうえで、第1章「国際通商法の基本体系」に目を通すと、各章で扱ったテーマが有機的につながっていることがわかるはずです。この章は、歴史的背景を含め、通商法の全体像を体系的に理解できるよう構成しています。個別のテーマだけでなく、全体の流れを把握することで、より深い理解につながることを目指しています。
本書には興味深いコラムも多く収録されていますね。
はい。本書では、専門的な解説に加えて、一般の方も日常的に体験しているような場面から通商法の理解を深められるコラムを随所に設けています。これを入り口として、徐々に専門的な内容にも興味を広げてほしいと考えています。
たとえば、「輸出時の消費税等の免税」では、海外でショッピングする際におなじみの免税制度について、「なぜ免税が可能なのか」「どのような国際的な枠組みがあるのか」といった点を法的根拠も含めて解説しています。そのほか、「半導体分野における対中輸出管理の強化」「CFIUS審査における政治の影響」など、昨今ニュースで取り上げられることの多いホットなトピックについても、関連する法制度も踏まえつつ解説しています。
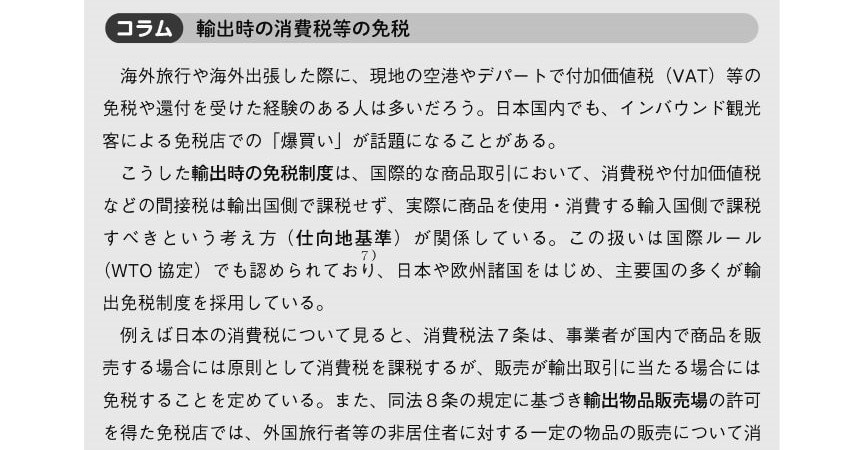
今後10年を見据えた実務対応のために
今後の通商法実務の展望について、どのように考えていますか。
「規制貿易×覇権主義」の流れは、今後10年から20年にわたり大きく変わることはないと見ています。米中対立をはじめとする世界経済の分断・対立がさらに進行し、各国がこれまでにも増して様々な規制措置を導入していくことが予想されます。人権や環境といった分野でも規制は拡大の一途をたどっており、実務上の相談も増加しています。
本書は、2024年時点における通商法実務の全体像をスナップショットとして捉えたものですが、もし10年後に同様の書籍を執筆するとなれば、その分量はおそらく現在の2倍、3倍になるでしょう。本書が、通商法実務の現在地を確認するとともに、今後10年間の国際的な動向を理解するための出発点として、多くの方々に役立つことを願っています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
今や、国際的なビジネスをまったく行わない企業は非常に少なくなっています。海外とモノ、サービス、カネ、さらにはデータ・情報のやり取りをすることは、すなわち通商法実務に関わることを意味します。各国が通商法を自国の競争力を維持・強化するための重要な手段と位置づけてしのぎを削るなかで、日本企業が国際競争を勝ち抜くためには、通商法リテラシーが不可欠です。
特に強調したいのは、なんとなく「わかったつもり」で済ませないことの重要性です。通商法実務は、一見シンプルに見える日常的な業務のなかにも、重要な法的論点が潜んでいることが少なくありません。そのため、基本に立ち返って継続的に理解を深めていく姿勢が大切です。
本書には記載しきれなかった内容も多くありますが、多くの方に「教科書」として活用いただき、通商法実務がさらに発展していくための発射台・スタートラインになれば大変光栄です。

- 国際通商法実務の教科書(WTO 貿易実務 輸出入通関・関税 EPA・FTA 貿易救済・アンチダンピング 輸出管理 投資管理 経済制裁 人権・環境・デジタル貿易)
- 著者:宮岡 邦生
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発刊年:2024年
- 詳細はこちら
