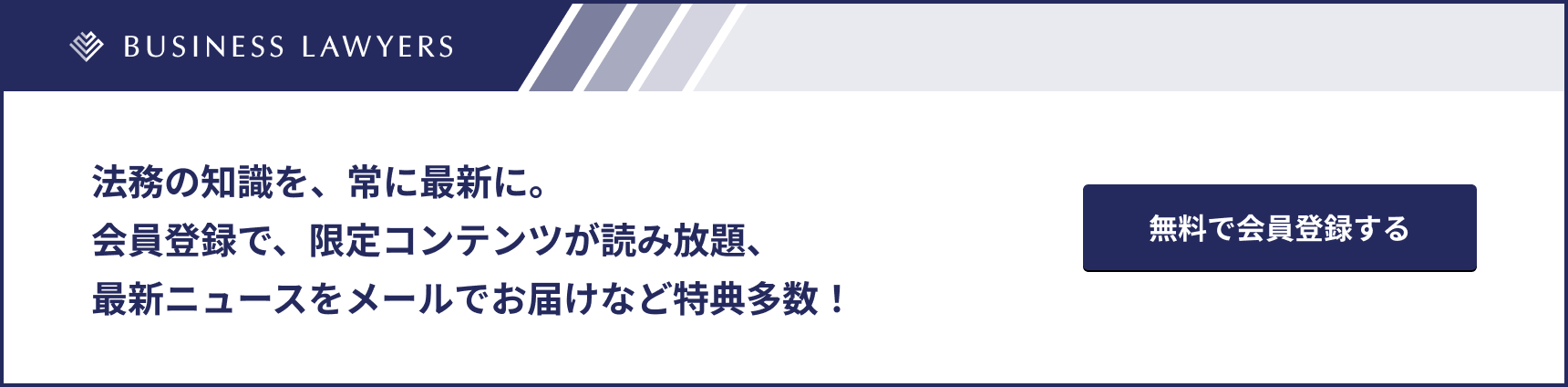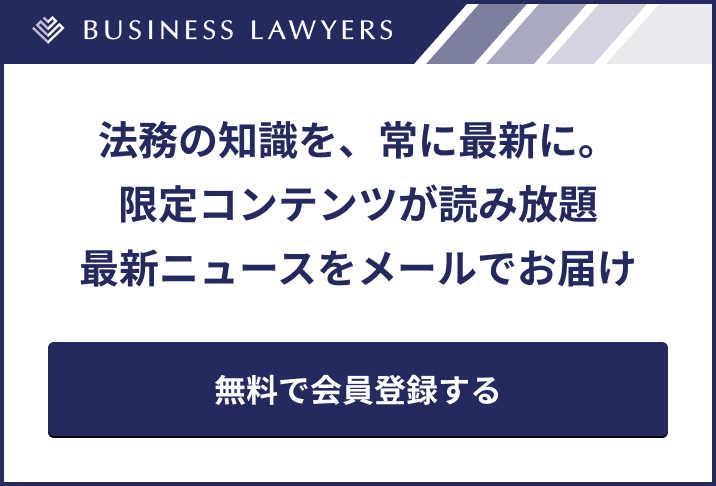大量保有報告制度の改正
コーポレート・M&A
目次
※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュースNo.223」の「特集」の内容を元に編集したものです。
2024年5月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号、以下「改正法」)が成立しました。本特集では、本改正のうち大量保有報告制度に関する改正内容について解説します。
大量保有報告制度の概要
大量保有報告制度は、株券等の大量保有に係る情報が「経営に対する影響力」や「市場における需給」の観点から重要な情報であることから、当該情報を投資者に迅速に提供することにより、市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者に対して一定の開示を求める制度であり、「一般報告制度」と「特例報告制度」の2種類があります。
なお、株券等の保有者は、その株券等保有割合の算出において、共同保有者の株券等保有割合も合算しなければならないとされ、共同保有者には「実質的共同保有者」と「みなし共同保有者」の2類型があります(金商法27条の23第5項、6項)。
| 一般報告制度 | 株券等の大量保有者(株券等保有割合が5%を超える者)となった場合には、その日から5営業日以内に大量保有報告書を提出し、また、その後、株券等保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合には、その日から5営業日以内に変更報告書を提出しなければならない。 |
|---|---|
| 特例報告制度 | 金融商品取引業者等については、事前に届け出た月2回の基準日において、大量保有報告書・変更報告書の提出義務を判断し、当該基準日から5営業日以内に大量保有報告書・変更報告書を提出すれば足りる。 |
共同保有者の規律に関する協働エンゲージメントの特例
改正の背景
機関投資家が企業と対話を行うにあたり、質的・量的なリソースを補い、コストを低減する観点から、協働エンゲージメント(※複数の投資家が協調して個別の投資先企業に対し特定のテーマについて対話を行うこと)の取組みを積極的に活用することが有用とされています。
もっとも、現行法上、株券等の保有者との間で、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者については、例外なく共同保有者に該当することとされ(金商法27条の23第5項)、合意には黙示の合意も含むものとされています。機関投資家が協働エンゲージメントを行う場合に、機関投資家が相互に共同保有者にならないかという点に関して、金融庁により以下のような解釈が示されてきましたが、どのような場合に当該合意に該当するかは個別事情を踏まえて判断せざるを得ず、機関投資家による協働エンゲージメントに委縮効果をもたらしているとの指摘がなされていました。
- 株主が、株主総会で議決権について話し合ったにとどまる場合は、共同保有者に該当しない(株券等の大量保有報告に関するQ&A問22)
- 法令上の権利の行使以外の株主としての一般的な行動についての合意にすぎない場合には、共同保有者に該当しない(金融庁「日本版スチュワードシップ・コードの策定を踏まえた法的論点に係る考え方の整理」11頁)
- 他の投資家との話合い等において、各々の議決権行使の予定を伝え合い、それがたまたま一致したにすぎないような状態では、共同保有者に該当しない(同11頁)
改正内容
上記の背景を踏まえ、改正法では共同保有者の範囲が明確化され、以下の3つの要件をすべて満たす場合には共同保有者から除外されることとなりました(改正法27条の23第5項柱書かっこ書、同項各号)。
- 当該保有者と他の保有者がいずれも金融商品取引業者等であること(※1)
- 共同して重要提案行為等を行うことを合意の目的としていないこと( ※2)(※3)
- 共同して株主としての議決権その他の権利を行使することの同意のうち、個別の権利行使ごとの合意として政令で定めるものに該当すること( ※4)(※5)
※1 特例の適用対象者は「金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および投資運用業者に限る)、銀行その他の府令で定める者」に限定されており、具体的には現行法上の特例報告制度の適用対象範囲を参考に今後政府令で定められることとされています。
※2 「重要提案行為等」の範囲については、今後政府令において検討される予定です。
※3 ここでいう合意の目的は、明示的に合意の対象に含まれる場面のみならず、共同して重要提案行為等を行うことが合意の前提となっている場面や、共同して重要提案行為等を行うために当該合意をしたという背景がある場面も含みます。なお、一方当事者が他方当事者から独立して単独で合意とは無関係に重要提案行為等を行う場合にただちに特例の適用が排除されるものではないと解されます。
※4 継続的に共同して株主としての議決権その他の権利を行使することの合意をしている場合については、当該合意によって保有者の経営に対する影響力が増幅するといえることから、特例の適用範囲から除外されています。「個別の権利行使ごとの合意」の内容については今後政府令において検討される予定です。
※5 共同して株券等の取得または処分を行うことを予定している場合は、市場の需給に関する情報としての重要性を有することになるため、特例の適用範囲から除外されています。
今後、改正法により、複数の機関投資家が特定の株主総会における特定の議案に関して議決権の共同行使を合意する形での協働エンゲージメントが促進されることが期待されます。
なお、6月7日に公表された「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」においても、協働エンゲージメントについて、単に協働するのみならず、テーマを絞った意味のある対話が行われることが重要との指摘を踏まえ、建設的な目的を持った対話に資する協働エンゲージメントを促進すべきことが示されています。今後、金融庁の「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度)においても協働エンゲージメントの促進に関する議論が予定されています。
(参考文献)野崎彰ほか「大量保有報告制度に係る金融商品取引法等の改正」(旬刊商事法務2346号10頁以下)、石綿学=越智晋平「大量保有報告制度の改正と実務への影響」(旬刊商事法務2368号37頁)
現金決済型エクイティ・デリバティブの適用対象化
改正の背景
現行法上は、現金決済型のエクイティ・デリバティブ取引(※株券等を原資産とし、当該株券等から生じる経済的な損益のみを一方当事者に帰属させるデリバティブ取引)のロングポジションを保有するのみでは、原則として大量保有報告制度の適用対象にならないと考えられています。
一方で、解釈の外延が不明確であり法的安定性に欠けることといった指摘や、そのことを奇貨として潜在的にデリバティブ取引を利用するケースが存在するといった指摘があり、金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告(以下「WG報告」)では、現金決済型のエクイティ・デリバティブ取引であっても、潜在的に経営に対する影響力を有しているものと評価できるものについては、大量保有報告制度の適用対象とすることが適当であるとの提言が示されていました。
改正内容
現行法では、株券等を所有する者に加え、①議決権行使について指図権限等を有する者(金商法27条の23第3項第1号)や②投資権限を有する者(同項2号)も「保有者」に該当するとされているところ、改正法では、それに加えて、以下の要件を満たすものが大量保有報告制度の適用対象となりました(改正法27条の23第3項3号)。
その詳細は今後政府令で検討予定であり、経済的な利益の獲得のみを目的とする場合が含まれないような範囲で設定することが考えられるとされています。改正法により、エクイティ・デリバティブ取引を利用して秘密裏に大量のポジションを形成した上で、一気にデリバティブを決済して突然大株主として出現することが現在よりは難しくなる可能性があると考えられます。
(参考文献)前掲野崎彰ほか12頁以下、前掲石綿学=越智晋平38頁以下
その他の改正等について
大量保有報告制度の実効性の確保
2008年の金商法改正により、大量保有報告書等の不提出および不実記載が課徴金制度の対象とされたものの、大量保有報告書等の提出遅延等が多く、大量保有報告制度の実効性が確保されていないという問題が指摘されており、WG報告では、その背景の一つに大量保有報告制度違反に対する摘発事例が少ないことを挙げており、今後は違反に対する金融庁の対応の強化が重要であることが示されました。
また、WG報告では、共同保有者の認定に係る立証の困難性の問題を解決するために、一定の外形的事実が存在する場合に共同保有者とみなす旨の規定の拡充や、公開買付届出書の提出後に大量保有報告制度の違反が発覚した場合には訂正命令等の是正措置を行うことができるような枠組みを整備すべきことが示されています。かかる制度的な取組みについては、今後政府令において検討される予定です。
重要提案行為等の範囲について
特例報告制度の利用の要件の一つとして、重要提案行為等を行うことを保有の目的としないことが必要とされています(金商法27条の26第1項)。重要提案行為等の範囲については一定の解釈の明確化が図られているものの、いまだ不明確または広範な規制であるとして、企業と投資家との実効的なエンゲージメントの促進のためには、更なる明確化または限定が必要との指摘がされていました。
WG報告では、重要提案行為等の範囲について、企業支配権等に直接関係する行為を目的とする場合については広くこれに該当する規律としつつ、企業支配権等に直接関係しない提案行為を目的とする場合には、その採否を発行会社の経営陣に委ねないような態様による提案行為を目的する場合に限りこれに該当する規律とすべきとの提言が示されており、その範囲については、今後政府令において検討される予定です。なお、上記2の改正法の「共同保有者」における「重要提案行為等」の要件は、特例報告制度の「重要提案行為等」の規定を引用する形で規定されています。
その他の改正について
改正法ではその他に、みなし共同保有者の範囲の再整理(みなし共同保者の基礎となる関係性から「親族関係」を削除、改正法27条の23第6項)や、取得請求権付株式等の換算方法の変更(改正法27条の23第4項)といった改正がされています。
経過措置について
大量保有報告制度に関する改正法は、公布日(2024年5月22日)から2年以内に施行されます(改正法附則1条3号)。その施行前に大量保有報告書および変更報告書の提出義務が生じた場合については、引き続き現行法が適用されます。
(参考文献)前掲野崎彰ほか12頁以下
三菱UFJ信託銀行
法人コンサルティング部 会社法務グループ
03-6214-7391(代表)