Legal Innovation Conference 〜取引先に潜むリスクをいかにコントロールするか?〜 開催レポートPR
法務部
目次
- 取引先のリスクコントロール ~リスクプロファイルの変化を踏まえて~
- 「いま」ならまだ間に合う! サプライチェーン対策強化の重要性とテクノロジーの活用
- BUSINESS LAWYERSから見た、実効性のあるガバナンス強化のための教育研修とは
- 取引先調査から取引先管理へ〜近時のトラブル事例の紹介、ビジネスと人権への対応を中心に〜
- 反社チェックによる取引リスク対策 ~反社排除の基礎と企業がするべき対策~
- 「クラウドサイン」は次のステージへ―法務業務DXを実現するハブ―
- グローバル商取引におけるリスクチェック最新動向 〜サプライチェーンの広がりと、あるべきグローバル・コンプライアンス体制〜
- カンファレンスの最後に懇親会を開催
- カンファレンス総括
取引先企業も含めたリスクを把握・管理しコントロールすることは、コンプライアンスを順守するうえですべての企業が無視できない喫緊の課題となっています。5月23日に開催されたイベント「Legal Innovation Conference 〜取引先に潜むリスクをいかにコントロールするか?〜」では、取引先のリスクコントロールやサプライチェーンの広がりに伴うグローバル・コンプライアンス体制の構築など、企業が直面するさまざまなリスクマネジメントについて、各分野の専門家や関連サービスの提供企業が講演を行いました。
取引先のリスクコントロール ~リスクプロファイルの変化を踏まえて~
事業のグローバル化やビジネスモデルの変化に伴い、企業が直面するリスクは複雑多岐にわたっています。パネルディスカッションでは、EY弁護士法人 ディレクター 前田絵理氏をモデレーターに、各社の事例を通じて重大リスクの認識やリスク管理体制のあり方について議論が交わされました。
まず、議題に上がったのは、各社が「重大リスク」として捉えている事柄についてです。
多様なビジネスをグローバルに展開する双日株式会社 常務執行役員 CCO 兼 CISO 兼 法務 内部統制統括担当本部長 守田達也氏は、「従来の国内外のトレーディングにおける信用リスクに加え、経済安全保障や地政学リスク、災害リスクなど、新たなリスクが顕在化している」と指摘。「法務や経理といった縦割り型の職能組織を超えた対応が求められる」と述べました。
製品の製造〜流通〜販売を自社で賄う株式会社ニトリホールディングス 上席執行役員 法務室 室長 青谷賢一郎氏は、「製品の品質や機能の正しい表示体制の構築が課題」と語ります。
通信をはじめとしたインフラや映像配信といったエンタメ業などを営むJCOM株式会社 管理本部 副本部長 兼 リスクマネジメント部長 松本行哲氏は、個人情報を扱うにあたって情報セキュリティリスクが重大であるとしたうえで、委託先管理の重要性を訴えました。
リスクの評価・管理手法についても意見が交わされました。守田氏は、「商社特有のグローバルで多岐にわたるビジネスモデルゆえに、リスクヒートマップの作成・更新が難しい」といいます。青谷氏は、「リスク・コンプライアンス委員会を通じてリスクの把握に努めている」と説明。松本氏は、「リスクマネジメントシステムで各部署が評価した結果を全社で取りまとめているが、客観性に課題がある」と述べました。
リスクマネジメント体制における法務人材の役割についても議論が及びました。守田氏は、「法務スタッフが自身の専門領域に限らず、より高い視点からリスクを捉えることが重要」と指摘。青谷氏は、「ルールが不明確ななかで、あるべき論から考えられることが法務の強み」と語ります。松本氏は、「事業部門から相談されやすい存在となり、リスク情報を集めるハブとしての機能を果たすべき」と述べました。
前田氏は「リスク管理体制をどう構築するかが企業における競争力の源泉になる。それを支える法務を含めたコーポレート人材の育成も重要」と総括しました。

「いま」ならまだ間に合う! サプライチェーン対策強化の重要性とテクノロジーの活用
トムソン・ロイター株式会社 プリセールス統括 マネージャー 森下馨氏は、サプライチェーン対策強化の重要性とテクノロジー活用について講演しました。
近年、貿易摩擦やサプライチェーンの混乱、それに伴う規制の変更など、企業はさまざまな課題に直面しています。これらのリスクを適切に管理しなければ、企業のレピュテーションリスクにつながります。特に人権問題は米国のウイグル人強制労働防止法をはじめグローバルで展開されており、ビジネスオペレーションへの落とし込みが重要です。
また、制裁国や懸念取引先の情報をリアルタイムでスクリーニングすることも必要不可欠です。手作業によるスクリーニングには限界があるため、森下氏は、トムソン・ロイターのプラットフォーム「ONESOURCE GLOBAL TRADE」の活用を推奨します。同社は、関税率表、輸出入規制、懸念取引先リストなど、貿易に関する情報を収集・更新しており、法務コンテンツも収録しています。森下氏は、生産性向上に向けたシステム活用を呼びかけました。

BUSINESS LAWYERSから見た、実効性のあるガバナンス強化のための教育研修とは
弁護士ドットコム株式会社 リーガルソリューション事業部 アカウントマネジメントグループ グループマネージャー 上村翔は、ガバナンス強化のための教育研修について紹介しました。
近年、人為的ミスによる情報漏えい事故が増加傾向にあります。これを防ぐためのガバナンス強化に向けては、コンプライアンス教育が重要となります。上村は、教育研修について「誰も置き去りにしないことが重要」と述べます。しかし、そうした教育研修コンテンツは、受講する側としては満足度が低く、実施部門にとっては受講者の興味を引きにくい一方で負担が大きいという課題があります。これらの課題を解決するために、BUSINESS LAWYERSでは『ドラマで身につくコンプライアンス』という動画コンテンツを提供しています。集合研修、LMS(学習管理システム)への搭載、Zoom研修など、さまざまな形式での活用が可能となっています。
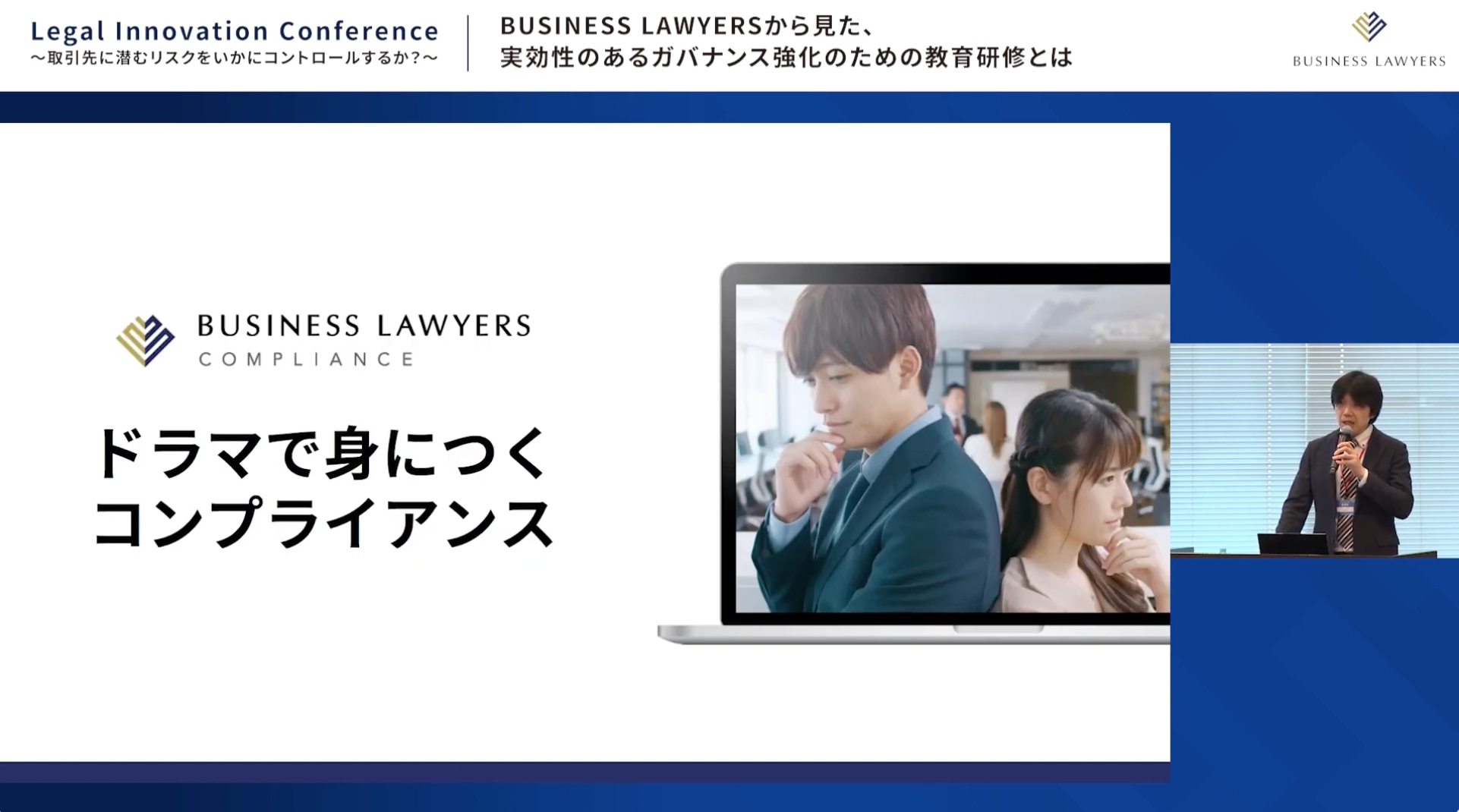
取引先調査から取引先管理へ〜近時のトラブル事例の紹介、ビジネスと人権への対応を中心に〜
ひふみ総合法律事務所パートナー 第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会幹事 弁護士 矢田悠氏は、取引先管理の基本として、反社チェックの頻度と範囲については自社の業態やリスクに応じて設定すること、チェック対象が増えるなかではツールの活用も重要だと指摘しました。
近年、暴力団員は減少する一方、準暴力団・半グレ、匿名・流動型犯罪グループの台頭による「グレー事案」が増えてきており対応が難化しています。これに伴い、担当者には高い感度が求められているといえます。矢田氏は、「取引開始後に契約を解消できるよう反社条項のアップデートを提案している」とも紹介します。
また、コンプライアンス意識の高まりや国際標準への適応から、ビジネスと人権への対応も求められるようになったと述べました。一方で、古典的な取引先トラブルも発生しており、循環取引への巻き込まれや名義借りなどへの対策も必要だと指摘しました。
ひふみ総合法律事務所 カウンセル 弁護士・ニューヨーク州弁護士 兼子良太氏は、ビジネスと人権が大きな話題となっている背景に、各国における法制化や、グローバルなサプライチェーンの構築などがあると説明します。
人権リスク対応の特殊性として兼子氏は、人権への負の影響を生じさせる行為が広く対象になる「非定型性」、海外を含む二次サプライヤーや下流の取引先も問題となる「間接性」、深刻なリスクから優先順位付けする「リスクベースアプローチ」という3つを挙げます。実務のアプローチとしては、自社事業の人権リスクを知ること、取引先を人権対応に取り組むパートナーと位置づけること、できることから小さく始めることなどを提案しました。
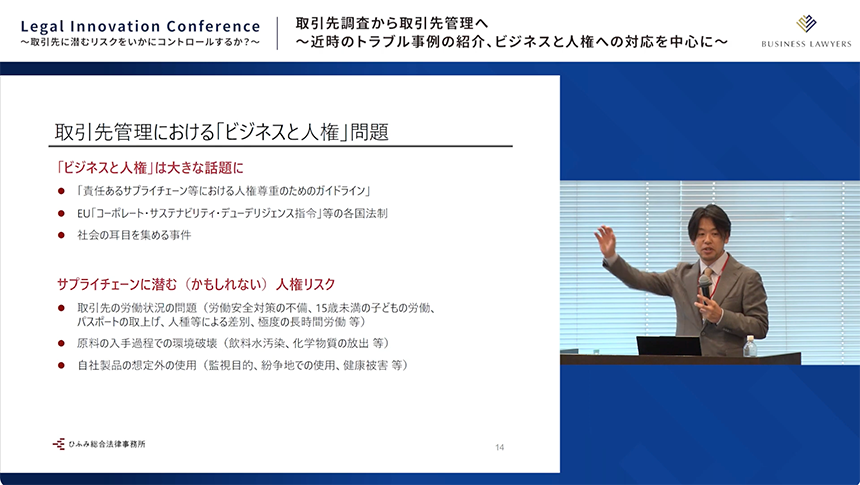
反社チェックによる取引リスク対策 ~反社排除の基礎と企業がするべき対策~
2011年に施行された暴排条例では、契約書への暴排条項の盛り込みや、取引先が暴力団関係者でないことの確認、暴力団関係者への利益供与の禁止が定められています。反社会勢力と関与した場合、企業存続の危機に陥る可能性があることから、ソーシャルワイヤー株式会社 リファレンス事業部長 杉山賢人氏は、反社チェックの重要性を指摘します。
杉山氏は、反社チェック運用体制構築のポイントとして、自社の商流に潜むリスクを把握し、関係会社も含めて漏れなくチェックを行うこと、取引リスクに応じてメリハリをつけることを挙げます。ソーシャルワイヤーでは、公知情報の検索をサポートするサービス「RISK EYES」を提供しており、同社自身も取引先、採用、株主に対して反社チェックを行っています。RISK EYESは、新聞やWeb情報だけでなく、制裁リストをもとにした海外企業のチェックも可能で、複合的な観点から反社チェックの効率化が図れます。杉山氏は、反社チェックが形骸化しないよう、RISK EYESなどのツールを活用した仕組み構築を推奨しました。

「クラウドサイン」は次のステージへ―法務業務DXを実現するハブ―
弁護士ドットコム株式会社のクラウドサイン事業本部 マーケティング部 チームマネージャー 稲葉誠人は、電子契約サービス「クラウドサイン」の新たな展開について紹介しました。
単なる契約締結・管理ツールから、法務業務DXを実現するハブへと進化しているクラウドサイン。以前より提供しているフォーム入力を掛け合わせて顧客・事業部門・法務部門の契約の流れをスムーズにする「クラウドサインSales Automation」に加え、締結した契約書の情報をもとに台帳を自動作成し、他のサービスとノーコードで連携できる「クラウドサインHub」といったソリューションの提供を新たにスタートしています。
稲葉氏は、「クラウドサインは100以上の外部サービスと連携しており、クラウドサインの機能だけでは賄えない部分は、これらのサービスと組み合わせながら課題解決方法を提案していく」と述べ、法務や商取引に関わるあらゆる業務の効率化を支援していく方針を示しました。

グローバル商取引におけるリスクチェック最新動向 〜サプライチェーンの広がりと、あるべきグローバル・コンプライアンス体制〜
東京国際法律事務所代表パートナー 弁護士 山田広毅氏は、グローバルサプライチェーンにおけるリスクマネジメントの重要性について指摘します。グローバルサプライチェーンとは、原材料の調達から販売・消費まで幅広い範囲を包含しており、上流と下流の両方が対象となります。
グローバルでは、地政学リスク、米中貿易摩擦、対露経済制裁など、企業活動に影響を与えるさまざまな問題が存在するなか、山田氏は「グローバルサプライチェーンのトレンドとしては、この先ブロック化がキーワードになる」と地産地消を指向するモデルになっていくとの見解を示します。また、こうした状況下では、グローバルサプライチェーンの良さを確保しつつも、地域内のサプライチェーンも両立し、サプライチェーンに冗長性を持たせることが求められるようになるともいいます。
グローバルサプライチェーンを考えるうえでは、ビジネスと人権が大きなトピックとなります。山田氏は、新興国での人権リスクや、日本国内での外国人技能実習生の問題など、具体的な事例を取り上げました。国内衣料品メーカーの事例では、自社のサプライチェーンを踏まえて、自社のみならず生産パートナー向けの行動規範(CoC)を制定。人権教育や人権デューデリジェンスを実施するほか、第三者機関による監査や現地訪問、工場従業員向けの通報ホットラインの設置、主要製造工場と主要素材工場のリスト公開など、具体的な対策を講じていることが紹介されました。
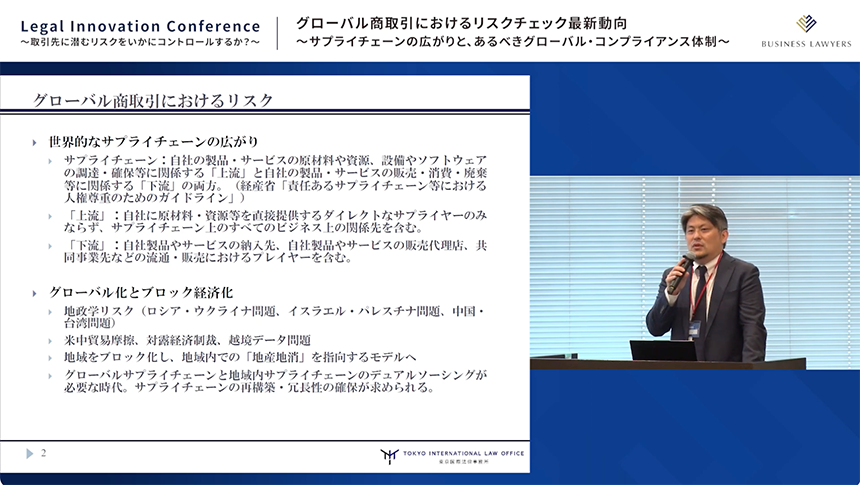
カンファレンスの最後に懇親会を開催
カンファレンス会場では、プログラムの最後に懇親会を開催しました。懇親会には各プログラムの登壇者も参加しました。参加者の方々から講師陣へ、講演内容についての質問や自社の課題についての質問が飛び交いました。ブースエリアには、株式会社MJリサーチをはじめ、各社が出展しました。
カンファレンス総括
講演内容は多岐にわたりましたが、いずれも複雑化・多様化するリスクに対し、従来の手法にとらわれない柔軟な対応の必要性を示唆するものでした。本稿で紹介した具体的な取り組み事例やソリューションを参考に、自社の状況に合ったリスクマネジメント体制を構築していくことが、今後のビジネスの発展に不可欠といえるでしょう。
