重要なのは消費者視点 – 『広告法律相談125問』著者に聞く、ステマ規制等の最新動向と法務の心構えPR
競争法・独占禁止法 更新
目次
知的財産権、著作者人格権、景表法をはじめとする法令に加え、消費者庁も様々なガイドラインを公表していることから、錯綜しがちな広告法務。インターネット広告市場が成長し、広告媒体が爆発的に増えるなか、広告に関する法律実務はさらに複雑化しています。
そのような状況において、『第2版 広告法律相談125問(以下、『基礎編』)』『実践編 広告法律相談125問(以下、『実践編』)』(いずれも日本加除出版)では、多数の規制を整理し、最新事例を踏まえて幅広い法律問題をコンパクトに解説することを試みています。今回は、著者の桃尾・松尾・難波法律事務所 松尾剛行弁護士に、広告業界の時流や実務における書籍の活用方法について伺いました。
松尾剛行 弁護士
桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士(第一東京弁護士会)、NY州弁護士、法学博士、慶應義塾大学特任准教授、中央大学、学習院大学、九州大学非常勤講師、一橋大学客員研究員(2024年1月現在、就任順)。
広告法を含む情報法全般に詳しい。『キャリアデザインのための企業法務入門』(有斐閣、2022年)、『ChatGPTと法律実務』(弘文堂、2023年)、『クラウド情報管理の法律実務』(弘文堂、第2版、2023年)、『キャリアプランニングのための企業法務弁護士入門』(有斐閣、2023年)他。
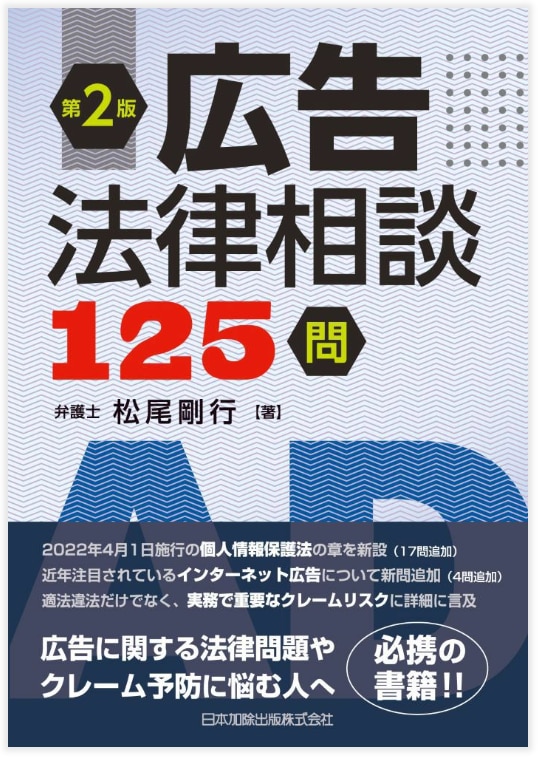
- 第2版 広告法律相談125問
- 著 者:松尾剛行
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2022年7月
- 詳細はこちら
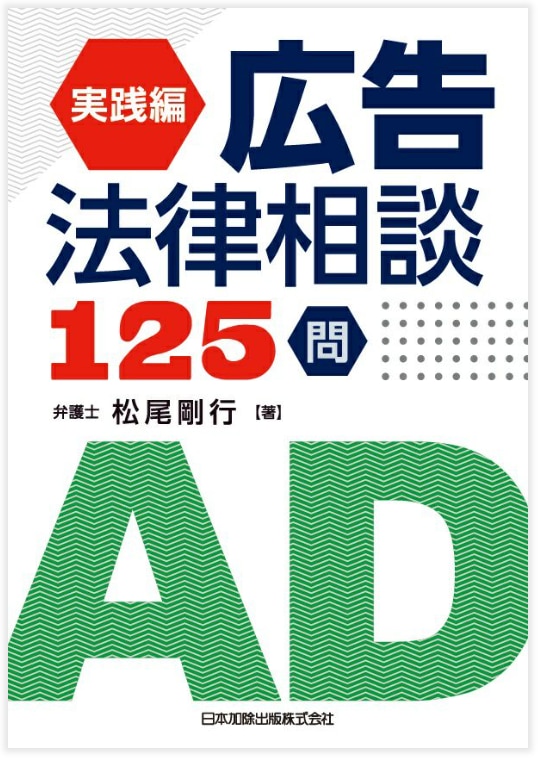
- 実践編 広告法律相談125問
- 著 者:松尾剛行
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2023年10月
- 詳細はこちら
インフルエンサーマーケティングの盛り上がりにより注目されるステマ規制と景表法改正
広告業界における法律に関して留意すべき問題は何ですか?
広告表示に関する法令は、景表法をはじめ、著作者人格権、知的財産権に大きく分けられます。最近では、やはりいわゆるステルスマーケティング規制(ステマ規制)が重要ですね。また、2023年に景表法も改正されており、関心が高まっています。
ステマ規制の施行前は、インフルエンサーマーケティングが禁止されるのではないかとか、普通の広告にも「PR」と入れなければならないのではないか等の誤解から、どうすればいいのかとご相談がありましたが、現在は正しい理解に基づく具体的な案件への当てはめのご相談が主流になりました。
ステマ規制対応のポイントは何ですか?
SNS利用者やインフルエンサーの個人的な感想なのか、広告なのかで消費者の受ける印象は大きく変わります。ステマは、消費者としてそれが「広告だ」という心の準備ができなくなるため、問題視されています。ステマ規制では基本的に「どのような場合に」「何をしなければならないのか」の2点が重要となります。
例えば、事業者(広告主)が、第三者(SNS利用者やインフルエンサー)の表示内容に関与している場合は、広告、PR等と明示すべきとされています。従って、SNS利用者の自主的な意思による表示だと整理できれば広告等の明示は不要となりますし、そこが怪しいとなると広告である旨を明瞭に表示しなければなりません。
景表法改正の実務への影響はいかがですか?
施行がまだ先であるため不透明なところはありますが、厳罰化ないしは規制強化と理解していただいて良いと思います。直罰が入り、例えばインフルエンサー等も共犯として景表法違反で刑事罰を科される恐れが出てきました。これまでより一層、広告審査・適切な広告表現か等の事前確認が重要となるでしょう。
画像やテキストなどのコンテンツを自動で作成できる生成AIに注目が集まっています。生成AIの広告業界への影響はどうでしょうか。
この問題は『ChatGPTと法律実務』や『実践編』でも触れましたが、生成AIはアイデアを大量に出すので、様々な種類のコピー等を「お試し」で表示させて、反響を踏まえて最善のものを選び出す等、広告の高度化に役立つ可能性はあります。ただ、例えば、100種類を試すなら、広告審査の対象が単純換算で100倍になる等、コンプライアンス対応をどうするかは留意が必要ですね。

「よく見かけるけど実はアウト」な事例に遭遇したら?
「よく見かけるけど実はアウト」な事例があれば教えてください。
問題ある「打ち消し表示」等はよく見かけますね。広告の適法性を判断する上では、全体として消費者に対してどのような印象を与えたのかが重要です。
例えば、体験談の形式で具体的に強い効果を強調し、小さな文字で「個人の感想だ」「効果効能を示すものではない」等という打ち消し表示をするという場合、その体験談を踏まえた広告全体が、消費者にとって効果が客観的に実証されていると認識できるようなものであれば、あまり意味のない打ち消し表示と言わざるを得ません。
そんな事例に法務担当として遭遇したらどうしたらよいでしょうか?
基本的には、「危ない橋もみんなで渡れば怖くない」のような、「他社もやってるから問題ない」という考えは危ないですね。問題がないから処分されていないのではなく、広告媒体が爆発的に増えるなか、消費者庁のリソースが足りないことから、全ての問題のある広告に対して行政処分等ができていない状況であることを依頼部門に説明していただきたいです。必要なら「弁護士もNGと言っている」と、外部弁護士もうまく使ってもらえればと思います。
実態をよく確認し、消費者の視点に立って考える
このインタビューを読まれる方は、広告法務のベテランだけでなく、新人や若手、たまにしか広告関係の案件が来ないといった方もいます。広告案件を対応するにあたり、法務担当者が「まず意識するべき」ことはどんなことでしょうか。
実態をよく確認し、消費者の視点に立ってどう見えるかを考える、ということですね。蚊取り線香の例をよく出しますが、「1個で6畳間までの広さなら蚊を寄せ付けない」と訴求していいかは、本当に6畳間まで蚊が来ないものか、3畳なら来ないが6畳なら蚊が来てしまうものかという実態次第です。
そして広告全体から消費者がどのような印象を受けるかを、消費者の目線から把握し、その実態と整合するかを確認するということになります。また、単に実態と整合するというだけではなく、消費者庁から根拠を出すように言われたらいつでも出せるよう客観的根拠の準備が必要です(景表法7条2項参照)。
なかなか大変そうですが、実務ではどのように対応すればいいですか?
一人でやれることには限界があるので、組織で対応できるよう、組織としての広告審査体制を確立することです。景表法上でも「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置」(26条)として求められています。
特に、広告の多いBtoC企業は、コストを掛けて広告審査体制を構築するという方向性が見られます。例えば、広告審査を専門的に担うメンバーやチームを法務部門に設け、知見を蓄えていくというやり方があります。あるいは、法務部員数が限られている場合、広告を扱うビジネス部門がメインで審査をできるように研修等を行うことが考えられます。
グレーの“濃さ”がわかれば対応方針がわかる
その他、実務上留意すべきことはありますか?
他にない良い(訴求効果が高い)広告には注意が必要であり、リスクが高いため他社がやっていない訴求かもしれません。また、どこかで見たことがあるような広告は著作権侵害の可能性があります。著作権侵害に至らなくても、パクリ・トレースの可能性が考えられるため、クレームリスク等に留意が必要です。
グレーな事例に遭遇した際のリスク判断のポイントがあれば教えてください。
法務担当者が実務で質問される場合というのは、やはり依頼部門としてグレーではないか、と思って依頼しているということが多いです。そのため、質問される案件に占めるグレーのケースの割合が多いことはある意味で当然のことですので、あまり心配する必要はありません。基本的には、景表法やガイドライン等が判断のベースになりますが、多数の処分事例が公表されているので、「目の前の事案に近い処分事例はないか」という観点でリサーチをし、リスクを検討すると良いでしょう。これによってグレーの“濃さ”がわかるようになります。
そのうえで、「少し表現を変えてもう少し白いほうに寄せてはどうですか」といったアドバイスができると、信頼される法務に近づけるのではないでしょうか。

一人で広告法務を担当する苦労を聞いて本書を執筆
『基礎編』執筆の経緯を教えてください。
いろいろな大学で教鞭をとらせていただいているなかで、ロースクール生だった教え子が広告会社の一人法務として就職し、大変だという相談がありました。そこで、具体的相談事案に照らし、ゼロから広告法務の基礎を教えてあげたのですが、その方から、「今後広告法務をやる人が自分のような苦労をしないで済むよう、広告法務の基礎をまとめてほしい」と言われたことをきっかけに執筆しました。
初版発行の2019年から第2版が刊行された2022年の間にどのような変化がありましたか。
広告媒体がかなりオンラインにシフトした印象です。結果として、オンライン広告に関する法律相談も増えています。なかでも、やはりインフルエンサーマーケティングへの問題意識が高まっています。そこで第2版では、オンライン広告についての新問を追加しました。
また、2022年4月1日に改正個人情報保護法が施行されたことを受けて、第2版では新たに個人情報に関する章を追加しています。
『実践編』はどうですか。
基礎編は読者の方にご好評いただき、基礎編の初版が出た2019年当時に新人若手法務としてお読みくださった複数の方から、「中堅として実務の役に立つ本が欲しい」という声をいただきました。
また、とある依頼者の方から、十分に改変する前提であれば具体的な相談を元にQ&Aを公表しても良いと言っていただき、より実務に即した内容とするよう努めました。さらにこの1年の広告法令改正が多く、それを反映しました。
それぞれ、どのような方に、どういった場面で、活用してもらいたいですか?
まずは基礎編で広告法務に必要な基礎知識を概観し、その上で実践編で実務対応に役立てていただきたいです。書籍では広告法務担当者の方に書いてもらったコラムを多数掲載しているので、コラムを読むだけでも参考になります。
また、広告に関する留意点について社内研修をする際に、基礎編の内容を参考にしたという声もいただいています。
「とっつきにくい」広告法務を事例ごとにコンパクトに整理
反響はどうですか?
多くの読者の方から声をかけていただきました。オンライン広告の普及により、広告会社だけではなく、一般の企業も広告法務の仕事が増えましたから、幅広いニーズがあるようです。
BUSINESS LAWYERSの読者に向けて、一言メッセージをお願いいたします。
広告関係は色々と法令やガイドライン等が錯綜しており、一見「とっつきにくい」部分があります。このような錯綜する状況に対して、できるだけコンパクトな整理を試みた拙著が皆様の広告法務実務に役立てば幸いです。
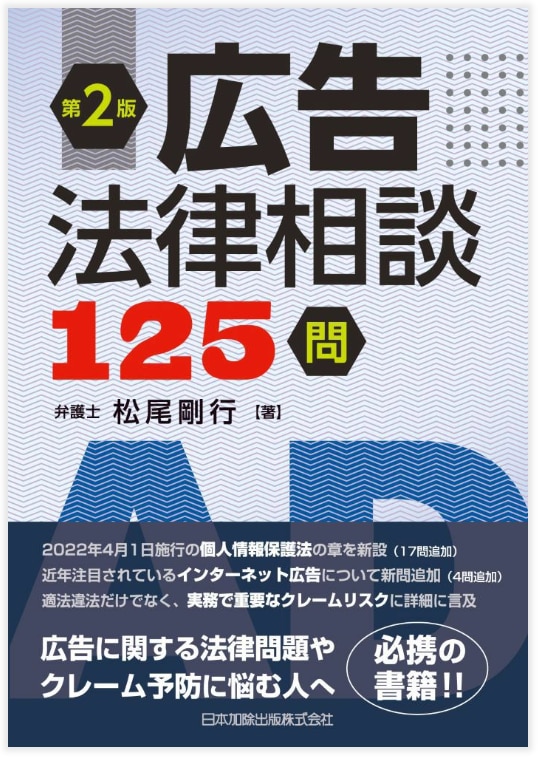
- 第2版 広告法律相談125問
- 著 者:松尾剛行
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2022年7月
- 詳細はこちら
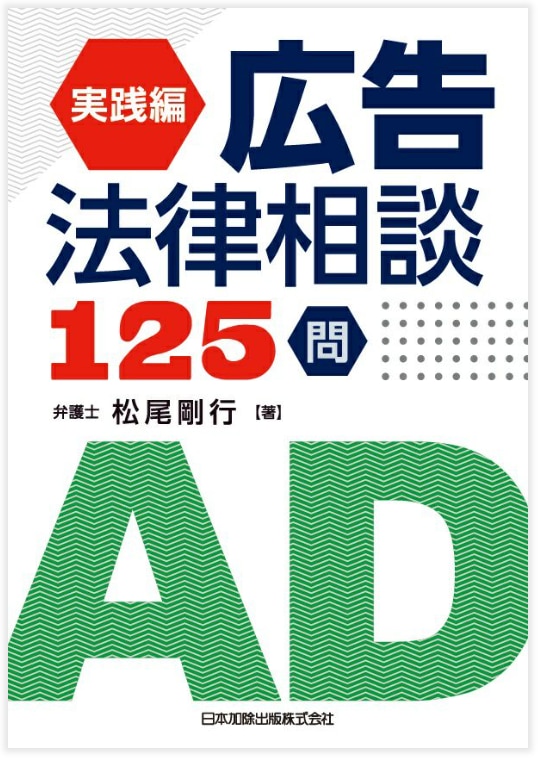
- 実践編 広告法律相談125問
- 著 者:松尾剛行
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2023年10月
- 詳細はこちら
