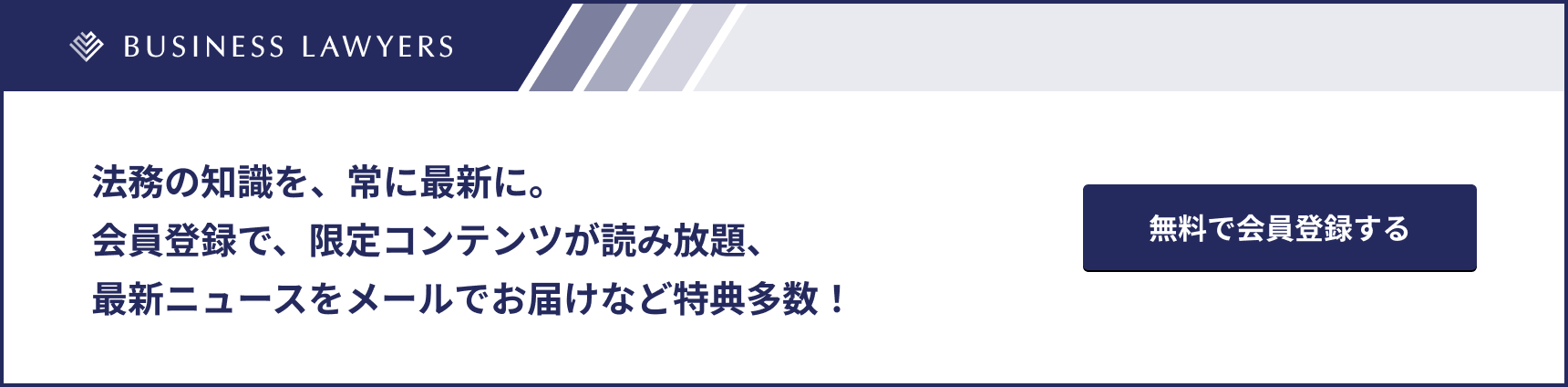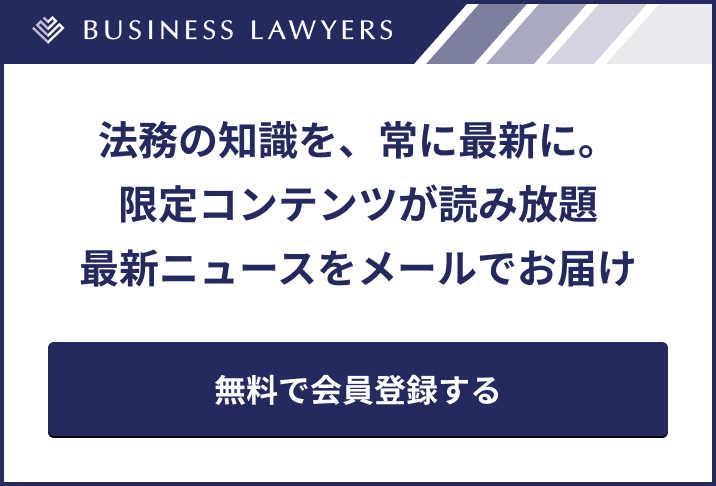法令の種類と違い、および読み方や解釈の基礎
法務部
目次
はじめに
人は交わした契約に縛られます。自らの意思でその契約を結び、それに従うことを決めたからです。同じように、国民は法律に、住民は条例に従わなければなりません。自分が決めたことではありませんが、自分に代わって自分たちの代表(議会)が決めたことだからです。法律や条例が自分たちを縛る範囲は、そうした法令に照らして決められます。
契約の場合、不明な部分があれば民法の規定の助けを借りるか、当事者間で確認することになるでしょう。しかし、法令の規定の場合には、議会が定めた法令の趣旨や目的に照らして判断するしかありません。この作業のことを解釈といいます。法令同士の関係や解釈についての基本的なスキルを身に付ければ、断然、法令を味方につけることができます。
法令の種類と関係事項
国の法令
国民の代表である国会が定める法令は法律だけです。ですから、国民の権利を制限したり義務を課すようなことは法律を根拠にしなければできません。政令や省令は、法律のより細かい内容や手続が定められているのが普通です。政令と省令では、政令の方が上位の法令です。より重要度が高いことが定められています。なお、内閣府の所管について省令に相当する法令は内閣府令となります。
| 名称 | 制定権者 | 具体例 |
|---|---|---|
| 法律 | 国会 | ◯◯法 |
| 政令 | 内閣 | ◯◯法施行令 |
| 省令 | 各大臣 | ◯◯法施行規則 |
自治体の法令
自治体(地方公共団体)の法令には、条例や規則があります。規則にも、首長(知事・市町村長)が定める規則もあれば、教育委員会や公安委員会などの委員会が定める規則もあります。後者の規則を委員会規則といいます。自治体の法令をグレード別に分けると、条例と首長が定めた規則が最上級のゴールドランク、委員会規則がその次のシルバーランクとなります。ゴールドランクの法令とシルバーランクの法令がぶつかる場合には、当然、ゴールドランクの法令が優先します。
| 議会 | ⇒条例 | ゴールドランク |
| 首長 | ⇒規則 | |
| 教育委員会・公安委員会など | ⇒委員会規則 | シルバーランク |
ともにゴールドランクの条例と規則がどう整理されているか気になったかもしれません。地方自治法などには、条例で定めるべき事項や規則で定めるべき事項が決まっています。これを専管事項といいます。専管事項以外は条例で定めてもいいし、規則で定めてもいいのです。この「ゆるさ」こそ、自治体のフレキシビリティや独自性につながるのです。
ただ、自治体には政令や省令のように条例の内容をさらに細かく定める法令が特に定められていません。そのため、この場合にも首長の規則が使われます。その場合には条例の下位法令であることを示すため「〇〇条例施行規則」という題名(名前)が付けられます。
国と自治体の法令との関係
憲法94条には「法律の範囲内で条例を制定することができる」とあります。ただ、法律に関連した規定がある場合には条例を制定することができないと解釈すべきではありません。条例が制定可能かどうかは、条例を定める必要性や法律の目的・趣旨を踏まえて、判断されます。関連する判例として徳島市公安条例事件(最高裁判所大法廷 昭和50年9月10日判決・裁判所ウェブサイト)があります。
この判例では、国に関連する法令がなく、ないことがその分野の活動を自由にしておく趣旨ではない場合には条例制定が可能としています。また、たとえ国の法令に関連する規制があっても、条例の規制の目的とは異なる場合などでは条例の制定は可能としています。
法令関係事項
(1)通達・訓令
通達、訓令ともに、上級行政機関が下級行政機関に出す命令や指示のことです。特に、法令制定時や改正時にその法令の解釈・運用について出されたものは、「行政の手の内を知る」うえで貴重な資料となります。通達と訓令の区別は一様ではありませんが、一般的な文章で示されたものを通達と、法令のような条文形式で示されたものを訓令と呼ぶことが多いです。
(2)要綱
行政内部のマニュアルを要綱といいます。たとえば、補助金を実施するために必要なマニュアルなら「◯◯補助金実施要綱」などの題名の文書が作られます。要綱は国民や住民に直接、向けられたものではなく、あくまでも行政組織内の利用文書です。国も自治体も要綱を利用していますが、どちらかといえば自治体での利用が幅広いです。行政組織は重要な要綱を訓令として出すことがあります。
(3)ガイドライン
法律や条例に、国や自治体が「指針を策定する」とか「指導及び助言その他の措置を講ずる」などの規定がある場合、こうした規定を受けて定められるのがガイドラインです。たとえば、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の冒頭では、その目的を次のように説明しています。
個人情報保護委員会ウェブサイト
世の中には色々なガイドラインがありますが、行政機関が定めるものは、上記のような法令が求める措置などを具体的に分かりすく示したものが多いようです。
(4)パブリックコメント
法律や重要な要綱などの原案を国民に示して、意見を求める手続を意見公募手続といいます。通常、パブリックコメント手続と言われることが多く、パブコメと略されることもあります。法律が私たちの代表である国会によって定められたとしても、その内容が政省令で骨抜きになってしまったら意味がありません。そこで、議会の関与しない政省令などの案、重要な要綱案について、国民の意見を聴く手続が行政手続法に定められています。これがパブコメなのです。自治体でも規則や重要な要綱などについて独自にパブコメを実施しています。自治体でのパブコメの対象や根拠はそれぞれの自治体によって微妙に異なります。
法令の構造
一部改正法令を除いて、法令の構造はほぼ同じです。まず、大きく本則と附則に分けることができます。本則にはこれからもずっと必要となる規定が並びます。附則は、施行期日に関する規定のほか、新しい制度へうまくバトンタッチするために必要な規定が並びます。ここでは本則に焦点を当てて、その構造をお話しすることにします。
本則は順番に次のような4つのパーツに分けることができます。こうした構造を理解できると、必要な規定をすばやく見つけることができるようになります。
| 本則 | 総則 | 目的規定、定義規定など全体に共通して関係する規定 |
| 実体的規定 | 中心的な規定(規制であれば規制手段など) | |
| 雑則 | 全体に関係する規定のうち雑多な規定や、実体的規定を補う規定 | |
| 罰則 | 罰則がない法令ももちろんある | |
| 附則 | 施行期日のほか、新しい制度へうまくバトンタッチするために必要な規定 | |
法令の解釈基礎
解釈の必要性と解釈権者
法令は誰もが適用される可能性のある定めですから、抽象的にならざるを得ないという事情があります。また、制定時だけでなく、ある程度、新たな現象や時代に対応するものでなければなりません。ここに解釈の必要性が生じます。ただ、解釈の幅が大きすぎて「それは無理かなぁ……」ということになると、これは解釈の限界ということになります。改正をしてその対象を取り込むなどして、決着させるしかありません。
法令を解釈する権利を持っているのは裁判所だけです。国や自治体が法令の解釈権を持っていると考えるのは誤りです。国や自治体の解釈も一般の人と同様に権限のない解釈ということになります。
ただ、国や自治体は法令を運用しているわけですから、運用にあたって解釈をせざるを得ません。こうした解釈を行政解釈といいます。行政解釈が法的なトラブルに結びつけば、裁判所はその解釈が正しいかどうか判定してくれます。そしてその判例の内容は決定的な解釈ということになります。
しかし、訴訟に関係しないような法令の条項については、裁判所による解釈はなされません。ですから、結果的に行政解釈が重要視されることになります。まずは判例による解釈、そして、そうしたものがない場合には、行政解釈を横目に見ながら、それぞれの条文の解釈を考えることになります。
条文の解釈の技術
解釈には、文字通り条文を解釈する文理解釈と、文字通りでなく意味を補うなどして解釈する論理解釈があります。文字通り解釈して問題がないなら解釈で悩むことはないのですから、実際に問題となるのは論理解釈の場合でしょう。
以下の表は「もし駅に『電車の窓から手を出してはいけない』と貼り紙があったら……」を例にとって、論理解釈の種類をあげています。ただ、どの解釈を取るかはその張り紙がされた目的との関係で判断されます。たとえば、窓の開け閉めの際に指先を挟む事故が多発し、それを避けるための張り紙だとしたら、その本当の意味は「電車の窓から手の先を出してはいけない」ということになります。このように法令の目的との関係で、解釈は行われ、適切な解釈を行うことが求められるのです。ただ、それは慣れの部分もあります。まずは、コンメンタール(逐条解説)などを見ながら、どの解釈がとられているか確認しましょう。さらには、法令の目的・趣旨との関係でどの解釈をとるべきか自分の頭で考えてみましょう。そうした地道な作業が解釈力アップにつながります。
もし駅に「電車の窓から手を出してはいけない」と貼り紙があったら……
| 文理解釈 | 「電車の窓から手を出してはいけない」と文字どおり捉える | |
| 論理解釈 | 拡張(拡大)解釈 | 「電車の窓から体の一部を出してはいけない」と広めに解釈する |
| 縮小解釈 | 「電車の窓から手の先を出してはいけない」と狭めて解釈する | |
| 変更解釈 | たとえば、駅に「汽車の窓から手を出してはいけない」との古い貼り紙が残っている場合なら「汽車」を「電車」に変更して解釈する | |
| 反対解釈 | 「『手を出してはいけない』とあるのだから、足は出していいのだろう」と解釈する | |
| 類推解釈 | 「『手を出してはいけない』とあっても、足も出してはいけないのだろう」と解釈する | |
| もちろん(当然)解釈 | 「『手を出してはいけない』とあるのだから、お尻を出すのはもってのほかだろう」と解釈する | |
※この場合には、「反対解釈」はとれません。
法令間の解釈の技術
古い法令を眺めてみると「よくもこんなアバウトな規定が許されたなぁ」と驚くことがあります。そんな時代とは異なり、現在は立法技術がかなり精緻化しています。そのため改正すべきところが改正されていないという改正漏れはほとんどありません。しかし、稀に2つの法令の規定が矛盾抵触する場合があります。また、法令の前提となる行政庁の権限が重複して与えられている場合もこれまた稀にあります。こうしたときには、次の解釈の4つのルールに照らして解釈することで解決することができます。
| 法令の所管事項の原理 | 法令は種類ごとに受け持ち分野というべきもの(所管事項)があり、その範囲を超えて定めることはできないとする原則 |
| 形式的効力の原理 | 法令においてはヒエラルキー(階層性)が存在し、上位の法令と下位の法令が矛盾抵触する場合には上位の法令が優先するという原則 |
| 後法優越の原理 | 後から制定された法令と前に制定された法令とが矛盾抵触する場合には後から制定された法令が優先するとする原則 |
| 特別法優先の原理 | 同じ事柄について一般法と特別法で規定されている場合には、特別法の規定が優先されるとする原則 |
吉田利宏『新法令解釈・作成の常識』(日本評論社、2017年)54頁
おわりに
知識はだんだんと失われます。それは法令に関する知識も同じです。ただ、知識を通じて得られた法令を理解するセンスは一生ものです。特に法令の解釈は様々な知識の総力戦で行われるといっていいでしょう。だからこそ、センスが鍛えられ、養われるのです。確実な法令用語の知識を基にして、法令の目的・趣旨や法令間の関係まで目配りした解釈がしっかりとできること、それがプロに求められることなのです。培われたセンスは、法務担当者としての仕事を生涯にわたって支えてくれることでしょう。
参考書籍
『新法令解釈・作成の常識』
著者:吉田利宏
定価:1,650円(税込)
出版社:日本評論社
発売年月:2017年