全企業に対応迫る 改正育児・介護休業法の実務ポイントを弁護士が解説
人事労務
目次
育児・介護休業制度の個別の周知・意向確認の措置の義務化や、いわゆる「産後パパ育休」など、「男性育休」の促進を目的に掲げる改正育児・介護休業法が、2022年4月1日から順次施行されています。すべての会社で対応が必要となる今回の法改正のポイントを、弁護士法人大江橋法律事務所の小寺美帆弁護士が解説します。
はじめに
育児・介護休業法改正の背景
今回の改正の目的は、男性育休の促進によって、少子化対策を推し進めることにあります。2020年5月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、男性の育休取得や育児参画を促進するための取組みを総合的に推進することとされました。その後、労働政策審議会で「男性の育児休業取得促進」の建議がなされ、今回の改正に至ったという背景があります。
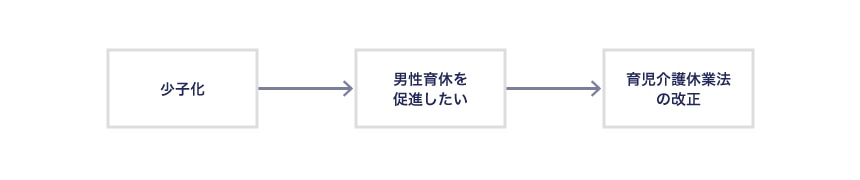
育児・介護休業法の改正内容・スケジュール・影響度チェックリスト
今回の主な法改正の内容とスケジュール、実務への影響度は次のとおりです。これらの内容を下記2から1つずつ解説していきます。
| 主な改正内容 | スケジュール | 実務への影響度 |
|---|---|---|
| ① 育児休業を取得しやすい雇用環境整備 | 2022年4月1日施行 | △ |
| ② 個別の周知・意向確認の措置の義務化 | ◎ | |
| ③ 有期雇用労働者の要件緩和 | 〇・△ | |
| ④ 産後パパ育休=出生時育児休業の新設 | 2022年10月1日施行 | 〇 |
| ⑤ 育児休業の分割取得 | 〇 | |
| ⑥ 育児休業取得状況の公表の義務化 | 2022年4月~2023年3月の 実績を2023年4月1日以降 に公表 |
△ |
2022年4月1日施行分
① 育児休業を取得しやすい雇用環境整備
企業は、以下のAからDまでの4つ措置のうち、1つを実施する必要があります(通達 1では、複数実施が望ましいとされています)。
| 措置の内容 | 実務対応ポイント | |
|---|---|---|
| A | 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 |
|
| B | 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) |
|
| C | 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 |
|
| D | 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |
|
② 個別の周知・意向確認の措置の義務化
今回の改正の中で、実務上の影響が最も大きいのが、この「個別の周知・意向確認の措置の義務化」ではないかと思われます。
実務対応のポイントとして、社員が上司に対し、配偶者ないし自らが妊娠したと伝えた場面で、特に配偶者が妊娠したと伝えた場合に、それが人事部等へ情報共有されず、個別周知・意向確認が漏れてしまうといった事態が考えられます。
2022年4月1日からは、「本人または配偶者の妊娠・出産の申出」に対して、個別の周知・意向確認の措置が義務化されたことを社内、特に管理職に周知し、理解してもらうことが重要です(上記2-1で紹介した、厚生労働省提供の社内研修用動画・レジュメ 5 を案内することも考えられます)。
| 措置の内容 | 実務対応ポイント | |
|---|---|---|
| 対象者 | (本人または配偶者の)妊娠・出産の申出をした労働者 ※2022年4月1日以降の申出が対象 |
申出がない場合、周知不要です。会社に妊娠・出産等の確認を義務付けるものではなく、申出があったときに周知すれば問題ありません。 |
| 周知内容 |
|
厚生労働省のひな型が参考になります 6。 |
| 時期 | 労働者が希望の日から円滑に育児休業を取得することができるように配慮し、適切な時期に実施することが必要とされています。

|
|
| 方法 | ①面談(オンライン面談も可) ②書面交付(郵送も可) ③FAX ④電子メール等 ※③④は労働者が希望した場合のみ |
アンケート欄の回答がない場合など意向不明の場合も、意向確認のための働きかけがされていれば、問題ないとされています。 |
③有期雇用労働者の要件緩和
有期雇用労働者の要件緩和の点については、育児休業のみならず、介護休業にも影響するため注意が必要です。
| 改正前 |
|---|
|
| 改正後 |
|---|
|
| 改正対応 | |
|---|---|
| 引き続き雇用された期間が1年以上という要件を残したい場合 | 引き続き雇用された期間が1年以上という要件を外したい場合 |
|
|
2022年10月1日施行分
④ 産後パパ育休=出生時育児休業の新設/⑤ 育児休業の分割取得
| 改正前 | |
|---|---|
| 育休制度のみ | |
| 取得時期・日数 | 子が1歳まで(最長2歳) |
| 分割取得 | × |
| 休業中の就業 | × |
| 改正後 | ||
|---|---|---|
| 育休制度 | 産後パパ育休 | |
| 取得時期・日数 | 子が1歳まで(最長2歳) | 子の出生後8週間以内に4週間まで |
| 分割取得 | 2回に分割可能 | 2回に分割可能 |
| 休業中の就業 | × | 〇(労使協定必要) |
| 改正対応 | |
|---|---|
| 就業規則の改正 |
|
| 労使協定の締結 (右記の場合は、労使協定の 締結が必要となります。) |
|
産後パパ育休中の就労
産後パパ育休中の就労については、次の条件があることに注意が必要です。
(2)休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、当該日に所定労働時間数未満
さらに雇用保険から支給される出生時育児休業給付金との関係にも注意しましょう 11。
2023年4月1日施行分
⑥ 育児休業取得状況の公表の義務化
2023年4月1日からは、常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表が義務付けられます。具体的には、(1)育児休業をした者、(2)育児休業をした者+育児を目的とした休暇制度(育児休業除く)を利用した者の合計を年1回公表することと定められる予定です。こちらの詳細は今後決定される予定ですので、該当企業は追って対応しましょう。
さいごに
男性新入社員の約8割が、子供が生まれたときには育休取得を希望しているという調査結果からも明らかなとおり(日本生産性本部「2017年度新入社員秋の意識調査」)、近い将来に子育て世代となる男性社員の意識は大きく変わってきました。それに伴って育休取得希望者が増加していくことは間違いなく、就職活動において、学生が「柔軟な働き方」を重視する流れも顕著に見られます。
少子化対策を目的とする今回の育児・介護休業法改正ではありますが、男性育休の促進は、企業の採用活動にも大きな影響を与えるものと考えられます。
-
厚生労働省雇用環境・均等局長「「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」
(改正令和3年11月4日雇均発1104第2号) ↩︎ -
厚生労働省「イクメンプロジェクト」参照。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「イクメンプロジェクト」よりダウンロード可能。 ↩︎
-
厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所
