法務DXの成功・失敗事例と導入障壁の乗り越え方PR 「Legal Innovation Conference ~法務DXの壁を越えろ~」講演レポート
法務部
目次
リーガルテックを導入している、または導入を具体的に検討している企業の数は増えつつあるものの、活用方法を試行錯誤している企業は少なくないようです。
2021年11月25日に開催されたオンラインカンファレンス「Legal Innovation Conference 〜法務DXの壁を越えろ〜」では、各リーガルテックベンダーや有識者が、リーガルテックを活用して戦略的な法務組織を作り上げた成功事例やDX推進の失敗例、現在多くの法務担当者がぶつかっている障壁の乗り越え方について解説しました。本稿では、その様子をダイジェストでレポートします。
不確実な社会で求められる主体的なルール形成・システム構築
複雑性や不確実性が高まる昨今のデジタル社会。Society 5.0の時代(サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会)においては、人々の価値観の多様化も相まって、ガバナンスを整備することがきわめて困難な状況となっています。一方で、企業はイノベーションを創出し、これを適切にガバナンスすることが必要です。
こうした背景のもと、経済産業省は2021年7月、「
GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」報告書を公表しました。報告書では、多様なステークホルダーが迅速にルールや制度をアップデートし続ける「アジャイル・ガバナンス」の実践が提唱されています。
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 ガバナンス戦略国際調整官 羽深宏樹氏は講演で、同報告書の内容を踏まえてアジャイル・ガバナンスの考え方の基本を解説するとともに、これからの企業法務に求められる役割について次のように説明しました。
「定められたルールを遵守するだけでなく、自らゴール(MVV:Mission、Vision、Value)を定義し、主体的にルール形成・システム構築していくことが求められる。また、それらに関する透明性・アカウンタビリティを確保し、幅広いステークホルダーに対して “Comply and Explain” を果たさなければならない」(羽深氏)

DX予算確保のためには、依頼者のメリットを説明することがポイント
「契約DXは、レガシーシステムを新しいシステムへ刷新する『スクラップアンドビルド型』が正しいとされることもあるが、多くの企業は、既存のシステムが共存する『共存共創型』を目指していくべき」—— そう語るのは、株式会社Hubble取締役CLO/弁護士 酒井智也氏です。
独自のデジタルキーテクノロジーをベースにさまざまなサービスを展開する株式会社ビットキーでは、必要最低限のツールを活用し、共存共創型の契約DXを実現しています。同社法務職の保泉綾香氏は、酒井氏との議論のなかで、当初は法務や営業の細かなペインからDXに着手したが、そのなかで「法務部門として依頼者の体験を向上していく」という使命を果たすためにはすべてのフローがつながっていることの必要性を感じ、社内でオンラインセミナーを開催するなど多くの人を巻き込むための施策に取り組んでいったことを明かしました。
また保泉氏は、DX推進のための予算確保について「リーガルテックの投資対効果は大きい。意思決定者に対しては、法務部門の視点だけで説明するよりは、依頼者側からも前向きな声をもらった方がプラスになるため、まずは依頼者に契約管理によるメリットを説明していくことが大事。それが最終的に経営者への訴求ポイントになっていくはず」と語りました。

法務部員の学習・人材育成に関する調査結果とポケモン社の事例
BUSINESS LAWYERSでは全国の法務部門の管理職・担当者を対象に、学習や人材育成、研修にかける時間や予算についてのアンケート調査を行い、460件の回答を得ました。講演では同調査の結果をもとに、株式会社ポケモン 管理本部 法務・労務部 法務担当ディレクター 宇佐美舞子氏とBUSINESS LAWYERS編集長 松本慎一郎が、これからの法務の学習・人材育成について議論しました。
アンケート結果からは、「研修制度が充実していない」「研修・教育、ITツールの導入や情報の獲得などに向けた予算が少ない」といった状況が明らかになりました。一方、宇佐美氏は、法務部門としてそれらの予算を確保し、語学研修をはじめ多様な研修や教育制度を設けているといいます。その秘訣について、次のように語りました。
「法務部員は、事業にコミットして前に進める、事業を阻害しないという意識を持って業務に取り組んでおり、社内でもそのような認識が浸透している。そうした姿勢が予算確保につながっているのではないか」(宇佐美氏)

弁護士ドットコム BUSINESS LAWYERS編集長 松本慎一郎
電子契約サービス導入の壁はどこにある? 電子契約が導入できない本当の理由
電子契約を導入できない理由としてあげられがちな「取引先NG」。しかし実際には「自社内における実務上の壁の存在が大きい」と、弁護士ドットコム クラウドサイン事業本部 リーガルデザインチーム 橋詰卓司は指摘します。講演では、同イベント・コンテンツチームの安川ちひろとともに、電子契約の導入を断念してしまった企業の生の声を取り上げながら、導入障壁への対処法を紹介しました。
「取引先NG」と一口に言っても、取引先には顧客、親事業者・下請事業者、グループ会社などさまざまな企業があるはずです。自社内にも、営業などのフロント部門、役職員、法務部、経理部、情報システム部と多様な立場の人たちがいます。橋詰は、「誰にとってのNGなのか、自社内・取引先の関係者の解像度を上げてその理由を理解し、対処していくことが大切だ」と語りました。

弁護士ドットコム クラウドサイン事業本部 リーガルデザインチーム 橋詰卓司
法務担当者や弁護士は政策起業家になれるか
東京大学 産学協創推進本部 FoundX/本郷テックガレージ ディレクター 馬田隆明氏は、テクノロジーで社会を変革する4つの原則を示した著書『未来を実装する――テクノロジーで社会を変革する4つの原則』(英治出版、2021)の内容をもとに、Airbnb Japan株式会社 Lead Counsel 日本法務本部長/弁護士 渡部友一郎氏とのディスカッションのなかで、これからの法務のあり方について探りました。
『未来を実装する』では、「政策起業」力の重要性が説かれています。「法務部や弁護士という職種でも政策起業家になれるか?」という渡部氏の問いかけに対して馬田氏は「なれると思うし、なることを期待する。社会的公正に対して強い思いを抱いているはずなので、自社の利益だけでなく、理想とする社会を描き、そこに必要なものを提言していけるはず」とコメント。渡部氏もこれに同意する形で「一般の人からするとルールは変えられないものだという思いがあるが、法務は日々の仕事で法解釈をするなか、ルールを疑うことができている。これは政策起業とも相性がよいのでは」と述べました。
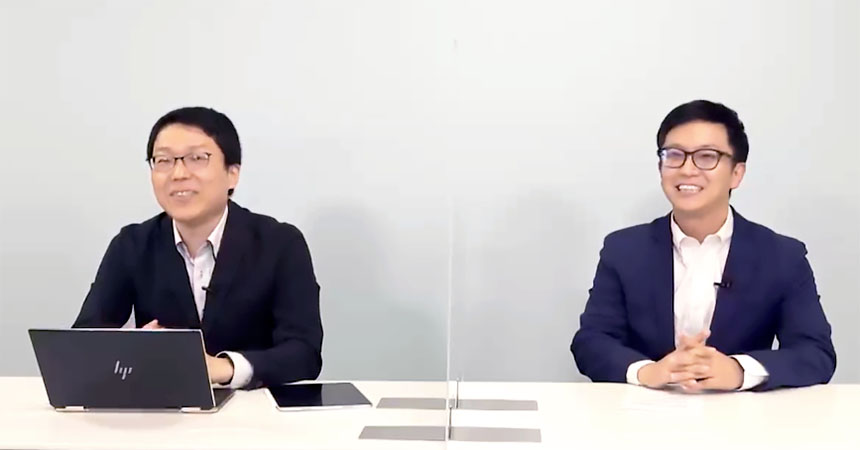
Airbnb Japan株式会社 Lead Counsel 日本法務本部長/弁護士 渡部友一郎氏
日本たばこ産業とSUPER STUDIOが語る、リーガルテック予算を獲得する秘訣
リーガルテックの導入には、乗り越えなければならないハードルが複数あります。日本たばこ産業株式会社 日本マーケット 法務担当 太田皓士氏、株式会社SUPER STUDIO 経営企画group 経営企画unit 法務・リスクマネジメントteam 中山洋子氏は、株式会社LegalForce 執行役員 最高法務責任者CLO 佐々木毅尚氏を聞き手に、各社での導入事例について語りました。
リーガルテック導入時の課題の1つに予算の獲得がありますが、両社はそれぞれ次のような工夫をすることで、周囲を説得していったといいます。
「トライアル(β版)導入の段階で、チームメンバーやユーザーに対してアンケートを実施。利用頻度などの定量的な面と、活用方法や感想といった主観的な面について調査し、資料化した。正式導入後にもLegalForceがどれだけ会社に貢献しているかを継続的に調査しており、サービスに関する要望がある場合は、直接LegalForce社にフィードバックしている」(太田氏)
「ツール導入によって期待できる効果や、顧問弁護士との棲み分け方法などに重点をおいて稟議のなかで説明した。リーガルテックは定型業務の効率化によって業務品質を向上できる点が一番の特徴である一方、顧問弁護士はそのアドバイスに価値がある」(中山氏)

リスクマネジメントteam 中山洋子氏、株式会社LegalForce 執行役員 最高法務責任者CLO 佐々木毅尚氏
SHIFT社によるDX推進の成功ケース・失敗ケース
契約業務DXの推進において重要なのは、業務分析を通じた課題の整理と特定、そしてそれらを検証していくこと——GVA TECH株式会社 取締役 CLO/弁護士 康潤碩氏はこう強調します。講演では、株式会社SHIFT 経営管理本部 経営管理部 法務グループ グループ長 照山浩由氏、同グループ 上西健太郎氏を迎え、DX推進の成功・失敗ケースについて議論を繰り広げました。
SHIFT社では、AI契約審査ツールや電子契約サービスの導入など、契約業務DXを推進しています。ただし、電子契約の導入に関しては、2020年のコロナ禍への対応において、スピードを優先させて急ピッチで導入したことから、導入後の理想の状態を設定するなどといった、課題の本質を検討しきれていなかったり、ワークフローの整理を十分に行えなかったりした結果、多くの課題が残ってしまったといいます。一方で、課題と目標を明確に設定して推進した契約審査の改革は成功しています。
こうした自社事例を踏まえ、照山氏は「ツールを入れたからといってDXが進むわけではない。課題をどこに感じ、ツールを導入することでそれがどう解決され、どのように業務の品質・効率が上がっていくか、という順序で考えていくことが大事。導入した結果どうなったかまで検証し、うまくいかないのであればやめるという判断もありえる。自分たちの仕事をきちんと分析していくことがDXにおいては重要」とコメントしました。
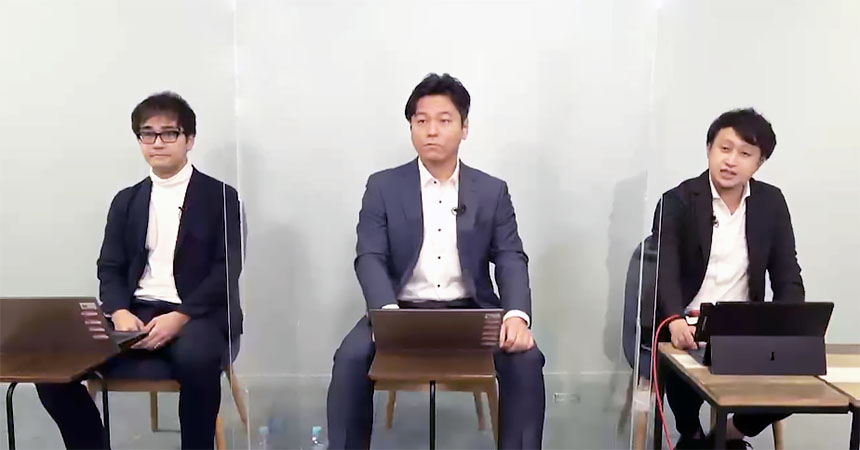
グループ長 照山浩由氏、GVA TECH株式会社 取締役 CLO/弁護士 康潤碩氏
法務DXに向けて一歩前に進むタイミング
このほかにも、契約ライフサイクル管理システム「ContractS CLM」を提供するContractS株式会社、クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」を提供するFRAIM株式会社、AI契約書チェックサービス「LawFlow」を提供するLawFlow株式会社、契約書レビューAIクラウド「LeCHECK」を提供する株式会社リセなど、多くのリーガルテックベンダーが登壇し、活用事例について紹介しました。
リーガルテックをはじめ、法務業務を変革するさまざまなツールが登場してきた今、法務DXに向けて一歩前に進むタイミングに来ているといえます。本カンファレンスの事例を参考に、これから取り組むべき具体的な課題やその解決策を探ってみてはいかがでしょうか。
