令和3年著作権法改正の影響度と実務対応 図書館関係の権利制限規定見直し、放送同時配信等に係る権利処理の円滑化
知的財産権・エンタメ 更新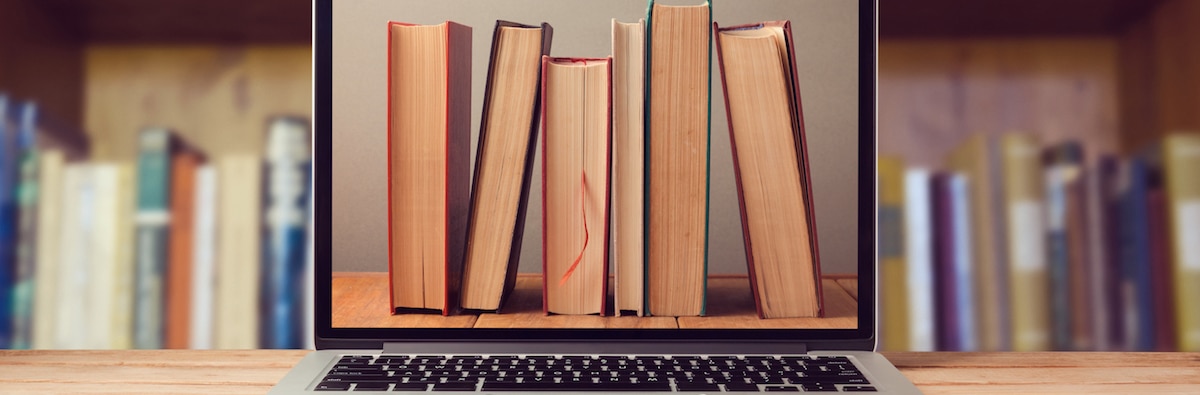
目次
令和3年5月26日、著作権法の一部を改正する法律案が参議院で可決・成立しました。本稿では、本改正の内容をご紹介します。
なお、文化庁が公表している関係資料は以下をご覧ください。
本稿では、改正法による改正後の条文を「新◯条」と記載します。
改正項目一覧
| 改正項目 | 改正法 | 現行法 | 影響度 | 施行日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館関係の権利制限規定の見直し | 国会図書館による絶版等資料のインターネット送信 | 31条4項~7項 | – | ◯ | 公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
| 複写サービス(図書館資料のメール送信等) | 31条2項~5項、104条の2、 104条の4 |
– | ◎ | 公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日 | |
| 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化 | 権利制限規定の拡充 | (a)34条1項、(b)38条3項、(c)39条1項、(d)40条2項、(e)44条、(f)93条 | 同左 | △ ※:(a) (b)(d)(e) ◯:(c) |
令和4年1月1日 |
| 許諾推定規定の創設 | 63条5項 | – | ◎ ※ | ||
| レコード・レコード実演の利用円滑化 | 94条の3、 96条の3 |
– | ◯ ※ | ||
| 映像実演の利用円滑化 | 93条の3、94条 | – | ◯ ※ | ||
| 協議不調の場合の裁定制度の拡充 | 68条、103条 | 68条 | △ ※ | ||
※ 放送事業者にとって
改正項目の柱は2つ
今回の改正項目は、①図書館関係の権利制限規定の見直し、②放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化、の2つの内容からなり、以下の文化審議会著作権分科会の報告書を受けたものです。
- 「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」
(令和3年2月3日) - 「放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する報告書」(令和3年2月3日)
図書館関係の権利制限規定の見直し
不特定多数の人たちが訪れる図書館は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下において、休館を余儀なくされました。そして、休館が明けた後も、外出自粛やリモートワーク等が求められ、高齢者をはじめとした重症化ハイリスク者を中心に、図書館に行きたくても行けないという状況が続いています。
こうした中、現実に図書館まで行かなくてもインターネット等を通じて図書館資料にアクセスすることができれば大変便利ですが、現行法上は以下のとおり限界があります。
現行法
(1)国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
著作権法31条3項は、絶版等の理由で入手が困難な図書館資料(「絶版等資料」)について、国会図書館は、著作権者に無断でデジタル化し、そのデータを他の公共図書館等にインターネット送信することができる旨を規定しています。これにより、利用者は、最寄りの公共図書館等に行けば、館内のパソコン画面を通じて、国会図書館がデジタル化した絶版等資料のデータを閲覧することができます。
しかしながら、国会図書館が絶版等資料のデータを送信できる先は公共図書館等に限られ、個別の利用者に直接送信するためには、現行法上、著作権者の許諾が必要になります。そのため、利用者が自宅や会社のパソコンから絶版等資料のデータにアクセスすることはできません。
このように、現行法の下では、利用者は、公共図書館等まで行かなければ国会図書館が保有する絶版等資料のデータを閲覧することはできない状況にあります。
(2)複写サービス
公共図書館等は、著作権法31条1項に基づき、いわゆる複写サービスとして、図書館資料の著作権者から許諾を得なくても、利用者の調査研究の用に供するため、図書館資料を用いて、著作物の一部を複製し、提供することができます。ここで、複写サービスにより作成された文献等のコピーは、そのまま利用者に手渡しされるのが通常ですが、郵送で送付することもできます。しかしながら、利用者にファックスで送信したり、PDFデータをメール送信したりすることは権利制限の対象とはなっておらず、別途著作権者の許諾を得る必要があることから、事実上不可能な状況にあります。
こうした課題はこれまでも度々指摘されていましたが、今般の新型コロナウイルス感染拡大を受けて、著作権法を改正すべきだという機運が高まることになりました。
改正法の内容
(1)国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
改正法は、国会図書館が絶版等資料のデータを直接個々の利用者に対しても送信できるとしています(新31条4項)。つまり、改正法が施行されれば、私達は、自宅や会社等から国会図書館のウェブサイトを通じて絶版等資料のデータを閲覧できるようになります。
ここで、「絶版等資料」にあたるかどうかは、現に一般に新品や電子書籍で入手することが困難か否かによって判断されますが(3か月以内に入手可能になる場合は除かれます。新31条6項)。実務上は、関係者(国会図書館や出版社等)の協議によって決められることなり、漫画や商業雑誌等は送信対象から除外されることが予想されます。
なお、利用者は、絶版等資料のデータを自ら利用するために必要な限度で複製(プリントアウト等)したり、一定の範囲で公に伝達したりすることができるとされています(新31条5項)。
(2)複写サービス(図書館資料のメール送信等)
改正法は、公共図書館等は、利用者の調査研究の用に供するため、所蔵資料を用いて、著作物の一部分(政令で定める場合は全部)をメールやファックスの方法で利用者に送信することができるとしています(新31条2項)。
ただし、文献コピーのメール送信等を無制限に認めてしまうと権利者(著者、出版社等)に経済的ダメージを与えてしまうことから、条文上、以下の要件が定められています。
(a)著作物の種類等に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合の送信禁止
(b)送信先は事前に氏名や連絡先等を登録した利用者に限定
(c)送信するデータにコピーガード等の技術的措置を講ずること
(d)送信できる図書館等は、責任者の配置や研修の実施等、一定の条件を満たす必要があること
このうち、(a)の詳細については関係者間で策定されるガイドラインで、(c)や(d)の詳細については省令(著作権法施行規則)で、それぞれ今後定められることになっています。
公共図書館等の設置者は、利用者に対して文献コピーの送信を行う場合、権利者に対し、補償金を支払う必要があります(新31条5項)。この補償金は、利用者が図書館等に支払う手数料が充てられることが想定されています。
なお、補償金を図書館等から徴収し、権利者に分配するのは、文化庁が指定する「指定管理団体」とされ(新104条の10の2第1項)、補償金の額の決定については、文化庁長官の認可が条件となっています(新104条の10の4第1項)。補償金の料金体系や金額の具体的なイメージについては、上記の文化庁説明資料の10頁にまとめられています。
放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化
放送番組のインターネット同時配信等は、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興等の観点から非常に重要であることから、より推進していくことが求められています。しかしながら、放送番組の同時配信等を行うためには、番組で利用されている多種多様かつ大量の著作物等の権利処理を行う必要があるところ、これがネックとなって同時配信等が円滑に進まないという課題があります。
改正法は、こうした課題を解決することを目的としています。
「放送同時配信等」
改正法が対象とする同時配信等は、「放送同時配信等」という名称で、以下を含む形で定義されています
(新2条1項9号の7)。
- 放送と完全に同タイミングで配信される「同時配信」
- 放送が終了するまでの間であれば冒頭から視聴ができる「追っかけ配信」
- 放送終了後も一定期間視聴が可能な「見逃し配信」
このうち③見逃し配信の「一定期間」については、週1回の番組を念頭に置いて1週間が基本とされていますが、月1回の番組は1か月とするなど、柔軟に対応することが想定されています(新2条1項9号の7イ)。
5つの改正事項
改正事項は、大きく分けて①権利制限規定の拡充、②許諾推定規定の創設、③レコード・レコード実演の利用円滑化、④映像実演の利用円滑化、⑤協議不調の場合の裁定制度の拡充、の5項目です。
(1)権利制限規定の拡充
現行法上、「放送」のみが対象となっている以下の権利制限規定につき、対象が「放送同時配信等」に拡大されます。
(a)学校教育番組の放送等(新34条1項)
(b)非営利・無料又は通常の家庭用受信機を用いて行う公の伝達等(新38条3項)
(c)時事問題に関する論説の転載等(新39条1項)
(d)国会等での演説等の利用(新40条2項)
(e)放送事業者等による一時的固定(新44条)
(f)放送のための実演の固定(新93条)
これらの権利制限規定は、(b)を除き、放送事業者のみに関係する規定であり、逆にいえば、放送事業者以外の者には関係しません。
他方、(b)は受信者に広く関係する規定です。具体的には、現行法上、たとえば会社のロビーにテレビを置き、不特定多数の人にテレビ番組を見せることは、権利者の許諾なくできますが、パソコンを置き、同時配信や追っかけ配信の形で番組を不特定多数の人に見せることはできません。改正後はこうしたことが権利者の許諾なくできるようになります(なお、見逃し配信は対象外とされています)。
(2)許諾推定規定の創設
写真やイラスト等の著作物を放送番組で使用するに際し、放送事業者は権利者から放送の許諾を得ています。ここで、放送だけでなく放送同時配信等もするということであれば、本来は、そのことをちゃんと伝えたうえで同時配信等についても許諾を得る必要があります。
しかしながら、1つの放送番組には多種多様かつ大量の著作物が使用され、また、放送番組はかなりタイトなスケジュールの中で制作されることから、使用する素材すべてにつき、放送だけでなく同時配信等もするということをしっかり説明し、許諾を得ることは、現実的に極めて困難です。そして、権利者から放送同時配信等につき許諾を得られなかった著作物については、放送同時配信等に際し、モザイク処理等がなされることになり(いわゆる「フタかぶせ」)、その結果、視聴者は、ネット経由では完全な形で番組を楽しむことができない状況になります。
そこで、改正法では、権利者が放送事業者に対し、放送の許諾を行った場合は、許諾の際に、別段の意思表示(「同時配信等は認めない」「同時配信等は別契約が必要だ」等)をした場合を除き、放送同時配信等についても許諾をしたものと推定するとされています(新63条5項)。
(3)レコード・レコード実演の利用円滑化
現行法上、レコード(市販の音楽CD等の音源)やレコード実演(音楽CD等に収録された歌や演奏等)を放送する場合、著作隣接権者から事前許諾を得る必要はなく、事後的に使用料を支払えばよい一方で、放送同時配信等をする場合には、事前許諾を得る必要があります。実務上は、著作権等管理事業者による集中管理等が行われているレコードに関しては、円滑に許諾を得ることができますが、そうでないレコードに関しては、許諾を得ることが困難だという課題があります。そして、許諾を得られないレコードの場合、放送には使用できても放送同時配信等では使用できない(音源の差し替え等を迫られる)という事態が生じます。
そこで、改正法では、集中管理等の対象となっておらず、また連絡先等の情報も公表されておらず円滑に許諾が得られないレコードやレコード実演につき、通常の使用料額に相当する補償金を事後的に支払うことで、放送同時配信等でも使用できると規定しています(新94条の3、新96条の3)。
(4)映像実演の利用円滑化
現行法上、映像実演(俳優の演技等)については、放送で利用する場合、著作隣接権者である実演家から事前許諾を得る必要がありますが、初回放送の許諾を得れば、再放送についての許諾は不要で、追加報酬を支払えばよいと規定されています(94条)。他方、放送同時配信等につきこうした規定は存在しないため、再放送する放送番組を放送同時配信等するためには、別途、著作隣接権者である実演家から許諾を得る必要があります。
そこで、改正法では、放送番組を再放送する場合に放送同時配信等が円滑に行えるように、以下の措置を講じています。
まず、集中管理等の対象となっておらず、また連絡先等の情報も公表されておらず円滑に許諾が得られない映像実演については、初回放送の放送同時配信等の許諾を得ている場合は、通常の使用料額に相当する補償金を事後的に支払うことで再放送の放送同時配信等でも使用できると規定しています(新93条の3)。
次に、初回放送時に放送同時配信等がなされておらず、初回放送の放送同時配信等につき許諾を得ていない映像実演については、実演家と連絡をするための所定の措置を講じても連絡がつかない場合には、文化庁長官の指定する著作権等管理事業者に対してあらかじめ補償金を支払うことで、再放送の放送同時配信等に使用できると規定しています(新94条)。
(5)協議不調の場合の裁定制度の拡充
現行法上、放送事業者が著作物を放送するに際し、権利者に許諾を得ようとしたものの協議が不調に終わった場合、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を支払うことにより放送できるという制度がありますが(68条)、この制度は、放送同時配信等については適用がありません。
そこで、改正法は、この制度の対象を放送同時配信等にも拡大するとともに、著作隣接権についても適用されるようにしています(新68条、新103条)。
施行期日
これら改正事項の施行期日は以下のとおりです。
- 国会図書館による絶版等資料のインターネット送信(上記 2–2(1)):公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日
- 図書館資料のメール送信等(上記 2–2(2)):公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日(関係者間で協議をして決める事項がいろいろあるため)
- 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化(上記3):令和4年1月1日
今後の注目ポイント
改正法が施行されれば、図書館サービスがより便利になり、また、テレビ番組やラジオ番組をパソコンやスマホ等を通じて楽しめるようになることが期待されます。
実際に改正法を運用するために必要となる詳細については、政令、省令といった下位法令や関係者間の協議、ガイドラインで詰めることが想定されていますので、こうした動きについても注視をしていく必要があります。

三浦法律事務所
