中国「外商投資法」がついに施行、対応のポイントは?
国際取引・海外進出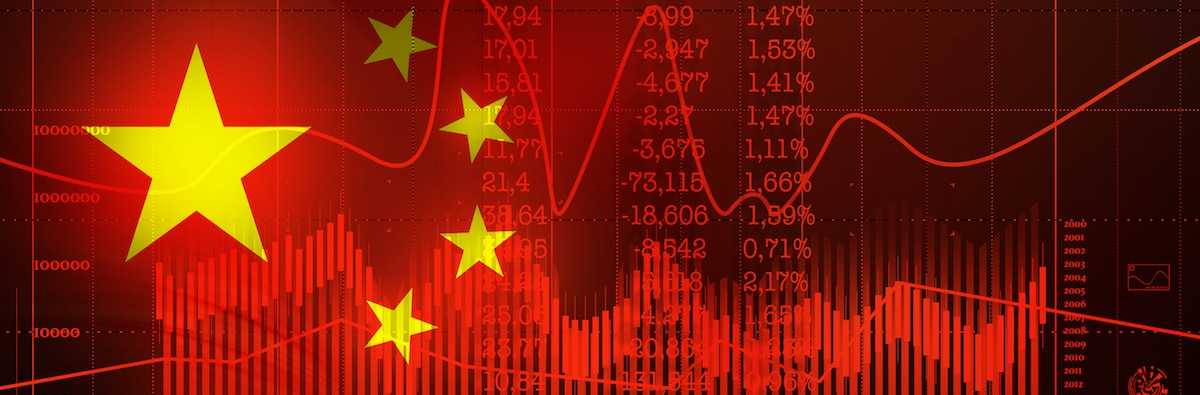
目次
中国における外資による投資の新たな基本法である「外商投資法」が、ついに2020年1月1日から施行されました(その具体的内容は「中国外商投資法が2019年3月に成立、制定による日本企業への影響は?」をご参照ください)。
外商投資法については、2019年3月15日の公布以降、その規定内容を具体化する関連規則・法令等の制定作業が進められ、注目を集めてきました。そして、外商投資法の施行直前の2019年12月半ばから年末にかけて、外商投資法の規定内容全般について定めた「外商投資法実施条例」をはじめとする関連規則・法令等が相次いで制定・公布され、外商投資法と同時に施行されました。
これらの関連規則・法令等の制定により、概括的・抽象的な内容が多かった外商投資法の規定内容について、まだすべての規定内容が具体化されたとまでは言えないものの、外商投資法の施行によりただちに生じる影響や実施すべき対応と、今後の関連規則・法令等の整備を引き続き注視すべき事項の区分が明確になってきました。
本稿は、2020年1月1日の外商投資法の施行に際して明らかとなった、外国企業や外商投資企業 1 にただちに生じる影響や対応すべき事項、および即時の対応ではなく引き続き状況を注視することとなる事項について、重要な点を整理するものです 2。
外商投資企業(特に中外合弁企業)におけるガバナンスの変更(緊急度低:引き続き検討継続)
外商投資法の施行に伴い、従来外資による法人形式の投資を規律してきた「外資独資企業法」、「中外合弁企業法」および「中外合作経営企業法」の、いわゆる外資三法が廃止されました(外商投資法42条)
これまで外資独資企業、中外合弁企業および中外合作企業に対しては、それぞれ特別法である外資三法が適用され、組織構成等について会社法のデフォルト・ルール(内資企業に適用)と異なる点が存在しましたが、外資三法が廃止されると、上記各類型の外商投資企業についても、組織構成等について会社法のデフォルト・ルールが全面的に適用されることとなります(外商投資法31条)。
特に、中外合弁企業の場合は、中外合弁企業法に基づき、株主会が存在せず、各出資者により選任された董事により構成される董事会が最高意思決定機関とされるなど、特殊な組織構成となっていましたが、中外合弁企業法の廃止により、会社法に基づく株主会の設置等、これらに大幅な変更が生じることとなるため、当該変更に伴う取扱いや影響が注目されていました(詳細については「中国外商投資法が2019年3月に成立、制定による日本企業への影響は?」をご参照ください)。
この点について、2019年12月26日に国務院により公布され、2020年1月1日から施行された「外商投資法実施条例」(以下「実施条例」といいます)により、以下の点が明らかになりました。
既存の外商投資企業の組織形態・機構等の移行猶予期間中の取扱い
外商投資法は、既存の外商投資企業について、外資三法の廃止に伴う会社法の強行規定に従った組織形態・機構等への変更に関して、外商投資法施行後5年以内は引き続き従前の組織形態・機構等を維持することができるとし、移行の猶予期間を設けていました(外商投資法42条)。もっとも、猶予期間の長さや過去の法令変更に際しての取扱い等から、実際上は、猶予期間中であっても、法定代表者や登録資本等の別の登記事項に関する変更登記等の際に、組織形態・機構等の変更も合わせて要求されないかなど、実務運用に対する懸念も存在しました。
この点、実施条例では、既存の外商投資企業は、5年間の猶予期間内は、従来の組織形態・機構等を前提に変更登記手続を実施可能である旨が明確にされており(実施条例44条1項)、上記のような懸念が一応解消されたと言えます。
なお、実施条例では、猶予期間経過後の2025年1月1日時点において、従来の組織形態・機構等の会社法の強行規定に合わせた変更が行われていない場合については、その他の登記事項に関する変更登記申請を受理しないとしています(実施条例44条2項)。
外商投資企業の組織形態・機構等の変更の具体的な実施方法および取扱い等
実際に既存の外商投資企業の組織形態・機構等の変更を行う場合には、その具体的な実施方法や取扱い等に関するルールが重要となりますが、外商投資法では、当該組織形態・機構等の変更に関する具体的な規則は国務院が制定するとされ、明確なルールは示されていませんでした(外商投資法42条)。
この点、実施条例では、既存の外商投資企業による組織形態・機構等の変更登記の具体的な取扱いは、国務院市場監督管理機関が制定・公布するとされています(実施条例45条)。これを受けて、国家市場監督管理総局により、2019年12月28日に「『外商投資法』を徹底実施し外商投資企業登記登録業務を遂行することに関する通知」が公布され、組織形態・機構等の変更にあたっては、定款の変更を行ったうえで、会社登記機関において変更登記および関連の届出を行う旨などが明確にされました。
また、より実質的な取扱いに関して、実施条例では、既存の外商投資企業が組織形態・機構等の変更を行った後であっても、従前の合弁・合作に関する契約において約定した持分・権益の譲渡方法、収益の分配方法、残余財産の分配方法等については、引き続き約定どおり取り扱うことができるとされています(実施条例46条)。
他方で、株主会の設置に伴う意思決定方法やマイノリティ出資者の拒否権事項等については、下位規則や関連法令等において特段の解釈や指針は示されていません。
まとめ
以上に鑑みると、既存の外商投資企業の組織形態・機構等の変更については、必ずしも急ぐ必要はなく、外商投資法施行後5年間の猶予期間中の適当なタイミングで実施することで足りるものと考えられます。
中でも、株主会の設置という重要な変更について合弁相手方との調整が必要となる中外合弁企業においては、上記1−2のとおり、持分譲渡の方法や収益・残余財産の分配等の権益に関する事項は維持されることが明確にされた一方、株主会の設置に伴う意思決定方法やマイノリティ出資者の拒否権事項等については、下位規則や関連法令等において特段の解釈や指針が示されていないことから、特にマイノリティ出資者である場合には、不利な変更を余儀なくされることのないよう、合弁相手方との協議のタイミングや、今後蓄積されていくことが想定される実務の動向を見極めながら、引き続き対応を検討していくことが多くの場合においては現実的な対応と考えられます 3。
外商投資情報報告制度(緊急度高:直ちに影響発生)
新たな「外商投資情報報告制度」への移行
外商投資法では、新たに「外商投資情報報告制度」を構築し、外国投資者または外商投資企業は、「企業登記システム」および「企業信用情報公示システム」により商務部門に投資情報を提出しなければならないとしていました(外商投資法34条1項)。
実施条例においても同様の規定が設けられ(実施条例38条、39条)、さらに、その具体的な内容について、商務部および国家市場監督管理総局により「外商投資情報報告規則」(以下「報告規則」といいます)が2019年12月30日に公布され、2020年1月1日から施行されました。
従来の外商投資に関する情報報告制度は、「外資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」の対象となる場合を除き、「外商投資企業の設立及び変更の届出管理暫定規則」に基づき、商務部門の「外商投資総合管理システム」を通じて運用・管理されていました。これに対し、新たな「外商投資情報報告制度」は、市場監督管理部門の企業登記システムおよび企業信用情報公示システムにより運用され、情報は市場監督管理部門を通じて商務部門に共有されることになります(報告規則4条、5条、6条)。
従来の「外商投資企業の設立及び変更の届出管理暫定規則」は2020年1月1日に廃止され(報告規則35条)、さらに、商務部により2019年12月31日に公布され、2020年1月1日に施行された「外商投資情報報告の関連事項に関する公告」(以下「報告公告」といいます)において、2020年1月1日以降に設立されるまたは変更が生じた外商投資企業については、新たな「外商投資情報報告制度」に基づき設立または変更の報告を行うことが要求されており、新制度への移行はただちに行われることが予定されています(報告公告6条2項)4 。
「外商投資情報報告制度」の概要および影響
「外商投資情報報告制度」の具体的内容については、報告規則および報告公告に規定されています。報告規則によれば、外商投資情報報告制度における報告義務者は外国投資者または外商投資企業とされ、①初回報告、②変更報告、③年度報告および、④抹消報告の4つの類型の報告が要求されており(報告規則8条)5 、各報告の概要は下表のとおりです。
各報告が必要となる場合や報告内容自体について、従来の届出制度から外国投資者および外商投資企業の負担を大幅に増加させるような変更は見受けられませんが(①初回報告、②変更報告および、③年度報告における報告事項の詳細は報告公告において、別紙に個別に報告様式を定める形で規定されています)、制度自体が新しいものとなり、手続を行うシステムも変更されることとなるため、各地方における移行の状況や実務運用の詳細については、管轄当局に直接照会する等の方法により情報収集を行う必要があると考えられます(たとえば、2020年1月23日現在において、上海市の各商務部門に電話照会を行った結果では、まだ具体的な実務運用の詳細が定まっていない状況でした)。
なお、商務部門への報告とは別途、市場監督管理部門における外商投資企業に関する会社登記については、上記 1–2の国家市場監督管理総局による「『外商投資法』を徹底実施し外商投資企業登記登録業務を遂行することに関する通知」によれば、外商投資法の施行に伴う重大な変更は見受けられません。
「外商投資情報報告制度」の概要
| 初回報告 | 変更報告 | 年度報告 | 抹消報告 | |
|---|---|---|---|---|
| 報告義務者 | 外国投資者 | 外商投資企業 | 外商投資企業 | 外商投資企業 |
| 報告事由 |
※ 既存外商投資企業については実施不要 |
※ 既存外商投資企業についても初期報告の報告項目に変更が生じた段階で報告を実施 |
※ 既存外商投資企業については2020年から2019年度分につき実施) |
|
| 報告時期・方法 |
|
|
|
|
| 報告内容 |
|
|
|
− |
その他
上記のほか、報告規則においては、①報告された情報を企業信用情報公示システムおよび外商投資情報報告システムを通じて公示すること(報告規則第18条)、②報告を懈怠した場合または報告内容に齟齬・遺漏がある場合は自ら補充または更正をしなければならず、商務部門は20営業日以内の補充または更正を命じること(報告規則19条)、③外国投資者または外商投資企業が当該補充または更正を実施しなかった場合、商務部門は20営業日以内の是正を命じ、是正しなかった場合は情状に応じて10万元から最大50万元までの罰金を科すこと(報告規則25条)、さらに、④外国投資者または外商投資企業の報告義務の遵守状況を外商投資情報報告システムにおいて公示できること(報告規則26条)などが規定されています。
その他引き続き動向を注視する必要がある事項
VIEスキームの取扱い
中国において厳格な外資規制の対象となっている分野(伝統的にはインターネット関連分野、最近では自動運転用の地図関連分野等)に外国企業が参入する際に実務上活用されている、いわゆるVIEスキーム 8 が、外商投資法におけるネガティブリストによる管理の対象とされるか否かについては、外商投資法の規定文言上必ずしも明らかではなく 9、外商投資法の公布後、実務上の解釈・運用が注目されてきました。
この点、実施条例においても、VIEストラクチャーへの適用の有無について明示的に言及した規定は見当たりません。もっとも、実施条例には、関連主管部門はネガティブリストの執行状況の監督検査を強化すべき旨、および外国投資者の投資活動がネガティブリストの規制に違反していることを発見した場合には外商投資法に従い処罰する旨が明確に規定されており(実施条例34条2項)、個別の規制業種ごとにVIEストラクチャーを通じた実質的な参与を含めた監督が強化される可能性は否定できないように思われます。
また、最高人民法院が、2019年12月26日に公布し2020年1月1日から施行した、外商投資法の下での投資契約 10 の効力等に関する解釈を定めた「『外商投資法』適用の若干問題に関する解釈」において、ネガティブリストにより投資が禁止または制限される分野への投資に関する投資契約について、当事者が当該規制の違反を根拠に投資契約の無効を主張した場合、人民法院はこれを支持するとされており、今後仮にVIEスキームに外商投資法が適用されることとなった場合、ネガティブリストに定める禁止または制限分野に関して締結されたVIEスキームの関連契約については、裁判または仲裁においてその民事上の効力が否定される可能性があります。
したがって、VIEスキームへの外商投資法の適用の有無については、引き続き今後の関連規則・法令等の制定や実務・解釈の動向に注目する必要があると考えられます。
外国投資安全審査制度
外商投資法では、国は、外商投資安全審査制度を構築し、国の安全に影響を及ぼし、または影響を及ぼすおそれがある外商投資について安全審査を行うとされていました(外商投資法35条1項)。
これは、米国のCFIUS審査の拡大や日本の外国為替及び外国貿易法による対内直接投資の規制強化を始めとする世界的な外資投資の規制強化の流れと軌を同じくするものと考えられ、米国や日本において規制強化により実務上大きな影響が生じているのと同様に、本格導入された場合には、中国への外資による投資に重大な影響が生じる可能性があるため、制度の動向が注目されていました。
しかしながら、実施条例においても、国家の安全に影響しまたは影響する可能性のある外商投資に対する国家安全審査制度を確立する旨の抽象的な規定にとどまっており(実施条例40条)、今後の関連規則・法令等の制定動向に引き続き注目を要すると考えられます。
-
従来の外資独資企業、中外合弁企業および中外合作企業など外国投資者が全部または一部出資している企業を指します。 ↩︎
-
なお、本稿における「緊急度」の評価は、あくまでも時間的な切迫性を評価したものであり、対象事項の重要性とは連動しておりません。緊急度低としている外商投資企業におけるガバナンスの変更は重要性が高い事項であり、緊急度高としている外商投資情報報告制度よりもむしろ重要性は高いと言えます。 ↩︎
-
特に、中外合弁企業法の下では、出資比率に関係なく、董事を1人でも選任する権利を有していれば、定款変更や増減資等の董事会の全会一致事項については拒否権が確保されていましたが、会社法のデフォルト・ルールの下では、出資比率が3分の1以下のマイノリティ出資者である場合は株主会の特別決議事項についても拒否権がなくなるため注意が必要と考えられます(拒否権を維持するためには、定款規定により決議要件の加重等の手当てが必要となります)。 ↩︎
-
従来の届出制度からの移行措置としては、2019年12月31日までに設立申請を実施した場合または変更事項が生じた場合に限定した取扱いが規定されているのみです(報告公告6条1項)。 ↩︎
-
外国投資者が直接に中国国内で会社や組合企業を設立する場合、外国企業が中国国内で生産経営活動に従事する場合、外国企業が中国国内で生産経営活動を従事する常駐代表機構を設立する場合、外商投資投資性会社等が中国国内で企業を設立する場合等(報告公告1条)、ならびに、銀行業、証券業および保険業等の金融業への投資を行う場合、香港、マカオ、台湾、および国外に定住する中国公民から投資を行う場合についても適用されるとされています(報告規則32条、33条)。これに対し、投資性会社以外の外商投資企業が中国国内で再投資により設立する企業については、市場監督管理部門において登記または届出手続および年度報告を実施すれば、市場監督管理部門が関連情報を商務部門に共有し、別途関連の報告の提出は不要とされています(報告規則28条、報告公告4条)。 ↩︎
-
上場会社または全国中小企業株式譲渡システム登録会社における外国投資者の出資比率の累計が5%を超えた場合等にも報告必要。 ↩︎
-
具体的には 定款上決議が必要な場合は決議時点、その他の発効条件がある場合は条件充足時。 ↩︎
-
中国籍の自然人が設立した国内法人に必要な許認可を取得させ、外国企業(または外国企業が設立した外商独資企業)が契約関係を通じて当該国内法人をコントロールして事業を行わせる投資方法。 ↩︎
-
具体的には、外商投資法の適用対象が、外国の自然人、企業またはその他の組織が、直接的または間接的に中国国内において行う投資活動をいい、(1)外国投資者が、単独で、または他の投資者と共同で、中国国内において外商投資企業を設立すること、(2)外国投資者が、中国国内企業の株式、持分、財産持分またはその他の類似権益を取得すること、(3)外国投資者が、単独で、または他の投資者と共同で、中国国内において新規プロジェクトに投資すること、および、(4)法律、行政法規または国務院の定めるその他の方式による投資とされており(外商投資法2条1項)、必ずしも外商投資法に基づくネガティブリストによる管理の対象となるかが明らかではなく、特に、「法律、行政法規又は国務院の定めるその他の方式による投資」に含まれるか否か等が懸念されていました。 ↩︎
-
外国投資者が直接又は間接的に中国国内において投資を行ったことによって形成される関連合意をいい、外商投資企業の設立契約、株式・持分・財産持分又はその他類似する権益の譲渡契約、プロジェクト新規建設契約等を含むとされています(同司法解釈1条)。 ↩︎

