中村直人弁護士に聞く、スルガ銀行問題の根幹にあるもの ガバナンスを変えても不祥事はなくならない
危機管理・内部統制
目次
2018年9月、シェアハウスなどの不動産投資向け融資に関するスルガ銀行の不正に、役員や支店長をはじめ、多数の行員が関与していたことが第三者委員会の調査で明らかになった。
銀行業界の中でも異例とも言える高収益の裏には、無理なノルマ設定と過酷なプレッシャー、そして組織ぐるみの不正が横行していた。
同年10月には金融庁からの行政処分、11月には旧経営陣9人への提訴がなされ、創業家出身の会長らは退任。関与した100人以上の役員・行員が処分され、不正を主導した元専務執行役員は懲戒解雇となった。
企業のガバナンス強化が求められる中、なぜ不正は蔓延したのか。第三者委員会の委員長を務めた中村 直人弁護士に伺った。
多方面からの情報を集めた第三者委員会で発見した、異常な不正の広まり
第三者委員会の調査をされる際に、どのような点を心がけていたのでしょうか。
第三者委員会の調査前に、社内の危機管理委員会が先行調査をされていました。その範囲が限定されていたため、問題がどこまで広がっているか、ガバナンス上の問題はどこにあるかというスコープを設定しました。
本件は不動産チャネルと呼ばれる不動産業者の方たちが複数いて、その先に投資家の方々もいる複雑な関係になっていたので、スルガ銀行外の情報をどうやって集めるかということを考えていました。
通常の第三者委員会では、社外の情報はなかなか取れませんが、破産した不動産チャネルの管財人の方々と協働してフォレンジック調査などを行ったり、投資家の弁護団の先生方からも情報をいただいたりしました。多方面から情報を集めることは今までの第三者委員会では例がなかったと思います。
投書や通報も多く寄せられ、その度に我々のスコープ内かどうか、どこまで調べるかということも検討していたので、フォレンジックには思ったより時間を要しました。
報告書では、かなり広範囲にわたってスコープを設定されていますね。
銀行内で発生していた書類偽装の原因には不動産チャネルとの癒着があったと思われたので、不動産関連の投資はすべて調べ、住宅ローンや不動産チャネルが関わっていない領域は調べないと線引きしていました。
かなり悪質な手口が蔓延していたようでしたが、特にどのような点を問題と感じましたか。
不動産ローンを担当している方々は、ほぼ全員不正に関わっているか、不正が行われていることを知っていました。
通常、書類偽装などを伴う不正は一部の人によって行われるもので、全社的に行われることはありません。あまりにも不正が広まり過ぎている異常な事例という感じがしましたね。
これだけの規模で不正が行われているのに、取締役会や監査役が気付いていないことは非常に不思議でした。

集団心理が引き起こした組織ぐるみの不正
不正発生の原因について、過剰な数字へのプレッシャーや恫喝があったということも報告書には記載されています。
数字のプレッシャーはすごく大きいですよね。不動産向けのローンは、一般的にはなかなか貸し付けられるようなものではないのですが、スルガ銀行では月に10億円というノルマが課せられていました。
このように大きなノルマを達成できるのは、不動産を買いたい人の情報を持っている不動産チャネルから融資の話をもらえた行員だけになります。
そのため、融資の話をもらうために、行員たちは不動産チャネルに対して融資基準を伝えていました。特にシェアハウスの場合、不動産チャネルが設定した家賃によって物件の評価をする仕組みだったので、不動産チャネルが本来の価値とは見合わない家賃設定をして借り手が付かないような物件だったとしても、銀行側は融資をしたのです。
そして、不動産チャネルは家賃収入の見込みがなかったとしても、投資家に販売した時点での利益を求め、後先考えずに売り続けました。
そこで書類の改ざんがなされるようになるのですが、営業マンが1人でもやり始めると、連鎖するんですよ。特に支店長が厳罰に処すことがないと、銀行側も認めていると現場は思ってしまう。
支店長も営業本部長からノルマを課されているから、数字を上げるために見て見ぬふりをすることになり不正が蔓延し始め、誰も問題を報告しなくなります。
これは言うなれば「楽ちんなチョンボ」です。真面目にやっていたら数字は上がらないけど、チョンボをすると数字を上げるのが楽になる。このパターンで不正が広がり始めると、誰も止めなくなります。
昨年発生した、自動車メーカーの燃費不正や鉄鋼メーカーの品質偽装も同様のパターンで、何十年も前から不正を知っていても、止めたら出荷ができなくなるから黙っているしかないという共謀関係になり、告発できなくなってしまう。
もし告発したら、今さら自分だけいい子ぶるなという話になりますよね。
個人だと不正はダメだとわかるんだけど、集団になると周りの判断に流されるんですよね。特に声の大きい人がいると、みんなそれに従ってしまう。
こういう考え方を「組織の心理学」というのですが、マネジメントには活用されていたものの、コンプライアンスに活かす方法は誰も考えてきませんでした。会社側はルールを作り、守れと言いながら、現場の人が守るかどうかはその人の良心に任せるというズルい行為をしていたのです。

審査部門、監査部門、役員陣はなぜ不正を止められなかったのか
審査部門では営業の書類について疑問を抱く動きもあったと報告されています。なぜ不正を止めることができなかったのでしょうか。
審査部門と営業部門でぶつかった時に営業部門の方が強くて、審査部門が黙るということは普通の銀行ではありえません。この理由を審査担当の役員に聞いてみると、数字を上げるためには仕方がなかったと言うのです。
スルガ銀行の審査の歴史を見ると、基準を緩める方向にしか動いていません。長い時間をかけて、基準を緩めて、なんとかこの高収益を上げ続けないといけないと思っている。だから、審査部門が疑問を抱いても結果的には認めてしまったのです。
また、人事にも問題があって、営業の執行役員だった人の部下が審査部門にも回されていました。
監査部門は不正を発見していなかったのでしょうか。
スルガ銀行の場合、監査部に行くのは定年間近の方で、何かを見つけようという発想はありません。
内部監査部門がやっていた監査は、支店の往査に行ってATMやビデオが動いているかなど、外形的な所を確認するだけで、業務上の違法はチェックする項目にも上がっていませんでした。
古い時代の日本の企業、コンプライアンスという言葉がなかったバブルより前の時代には見られた光景だったのかもしれませんね。
取締役会、役員陣は何をしていたのでしょうか。
社外取締役の方々は足元が腐っていることをまったく知らず、好業績を評価していました。
取締役会には、内部監査部門の監査計画、監査結果、コンプライアンス関係の活動報告など、金融検査マニュアルや金融庁の監督指針で定められている議題はすべて上がっていました。そして問題ないと報告されている。社外取締役の方々は他に情報を入手する方法がないので、うまくいっていると思いますよ。
報告書を見ると中期経営計画の数字も社外取締役には知らされていないという記載もありました。社外取締役の方も、もう少し情報を取りに行くアクションをしてもよいような気もしたのですが。
正直に言えば、もっと突っ込んだことを聞かなければいけないだろうとも思います。
中期経営計画の数字も出てないし、ビジョンは抽象的なことしか書いていない。内部監査部門の報告や人事に関する議案もシンプルでした。
ただ、それが議案書として著しく不合理で、善管注意義務違反になるほどかと言われると躊躇しました。そのため、社外役員の方々の善管注意義務違反は認めてはいません。
社内の役員についてはいかがでしょうか。
社内役員の中には疑問を抱いていた人たちもいましたが、彼らは取締役になることを現場からの「卒業」と言っていて、現場の問題は執行役員に任せればよいと思っていました。
営業部門や審査部門の管掌役員は積極的に何かをチェックするわけではなくて、ただいるだけに近い状態でしたね。
ここまで問題を隠すのは異常にも思えます。
役員含めて従業員全員が創業家である岡野家というお殿様の家臣で、良い報告をしたい一心で行動していたのです。
普通の上場企業では上司に悪い報告をすると、怒られることがあります。不正行為や悪い情報を報告したら「自分もアウトになる」と役員も上司も思っているから、情報を上げてくるなと言う人もいるのですが、この銀行の場合にはそういう痕跡がまったくありませんでした。
悪い情報を上司に報告すると怒られるという経験から問題を隠していたのではなくて、悪い報告なんて最初からお殿様に持って行けないと思っていたようです。
長い歴史の中で、そういう企業風土ができてしまったのでしょうか。他に着目すべき点はありますか。
BSC(バランス・スコア・カード)という人事制度が導入されていたのですが、評価の仕方は営業成績一辺倒でした。本来は業績だけでなく、お客様、従業員などのステークホルダーごとの満足度を評価しようという発想の制度なのですが、スルガ銀行ではほぼすべての項目が営業成績で占められていました。
役職員の行動基準である人事評価システムの中に、コンプライアンスにウエイトを置くような項目を取り入れるべきだったのでしょう。
ただ、色々な書物を読んでも、コンプライアンスを実施する、あるいは促進するための人事評価の仕組みは誰も研究していませんでした。その点は、今回の調査を経て、我々も含めて学者などの研究者もマズかったかなという気がしましたね。
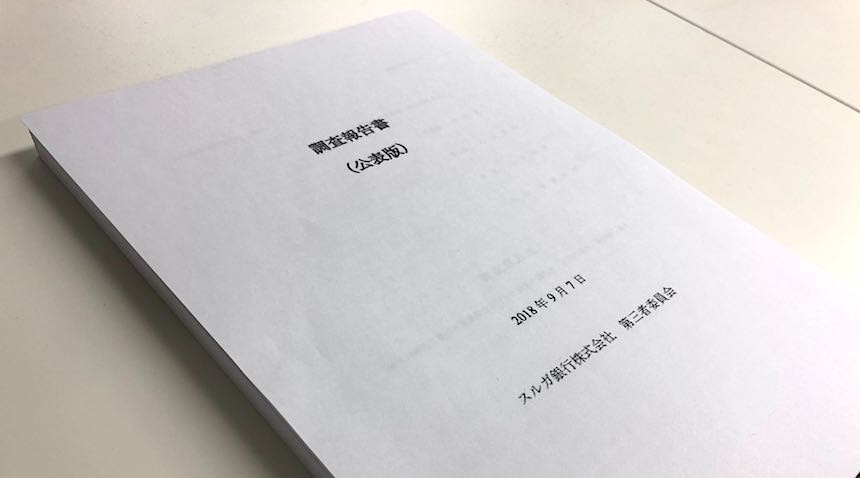
ガバナンスを変えても不祥事はなくならない
コーポレートガバナンスの強化が求められている中で、なぜ不祥事が多発するのでしょうか。
こういうことを言うと怒られるかもしれませんが、ガバナンスをいくら変えても不祥事はなくなりません。
ガバナンスの強化は、社外取締役や社外監査役が担うものですが、経営者をコントロールするために有効なのです。たとえば社長の指名や報酬の決定、あるいは重要な意思決定に関わるプロセスの構築があげられます。
社外役員は現場の情報を集めきれないので、不祥事を発見する機能を持ちません。
本件でも不正に関与した人間は大勢いるのに、取締役会では好業績が評価されています。なぜそんなことが起きると思いますか。
企業風土がおかしくなっていることを検出できない、アセスメントできないことが問題なのです。
企業風土を評価するためのツールやサービスが普及し、取締役会に上げることが必須になれば、社外役員にも情報が上がってきますのでガバナンスの強化も不祥事防止に有効になってきます。
仮に、そういう仕組みができたとしても、経営者が暴走してしまったら終わりということでしょうか。
そのとおりです。企業風土やコンプライアンスの根幹は、社長が向いている方向にあり、その方向を部下たちは敏感に見ているのです。
たとえば、年頭に社長が「当社はコンプライアンスを重視します」と言っても、みんな従いません。「各入社年次で優秀な人間は営業の第一線にいるな、コンプライアンス部や内部監査部には成績の悪い人間が行っているぞ」とか「口ではコンプライアンスが大切だと言っているけど、予算が付いていないぞ」とかね、そういう所を部下は見ているわけです。
人事や予算編成を見ていると、社長が本当にコンプライアンスを大事にしているのかすぐわかります。大事にしていないことがわかると、「あれは口で言っているだけだから、数字を上げればいいよ」と部下は思うんです。トップが行動で示さないと、企業風土は根付かないですよね。

経営陣はルールを守って会社が回る仕組みを作れ
今まで伺ったお話に通じる部分もあると思うのですが、不正の芽を早期に発見するために、今後企業に求められるものについて教えてください。たとえば社内でどういう機能を強化すればよいのでしょうか。
コンプライアンスという概念が日本の経済界に入ってきた1990年頃から、贈収賄のような不正は減ってきました。一方、最近になって次々と発覚している不祥事は長い年月の間、大勢の人が関与していたものが多いですよね。
スルガ銀行の人たちも、入社当初から不正をしようと思っていた人はいないはずです。燃費や品質の偽装もすべて同じ構造で、みんな根っから悪い人じゃなかったはずなのに、従業員に不正を強要する仕組みになっている。
「ちゃんとルールを守れ」と会社の規則には書いてあるけれども、ルールを守ったらノルマが達成できないし、納期に間に合わないという、会社が破綻するような道しか残されていない。だから現場は困って、仕方なく不正に走ってしまうのです。
どうしたらこの状況を変えられますか。
ルールを守りながら会社が回っていく仕組みを、経営陣や担当役員が作らなければなりません。
たとえば、品質基準を満たさないと出荷できない取引先があったとしても、別の用途であれば出荷できる先を探し、無駄にならなくて済む仕組みを作るという発想が必要です。
他にも、従来のコンプライアンスから見直すべき点はありますか。
AIやIoTなどのテクノロジーを使って不正を検知する仕組みを取り入れることも有効でしょう。テクノロジーに加えて、先ほどお話ししたような組織の心理学の考えも取り入れて、本人の良心に依存せずに、ルールを守りながら会社が回っていくような仕組みを作れるとよいと思います。コンプライアンスのためにAIが用いられているケースは少ないので、開発が進んでほしいですね。

不正に気付いた法務・コンプライアンス部門の担当は何をするべきか
法務やコンプライアンス部門に所属している方が、自分の会社の不正に気付いた場合、どうするべきでしょうか。
問題を抱えた社員が、法務やコンプライアンス部門の人に言っても握りつぶされる、役員に言ってもどうせ黙って放っておかれると思い始めると、完全に会社は腐ってしまう。そうすると良い人はどんどん逃げてしまいます。
腐ってダメになる会社かどうかの分かれ道は、最後の支えになってくれる人がいるかどうかです。法務やコンプライアンスの人たちが「これは社長には報告しづらい問題だな、何て言い出そう」と思った時には、社外役員をうまく利用してほしいです。社外役員が動くと社長をはじめとして「NO」とは言えなくなるので。
不正につながることであれば、スルガ銀行のように全役員が交代ということもありえます。
社外役員は問題を知った際に動かないとアウトとわかっていますから、何かしらの動きはあるはずです。社外に「ここに言えば何とかしてくれる」という道を確保しておくべきでしょう。
社外役員に相談しても社長に伝わってしまうのではないか、という心配もあります。
そういう時に社外役員の人柄がわかると安心できますよね。社外役員の方々も、現場に来て社員とスモールミーティングをやったり、食事でもしてみたりした方がよいでしょう。その時に「あの社外役員の人はちゃんとしているな」と伝われば、「じゃあ言ってみようかな」となります。
社外役員には高いお金を払っているはずですから、ぜひ活用してください(笑)。
(取材、構成:BUSINESS LAWYERS 編集部)

中村・角田・松本法律事務所
- コーポレート・M&A
- 危機管理・内部統制
- ファイナンス
- 訴訟・争訟
