派遣社員に変形労働時間制を適用することができるか
人事労務 当社は製造業で、年間カレンダーによる管理を行い、1年単位の変形労働時間制を採用しています。
何名か来てもらっている派遣社員にも、同じ労働時間管理を行っており、派遣元からは、36協定を毎年出してもらっています。
先日、労働基準監督署の調査が入り、派遣元も1年単位の変形労働時間制を採用していなければ、派遣社員を同じ労働時間体制で働かせることができないと聞きました。具体的に何をすればよいですか?
派遣先である御社で派遣労働者を1年単位の変形労働時間制によって働かせるためには、36協定だけでは足りず、派遣元の会社で1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結・届出をし、就業規則に定めなければなりません。
また、1年単位の変形労働時間制により労働させることについて、派遣元の就業規則に定め、派遣労働者に労働条件を明示しておく必要があります。
解説
目次
派遣社員の労働時間管理
労働者派遣は、派遣元事業主と雇用関係にある労働者を、派遣先において派遣先事業主の指揮命令を受けて労働に従事させるものです。派遣労働者の労働基準法の適用については、原則として雇用主である派遣元事業主が責任を負いますが、派遣先事業主が責任を負う項目もあります(労働者派遣法44条)。
労働時間等の枠組みの設定に関する事項は、派遣元において定める必要があり、派遣先は派遣元で定められた枠組みの範囲内で派遣労働者の労働時間等を管理しなければなりません。
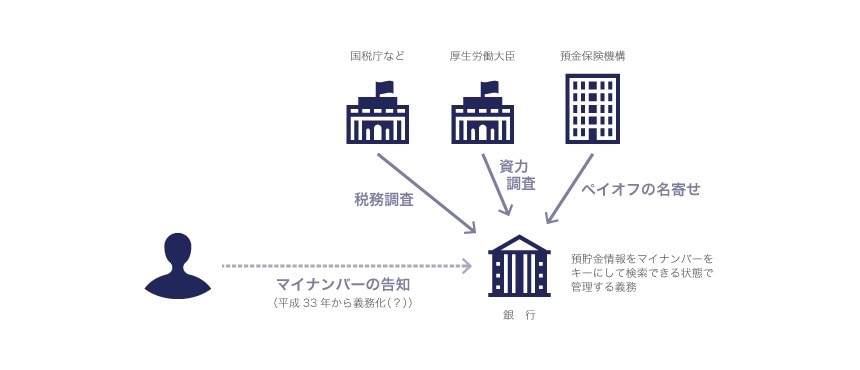
派遣労働者に1年単位の変形労働時間制を適用するには
変形労働時間制やフレックスタイム制を導入するには、就業規則の定めと会社と従業員代表との労使協定が必要です(労働基準法32条の2、32条の3)。変形労働時間制やフレックスタイム制については、「変形労働時間を取り入れる際に就業規則の作成において留意すべきポイント」や「フレックスタイム制とはどのような制度か」をご覧ください。
前述のとおり、派遣労働者は派遣先ではなく、派遣元と雇用関係にあります。したがって、派遣先は使用者とはなりえず、派遣元で1年単位の変形労働時間制を就業規則に定めず、労使協定の締結・届出をしていない場合は、派遣先で1年単位の変形労働時間制を定めていたとしても、派遣労働者を1年単位の変形労働時間制によって働かせることはできません。
派遣先で派遣労働者を1年単位の変形労働時間制のもとで働かせるためには、派遣元において、①1年単位の変形労働時間制の協定を締結・届け出ること、②就業規則に1年単位の変形労働時間制について定めること、③労働者派遣契約において1年単位の変形労働時間制が適用になる旨およびその内容を定めておくこと、④派遣労働者に対して労働時間等の労働条件を明示することが必要となります(労働基準法32条の4、労働基準法施行規則12条の4)。
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の締結・届出
派遣元は、以下の項目について、労使協定を締結し、派遣元の所轄労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法32条の4第4項、32条の2第2項)。
- 対象労働者の範囲
- 対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日
- 特定期間
- 労働日および労働日ごとの労働時間
- 労使協定の有効期間
就業規則への制定・届出
派遣元の就業規則に1年単位の変形労働時間制の規定を制定し、従業員が10人以上の場合には、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法32条の4第4項、32条の2第2項)。
第〇条 労使協定により1年単位の変形労働時間制を採用し、所定労働時間は対象期間を平均して1週40時間以内とする。
2 1 年単位の変形労働時間制の労働日ごとの所定労働時間は8時間とし、始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
始業:8時30分
終業:17時30分
休憩時間:12時から13時
3 1年間における労働日及び休日は、別途定める年間カレンダーによるものとする。
4 起算日は毎年4月1日からとする。
労働者派遣契約での規定
派遣元と派遣先の間の労働者派遣契約において、労働派遣者に対しても1年単位の変形労働時間制が適用になる旨、およびその内容を定めておくことが必要となります(労働者派遣法26条1項4号、5号)
労働条件の明示
派遣元は、派遣労働者と労働契約を結ぶ際に、派遣労働者に対し労働時間等の労働条件を書面などにより明示しなければなりません。
おわりに
これらの手続きを派遣元で行った派遣労働者については、派遣先でも1年単位の変形労働時間制によって働かせることができます。派遣先では、1年単位の変形労働時間を適正に運用するための労働時間、休憩、休日の管理を行うことが求められます。

田中セラタ事務所 社会保険労務士法人・行政書士事務所