新聞記事をコピーするのは違法?著作権を侵害しないためには?
知的財産権・エンタメ 更新当社では社内ミーティングの際に、業務に関係する新聞記事をコピーし、参考資料として配布しているほか、当社の商品が紹介された新聞記事をコピーしてファイルし、営業活動に利用しています。いずれもコピーの部数は10部以内と少ないのですが、このような利用は許されるでしょうか。
新聞記事は、客観的な事実のみを伝えるものであっても、基本的に著作物として保護されていると考えられます。業務上のコピーは、一般的に、部数にかかわらず、著作権法の定める私的使用目的での複製にはあたらないと考えられています。検討目的での利用や引用などの場合には許諾は不要ですが、利用が認められていない場合には許諾を得て利用するようにしましょう。
解説
目次
新聞記事は著作物にあたるか
客観的な事実や事象はそれ自体では著作物として保護されていないため、「いつ、どこで、誰が、何をした」という事実の骨子のみが記述されているようなごく短い新聞記事であれば、創作性がなく著作物として保護されない場合もあります。
しかし、ある程度の長さを持つ記事であれば、たとえ客観的に事実を伝えることのみが目的であっても、素材の選択や、事実の配列、表現などに著作者の創作的な工夫が発揮されており、著作物として保護される可能性が高いでしょう。したがって、客観的な事実のみを伝える新聞・雑誌等の記事であっても、基本的に著作物として保護されており、原則として著作権者の許諾を得ずに利用することはできないと考えておくことが必要です。
最近は、購読している紙の新聞で記事を読むよりも、新聞社や出版社が配信するオンライン記事を読む人のほうが多いかもしれません。オンライン配信記事は無料で読むことができる場合も多く、文章のコピー&ペーストも容易であるため、紙の新聞記事よりも気軽に利用してしまいがちです。しかし、著作物かどうかという点においては、紙の新聞記事でもオンライン配信記事でも、考え方は変わらないので注意が必要です。
新聞記事の著作物性については、2023年に注目すべき判決が出ました(つくばエクスプレス事件・知財高裁令和5年6月8日判決)。これは、被告企業が新聞記事をスキャンし、社内イントラネットで共有した行為が著作権侵害に該当すると認定された事案です。裁判所は、まず、報道を目的とする新聞記事が著作物と認められるためには、作成者の何らかの個性が発揮されていれば足りると述べました。その一方で、新聞記事の内容には様々なものがあり得ることから、新聞記事であることをもって直ちに著作物ということはできず、また、著作物であるとしても、新聞社の著作物とは限らないことから、裁判所に提出された資料では内容を確認できない記事については、著作物性を認めることはできないとの判決をしています。
許諾を得ずに著作物を利用できる場合とは
著作権法では、一定の場合には、著作権者等に許諾を得ることなく著作物を利用できることが規定されています(著作権法30条〜50条)。これを権利制限規定といいます。
権利制限規定は多数ありますが、代表的なものは以下のとおりです。
| 内容 | 条番号 |
|---|---|
| 私的使用のための複製 | 30条1項 |
| 付随対象著作物の利用 | 30条の2 |
| 許諾を得る検討の過程における利用 | 30条の3 |
| 思想または感情の享受を目的としない利用 | 30条の4 |
| 図書館等での複製・インターネット送信等 | 31条 |
| 引用 | 32条1項 |
| 学校その他の教育機関における複製・公衆送信等 | 35条 |
| 非営利・無料の場合の著作物利用 | 38条 |
| 新聞の論説等の転載 | 39条 |
| 時事の事件の報道のための利用 | 41条 |
米国著作権法においては、権利制限について包括的に定めた「フェアユース規定」がありますが、日本の著作権法には、現時点ではそのような汎用性のある条文はありません。そのため、著作権者等に許諾を得ることなく著作物を利用するためには、著作権法に定められた権利制限の要件を充足することが必要になります。
新聞記事のコピーについては、私的使用のための複製、検討の過程における利用、引用という3点が関わってきます。以下では、新聞記事のコピーが許容されるための要件や、判断に迷いやすいポイント等を中心に、具体的な場面ごとに解説します。
私的使用のための複製
著作権法30条1項は、私的使用目的のための複製は権利者の許諾を得なくても可能であると規定しています。私的使用目的であれば、使用する本人は、著作物のコピー・写真撮影・録音・録画・翻案などができます。著作権法30条1項によってコピー行為が許容されるための要件は以下の2つです。
- 私的使用を目的とすること
- 複製の手段が、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」によるものでないこと
一般的に業務上のコピーは、①の要件を満たさないと解されるため、原則として許諾が必要ということになります。
コピーする部数が少ない場合
「私的使用」の意味について、業務上であっても少部数のコピーなら問題ないのではないかと考えている人も多いようです。しかし、著作権法の条文が定める私的使用の範囲は「個人的又は家庭内その他これに準じる限られた範囲」という狭いものであり、たとえ1部のみのコピーであっても、業務上のコピーは私的使用目的にはあたらないという見解が、判例・通説といわれています(舞台装置設計図事件・東京地裁昭和52年7月22日判決・無体集9巻2号534頁)など)。

コンビニなどのコピー機を利用する場合
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」の「自動複製機器」とは、ビデオデッキなど、複製の機能を有し、その機能に関する装置の全部または主要な部分が自動化されている機器を意味します。
著作権法附則5条の2は、自動複製機器について、当分の間、「専ら文書又は図画の複製に供するもの」を含まないと規定しています。「専ら文書又は図画の複製に供するもの」としては、コンビニエンスストアに置いてあるコピー機があげられ、そのような機器による複製は、私的使用目的であれば問題ないと考えられます 1。
なお、新聞紙面から記事を切り抜いて回覧するだけの場合には、記事の複製行為がないので、業務目的であっても著作権法上の問題はありません。
SNSや社内サーバーなどへアップロードする場合
私的使用目的であれば著作物の翻訳・編曲・変形・翻案を行うことも可能ですが、公衆送信(アップロード)することについては、権利制限規定の適用はなく、著作権侵害となることに注意してください。
私的使用目的で新聞記事の写真撮影やコピーをすることはできますが、これをSNSにアップしたりすると、公開の規模にもよりますが、原則として著作権(公衆送信権)を侵害することになります。
会社内での利用であれば、新聞記事を参考資料として社内サーバーへ保存することも考えられます。この場合は、社内サーバーに記事のデータを保存する段階で複製が行われたことになり、上で述べたように、この複製は私的使用目的の複製にはあたらず、著作権(複製権)侵害になると考えておいたほうが安心です。
さらに、保存したデータを社内イントラネットに掲載することは、多くの場合、公衆送信に相当します。例外は、イントラネットが同一構内における送信に限定される場合で、このような場合は公衆送信にはなりません(著作権法2条1項7号の2)。
一方、新聞記事を社内外のメルマガで紹介する場合は、送信先が同一構内にとどまりませんので、公衆送信にあたることになります。なお、著作権法の「公衆」には不特定多数・特定多数・不特定少数が含まれますが、「特定少数」は公衆にあたらないので、きわめて小規模な社内での配信であれば公衆送信に該当しない可能性があります。
オンライン記事を、サーバーに保存せずにオンライン会議での画面共有で掲示するような場合には、複製はなく、公衆送信にもあたらない可能性があるでしょう。
このように、新聞記事を業務で利用しても著作権侵害に該当しない場面がいくつか想定はできるものの、著作権侵害を確実に回避しながら新聞記事を紹介するためには、基本的に、インターネット上の正式な記事にリンクを貼ったり、X(旧Twitter)の「公式リポスト(リツイート)」、Facebookの「シェア」などを活用するか、5に述べる「引用」にあたるような方法で行うようにしましょう。
なお、著作権侵害を避ける目的だと思われますが、新聞記事の一部のみを残して画像にボカシ加工をしたうえでSNSにアップしている例をよく見かけます。著作物である文章や写真が、それと認識できない状態で利用されても著作物の利用には該当しないので、アップされた「記事の一部」がそれだけでは著作物といえないのであれば、著作権侵害にはならないと思われます。たとえば下記の画像では、記事の見出しは読める状態ですが、このような短い一般的な見出しは、それ自体は著作物には該当しないと考えられます。
著作権侵害とならないボカシ加工の例
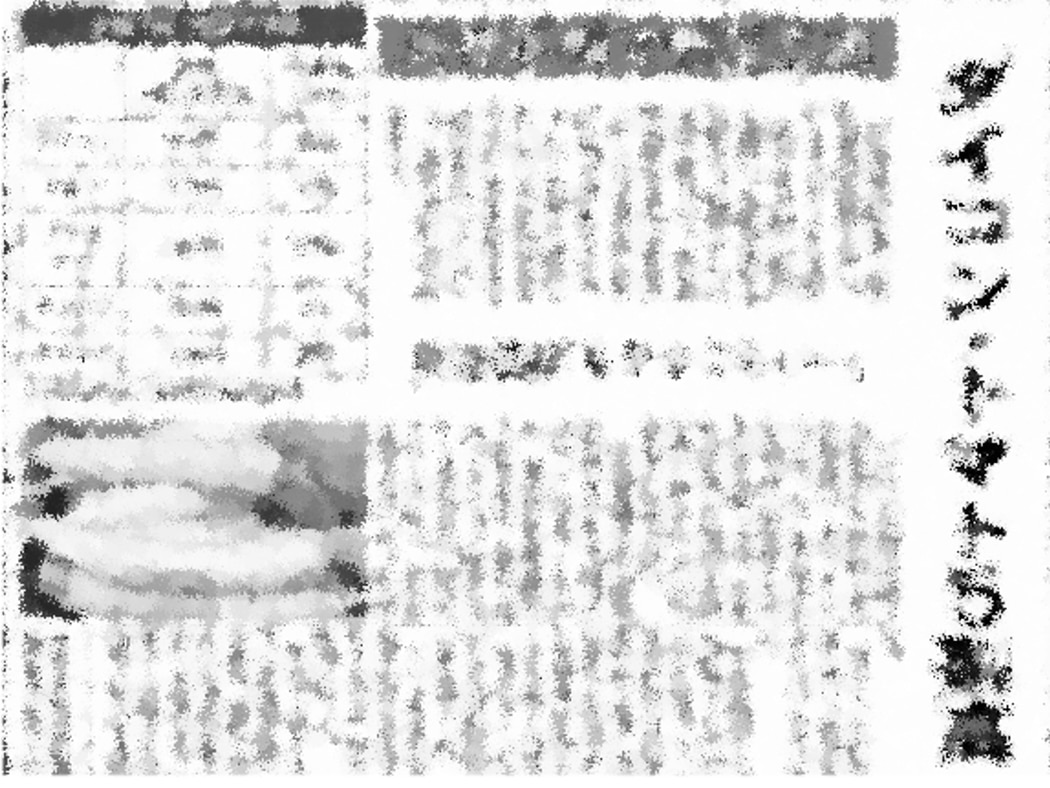
許諾を得る検討の過程における利用
新聞記事をプレスリリースや商品パンフレットの中で使用したいと考えている場合、必ずしも社内の検討段階で著作権者の許諾を得ておく必要はありません(著作権法30条の3)。プレスリリースやパンフレットの内容が確定して社内で承認されてから許諾を得ようと考えているのであれば、内容検討のために必要と認められる限度において新聞記事を利用することが可能です。
ただし、検討の目的を超えて使用したり、許諾がないまま実際に使用すると著作権侵害となるので、社内の関係者で、許諾を得ずに利用できる範囲について情報を共有しておく必要があります。
引用
新聞記事の利用の方法によっては、「引用」として記事の利用が認められる可能性もあります。引用に該当するためには以下の要件が必要とされています(著作権法32条1項)。
- 公表された著作物を使用していること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること
その他、過去の裁判例では、④主従性(自己の著作物が主であり、引用された著作物が従であること)や、⑤明瞭区分性(引用部分が明瞭に区別されていること)が必要とされてきました。しかし知財高裁は、美術鑑定書事件(知財高裁平成22年10月13日判決・判時2092号135頁)において、「引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内、すなわち、社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要」と述べたうえで、引用の成否は、(1)利用の目的、(2)方法、(3)態様、(4)利用される著作物の種類や性質、(5)利用される著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない、と判示しました。
今後は、このような総合的な判断手法がスタンダードになっていく可能性が高いと思われます。
- 方法や態様が公正な慣行に合致しているか
- 引用の目的との関係で正当な範囲内(社会通念に照らして合理的な範囲内)のものであるか
- (1)利用の目的、(2)方法、(3)態様、(4)利用される著作物の種類や性質、(5)利用される著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮
許諾を得る方法
業務上の目的でコピーする場合には原則として許諾が必要、と言われても、コピーのために毎回権利者を探して連絡をとって許諾を得ることには負担を感じる人が多いでしょう。
このような場面における権利処理を行う団体として、「公益社団法人日本複製権センター(JRRC)」があります。(1)日本国内の著作物でJRRCが管理している著作物であり、(2)譲渡を目的としない複製やファックス送信など所定の利用形態であって、対象範囲が小部分・少部数であれば、著作権者から個別の許諾を得ることなくJRRCとの契約で一括して権利処理ができるという仕組みです。毎回許諾を得る労力を考えれば、特に企業にとっては利用価値のある制度といえるでしょう。ビジネス上の利用頻度が高い日本経済新聞も、2021年8月からJRRCが管理することになり、ビジネスパーソンにとって利便性がより高いサービスになったといえるでしょう。
これらのサービスも上手に利用して、著作物を適切に利用することを心がけてください。
-
レンタルビデオ店(だいぶ少なくなりましたが)に、DVDを自動的にリッピングしたりコピーを焼いたりできる装置が置いてあれば、そのような機器を利用してコピーを複製することは、たとえ私的使用目的でも違法ということになります。 ↩︎

高樹町法律事務所
- コーポレート・M&A
- IT・情報セキュリティ
- 知的財産権・エンタメ
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
