令和5年仲裁法改正・条約実施法制定・ADR法改正の概要と実務への影響 国際水準に合わせた民間ADRの強化
訴訟・争訟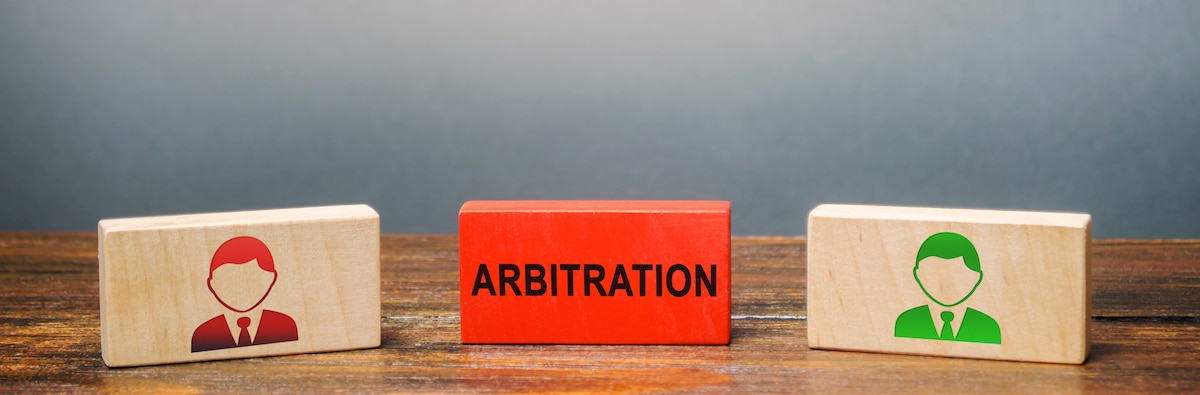
目次
令和5年4月21日、仲裁法の一部を改正する法律(令和5年法律第15号)(以下「改正仲裁法」といいます)、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和5年法律第16号)(以下「条約実施法」といいます)および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第17号)(以下「改正ADR法」といいます)が成立し、同月28日に公布されました。
これら三法は、民間ADRを最新の国際水準に対応する形で一体的に強化することを目的として、改正・制定されたものです(以下「改正等」といいます)。本稿では、改正仲裁法、条約実施法、改正ADR法のそれぞれについて、実務上特に影響が大きいと思われる主要なポイントを解説します。
改正等の概要
改正等の背景・経緯
改正仲裁法、条約実施法、改正ADR法は、以下のような経緯を経て、衆議院および参議院での審議の結果、可決・成立に至ったものです。
- 令和2年9月、法務大臣から法制審議会に対し、「経済取引の国際化の進展等の仲裁をめぐる諸情勢に鑑み、仲裁手続における暫定措置又は保全措置に基づく強制執行のための規律を整備するなど、仲裁法等の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい」との諮問(諮問第112号)がなされる
- 上記①の諮問を受け、法制審議会において専門部会(「仲裁法制部会」)が設置され、第13回会議において「仲裁法の改正に関する要綱案」が取りまとめられ、また、第18回会議において「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」が取りまとめられる
- 法制審議会が上記②の要綱案を原案どおり採択して法務大臣に答申し、これをもとに法務省民事局が「仲裁法の一部を改正する法律案」「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案」「裁判外紛争手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を立案、令和5年2月28日、第211回国会に提出する
改正等の目的
今回の改正等は、経済取引の国際化の進展等の情勢の変化に鑑み、民間の紛争解決機関(民間ADR)の利用をいっそう促進し、紛争の実情に即した迅速、適切かつ実効的な解決を図る観点から、最新の国際水準に対応する形で一体的に強化することが目的とされています。
改正等の影響
今回の改正等の影響を受ける民間ADRの類型および改正等のポイントは以下のとおりです。
| 類型 | 仲裁 | 民間調停 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 国際・国内仲裁 | 国際調停 | 国内の民間調停 |
| 適用法 | 仲裁法 | 条約実施法(新法) | ADR法 |
| 改正等のポイント | 仲裁判断までの間に権利・証拠を保全するための命令(暫定保全措置命令)に基づく強制執行を可能とする(改正仲裁法47条~49条) | 国際的な調停において成立した和解合意(国際和解合意)に基づく強制執行を可能とす | 認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解(特定和解)に基づく強制執行を可能とする(改正ADR法27条の2等) |
仲裁法改正 - 国際・国内仲裁への影響
仲裁法は、国連国際商取引委員会(UNCITRAL)による国際商事仲裁モデル法(以下「モデル法」といいます)に準拠して2003年に制定されましたが、2006年のモデル法改正(仲裁廷による暫定保全措置の定義(類型)、発令要件、承認・執行等に関する規律等の追加)に対応した仲裁法の改正は行われてきませんでした。
そこで今回、最新の国際水準に見合った法制度を整備することによって日本における国際仲裁を活性化させるべく、仲裁法が改正されました。
暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする制度の創設
(1)現行法下の状況
現行仲裁法24条では、仲裁廷は暫定措置または保全措置を講ずることを命ずることができるとされていますが、かかる措置の執行に関する規定は置かれていませんでした。
仲裁廷により暫定措置命令または保全措置命令が出された場合、仲裁手続の当事者は、その後の仲裁判断への影響等を考慮して、これに任意に従うことが多いとされています 1。しかし、あくまで当事者の任意の履行を期待するほかないため、当事者が暫定措置命令・保全措置命令に従わない場合は、これを強制執行することができませんでした(この場合、暫定措置命令・保全措置命令の申立てをした当事者としては、基本的には相手方に対して損害賠償を求めうるに留まります)。
一方、仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関しても、裁判所に対して保全処分の申立てをすることは妨げられていない(仲裁法15条)ことから、当事者としては、仲裁手続外で裁判所に対して保全処分の申立てをする選択肢もあります。もっとも、仲裁廷による暫定措置または保全措置の内容は多岐にわたるところ、保全処分の申立てには馴染まない場合もありますし、仲裁合意により裁判外での紛争解決手続である仲裁手続を選択したにもかかわらず、裁判所による実体的な判断を求めなければならないのは当事者の合理的意思に反するとの批判もありました。
(2)改正の概要
まず、改正仲裁法は、仲裁廷が発令する権利・証拠を保全するための命令(「暫定保全措置命令」)の類型・発令要件を整備しました(改正仲裁法24条)。暫定保全措置命令は、以下のとおり①予防・回復型と②禁止型の2つに大別されます。
- 予防・回復型(同法24条1項3号)
紛争対象の物・権利について、著しい損害または窮迫の危険を避けるために必要な措置・原状回復措置 - 禁止型(同法24条1項1・2・4・5号)
財産の処分等の禁止、審理妨害行為の禁止、証拠の廃棄行為等の禁止の措置
そして、暫定保全措置命令を得た当事者は、裁判所に対して、裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定(「執行等認可決定」)を求める申立てをすることができ(同法47条1項)、執行拒否事由(同法47条7項各号)があると認められる場合を除き、当該申立ては認められることになります。
手続面に関しては、暫定保全措置命令の類型によって強制執行までの手続が異なります。
まず、①予防・回復型(同法24条1項3号)の暫定保全措置命令の場合は、暫定保全措置命令の申立人は、裁判所に対し、暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定(①予防・回復型における執行等認可決定。同法47条1項1号)を求める申立てをすることができ、裁判所が執行等認可決定をした場合には、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令を債務名義として、強制執行が可能となります(同法48条)。
他方、②禁止型(同法24条1項1・2・4・5号)の暫定保全措置命令は、財産の処分禁止や証拠の廃棄禁止など、仲裁判断があるまでの間一時的に一定の行為の禁止を命じるものであり、それに基づく間接強制が基本的に認められていないものに相当する内容も含まれることから、一律に強制執行を認めることは我が国の民事執行法制に馴染まないと考えられました。
そこで、暫定保全措置命令の申立人は、裁判所に対し、当事者が暫定保全措置命令に違反し、または違反するおそれがあると認めるときに、一定の金銭の支払命令(「違反金支払命令」)を発することを許す旨の決定(かかる決定が②禁止型における執行等認可決定となります。同法47条1項2号)を求める申立てをすることができ、裁判所が執行等認可決定をし、さらに(申立人の申立てに基づき)裁判所が違反金支払命令を発した場合に(同法49条1項)、違反金支払命令を債務名義とした強制執行ができるという手続となりました。なお、執行等認可決定と違反金支払命令は同時にすることができるとされています(同法49条2項)。
暫定保全措置命令が発令されてから強制執行をするまでの手続の流れは、以下の図のようになります。
暫定保全措置命令発令から強制執行までの手続

なお、上記改正を反映するため、民事執行法22条が定める債務名義として、「確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成15年法律第138号)第48条に規定する暫定保全措置命令」(民事執行法22条6号の3)が追加されることになります(改正仲裁法附則6条)。
仲裁判断書等の翻訳文の添付の省略
(1)現行法下の状況
現行仲裁法46条2項では、申立人が裁判所に対して仲裁判断の執行決定の申立てをする場合において、仲裁判断書が日本語以外の言語で作成されているときは、日本語の翻訳文の提出が必要とされていました。特に国際仲裁においては仲裁判断書が長文になることが多いことから、仲裁判断書の日本語訳の作成は執行決定を申し立てる当事者にとって実務的な負担が大きいとされていました。
(2)改正の概要
これに対して、改正仲裁法46条2項では、裁判所が相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いたうえで、仲裁判断書の全部または一部について日本語による翻訳文の提出を要しないとすることができるとされました。また、執行等認可決定の申立てをする場合に裁判所に提出する暫定保全措置命令の命令書についても、同様とされています(同法47条2項)。
この改正により、仲裁判断の執行決定や執行等認可決定を求める当事者の負担が軽減されることが期待されます。
仲裁関係事件の裁判管轄
(1)現行法下の状況
現行仲裁法5条1項では、仲裁法の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、以下の裁判所が管轄権を有するとされていました。
- 当事者が合意により定めた地方裁判所
- 仲裁地を管轄する地方裁判所
- 被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
(2)改正の概要
これに対して、改正仲裁法では、仲裁地が日本国内にあるときは、東京地方裁判所および大阪地方裁判所にも競合管轄が認められることとなりました(改正仲裁法5条2項)。
仲裁関係事件の専門性に鑑み、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において専門的な事件処理体制を構築することを目的とした改正であり、これにより、前述した執行等認可決定についても東京地方裁判所・大阪地方裁判所に申し立てることが可能となります。
施行日
仲裁法の改正は、その公布の日(令和5年4月28日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています(改正法附則1条)。
条約実施法の制定 - 国際調停への影響
調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設
(1)現行法下の状況
我が国の現行法制上、裁判所など国の機関が関与する民事調停や裁判上の和解などは民事執行法に基づく強制執行が可能ですが、裁判外で行われる当事者間の和解合意には執行力が認められていませんでした(民事執行法22条各号等)。
他方、国際的には、調停による国際的な和解合意に執行力を認めることなどを内容とする「調停による国際的な和解合意に関する国連条約(United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation)」(以下「シンガポール条約」といいます)が2018年12月20日に国連総会において採択され、2022年9月に発効しました。
シンガポール条約が発効したことで、今後、同条約の規律が世界標準となっていくことが見込まれます。そのような中で、我が国の法制度が同条約に対応できていなければ、同条約に対応した法制度を持つ国の当事者からすると、日本の当事者との間で紛争が生じ、調停により和解合意に至ったとしても、自身が債務を負う和解合意について自国で強制執行がされるにもかかわらず、日本の当事者が債務を負う和解合意について日本で強制執行をすることができないことになります。
このような事態が生ずるとすれば,海外に進出をする日本企業が国際調停を利用することは困難となることから、国際性を有する和解合意に執行力を付与する必要性は高いものと考えられてきました。
(2)新法の概要
条約実施法では、民事または商事の紛争 2 の解決のための調停において、当事者間で成立した「国際性」を有する和解合意(「国際和解合意」)につき、その当事者がシンガポール条約または同条約実施に関する法令に基づき民事執行をすることができる旨の合意をした場合には、裁判所の執行決定を得たうえで、強制執行をすることができるとされました(同法3条、5条)。
「国際性」を有する和解合意(国際和解合意)とは、次のいずれかに該当するものをいうとされています(同法2条3項柱書)。
- 当事者またはその親会社の住所または主たる事務所もしくは営業所(以下「主たる事務所等」といいます)が日本国外にあるとき(1号)
- 当事者の主たる事務所等が互いに異なる国にあるとき(2号)
- 当事者の主たる事務所等と、和解合意に基づく義務履行地等が異なる国にあるとき(3号)
ただし、シンガポール条約に倣い、以下の紛争類型については条約実施法の適用除外とされています(同法4条各号)。
- 当事者の全部または一部が個人(事業としてまたは事業のために契約または取引の当事者となる場合におけるものを除く)であるものに関する紛争
- 個別労働関係紛争
- 人事に関する紛争その他家庭に関する紛争
このうち、①については、いわゆる「B to C事案」と「C to C事案」の双方が適用除外とされています(この点において改正ADR法の適用除外と異なりますので留意が必要です)。
なお、上記を反映するため、民事執行法22条が定める債務名義として、「確定した執行決定のある国際和解合意」(民事執行法22条6号の4)が追加されることになります(条約実施法附則5条)。
翻訳文の添付の省略、裁判管轄
条約実施法においても、改正仲裁法と同様に、裁判所が相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いたうえで、国際和解合意の内容が記載された書面の全部または一部について日本語による翻訳文の提出を要しないとすることができるとされています(同法5条4項)。
また、執行決定の申立てに係る事件について、東京地方裁判所および大阪地方裁判所の競合管轄が認められている点も改正仲裁法と同様です(同法5条6項4号)。
施行日
条約実施法は、調停に関するシンガポール条約が日本において効力を生ずる日 3 から施行するとされています(条約実施法附則1条)。
ADR法改正 - 国内の民間調停への影響
ADR法に定める認証紛争解決手続による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設
(1)現行法下の状況
国際性を有する調停での和解合意と同様に、ADR法に定める認証紛争解決手続(ADR法2条3号)により成立した和解合意についても、我が国の現行法制上、執行力が認められていませんでした(民事執行法22条各号等)。
(2)改正の概要
改正ADR法により、同法に定める認証紛争解決手続により成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの(「特定和解」)については、裁判所の執行決定を得たうえで、強制執行をすることができることになりました(同法27条の2)。
ただし、以下の紛争類型に係る特定和解は、改正ADR法の適用除外とされています(同法27条の3)。
- 消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争
- 個別労働関係紛争
- 人事に関する紛争その他家庭に関する紛争(ただし、養育費等の民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係るものは適用対象)
このうち、①については、いわゆる「B to C事案」のみが適用除外とされており、「C to C事案」は適用対象に含まれます(この点において条約実施法の適用除外と異なりますので留意が必要です)。
なお、上記改正を反映するため、民事執行法22条が定める債務名義として、「確定した執行決定のある特定和解」(民事執行法22条6号の5)が追加されることになります(改正ADR法附則5条)。
なお、仲裁法制部会においては、弁護士会のADR手続において成立した和解についても執行力を付与することが検討されましたが、認証紛争解決手続と同程度に手続の公正かつ適正な実施が制度的に担保され、かつそのことが広く国民に周知される必要があることなどの理由から、今回の改正では見送られています。
施行日
改正ADR法は、その公布の日(令和5年4月28日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています(改正法附則1条本文)。
ただし、11条2項の改正規定(認証紛争解決事業者の情報提供方法としてインターネットによる公表その他の方法による公表を追加するもの)および34条1項1号の改正規定(11条2項の改正に伴う同条項の罰則規定の調整)は、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行するとされています(改正法附則1条但書き)。
-
仲裁法制部会資料1-2「仲裁法等の改正に関する論点の検討(1)」参照。 ↩︎
-
この点、シンガポール条約1条1項において、同条約は「商事紛争」を解決するための和解合意に適用されるものであることを明示していますが、我が国においては「商事」の外延が必ずしも明確でないことから、条約実施法においては「民事又は商事の紛争」との文言が用いられています(仲裁法制部会資料16「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案の取りまとめに向けた検討」参照)。 ↩︎
-
2023年8月時点では具体的な時期について明らかにされていません。 ↩︎

島田法律事務所
