『アジャイル開発の法務』著者に聞く、アジャイル開発のメリットを活かすために法務が知っておきたいことPR
IT・情報セキュリティ
目次
目まぐるしく変化するビジネス環境においては、顧客や社会のニーズに合わせて柔軟かつ迅速にシステムの開発・導入を進めていくことが求められます。こうしたなか、プロジェクトの初期段階ですべての要件を洗い出す「ウォーターフォール開発」に対し、小さな機能を短期間で開発する作業を繰り返す「アジャイル開発」への注目が高まっています。
しかし、アジャイル開発にも向き不向きがあるほか、過去にはユーザーとベンダーの双方が開発内容に納得できず裁判になったケースがあるなど、契約において気をつけるべきポイントも多くあります。
そこで今回は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のアジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」の策定に携わり、『アジャイル開発の法務』(日本加除出版)の執筆を手がけた梅本大祐弁護士に、同書の概要やアジャイル開発を行ううえでの留意点などについて伺いました。
梅本 大祐弁護士
ブレークモア法律事務所 弁護士、情報処理安全確保支援士。一橋大学法学部卒業後、日本ヒューレット・パッカード株式会社にて3年間エンジニアとして勤務。その後、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ソフトウェア・エンジニアリング・センター専門委員として、「非ウォーターフォール型開発に適したモデル契約書」の策定に関与する。
2017年からは総務省総合通信基盤局消費者行政第二課の専門職として、違法・有害情報対策等を担当。2019年より、IPA社会基盤センターの専門委員として、アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」の策定に関与する。
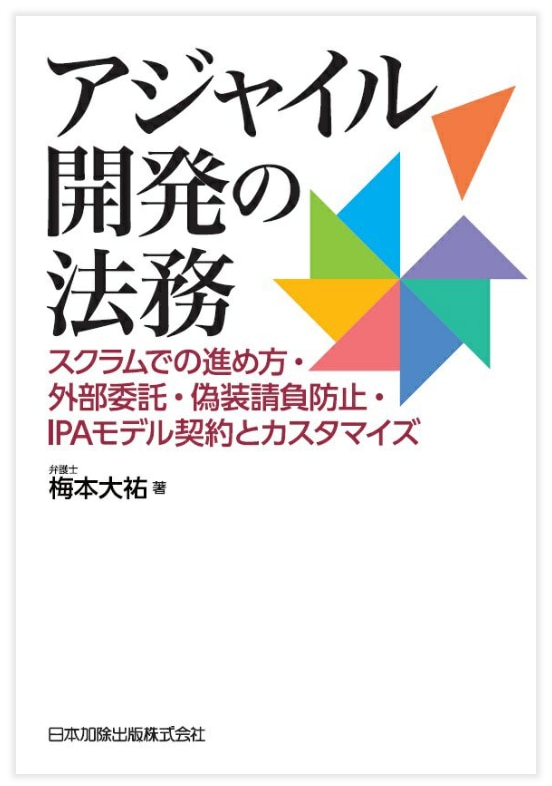
- アジャイル開発の法務
- 著 者:梅本大祐
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2022年
- 書籍の購入・詳細はこちら
- BUSINESS LAWYERS LIBRARY会員はこちら
ウォーターフォール開発との比較により、アジャイル開発のイメージをつかめるように工夫
まずは本書の執筆を企図された理由をお聞かせいただけますか。
これまで私は2010年からと2019年からの2回に渡り、IPAの専門委員としてアジャイル開発に適したモデル契約書の策定に携わってきました。1回目の策定の際は、IPAとしてもアジャイル開発の普及を促進しようとする機運が高まっているところでしたが、契約をどうすればよいかという課題は依然として残っている状況でした。
当初はアジャイル開発について詳しく知らなかったため、関連書籍を読んだり、有識者からヒアリングをしたりしながら理解を深めていったのですが、その際にアジャイル開発の法務に関してまとまった文献がないことに私自身課題を感じていました。
2回目の策定が終わり、その過程で蓄積してきたさまざまな知見を社会に還元できる機会があればと思っていたところ、日本加除出版の編集者の方からお声がけいただき、書籍としてまとめたという形です。

法務担当者や弁護士にとって、アジャイル開発を理解する難しさはどこにあるとお考えですか。
アジャイル開発の法務を扱うにあたっては、まずアジャイル開発というものが何なのかを知らなければなりません。さらに、「アジャイル開発」と一口に言ってもさまざまな手法があります。考え方を指しているのか、具体的な開発手法を指しているのか、はっきりしないまま使われている言葉なので、非開発者からすると勉強しにくい面もあるように思います。
また、アジャイル開発は小さな機能開発を調整しながら進めることから、大きなトラブルになった事例や具体的な裁判例があまりないため、何に気をつけるべきなのか手がかりがつかみづらい領域です。
そのため本書では、アジャイル開発のうち、最もよく用いられている「スクラム」という開発手法に絞ることで、非開発者にとっても理解しやすいようアジャイル開発の法務の論点をピックアップしています。また、従来のウォーターフォール開発と比較することにより、具体的なイメージをつかみやすくしています。さらに、第3章では、読者の参考になりそうな裁判例を複数取り上げており、法務担当者がアジャイル開発の法務を理解するうえでの取っ掛かりになるような書籍を目指しました。
アジャイル開発のメリットを享受するために契約時に気をつけるべきこと
アジャイル開発という手法を採用することで、実際にどのようなことが問題になるのでしょうか。
従来のウォーターフォール開発を外部委託する場合、ベンダー任せの状況が生まれやすく、ユーザーが実際に動くソフトウェアを見るのはプロジェクト後半のテスト段階になることも多くあります。この際、想定したシステムやプロダクトのイメージとの齟齬が発見されユーザー側が変更を求めたとしても、コストと時間の都合上受け入れられず、トラブルになってしまうケースがあります。
一方、アジャイル開発は、開発対象を機能ごとに細かく分けて短期間で開発し、実際の動作をユーザーに見てもらいながら、機能を追加したり改善したりするという進め方を採るため、ウォーターフォールのようにできあがったプロダクトやシステムに対する認識がベンダーとユーザーとのあいだで大きく異なってしまうという状況は起きづらいといえます。また、開発がうまく進まない場合でも小規模なので打ち切りやすい面もあり、その意味でも実際のところ目立ったトラブルは起きにくいようです。
アジャイル開発ではユーザー企業やユーザー部門にも継続的かつ深いコミットメントが求められます。大きなトラブルが発生するとしたら、本来あるべきアジャイル開発のやり方を採用せず、実質的にベンダー任せになってしまっているケースだと思います。ただし、そうした状況が生まれている時点で、もはやアジャイル開発とは言えないですよね。

発注者であるユーザー側もアジャイル開発のメリット・デメリットをよく理解したうえで、意識を変えていく必要がありますね。
ユーザー側からすると、アジャイル開発は不安な部分も多いと思います。要求事項が常に変化し、全体の仕様が確定しないなかでは、投入するコストに見合った成果が出るかわからず、予算を検討することが難しいというデメリットがあります。
ユーザー側としては、一定の成果を保証するような請負契約を希望したくなるところです。しかし、対価を固定しつつ要件変更まで対応しようとすると、ベンダー側にとってはなるべく要件変更がない方がよいということになり、アジャイル開発のメリットがうまく機能しない方向にインセンティブが働いてしまいます。ユーザーとして、柔軟な変更対応というアジャイル開発のメリットを活かしたいのであれば、ある程度のリスクがあることを受け入れたうえで発注する必要があるでしょう。
本書では、請負契約よりも準委任契約のほうがアジャイル開発になじみやすいとされています。
IPAのモデル契約でも、準委任契約がふさわしいという方針が示されています。実際に、近年のアジャイル開発の外部委託契約では、準委任契約が用いられるケースが多いです。第1回目のIPAモデル契約の策定時には、請負契約と準委任契約の2つの個別契約を含んだ基本個別契約モデルを作成しましたが、請負契約を入れるかどうかは当時議論になったポイントです。
しかし、第2回目の検討では、早い段階で準委任契約をベースとする方針に決まったので、この10年ほどでアジャイル開発の場合は準委任契約とすべきというユーザー側の理解が進んだように感じています。本書では、最終章にIPAのモデル契約を記載しています。モデル契約の内容だけでなく、その具体的な変更例についても解説していますので、ユーザー・ベンダー双方が納得のいく契約に落とし込むためにぜひご活用いただければと思っています。
また、実態としては、偽装請負が問題になるという不安から、過剰な対策や運用をしているケースが見られます。そのため、第4章では、偽装請負についても詳しく解説しています。厚生労働省が公表している疑義応答集などを参照しながら、なるべく丁寧に説明するよう心がけました。

日常業務に応用できる「アジャイル」の考え方
どのような方々に本書を読んでいただきたいですか。
まずは法務担当者の方々に、アジャイル開発とは何かを理解していただき、現場の方々とのコミュニケーションを円滑に進めていただければと思っています。また、アジャイル開発の案件を突然依頼されたときにも、概要を把握して、重要なポイントの抜け漏れがないようチェックするためのツールとしてご活用いただけます。
また、開発者やプロジェクトマネージャーなど現場の方々にとっても役に立つ内容になっていると思います。契約締結時に法務がどのような観点で見ているのか、また偽装請負等の問題にどう対応すればよいか、その概要を本書でつかんでいただければと思っています。
最後に、BUSINESS LAWYERSの読者へメッセージをお願いします。
アジャイル開発は、試行と改善を重ねながらユーザーにとって真に価値のあるプロダクトを開発するものです。ユーザーの声を迅速に反映していける一方で、それを具体的にどのように開発するかというHOWの部分については、開発者側に大きな裁量が与えられます。個々の開発者が創意工夫を凝らしてモチベーション高く仕事ができるという点でも、アジャイル開発には大きなメリットがあります。
また、To Doリストを柔軟に入れ替えながら、短期間で目に見える機能を開発して改善していくというアジャイル開発のコンセプトは、システムやソフトウェア開発に限らず日常業務レベルから組織、社会の改善にも応用できる考え方で、世間的に近年ホットになってきている領域です。ぜひこうしたアジャイル開発のコンセプトについて、本書を活用して学んでみてはいかがでしょうか。
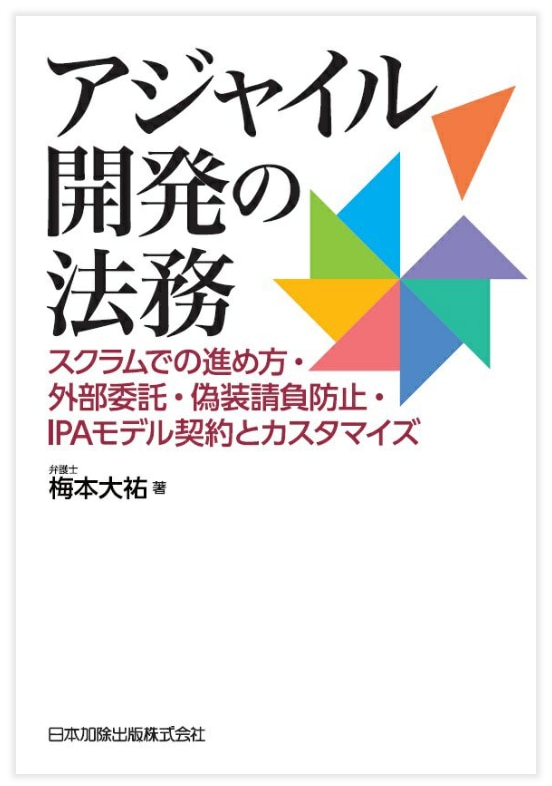
- アジャイル開発の法務
- 著 者:梅本大祐
- 出版社:日本加除出版株式会社
- 発売年:2022年
- 書籍の購入・詳細はこちら
- BUSINESS LAWYERS LIBRARY会員はこちら
