はじめて法務担当となった方に向けた会社法の基礎
法務部私は法務部に配属されたばかりの新入社員です。会社法に関係する業務を担当することになりましたが、わからないことが多く、日々、悪戦苦闘しています。当然のことながら会社法についてはしっかりと理解しておかなければならないと言われましたが、どこから手をつけていいのかわかりません。会社法とは、どういう法律なのか。基礎的なことについて教えてください。
会社法は、日本における会社に関する法律で、主として
- 株主と役員の関係や企業の運営を規律する「ガバナンス」の領域
- 会社の資金調達を規律する「ファイナンス」の領域
- M&A等を規律する「事業再編」の領域
に分類され、「設立」から「解散・清算」まで、4つの種類の一般的な営利社団法人である会社について基本的なルールを定めています。
会社法は強行法規であるため、規律を正しく理解して、法令違反をしないように会社の運営をしていくことが重要です。また、会社法における多くの問題は形式よりも実質的な評価がポイントとなります。複雑化して、膨大な情報量が集積されている会社法は、現代のニーズと過去のトラブルの蓄積を反映したものです。じっくりと時間をかけて取り組んでいただければと思います。
解説
会社法の構成
企業社会を規律する法律にもいろいろありますが、その中でも最も基本的なものに「会社法」があります。日本の現行会社法は、商法の中から会社に関するルールを独立させて作られたもので、2005年6月に成立しました。この会社法は、そのほとんどの部分が2006年5月1日から施行され、2007年5月1日から全面施行されました。軽微な改正を除くと、少しまとまった会社法改正が2014年にあり、また次の改正にむけて、法制審議会の会社法制(企業統治等関係)部会で、2019年1月16日に「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」が作られています。
会社法は、株式会社と3つの持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)と、外国会社に関して定めており、次の編から成り立っています。

このほか、会社法の本体とは別に、細かな定めが会社法施行規則や会社計算規則などの法務省令に定められており、会社法の正確な規律を知るためには、それらの法務省令などもチェックする必要があります。
会社法は強行法規
法律の規定には、当事者が法律の定めと異なる約束をしても、その約束が無効となる規定(=強行法規・強行規定)もあれば、約束が優先される規定(=任意法規・任意規定)もあります。
会社法は利害の対立する多くの人々の利害を調整する法律です。このため、一部の人たちによって勝手に曲げられては困ります。
民法の定めの多くが任意規定であるのに対して、会社法はほとんどが強行規定となっています。

このため、会社法の規律を正しく理解して、法令違反をしないように会社の運営をしていくことが重要です。株主との関係や株主総会の運用、取締役会のあり方や役員等の責任については、会社法のルールに従うことが大前提となっているのです。
もっとも、会社の選択できる範囲が、旧商法のころと比較すると多くなっているため、その自由度を高め、規制緩和が図られてきました。この動きは、会社の基本的なルールを定める「定款」の内容の自由度を高める改革ことから、「定款自治の拡大」とも呼ばれています。
形式よりも実質的な評価が重要
会社法の問題を考えるには、技術的な仕組みを理解しつつも、実質的な意味から適切な解決を見出すことが求められることに留意する必要があります。とかく技術的な理屈だけで結論を出すと、きわめて不当な結果となることがありますが、その場合に会社法ではいろいろな知恵を働かせて正義に合致した結論を導こうとすることが少なくありません。
たとえば、「法人格否認の法理」は、株式会社は法人であり、株主とは別人格を有するという原則に対して、所有と経営が分離していないような会社に対して、形式的な理屈どおりに解釈すると正義に著しく反する場合があるため、個別事案の解決では会社の法人格を否定し、背後にいる株主(=会社法104条に定める、本来の「株主有限責任の原則」では責任を負わないはずの株主)に責任を負わせることがあります(最高裁昭和44年2月27日判決・民集23巻2号511頁)。
これに限らず、会社法において、形式的な理屈だけで結論が確定してしまう問題は一部の論点に限られており、多くの問題は形式よりも実質的な評価が重要と考えられています。
現代のニーズと過去のトラブルの蓄積の反映
会社法は、かなり技術的なものを含んでおり、一般的にはなかなか難しく、敬遠されがちです。とはいえ、会社法がもたらす企業社会への影響は、とても大きく深いものがあります。
会社法が複雑になっているのは、いろいろなタイプの会社によって異なったルールになっているからです。したがって、会社法の問題を考えるにあたっては、どういう会社であるかを押さえることから出発する必要があります。特に、株式会社には、小さい会社から大きな会社、閉鎖的な会社から公開会社まで、いろいろなタイプがあることをふまえ、会社の実情に応じて規制も異なります。
また、会社法は、昔の商法と比べると、かなりの規制緩和を進めた結果、その選択肢が多く認められるのですが、その代わり条文が抽象化されてわかりにくくなっている部分が少なくありません。
そのように複雑化して、膨大な情報量が集積されている会社法の世界は、過去のおびただしい数の会社紛争に由来しています。会社をめぐる400年以上にわたる利益と損失をめぐる多くの人々の争いを解決するための理論と仕組みが会社法に凝縮しています。
また、会社を経営者に任せた場合に、その経営者をコントロールする方法も大きな問題で、小さな会社から大きな会社に至るまで、会社の支配をめぐって多くの争いが展開されてきました。
今日の会社法は、現代のニーズと過去のトラブルの蓄積を反映したものです。会社をめぐる過去の争いや教訓をベースに、複雑な制度が発展してきたわけです。ただ、様々な政治的な妥協も多いので、すべてが論理的にすっきりと説明できるものではありません。さしあたり、現実と理論の現時点における調整のルールとして、じっくりと時間をかけて会社法の問題に取り組んでいただければと思います。
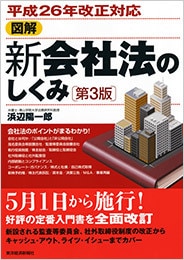
- 参考文献
- 図解 新会社法のしくみ(第3版)
- 著:浜辺陽一郎
- 定価:本体1,800円+税
- 出版社:東洋経済新報社
- 発売年月日:2015年4月3日

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック
- コーポレート・M&A
- 人事労務
- 事業再生・倒産
- 危機管理・内部統制
- 国際取引・海外進出
- 訴訟・争訟
- 税務